「ハッシュタグ」を基点にしたキャンペーンとは?

宮原 渉
X Corp. Japan 株式会社
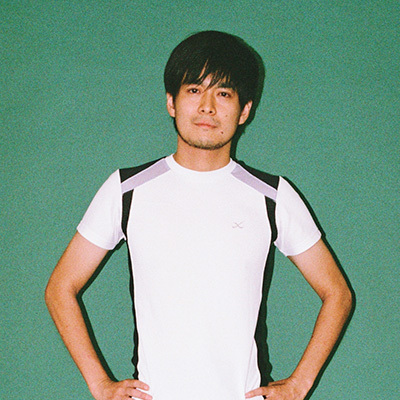
中川 賢太
株式会社 電通

いまやブランドのマーケティングや広告キャンペーンに欠かせない存在になっているX(旧Twitter)。本連載では、Xのクリエイティブ戦略集団「Next」と電通が100件以上の広告キャンペーンの研究を重ねて編み出したCXプランニングのステップ「4X」を紹介しています(4Xの概要は、こちら)。
今回は、「ステップ2・eXecute」を取り上げます。ハッシュタグの歴史を振り返りながら、広告キャンペーンにおいてどのような価値があるのかを解説し、効果的なハッシュタグを開発した事例を紹介します。
ハッシュタグには、新しい会話を生む機能がある
X上で初めて使われたハッシュタグは、2007年8月、クリス・メッシーナ氏という人物がbarcampのイベントについて、「#」をつけて投稿しようと呼びかけたのが始まりだと言われています。

なぜ、このような提案をしたのか。もし「Bar Camp」で会話を検索したら「Bar」と「Camp」の2つが入った関係のない投稿まで引き寄せてしまいます。そこで、特定の会話をグルーピングして見返す(アーカイブ化)ためにハッシュタグが利用され、その後、世界中に広がりました。
Xの誕生から15年以上がたち、Xは数億人のユーザーが言葉を交わし合うための場所となったことで、ハッシュタグの使われ方も進化しました。その転換を象徴するハッシュタグが「#MeToo」です。

「#MeToo」は、2017年ごろよりセクハラや性的暴行などの体験を告白・共有する際に使用されるハッシュタグです。
横にあるのは、勇気を持って挙げられた手。この絵文字のように「#MeToo」がついた投稿を見た人たちが、「わたしも!」と自分が受けた体験を次々と告白しムーブメントになりました。「新しい会話に不特定多数の参加を促す」機能がハッシュタグにもたらされた瞬間と言えるでしょう。
ハッシュタグの変化は日本でも見られました。単語だけのものが多かった2010年代前半と比べ、内容が具体的で、初見でもどんなテーマで会話すべきかがよく分かるようなものが登場。元々あったアーカイブ機能に加え、「新しい会話を生む」機能が強まっていきました。
広告宣伝において、ハッシュタグはキャッチコピーのように捉えられますが、両者には大きな違いがあります。キャッチコピーは、よく「What to say, How to say.(何を言うか、どう言うか)」をベースに開発されます。それに対し、ハッシュタグは、「What to talk, How to talk.(何を会話するか、どう会話するか)」と、会話を促すことを意識すべきでしょう。企業から一方的にユーザーへメッセージを送るだけではなく、両者が同じ目線に立って会話を盛り上げるところにハッシュタグの本質があります。
ハッシュタグには、3つのスタイルがある
X上のキャンペーン投稿で見られるハッシュタグの組み合わせは、下記の3種類です。

「③会話を生みアーカイブにもなる」とは、「①会話を生む」+ 「②キャンペーンのアーカイブ名になる」の2つのハッシュタグをポストに組み込んだもので 、他メディアでも展開するような大きなキャンペーンの傘に入りつつ、発話も生み出したいときに使われます。
例えば、森永乳業は「リプトンミルクティー」の再発売時に、「#667通のラブレター」と「#リプトンミルクティーおかえり」という、2つのハッシュタグを使ってキャンペーンを展開しました。
「#667通のラブレター」というハッシュタグは、「リプトンミルクティー」の終売後、ファンから再発売を望む声が半年間で667通届いたことにちなんで作られました。キャンペーンにおいては、「リプトンミルクティー」に対する思いをXでポストしてもらうためのもので、キャンペーンテーマに対する投稿を蓄積するアーカイブ機能を持っています。「#リプトンミルクティーおかえり」は、会話を生む機能を持ったハッシュタグです。
ちなみに「#リプトンミルクティーおかえり」のようなハッシュタグを開発する場合、「#おかえりリプトンミルクティー」と「#おかえリプトンミルクティー」の2つの言い回しが考えられそうです。
前者は「り」がかぶってつっかえてしまう。そこで「リ」を1つにした後者を思いつきます。しかし、そうすることで途端に企画っぽい印象を受け、ブランドからの言葉のように感じられます。
あくまでユーザーに使ってもらうことを前提とするなら「#リプトンミルクティーおかえり」が自然でしっくりきます。一見シンプルなハッシュタグですが、ユーザーのことをきちんと考えていることが分かります。
「リプトンミルクティー」の再発売キャンペーンについて、こちらの記事もおすすめです。
お問い合わせから生まれたリプトンミルクティーの短編アニメ「667通のラブレター」
「アーカイブ機能」と「会話を生む機能」を1つのハッシュタグに集約したキャンペーンもあります。人材派遣や転職サービスなどを提供するパーソル社が始めた「#これ誰にお礼言ったらいいですか」は、その代表例です。
「#これ誰にお礼言ったらいいですか」は、勤労感謝の日のタイミングに、「ありがとうを言いたい名仕事」を募集した、同社のブランディングキャンペーンです。ハッシュタグをつけて名仕事をポストしてもらい、仕事を行った本人に感謝の気持ちを届けることが狙いです。「気持ちを伝える先が分からないから、Xで多くの人に伝えたい」というインサイトをくすぐり、発話のモチベーションを作っています。
こちらのハッシュタグもブランドから発信されていますが、ユーザーのポストにあっても違和感のない言い回しになっています。実際にそのハッシュタグが使いやすいかどうか検証するときに、「自分だったらどんなことをポストするか」を頭の中で考えるだけでなく、ポストのような体裁にして書いてみることをおすすめします。書きづらかったら何が足りないのか、書けた場合もワンパターンな内容になったりしないかを考えながら、多様なポストが集まるハッシュタグを作ることをおすすめします。
会話を生む機能を最大限に発揮するには、「ハッシュタグの分かりやすさ」と同じくらい「発話するモチベーションの設定」が重要となります。企業からの一方的な言葉では会話は生まれません。そこでカギとなるのがユーザーインサイトの発掘です。ユーザーが日々疑問に思っていることや、ブランドについて語っていることなどを発見することが、会話する価値があるハッシュタグを作る第一歩となります。
ユーザーインサイトの発掘について、こちらの記事もおすすめです
2800万リーチを記録した「ランダムマック」。若手クリエイターのX活用術とは?
感情が爆発するXは、広告プランナーにとってインサイトの宝庫
ハッシュタグを考えるのに大事な視点
「インサイトも見つけた。どんな会話が生まれるかもイメージできる。でもどんなハッシュタグにすればいいか難しい!」と不安になったときのために、役立つリストを公開します。下記は、100以上のキャンペーンハッシュタグを代表的な11の型に分類したものです。

ついつい回答を考えてしまいそうな、「#どうして〇〇ですか」のような【問いかけ型】。「#〇〇総選挙」のような【イベント型】。これらはXでもよく見られる定番の型です。それに加えて、【ルール型】や【誘い型】といったユニークな型もあります。もちろん、ここに挙げた11の型を超えていくチャレンジも面白いでしょう。
ハッシュタグの役割から具体的な型まで、ポイントをまとめると下記になります。

ここまで紹介した①から④に加え、ハッシュタグの効果をさらに高めるためには「⑤ハッシュタグを起点にしたキャンペーン設計」も考える必要があります。⑤について3つの事例を紹介します。
ハッシュタグを起点にしたキャンペーン設計
・#これ誰にお礼言ったらいいですか
これは、パーソル社(@PERSOLgroup)によるブランディングキャンペーンです。Xは、「知る」「語る」「討論する」「応援する」など、さまざまな側面を持つプラットフォームですが、「#これ誰にお礼言ったらいいですか」は、ハッシュタグを通じて「つながる」「感謝する」という面にフォーカスした企画です。

Twitter時代から、タイムライン上には実は多くの「感謝」が存在していました。お店での素晴らしい接客への感謝や、おいしいスイーツを開発したコンビニへの感謝、そんな誰かの素晴らしい仕事への感謝ポストに注目したことが本キャンペーンの始まりでした。
企画の概要は、「#これ誰にお礼言ったらいいですか 」のハッシュタグを使い、お礼を伝える相手が誰かは分からないけど、ぜひとも伝えたい感謝を募り、パーソル社がその相手を探し出して、実際に感謝を伝えにいくというもの。言うなれば、恩人探しと感謝代行です。

勤労感謝の日に合わせた新聞15段とXでのポストで募集を呼びかけ、実際に集まったたくさんの名も知らぬ相手への感謝からいくつかを選び、さまざまな聞き込みを通じて、相手を突き止める過程はXらしからぬ、非常に地道でアナログな作業だったそうです。

この企画においては、まさに「#これ誰にお礼言ったらいいですか」という【主張・報告型ハッシュタグ】が、コアアイデアでもあり、呼びかけの言葉としても機能しています。担当コピーライターである電通・福島陽氏は、このハッシュタグ開発にあたり、いわゆる100本ノック状態で、どうすれば機能する言葉になるかをとことん考え尽くしたそうです。
ユーザーにポストしてもらうタイプのハッシュタグで必要なことは、「いかに自分のタイムラインに載せてもいいかもと思わせられるか」ということ。今回の場合は、「お礼をする」というユーザーの気持ちをうまく刺激しながら、Xに自然に溶け込むハッシュタグがポストのハードルを下げることに成功しています。
ちょっとした語尾や言い回しを工夫する広告コピーのスキルと、Xの空気感を理解するスキルを掛け合わせることで、キャンペーンの成否に大きな影響を与えていて、ハッシュタグにはまだまだ可能性があることを感じました。
・# 女子昔ばなし
ハッシュタグの基本とも言える、「たくさんの声を集約し、1つの大きな塊に見せる」という機能は、「#MeToo」のように社会的な問題についての議論を呼びかけたりする際に非常に効果的です。
「#女子昔ばなし」は、国際NGOプラン・インターナショナルによる、日本におけるジェンダーギャップへの問題提起として行われたTwitter(実施当時)キャンペーンです。

「女子昔ばなし」について、こちらの記事もおすすめです。
クリエイティブで社会課題に挑む。ジェンダー問題と正面から向き合った「#女子昔ばなし」
昔の当たり前が、今では非常識。世界がどんどんアップデートされていく過程で、古い慣習は淘汰されていくもの。この考え方を少し先の未来から捉え、今も存在する時代遅れな女性差別のエピソードを、これから先は過去の話に変えていこうねというのが本キャンペーンの狙いです。
そこで、「#女子昔ばなし」という【テーマ型ハッシュタグ】を使い、昔ばなしの定型である「むかしむかし……」という始まりで、エピソードを募りました。その結果、集まったエピソードはなんと3000件以上。
ここまで多くの数が集まったのは、普段、ストレートには発信しにくい問題を、「#女子昔ばなし」というフォーマットにのせることでセンシティブな問題でも発信しやすくするハッシュタグの工夫があったからこそ。
そして、本施策では集まった声をさらに活用するために、絵本を制作し、教材として学校の授業に活用する、読み聞かせをするという展開を行いました。デジタル上の施策をより広く深く認知させるためには、同じハッシュタグをマスでも展開する、実際のポストをOOHとして活用するなど、リアルとの掛け合わせが効果的です。

昔ばなしと絵本という親和性が非常に高く、「#女子昔ばなし」は、リアルとの掛け合わせを意識した展開性のあるハッシュタグであった点も特筆すべきことです。
多くの企業が、パーパスブランディングという形で自社の社会的意義を考えるようになり、製品・サービスを通じて社会に貢献するという意識を持ち始めた近年、ハッシュタグの持つソーシャルパワーは大いに活用のチャンスがありそうです。
・#みつけてくれまSENKA
ハッシュタグを活用し、Xというデジタルの場をリアルと掛け合わせることで企画のパワーをあげている好事例が、ファイントゥデイ社の洗顔料SENKAと、LINE FRIENDSのグローバル人気キャラクターブランドBT21のコラボパッケージローンチキャンペーンです。キャンペーンはこんなポストと共にスタートしました。

このポストに先駆けて、今回のコラボのメインビジュアルポスターを新大久保に10カ所掲出。さらにX内に立ち上げた11個の隠しアカウントでポスト。ユーザーにそれらを探してもらうというお題を投げかけたのです。
そのお題にファンたちが次々と行動を起こし、Xの中に無数にあるアカウントからお目当てのアカウント探しと、Xというデジタルの世界を抜け出してのリアルなポスター探しが同時に始まりました。
当然のように熱量の高いファンたち。楽しみながら、次々と隠されたポスターとアカウントを探し出し、「#みつけてくれまSENKA」のハッシュタグと共に多くのポストをしてくれました。

一方で、Xでのキャンペーンで注意しなければならないのは、加速度的に一気に盛り上がるほど、その熱の冷め方も早くなる傾向にあることです。デジタル、特にXの世界での時の流れは速く、先週のトレンドが翌週まで生き残っていることはかなりまれなこと。なるべく長くこの熱を保つための施策が、こちらのポストです。

実は事前に新大久保10カ所のポスター、11個の隠しアカウントの画像すべてに、1つずつまちがいを忍ばせておいたのです。そのまちがいはパッとみたら分かるものから、かなり注意しなければ分からないものまで多種多様。こうして、メインハッシュタグである、「#みつけてくれまSENKA」 にもうひとつの意味を持たせ、一度参加した人たちも、もう一度楽しめる仕掛けにすることでキャンペーンの熱量を保ち続けることに成功したのです。

本企画でのハッシュタグの役割はこれまでのどのタイプとも異なり、スタンプラリーにおけるスタンプのような達成の証とも言えます。あるいはまだ見つけていないユーザーにとっては、探すためのヒントにもなっています。
結果として、本キャンペーンではリアルとデジタルを通じて、実際に「見つける」という行為を促すことで、新大久保まで足を運ぶ、X内を回遊するなど、より長く深くブランドに対してのエンゲージを作っていくことに成功しています。
さらに、時期を分けて、
・「ポスター/アカウントを」#みつけてくれまSENKA
・「まちがいを」#みつけてくれまSENKA
という形で、1つのハッシュタグに2つの意味を持たせることで、熱量をより長く維持することに成功した、という点でも非常に優れたキャンペーンであると言えます。
本記事では、広告キャンペーンにおけるハッシュタグの価値と、ハッシュタグを効果的に使った事例を紹介しました。ハッシュタグは声を集め、塊に見せる装置という基本的な機能がありますが、その使い方はまださまざまな可能性を秘めていると言えます。今回紹介したハッシュタグの型や事例を、新たなハッシュタグとキャンペーン開発に役立てていただけると幸いです。
この記事は参考になりましたか?
著者

宮原 渉
X Corp. Japan 株式会社
Next チーム
Creative Strategist
言葉と企画を行ったり来たりするコピーライターとして外資系広告代理店で働き、2021年に言葉のプラットフォーム「Twitter」へ。広告にとらわれず、番組コンテンツやXR・メタバースなど様々な領域を行ったり来たりして得た知見を混ぜこんで、実験するのが好き。One Show, Clio Awards, The Webby Awards など受賞。
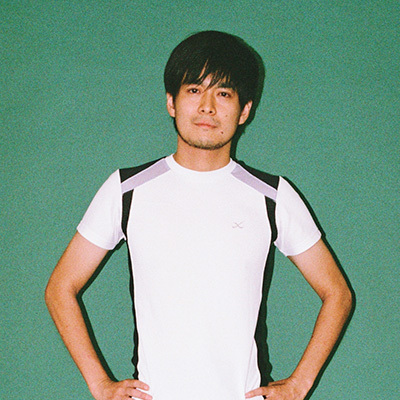
中川 賢太
株式会社 電通
第4CRプランニング局
クリエーティブディレクター/コミュニケーションプランナー
1年の雑誌局勤務後、現局にてコピーライター・CMプランナーとして活動。マス・デジタル・プロモーションを限りなくシームレスに繋げた統合的コミュニケーションを得意とする。第9回テレビチャンピオンラーメン王選手権出場。東京マラソン7度出場。ベスト3時間29分。





