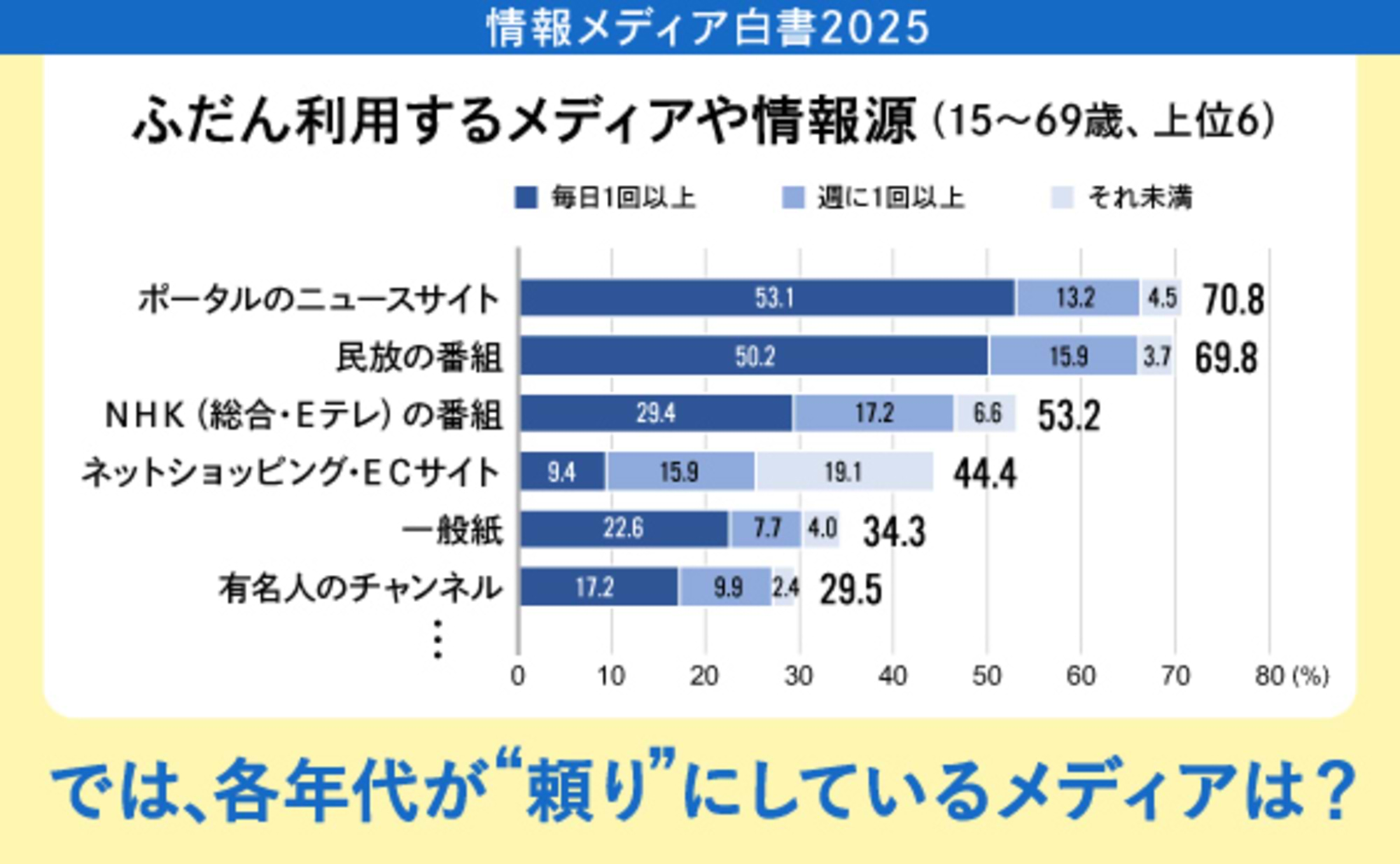2025年3月22日、日本のラジオは誕生から100年を迎えました。この節目にウェブ電通報では、ラジオの第一線で活躍されている方にお話を伺います。今回のゲストは、TBSラジオの人気Podcast番組「ジェーン・スーと堀井美香の『OVER THE SUN』(以下、OVER THE SUN)」のプロデューサー・吉田周平氏。
音声メディアが注目を集めるいま、Podcast(※)でさまざまなコンテンツが配信されています。本記事では、「OVER THE SUN」の制作秘話を交えながら、地上波ラジオとは異なるPodcastならではの番組作りや、リスナーとの信頼関係の築き方、ファンコミュニティの育て方について、電通メディアイノベーションラボの森下真理子氏がお話を伺いました。
※Podcast:インターネットを通じて配信される音声や動画コンテンツサービス。自分の好きな番組を好きなタイミングで聴取できる。
ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」
2020年10月にスタートした、TBSラジオが制作するPodcast番組。毎週金曜日夕方5時配信。パーソナリティは、コラムニストのジェーン・スーさんと、フリーアナウンサーの堀井美香さん。番組にはペライチの台本しかなく、パーソナリティやリスナーのエピソードで構成される。イベントも活発に行い、2025年3月には日本武道館で「オーバーザサン 私たちのレッドカーペット」を開催し、約8000人を動員した。
radikoの誕生が、広告営業の追い風になった
森下:本日はよろしくお願いします。初めに、自己紹介をお願いします。
吉田:TBSラジオで、地上波ラジオとPodcast番組のプロデューサーを務めています。担当番組は、「OVER THE SUN」「金曜ボイスログ」「きしたかののブタピエロ」「カラタチの最果てのセンセイ!」などです。2010年に入社して、営業局に11年間所属した後、コンテンツ制作局に異動しました。
森下:小さいころからラジオがお好きだったのですか?
吉田:父、母、兄の4人家族で、ラジオが流れている環境で育ちました。父はニッポン放送、母はFMをよくかけていた記憶があります。夜は、2段ベッドで兄と一緒に、深夜ラジオを聴いていました。
森下:本当にラジオが身近にあったのですね。
吉田:当時、クリス・ペプラーさんの「TOKIO HOT 100」の人気企画「逆電バスター」で、クリス・ペプラーさんと話すために何度も電話してつながったとき、とてもうれしかった思い出があります。
森下:TBSラジオに入社された2010年から11年間、営業局にいらしたとのことですが、その間、ラジオ領域ではデジタル化がかなり進んだのではないでしょうか。ラジオの変化をどのように感じていましたか?
吉田:radikoが登場するまで、地上波ラジオは、限られた地域でしか電波がキャッチできない、リアルタイムでしか聴けないという状況でした。広告主は、ターゲットに的確にCMを当てにくく、それが営業課題になっていたのです。
2010年にradikoが誕生し、2016年に「タイムフリー機能」が加わり、同時期にはスマホが普及していきました。さまざまな番組を好きな時間に手軽に聴けるようになり、デジタルデータでリスナーの属性も把握できるようになった。ラジオのデジタル化は、営業面で大きな追い風になりましたね。
みんなでヒヤシンスを育てる企画で、SNS投稿が加速
森下:今回、Podcastをテーマにお話を伺っていきたいのですが、吉田さんが担当されている「OVER THE SUN」 は、数あるPodcastコンテンツの中でも特に人気がありますね。
吉田:おかげさまで、多くの人に楽しんでいただいています。「OVER THE SUN」は、毎週金曜日の夕方5時に配信していて、月間約80万人、1配信当たり約20万人に聴いていただいています。
森下:ウェブ電通報の読者に向けて、改めて番組の概要を教えてください。
吉田:コラムニストのジェーン・スーさんと、フリーアナウンサーの堀井美香さんがパーソナリティを務めるトーク番組で、2020年10月にスタートしました。台本はほぼなく、お二人やリスナーのエピソードで番組が構成されています。
森下:私も聴いていますが、いつもお二人が熱のこもったトークを展開されていますね。
吉田:「OVER THE SUN」の特徴を一言で表すと、「内容のない無駄話を最高のクオリティでお届けしている番組」です。
森下:番組がブレークしたきっかけは何だったのでしょうか?
吉田:何でしょう……。番組がスタートして2年目に行った、「みんなでヒヤシンスを育てる企画」ですかね。「OVER THE SUN」のリスナー100人で何をしたいか、メールでテーマを募集したことがあったのですが、あるリスナーの方から、「みんなで同じタイミングで花を育てて咲かせたい」という提案がありました。それで、みんなでヒヤシンスを育てることになったのです。
森下:リスナー参加型企画ですね。
吉田:そのころから番組に関するSNS投稿が活発になりました。Twitter(現・X)とInstagramで、「ヒヤシンスを植えました」「芽が出ました」「咲きました」という報告が上がるようになりました。
同時期、ヒヤシンス企画とは別に、番組グッズとしてTシャツなどを制作していました。すると、Tシャツを着た画像とコメントをSNSにアップしてくださるリスナーも現れました。
森下:番組がブレークするきっかけとして、やはりSNSの影響は大きいのですね。
吉田:はい。自分以外にもたくさんの人が同じ番組を聴いていることが可視化され、みんなで番組を盛り上げるムーブが生まれますね。
リスナーとの信頼関係をベースに、地上波では扱いづらいテーマも取り上げる
森下:SNSもさることながら、番組の盛り上がりの原動力は何といっても、パーソナリティのお二人のキャラクターですよね。特に、堀井さんの発言に対して的確にツッコミを入れる、スーさんの「瞬発力」はすごいです。
吉田:リスナーのことを「互助会員」と呼ぶなど、スーさんの言語化能力はすごいですね。
森下:「OVER THE SUN」からは、他にも「負けへんで」「おはこんばんちは」「ご自愛ください」など、リスナーとの共通言語がいろいろ生まれていますよね。これらは、スーさんが瞬発的に考え出したのでしょうか?
吉田:リスナー発のものもあります。「おはこんばんちは」「ご自愛ください」は、リスナーからのメールのあいさつによく使われています。Podcastは尺が決まっていないので、時候のあいさつも全部読み上げる。すると、それが定着していって、みんなが使うワードになっていく。
森下:尺が決まっていないというのは地上波ラジオとの大きな違いですね。
吉田:そうですね。「OVER THE SUN」は、毎回、尺がまちまちで、30分で番組が終わるときもあれば、1時間を超えることもある。回ごとにテーマについて深くトークできるのは、地上波ラジオにはない特徴です。
森下:他に、Podcastには地上波ラジオとはどのような違いがあるのでしょうか?
吉田:Podcastは、地上波では取り上げるのが難しいテーマも扱います。「OVER THE SUN」でも、離婚、整形、中高年の恋愛など、ディープなテーマについてトークを展開することが珍しくありません。編集は、地上波ラジオに比べて、パーソナリティの発言をカットすることが少なく、一歩踏み込んだ発言もそのまま流す傾向があります。それは、リスナーとの信頼関係があるからこそだと思います。
「OVER THE SUN」は、みんなのハブであり、帰れる場所
森下:そのようなリスナーとの信頼関係は、どのようにしたら築けるものなのでしょうか?
吉田:地上波ラジオは不特定多数の人が聴いているのに対し、Podcast番組は自分から番組にアクセスして能動的に聴くものです。番組やパーソナリティが好きという人が集まってくる。その好きという気持ちを裏切らない番組作りを心掛けていくことでしょうか。
「互助会員」という言葉に象徴されるように、「OVER THE SUN」は、いろいろな人のエピソードをパーソナリティとリスナーが共有し、さまざまな知見を提供して支え合っていこうという雰囲気があります。番組がみんなのハブだったり、みんなが帰れるような場所になっています。
森下:「OVER THE SUN」は、リスナーの方の関与にとても特徴があると感じます。
吉田:地上波ラジオとPodcastでは、リスナーが送ってくるメールの文章量が全然違います。地上波ラジオは聴いていないが、Podcastは聴いているという人は結構多い。ですから、メールのトンマナが地上波ラジオと違うんですよ。例えば、A4で3枚にもなる長文で、パーソナリティに手紙を書くみたいな感覚で送られてきたりする。中身も割と濃いめな身の上話とか、「ここまで書いて大丈夫?」と思うようなことを赤裸々に語られる人もいます。
あるリスナーのエピソードが番組で紹介されることで、他のリスナーが、「自分も同じような経験をしていて、同じようなことに苦しんでいる」「このリスナーはこんなふうに課題と向き合って乗り越えようとしている」と感じる。そういった思いの共有に、番組が役立っているのかなと思います。
森下:リスナーはパーソナリティに宛ててメールを送るけれど、その先にいる20万人のリスナーにも思いは届いて、みんなで話題を共有できる。深い世界ですね。
吉田:そういった話題の共有は、「OVER THE SUN」に限ったことではありません。でも、パーソナリティ、制作陣、リスナーみんなにとって、「ハブであり、帰ることができる場所」という感覚は、他の番組より強いかもしれないですね。
番組からさまざまなファンコミュニティが生まれる
森下:「OVER THE SUN」のファンコミュニティについてお話を聞かせてください。
吉田:イベントを活発に行っています。2025年3月に日本武道館で、「オーバーザサン 私たちのレッドカーペット」を行い、約8000人を動員しました。他にも、リスナー参加型の運動会、旅行イベント、展覧会などをこれまで開催しました。

「オーバーザサン 私たちのレッドカーペット」。撮影:上飯坂一
吉田:互助会員(「OVER THE SUN」のリスナー)のみなさんは、イベントで知り合った方々と仲を深め、「OVER THE SUN」をハブにして思い思いに楽しんでくれている感じです。
森下:何の利害もない人同士が番組を通してつながれる。それは、安心感があるからでしょうか?
吉田:そうですね。自分と同じようなマインドを持っている人が多かったり、自分を傷つけてくる人がいないので、安心できるのだと思います。2022年に配信100回を記念して初のイベントを行いました。そのとき、この盛り上がりを無駄にしたくないという思いでリスナーの方が、LINEで「OVER THE SUN」のオープンチャットを立ち上げました。
森下:何人ぐらい参加されているのですか?
吉田:現在、4000人以上だと思います。僕らスタッフが知らない間に立ち上がったので、何か怪しい商売の勧誘があったりしたらまずいなと思って、僕も入ってこっそり見てたんですよ。そうしたら、まあ平和でして。これなら安心だなと思い、もう見ていません。
オープンチャットをきっかけに、登山好きな人たちが集まる「オーバーザサン登山部」や、ランニング好きの集まりとか、勝手にイベントオフ会みたいのを開かれていて。さらに、オフ会で仲良くなった人たちが、「OVER THE SUN」の次のイベントに参加するみたいな。そういう複合的で勝手な楽しみ方があり、もうスーさんと堀井さんがいなくても、ファンコミュニティが成立するようになっています。
森下:でも、そのように安心して楽しめる雰囲気が生まれるのは、パーソナリティのお二人のお人柄の影響も大きいのでしょうね。
吉田:配信で絶対人を傷つけるようなことは言わない、といった信頼がリスナーさんから寄せられている。だから安心して聴いて盛り上がれる。誰かを置き去りにすることもしない。僕らスタッフも、パーソナリティも、リスナーも互いに信頼し合って良い関係が築けていると思います。
タイアップ枠が完売するのは、スポンサーも互助会員だから
森下:広告のお話もうかがわせてください。吉田さんは、2010年から11年間、営業職だったわけですが、広告主のニーズの変化をどう感じていますか?
吉田:2010年代の初めは、タイムやスポット広告がまだ売れていました。知名度の高いタレントが生コマーシャルを読むと、商品プレゼント企画に何千通もの応募が来たり。その後、番組内で広告主とのコラボ企画が行われるようになり、いまはSNSを絡めて動画を出したり、ライブ配信したりするようになっています。
森下:手間暇をかけて企画を考えるようになったということでしょうか。
吉田:そうです。広告主からは、「30~40代に50万回、広告を当ててほしい」といった明確なオーダーが来たり、広告効果をちゃんと報告しないと受け入れられないようになりました。
森下:「OVER THE SUN」では、どのような広告施策を行っていますか?
吉田:毎回、番組後半に5分ほど、広告主とのタイアップコーナーを設けています。一配信につき一社というルールで、おかげさまで今年配信分はすでに完売しています。
森下:広告枠がかなり先まで完売することは、なかなかありませんよね。
吉田:「OVER THE SUN」は、企業の宣伝担当者がリスナーで、番組が好きだからぜひ自社とのタイアップ広告企画を行ってほしいと番組にメールが来ます。担当者自らが社内で稟議(りんぎ)を上げる努力をして、予算を取ってくる。
森下:なるほど。広告主がリスナーと一緒に、番組を推している雰囲気がありますが、タイアップコーナーのフォーマットはどのように作ったのでしょうか?
吉田:一般にスポンサーコーナーは、番組のトンマナと合わせるのに苦労することも多いんですが、そうならないように、僕と営業担当、スーさん、堀井さんとで企画の相談をして作っています。リスナーにとっても得があるようにプレゼントを提供したり、広告主が嫌われそうなこともやらない。うまくバランスがとれていると思います。
地上波ラジオやPodcastに対して、広告主は、「機動力」や「パーソナリティとの距離の近さ」を期待されています。
日々の放送や配信でリスナーを裏切らないことの積み重ね
森下:「OVER THE SUN」の今後についてはどのようなことを考えていますか?
吉田:日々の放送や配信でリスナーを裏切らないことの積み重ね。それしかないですね。
森下:裏切らないというのは?
吉田:常に楽しい内容をお届けすることや、みんなが安心できる場所を作ること。全てにおいてですね。スポンサーさんもそうだと思います。
森下:全方位で取り組まれている感じが伝わってきます。
吉田:「OVER THE SUN」は、最初のころに、「エグゼキューション(仕切り)が大事」というメールを紹介しまして……、進行管理など、すべての進行をリスナーに見られているという意識があります。どこで何をするにも、細かいところまで楽しんでいただきたいと思っています
森下:「OVER THE SUN」のような番組は、再現性があるものなのでしょうか。
吉田:再現性はないですね。そもそも狙って作っているわけではないし、どうしていまのような番組になったのか、僕たちもよく分かっていません。40~50代女性がメインリスナーですが、その世代に刺さるコンテンツを作ろうと思って立ち上げたわけではないですし、前述したヒヤシンスを育てる企画もリスナー発です。運動会も番組内の話の流れから生まれたもので、全てにおいて狙って企画しているわけではない。第二の「OVER THE SUN」を狙って作るのは難しいのかなと思っています。
森下:Podcastならではの番組の作り方のほか、関係するみなさんと向き合いながら吉田さんが日々新しいことに取り組まれていることがよくわかりました。本日は貴重のお話をありがとうございました。