──小布施GO、未来を誰と、どうつくりますか?
dentsu Japan(国内電通グループ)は、重点領域を切り開く事例創出を担う役職として、グロースオフィサー(GO)を設置しており、2025年度には、各領域から7人が選出されています。本連載では、電通が掲げる「真の Integrated Growth Partner(インテグレーテッド・グロース・パートナー)」を体現するGOたちの、未来に向けての視点と思考に迫ります。
第1回に登場するのは、小布施典孝GO。Future Creative Center(フューチャー・クリエイティブ・センター)のセンター長も務める小布施GOが注力する「未来づくり」の仕事とは。そして、理想とする「一人ひとりが創造性を発揮できる社会」とは。

「未来づくり」という仕事
──小布施さんは、グロースオフィサーであるとともに、クリエイター100人が在籍するFuture Creative Centerのセンター長でもあります。最近はどのような仕事やプロジェクトに取り組んでいますか。
小布施:広告の仕事ももちろん多いのですが、最近は「未来づくり」とでも呼ぶべき仕事が増えています。例えば、「これからの日本のロールモデルになるような街をつくりたい」「日本の教育を変えるにはどうすればいいのか」「新しい旅の提案をしたいのだけれど、どうすればいいか」といった相談から、「スポーツ界に新しいヒーローを生み出したいが、どうすればいいと思う?」といった相談まで、大きな意思はあるのだけれど、どう仕掛けていけばいいのかまだわからないという段階から相談を受けるケースが増えています。
──そうした相談は、どのような企業や人から寄せられるのですか。
小布施:大企業やスタートアップの経営層の皆さんや、スポーツ選手やアーティストや有識者の方など、幅広くさまざまな方からの相談にのらせてもらっています。共通しているのは「未来を変えたい」という強い思いを持った人たちであることだと思います。彼ら・彼女らの野望に、僕たちは並走していると言ってもよいかもしれません。
──企業の経営層からも、そうした相談が増えているのは、なぜなのでしょうか。
小布施:企業の経営層の方々と話をしていると、課題解決型の発想にちょっと疲れているというか、そうではないアプローチを欲しているのではないかと感じることがあります。
会社や組織の中に課題を見つけようとすると、いくらでもあるのが普通なので、その課題を一つ一つつぶしていっても、マイナスがゼロにはなるけれど、ゼロがなかなかプラスになっていかない――そういった悩みを抱えている経営層が多いように感じます。そうした背景から、課題解決型の発想法とは別に、「ありたき未来にむけて何をするといいのだろうか」という未来創造の視点から、相談をしてくださる方が増えている実感があります。
──個々人の強い思いや未来創造の視点がプロジェクトの出発点となるのですね。
小布施:はい。数年前に視察に行った世界的に有名なデンマークのビジネススクールでは、これから自分が仕掛けていく活動を、自分の内発的動機と結びつけ、自分の言葉で語ることを大切にしていました。それを「クリアボイス」と呼んでいて、クリアボイスを持っているからこそ、さまざまなステークホルダーを、そして世の中を動かすことができる。そうした考え方をしていました。
実際、デンマークは世界競争力ランキングで世界1位でありながら、幸福度ランキングでも世界2位。このように強さと幸せを両立できているのは、一人一人がやらされているのではなく、意思をもって主体的に仕掛けている、ということが秘訣なのではないかと思いました。
正解のない時代になればなるほど、これまでの経験が通用しません。何が正しいのかわからないからこそ、むしろ自分の手で正しくしていくんだ、という姿勢こそが重要で、とすると、それほどの情熱を注げることは何なのか、そもそも自分たちや自社のモチベーションの源は何なのか、その内なる意思との対話から、未来に向けての企画が生まれてくる時代になってきているのでは、と考えています。

「プレゼンテーション」から「クリエイティブセッション」へ
──「未来づくり」の仕事の事例を教えてください。
小布施:北海道ボールパークFビレッジ(エスコンフィールドHOKKAIDO)の開発プロジェクトの仕事は、完成したスタジアムを宣伝する広告の仕事ではなく、どんなスタジアムにするのか、どんな街にするのか、どんな体験ができるようにするのか、そうした未来を構想するところから、ファイターズの皆さんと並走させていただいたプロジェクトでした。
新しいスタジアムをつくるにあたって、あるべき体験のかたち、施設のかたち、あるいは「北海道にできるスタジアム」として他の観光地やテーマパークとどう差別化するか、そして完成後も持続的に発展するためにどうすればよいのかなどを、ファイターズの皆さんと何度も議論させていただきました。まさに、広告の手前の、「未来づくり」から関わらせてもらった仕事だと思います。




──「未来づくり」の仕事の進め方は、広告の仕事とどう違うのですか。
小布施:広告の仕事は、クライアントから「ブリーフシート」をいただいて、それに沿って企画を考えて、「プレゼンテーション」という形で提案をするのが、これまでの慣習でした。これは、依頼者と提案者をしっかりとわける方法論ですよね。
けれども、「未来づくり」の仕事というのは、広告表現制作とは違う、もっと手前の領域なので、輪郭がぼんやりしているところから始まることが多いです。だから、依頼と提案を明確に線引きすることが難しい。なので、その場で問いと答えをいったりきたりする、概念と具体をいったりきたりする、意思と合理をいったりきたりする、そうした往復運動を一緒に行っていく中で、未来に向けての企画を練り上げていくという仕事の進め方になってきています。
ということは、その一緒に考える場のクオリティが、そのまま企画のクオリティになってくる、ということなので、いわゆる普通のワークショップとはまたちょっと違う、「クリエイティブセッション」という独自の方法論を磨いています。つくり方をつくる挑戦です。
──クリエイティブセッションについて、もう少し詳しく教えてください。
小布施:よくある普通のワークショップは、面倒くさいわりに、あまりいい企画が生まれないイメージがありませんか? 企画を出し合って、グルーピングして、ポストイットを貼って、多数決で決めて……これだと結局、企画がはじめに出している企画以上のものになっていない、という問題を抱えていると思うのです。
ですから、僕らが行っているクリエイティブセッションは、参加者みんなで対話をしながら、アイデアを「重ねていく」ことを重視しています。みんなで重ねていくことで、一人では到達しなかった高みに企画を昇華させていくというやり方です。
そのためにも、まずはそのセッション自体を、即興舞台芸術の場だと捉えるところから始めます。その時、その場所、そのメンバー、その空気の中からしか生まれない企画をつくっていく――そうした場の捉え方です。
企業秘密でもあるので、それ以上のことはあまり言えないのですが、体験された方はみなさん、良いのか悪いのかわかりませんが、「楽しかった!」と、熱量高く言ってくださいます(笑)。でも、それはとても大切なことで、緊張感漂う、ピリッと張り詰めた空気の会議室の中からは、未来に向けてのワクワクする企画は生まれてこないと思うんです。最近は会議室から離れるために、固定観念を取り除いたり、発想のストレッチをしたりするのに適した小旅行を組み合わせたプログラムも実施しています。


──クライアントに企画を提案するのではなく、クライアントと一緒に企画を生み出すのですね。
小布施:はい。もちろん企画の最終的な仕上げは、プロとして僕らがしっかり作り込みますが、企画の種は一緒にみつけます。ちなみに、よくよく考えると、経営企画、事業企画、商品企画、人事企画、アクション企画……「企画」という言葉がついた領域は多くありますが、企画のつくり方を習う機会は意外とないのではないでしょうか。先日も、経営者の方が「うちの経営企画は、経営整理にとどまっているかもしれない」とおっしゃっていて、下から上がってきた数字をまとめているだけで、未来に向けての打ち手を企画できていないかもしれない、と危機感を持たれていました。なので、僕たちがやっていることは、クリエイティブセッションを通して、皆さんと一緒にやりたいことを出し合い、みんなでアイデアを重ね、そこに僕たちのクリエイティビティを掛け合わせて、未来に向けての企画をつくりあげていくことなんだと思っています。
そして、もう一つポイントだと思っているのが、この場を通じてできあがった企画は、「電通さんから提案してもらった企画」ではなく、「自分たちが生み出した企画」になっていくことなんです。自分たちの内側から生まれたものだからこそ、そこに愛情がのってくる。この企画を実現させたい、そのためにプロジェクトを前に進めたい、そうしたモチベーションが大きくなり、クライアントさんの社内での大きなうねりになっていきます。そう考えると、もしかしたら「企画は広告会社だけでつくるもの」という考え方自体が、もはや古いのかもしれません。関わる人みんなが自分ごと化できる作り方をすることで、大きな求心力を持たせられるのではないかと感じています。


──みんなの気持ちを一つにするクリエイティブセッションは、企業の中から変革を起こすための手法にもなりそうですね。
小布施:そう思います。クリエイティブセッションは、社長と役員の皆さまとで行うことが多いのですが、「会社の未来について、こうした形でみんなと自由に考える機会って、実はこれまでなかったんです」という感想をいただくことが多いです。おそらくその背景にあるのは、多くの企業にまん延している「課題分割病」なのでは、とにらんでいます。企業が直面している課題を細分化して、役員に振ることによって、役員の方々が自分の担務領域の視点しか持てなくなる。故に、組織がどんどん縦割りになる。タスクと数値目標だけが現場に振られ、こなす仕事が生まれていく。結果、「未来をこうしたい!」というWILL(意志)がない状態になってしまう。もしこういう状態が会社の中で起きている場合には、その企業の「未来のありたき姿と打ち手」を、みんなで「統合的に構想」し、変革の種火を生み出すクリエイティブセッションというものは、大きな意味を持つ、と思っています。



──最近は、このようなクリエイティブセッションの仕事が多いのでしょうか。
小布施:そうですね。このクリエイティブセッションを起点にして、企業価値向上にむけてのブランディング・コミュニケーションであったり、アクションやエクスペリエンス開発、インナーアクティベーションのプロジェクトだったりへと進んでいくことが多いです。やっぱり最終的なアウトプットに関わっているからこそ、人の心を打つにはどうすればいいのか、人の心を動かすってどういうことなんだろう、ということへの肌感覚を常に磨き続けることが出来ていると思っていますし、その感覚をもって抽象的な戦略の議論もできる、というのは強みになっていると思っています。
一人ひとりが創造性を発揮できる社会へ
──今、注視している社会の変化や課題はありますか。
小布施:一緒に仕事をしているチームのみんなとは、社会全体が効率化や合理化の方向に進みすぎていて、人間の創造性が失われつつあるのではないか、という話をよくしています。物事を効率的に進める「システム化」は、正しいことである一方で、そこに関わる人の楽しさを奪い、新しい発想を妨げるものになってしまうと良くないですよね。もっと一人ひとりが主体性を持って、創造力を生かせるような社会をつくっていけないか。そうすれば、そこで暮らす一人ひとりが、もっともっとWell-being(ウェルビーイング)でいられる未来になるのではないか、そう考えています。
──「創造力を生かせる社会」とのことですが、創造力やクリエイティビティをどのようなものと捉えていますか。
小布施:僕は、「クリエイティビティ」とは「画一性」の対極にあるものだと思っています。画一的な世界はイメージでいうなら、なんだろう……例えば最近、駅に降り立った時に街の風景がどこも同じに見えるんですが、そのイメージに近い感じでしょうか。あらがえない大きなシステムの一部に人間が組み込まれてしまって個性を発揮できないでいる状態――そうした状態を変え、一人ひとりが意志を発露できる社会をつくることができたら、それこそが「創造力を生かせる社会」なのではないかな、と考えています。
クリエイターというと何か特別な能力を持ってアイデアや表現を生み出す人のことを指すと思いがちですが、これからの時代は、「こんな未来をつくりたい!」「こんな社会をつくりたい!」というクリアボイスを持って、主体的に生きていく人全員がクリエイターなのではないかなと思っています。だから、僕たちは意志ある経営層の方々もクリエイターだと捉えていますし、もっと言うと、子どもたちなんてもう根っからのクリエイターですよね。
余談になりますが、僕は仕事とは別に私的な活動として、園児や小学生に「企画する楽しさ」を体験してもらうプログラム「きかくのがっこう」を定期的にサポートしています。そこで印象的なのは、「あ、ひらめいた!」というアイデアが降ってきた瞬間に、子どもたちの目が、急にキランと輝き始めるマジックモーメントがあることなんです。そうすると、そこから急に子どもたちは夢中になって紙にアイデアを書き、絵を描き、自分の思いついたことを思い思いに表現するんです。アイデアが降ってきたのをきっかけに、前に進もうとする力が湧き出すんですね。

実はクリエイティブセッションをしている時の経営層の方々も同じなんです。アイデアが降りてきた瞬間に目がキランと輝いて、「やりたい、やろうよ!」と、どんどんと前のめりになっていく。そうした経営者や子どもたちの目がキランと輝く瞬間に何度も出会ううちに、そういうマジックモーメントを創造することこそが、企画をつくるということの本質なのではないか、と思うようになりました。
──最後に、「未来づくり」や「創造力を生かせる社会」といった取り組みを踏まえて、今後のご自身のグロースオフィサーとしての役割をどう考えていますか。
小布施:そうですね、電通はまさに今、広告会社から次のフェーズへと飛躍しようとしていますが、その中で僕がイメージするこれからの電通は、広告にとどまらず、世界をこう変えたい、と思っている方々の「未来づくり」に伴走していく会社です。僕らのチームが持っている、構想化、言語化、可視化、物語化、体験化という日本トップレベルのクリエイティビティとプロデュース力を、いろんな方々の思いと掛け合わせることで、世の中に大きなうねりを生み出していく。それが、より良い未来をつくることにつながっていけたら、とても意義のあることですよね。そうした未来づくりのためのたくさんの仲間を作っていくことが、自分のグロースオフィサーとしての使命なのかなと考えています。

クリエイティブセッションを通して、人々のクリアボイスを引き出し、未来をつくる。広告制作とは全く違うアプローチで広告会社の新たな可能性を示す小布施GOの思考と視点は、独創的かつ刺激的です。そんな小布施GOご本人のクリアボイスを伺ったところ、いろいろな企画の始まりになっている企画書をずらっと展示する「企画書博物館」をつくり、そこの館長になることだそう。そう語る小布施GOの目はキランと光っていました。
この記事は参考になりましたか?
著者
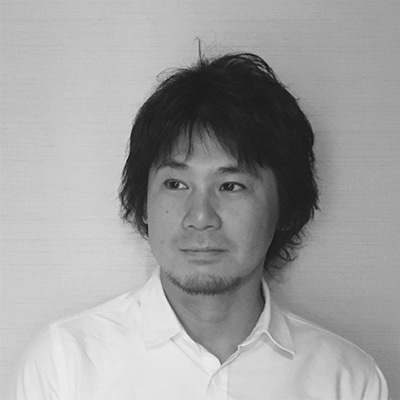
小布施 典孝
dentsu Japan /株式会社 電通
dentsu Japan グロースオフィサー/Future Creative Center センター長
さまざまな企業とのマーケティング/プロモーション/クリエイティブ領域でのプロジェクトに関わり、2020年、未来価値創造を支援するFuture Creative Centerのセンター長に就任。経営の打ち手のグランドデザイン、ビジョン策定、シンボリックアクション開発や、企業や事業の価値向上につながるブランディングやコミュニケーションを手掛ける。カンヌライオンズ2023金賞銀賞銅賞、ACC2024金賞銀賞銅賞、日本マーケティング大賞2024グランプリ受賞。その他、国内外の受賞多数。


