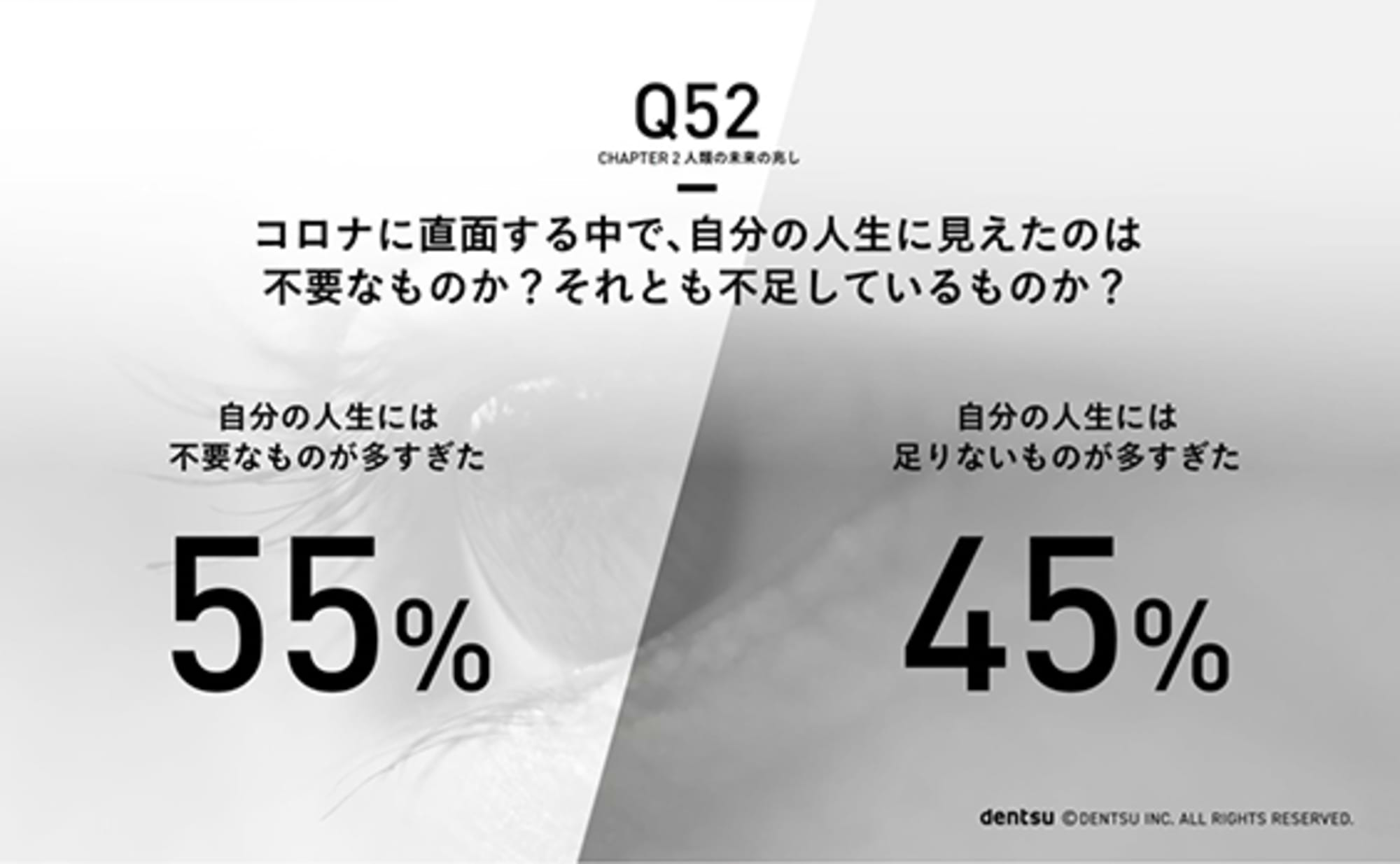企業広告の「目的」が見えてきた。 個人投資家時代のIRとは?

新NISAが浸透し、生活者にとってより身近になった投資。いまや日本の個人株主の数は延べ人数で8000万人を超えました。そして今後も、個人投資家の増加は加速していくでしょう。
電通は2025年、「IR-Branding360°」を開発・提供開始しました。電通が持つ「生活者マーケティング」の知見を個人投資家向けIRに活用し、コミュニケーションの戦略策定を支援するソリューションです。
電通、上場企業の個人投資家向けIRを支援するマーケティングサービス 「IR-BRANDING 360°」を開発・提供開始 - News(ニュース) - 電通ウェブサイト
本稿では、企業のIRブランディングに伴走する電通のマーケティング・コンサルタントの上西美甫氏と、ビジネスプロデューサー鹿川耕治郎氏にインタビュー。ソリューション開発の背景と、これからのIRの在り方を聞きました。
個人株主数は延べ8000万人超。企業と生活者の新しい関係

──お二人の自己紹介をお願いします。
上西:私はマーケティング・コンサルタントとして、主に生活者を対象としたマーケティングに取り組んできました。今回のプロジェクトでは、長年培ってきた生活者マーケティングの知見と、電通の持つアセットでもって、個人投資家の分析と、コミュニケーション開発を行っています。
鹿川:私はクライアント企業のパートナーとして、さまざまな課題解決に取り組むビジネスプロデューサーです。私の担当クライアントである日清製粉グループさんから、生活者とのコミュニケーションに投資家視点も入れたいとご相談を受け、上西のチームに声がけをしたことが、「IR-Branding360°」を開発する最初のきっかけになっています。
──マーケターやビジネスプロデューサーという職種のお二人が、IRという領域をサポートするのは意外な気がします。
鹿川:そもそも、電通がIRの支援というのも、ピンと来ない方がいるかもしれませんね。でも、この連載で詳しくお伝えしていきますが、これからの生活者とのコミュニケーションには、「投資」の視点が欠かせないと考えています。
というのも個人投資家、すなわち「生活者」が企業の多くの株を持つようになり、経営に影響を与えるようになっているのです。私もビジネスプロデューサーとしての立場から、クライアントの課題解決のために「IRを変えていきませんか」というご提案をさせていただくようになりました。
上西:そしてIRを生活者とのコミュニケーションと捉えるならば、電通には長年培ってきた豊富な知見があります。さまざまなデータ分析による生活者理解と、それに基づいて生活者に伝わりやすいコミュニケーションを開発するのは電通の得意とするところで、これらをIRの領域に拡張したのが今回の取り組みです。
──それではまず、個人投資家へのコミュニケーションを意識する企業が増えている背景を教えてください。
上西:日本取引所グループが、国内で株式を保有する個人投資家の延べ人数が8000万人を超えたという調査結果を発表しました。個人投資家の数は11年続けて過去最多を更新しており、新NISAの影響もあって投資のすそ野は広がっています。
企業によって異なりますが、私たちのクライアントでは、株主構成として、全体のだいたい10%前後から、多いところでは40%や、半数超を個人投資家が占めるケースもあります。いまや個人投資家は、あらゆる企業にとって見逃せない存在なのです。
また、近年、海外のアクティビスト(物言う株主)や、外国企業からの買収計画など、株主構成によっては企業経営に大きな影響が出るケースもありますよね。その点、個人投資家の中には、企業に愛着を持つ「ファン株主」と呼ばれる人たちもいて、長期で株を保有してくれたり、株価が下がったら買い増してくれたりする傾向があります。
つまり、株価の変動抑制や、買収のリスクを低減するためにも、ファン株主の獲得や個人投資家に向けた施策に力を入れ始めている企業が出てきているということです。
──個人投資家が増えることで、企業のIRにはどのような変化が起こるのでしょうか。
鹿川:伝えるべき情報、メッセージが変わります。これまで企業のIRは、多くが保険会社や投資信託会社、年金基金等の機関投資家に向けたものでした。そして機関投資家が企業を評価するときには、いわゆる「財務情報」を中心に見ていました。企業側の発信もやはり財務情報や経営戦略が大半です。
一方で個人投資家が注目するのは、「この投資が自分の生活とどうつながるか」です。今はまだ、自分の資産をいかに増やすかを重視している方が多いですが、新NISAの広がりによって個人投資家の行動も今後、変わってくると考えています。最初はローリスク・ローリターンの投資信託から始める方も多いですが、いずれ自分で銘柄を指名して買うようになっていくはずです。電通の調査でも、多くの人がインデックス系の投資信託を購入するところから始まり、だんだん個別株に投資するようになる推移が見て取れます。
そして、その時はよく知らない会社の株をいきなり買うのではなく、親族が働いている会社や仕事で関わっている会社など、まずは自分にとって身近な、応援したい会社に目を向けると思います。つまり、企業への「応援投資」の要素が次第に入ってくるのです。そこで重要になるのが「非財務情報」です。その企業を応援する気持ちを持ってもらうには、財務情報だけでは足りません。
上西:これまでIRにおいて、非財務情報は“付帯物”のように扱われてきました。非財務情報とは、企業が創出している価値や、行っている活動のうち、財務の数値としては表れていないものを指します。例えば持っている技術力や人材力、知的財産や、社会からのレピュテーション、環境に対する取り組みなども含まれます。
非財務情報は別の言い方で「未財務情報」といわれることもあり、いわば「財務指標に表れる前」の企業活動などを表す指標でもあります。これらは投資判断とはあまり関係ないと思われがちですが、のちのちインパクトを与えていくものもあるんです。
鹿川:財務情報の“背景”に、非財務情報があるということもあります。財務情報はただの数字ですが、その数字の背景には必ず企業や人間の意思や営みがあり、それをストーリーとして語ることで、生活者に共感が生まれます。これからはそうした情報も、投資判断に影響を与えるようになってくるということですね。
上西:機関投資家の間では、例えばインパクト投資のように、「財務的リターンと同時に、社会へのポジティブな影響を生み出すことを重視して投資しよう」という考えが広まっています。個人投資家にとっても、「企業活動を通じて自分たちが暮らす社会にいい影響を与えている会社かどうか」は投資の判断材料になってくるはず。そのため両者に向けて、非財務情報を分かりやすく魅力的に伝えていくことも、企業の重要課題となっています。
これからのIRは「成長戦略」を魅力的なストーリーで伝える

──企業コミュニケーションに、具体的には、どのような変化が起こっているのでしょうか。
上西:これまで分断されることが多かった企業広告を担当する宣伝部のようなチームと、メディア対応を担当する広報チーム、そしてIRなど投資家対応を担当するIRチームを、統合的にマネジメントする機運が高まっています。というのも、個人投資家へのコミュニケーションと生活者へのコミュニケーションは、かなり重なる部分があるからです。
私や鹿川は個人投資家のことを「生活者投資家」とも呼んでいますが、個人投資家は、生活の延長で投資をする「一生活者」でもあります。生活者に向けて、企業の価値をどう伝えていくかが重要になっていく。今後特に重要になるのが、企業広告の目的設定です。
鹿川:企業広告とIRというのは、少し結びつきにくいかもしれないので、掘り下げてお話をします。従来、ブランディングを目的とした企業広告は、「私たちはこういうことをやっている会社です」という、いわば自己紹介に近いものが主流でした。特にBtoB企業はそうなのですが、取引先や就活生といったステークホルダーに向けて、「自己紹介」をするのが、企業広告の在り方でした。しかし今後は、個人投資家という新たなステークホルダーに向き合う必要があります。
そこで、企業広告のメッセージは、「自己紹介」から「成長戦略」へと拡張していく必要が出てきます。個人投資家を味方につけるため、「これまでやってきたこと」を自己紹介的に伝えるだけでなく、「これからやろうとしていること」を分かりやすく魅力的なストーリーにして伝えることが求められるようになります。
そして、企業が発信する成長戦略では、「このくらい収益が上がるようになる」ということだけでなく、「この会社が成長すれば、収益とともに、社会が良くなる」ことを伝えなければなりません。電通グループでは「B2B2S」(ビジネス・トゥ・ビジネス・トゥ・ソサイエティ)を掲げていますが、これはクライアントが社会を良くするお手伝いを電通がするという文脈ですね。
──個人投資家というステークホルダーの存在を考えたとき、企業広告の「主な目的」が、認知や好意向上だけではなくなっていくということなのですね。
上西:はい。企業広告のKPIには今後、「認知向上」だけでなく、「投資意向」や「企業への期待度」も含まれてくるはずです。企業に対する「好き」「知っている」という評価だけでなく、「この企業は将来良くなっていく」という、未来視点を入れた指標も必要になる。つまり、企業コミュニケーションの成果指標がアップデートされるのではないでしょうか。
鹿川:企業はこれまで、自社の商品やサービスによって生活者から「選ばれて」きました。そして今後は、もう一つの選定行動が加わります。つまり、投資すること。単なる資産形成ではなく、生活者が「この企業は社会を良くしていくんだ」と考えて、投資をするという構図です。
上西:広告に限らず、企業のブランディング活動全体を通して、成長戦略をストーリーにして伝えることも求められます。これまでは、広報部、宣伝部、IR部署などが、従業員や投資家、一般生活者や取引先など、ステークホルダーごとにバラバラにメッセージを発信していました。企業のコアとなる価値はどこなのか。将来に向けて何をやっていこうとしているのか。これらのメッセージを、今後はより統一して考える必要があるでしょう。
──お二人が企業ブランディングやIRを支援している日清製粉グループの事例について教えてください。
鹿川:日清製粉グループは、国内の小麦粉の販売シェア(重量ベース)約40%を担う企業です。また食物繊維を豊富に含んだ高食物繊維小麦粉の開発なども行い、国内だけでなく、アメリカ、カナダ、オーストラリアなど海外でも大きな生産能力を持っています。日本の企業ですが、小麦粉が主食のオーストラリアでも、なんと生産能力ナンバーワンなんですよ。
私が日清製粉グループを担当することになって、これらの情報を知ったとき、個人的にも「世界の食を支える、こんなすごい会社が日本にあるんだ!」と驚き、ワクワクした気持ちになりました。「世界を舞台に食文化や食の未来を豊かにすること」。これこそが、日清製粉グループの「成長戦略」と言えると思います。
例えば、従来の投資家向けコミュニケーションは、「小麦粉で市場の40%のシェアを持つ」といった情報の開示でした。ここに「125年前から、小麦粉の安定供給により日本の食生活を支えてきた企業」というストーリーも併せて伝える。こうしたコミュニケーション設計は、クリエイティブと生活者コミュニケーションに取り組んできた電通ならではだと思います。
──非財務情報を魅力的に伝えることが、投資につながる。だからこそ、IR領域に広報・コミュニケーション視点を入れることで企業価値を上げていこうという提案なのですね。
鹿川:まさに、そういうことです。企業の成長戦略を、未来への期待感を持ったストーリーとして、分かりやすく伝えることができれば、その企業に投資をしたくなるし、企業を応援している自分を好きになれるし、日常生活の中での意識も変わってくるはずです。
「この企業が好きで、共感できるから、商品やサービスを買う」ということに加えて、「投資する」という選択肢が入ってくる。これが、新しい時代の企業コミュニケーションの形ではないでしょうか。
電通の生活者マーケティング知見をIRに活用すると?

──「IR-Branding360°」がどういうサービスなのか、詳しく教えてください。
鹿川:概観としては、全方位型のマルチステークホルダー視点で、企業コミュニケーションとIRを統合的にマネジメントするソリューションです。これを実現するために、電通の生活者マーケティングの知見を活用しています。まず、基点となるのが生活者理解です。
上西:企業はIR活動として、株主総会を開いたり、個人投資家向けにセミナーを行ったりすることもありますが、参加する株主は一部です。そのため、「自社の株を買ってくれたり、興味を持っている個人投資家がどのような人なのか」が見えていない企業が意外と多いという課題がありました。
IR-Branding360°は、電通が持つ生活者のビッグデータと、個人投資家に対して大規模に実施する調査結果をかけ合わせたデータから、
個人投資家の投資傾向別タイプ
各クラスターごとのペルソナ
各クラスターごとの投資ジャーニー
を分析・可視化できます。
電通のPeople Driven DMPなどのデータ基盤や、生活者のテレビ番組への接触と広告効果を可視化するSTADIAといったソリューションを活用することで、自社の株に関心を持ってくれている人の性別や年齢、趣味、価値観、投資の予算、投資家としてのタイプや、銘柄を知ってから購入に至るまで、どのメディアでどんな情報に接しているかなど、さまざまなことが分かります。
──投資家としてのタイプというのは、どういったものでしょうか。
上西:新NISAをきっかけに個人投資を始めた「新NISAエントリー型」や、商品や企業自体を応援するために株式を購入している「応援志向サポーター型」など、8つのクラスターに分けており、自社株の購入者にはどのタイプが多いかを分析可能です。調査・分析してみると、かなりくっきりとタイプが分かれていることに私も驚きました。各タイプごとのペルソナやジャーニーだけでなく、どの層にどのくらいボリュームがあるのかも分かります。

上西:ここにさまざまなデータをかけ合わせることで、どのクラスターの人が自社の株を買ってくれているのか?このクラスターの人は、どういう趣味を持っていて、どの時間帯にどのテレビ番組を見ているのか?銘柄を知ってから購入に至るまで、どういうメディアに接してどういう行動をしているのか?といったことが分かります。
──分析結果はどのように活用されるのでしょうか。
上西:「このクラスターの人たちが、このくらい自社の株を買ってくれている」「銘柄を知ってから投資に至るまで、こんなメディアにこんなふうに接触している」ということが具体的に分かれば、その層に向けた効果的なメディアプランニングなど、個人投資家向けコミュニケーションの戦略を策定できます。
また、自社の株を買ってくれている個人投資家たちが、会社のどの事業に魅力を感じているか、どういうストーリーが“刺さる”かも、投資家タイプ別で分かるので、成長戦略を伝える方法や情報発信も、より効果的に設計できます。本ソリューションでは、分析を基にした情報発信はもちろん、統合報告書の作成に至るまでワンストップで提供しています。
鹿川:日清製粉グループさんのケースで、どんな分析をしてどんなコミュニケーション設計をしたかについては、別の回で詳しくお伝えします。最終的なアウトプットの部分だけ少しお話しすると、私たちは上記のような分析を基に、日清製粉グループさんのブランディングサイトと、IRサイトのリニューアルを担当しました。どちらも、広報部宣伝チームとIR・SR室の垣根を越えたご協力をいただいて実現したものです。
ブランディングサイトでは「自己紹介」よりも「成長戦略」を、個人投資家が共感できるような物語で見せる作り方にしました。「IRは、IRだけでは伝えきれない」というのが私の考えで、ブランディングだからこそ伝えられるストーリーや意思というものがあります。
一方IRサイトでは、図版やインフォグラフィックを活用し、UI/UXの観点を意識的に入れました。従来のIRは、多くの場合は機関投資家向けに作っていて、「リンク集」のような形になっている企業も多いと思います。また、正確な財務情報を発信することに特化していて、ある意味「無表情」なところがあります。そこに、広報・広告的な視点を入れていくことで、企業や経営者の「意思」が投資家に伝わりやすくなるという設計です。
>The Base of Life スペシャルサイト
https://www.nisshin.com/thebaseoflife/
>個人投資家の皆様へ
https://www.nisshin.com/ir/investor/
上西:企業のトップが持つ「意思」を投資家に伝えるのはとても大事なことなんですが、従来のIRのコミュニケーションだと意外と見えづらかった部分なのかなと思います。会社がこの方向に成長していくんだという意思も、投資家にとっては重要な情報になります。
──生活者が企業活動を応援したくなるようなストーリーとして伝える、それも広告や広報のコミュニケーションも統合して行う、という事例になっているんですね。
鹿川:最後に今日の話をまとめます。これからの生活者は、商品やサービスで企業を選ぶだけでなく、「投資対象」としても企業を選ぶようになっていきます。投資が身近になり、生活者と企業の関係が大きく変わる中で、IRの考え方も、企業広告の考え方も変わっていかざるを得ません。従来は「いろんなステークホルダー」に向けてバラバラに行っていた施策が、これからは一つのストーリーを中心に一貫性を持って行うものになっていくと私たちは考えています。
今後、ますます生活者が企業に投資するようになっていく中、私たち電通は生活者マーケティングの知見を強みにしながら、クライアントの企業コミュニケーションをサポートしていけたらと思います。

※掲載されている情報は公開時のものです
この記事は参考になりましたか?
著者
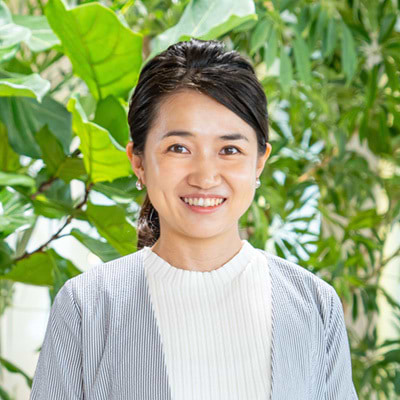
上西 美甫
株式会社 電通
第3統合ソリューション局
シニア・ソリューション・プランナー
電通入社後、大手電機・住宅・食品メーカー、流通、スタートアップ等の営業担当を経て、2016年よりストラテジックプランナーとして活動。食品・飲料や化粧品など複数のクライアントのブランド戦略立案、コミュニケーション戦略立案の他、商品開発やサステナビリティコンサルティング等も実施。電通Team SDGs SDGsコンサルタント。
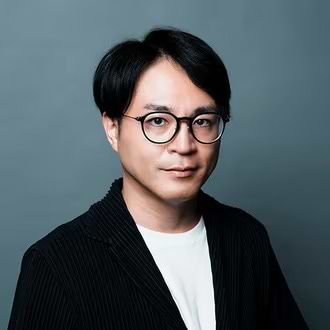
鹿川 耕治郎
株式会社 電通
第20ビジネスプロデュース局
統合マーケティング・プロデューサー
美術大学でデザインを学び、その後大学院でメディアアートを学ぶ。入社後はその経験を生かしながらも、マーケティング、プロモーション、キャンペーンプランニング、クリエイティブまでを経験し、現在は多領域で統合的にさまざまなプロジェクトを推進する。「本当に必要なことをカタチにする」がモットー。