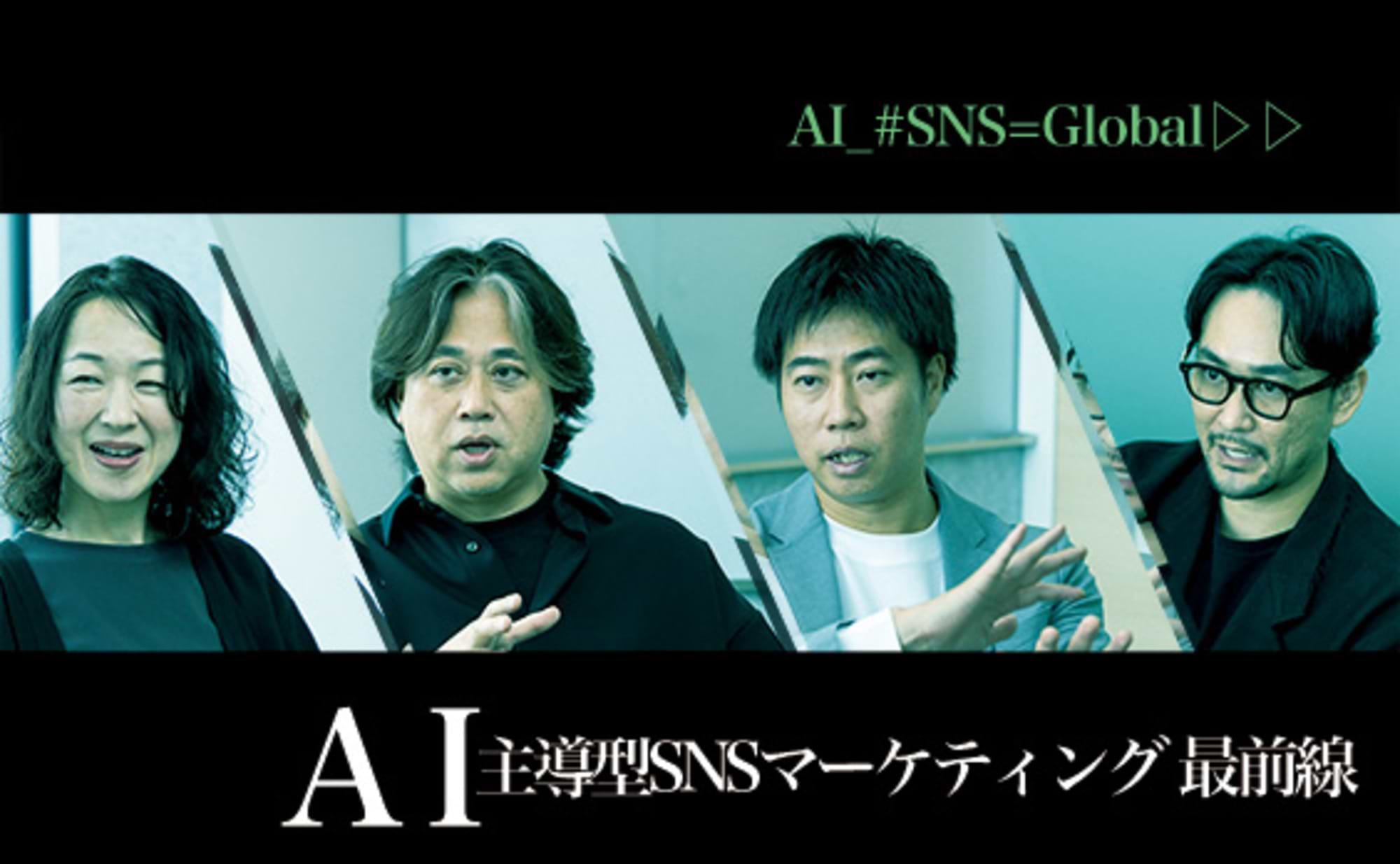Google Veo 3の衝撃。超進化する動画生成AIは、SNS動画施策をどう変える?

非常に速いスピードで進化し、近年ビジネスの舞台でも積極的に活用されている生成AI。
特に動画生成AIは、高い制作効率と無限の創造性、そして現実世界と見間違えるほどの精巧さにより、広告やマーケティング領域において大きな存在感を示しています。
今回は、そんな動画生成AIの中から、Googleの動画生成AIモデル「Google Veo 3(以下、Veo 3)」とショート動画施策の可能性に着目。
トヨタ自動車(以下、トヨタ)のグローバルSNS施策を担当する電通の伊豫田敏広氏と餅原創平氏が、Googleのグローバル営業チームとしてトヨタをサポートするランディ・ハン氏と、マーケティング領域における動画生成AI活用の可能性について語り合いました。
Journey on a whole different scale.
https://www.youtube.com/shorts/ln3UAkOs9c8
What rumbles but never crumbles?
https://www.youtube.com/shorts/rhPSf1GJ7Ew
もはやAIが生成したと気付けない?Google Veo 3の3つの進化ポイント

そんな中、2025年5月に行われたのが、トヨタと電通が参加したGoogle主催のワークショップです。そこで、同月に日本でローンチされたばかりだったVeo 3を試用させていただき、性能の高さとSNSマーケティング領域での可能性を強く感じました。
餅原:このワークショップについては、前世代のモデルであるVeo 2で制作した映像を見て衝撃を受けた私が、ランディさんにお声がけして、開催に至りました。ちなみにその映像はLaszlo Gaalというクリエイターがつくったものですが、本当に衝撃的な作品で、大きな話題を呼んだものです。
ランディ:もともとは「Veo 2のワークショップを」という話だったんですよね。ところがそのワークショップ開催の3日前にVeo 3が公開されまして(笑)。結果として、早い段階でVeo 3に触れていただくことができました。
Google Veo
https://gemini.google/overview/video-generation/?hl=ja
「Google Veo」は2024年5月に発表された動画生成AIモデルです。約半年後の2024年12月にVeo 2を、2025年5月にVeo 3を発表。約半年ごとという非常に速いペースでバージョンアップを行っています。
伊豫田:生成AIの進化のスピードを感じる話です。そんなVeo 3ですが、Veo 2と比べてどの部分が進化したのでしょうか?
ランディ:進化したポイントは大きく3つで、「物の動きを再現した動画生成」「複雑な演出への対応」「アクセシビリティの向上」です。
まず物の動きを再現した動画生成ですが、プロンプトで細かく指示しなくても、物理的な特性を再現して、より自然な動画を生成できるようになりました。例えばVeo 3は重力などの「現実世界の物理法則」も再現できます。水が流れ落ちたり、地面ではじける様子なども、簡単に生成可能です。また、プロンプトで「車が走る」と指示すれば、車が人間のように走るのではなく、車として正しく走行する動きを生成できます。プロンプトに対しての出力が、全体的に自然になっているんです。
2つ目は、クリエイターの創造の幅をより広げる、複雑な演出が可能になった点です。物の動きを再現したことで、ドローンショットやパノラマショットなどの高度なカメラワークが実現できるようになるなど、クリエイターが使いやすい機能が追加されました。
最後に、アクセシビリティの向上です。Veo 2まではあくまでも単体のツールでしたが、Veo 3ではGoogleのさまざまなサービスからVeo 3にアクセスできるようになりました。Geminiや、現在はアメリカのみですがGoogle フォトといったプラットフォームへの提供も開始しています。自由な発想を表現するためのツールとして、より多くのユーザーに使ってもらいたいという狙いです。
餅原:ワークショップでは、クリエイターの制作したデモ映像のクオリティの高さに衝撃を受けました。Veo 2の段階でも実写のような完成度だと思っていましたが、Veo 3はもはや実際に撮影した映像と比べてもほとんど遜色ない出来で、「プロンプトを打つだけでこのレベルの映像が作れるのか」と。
伊豫田:私が注目したのは、映像と音が同時に生成できることです。特に、音声に合わせて人の口が動く、「リップシンク」の精度の高さには驚かされました。音声の内容と人の動きの整合性も問題ありませんし、日本語の方言もプロンプトひとつで再現できるんです。
また、トヨタの動画施策で使うことを考えると、車のエンジン音や走行音の再現度の高さもうれしいですね。まだよく見ると細部に違和感がある場合はあるのですが、車が静止している映像や、細かい部分が見えない引きのカットであれば、十分なものを作ることができています。Veo 3ではすでに企業がSNS向けに活用できるレベルのものになっていると思いますね。
トヨタのグローバルSNSのコンテンツとして、Veo 3を使った動画制作はスタートしており、現在プロトタイプを公開中です。冒頭でご紹介した2つの動画ですが、トヨタのランドクルーザー300を主役に、「クッキーでできた荒野を走り抜ける」というユニークな世界観の映像と、反対に自然のエネルギーや雄大さを感じさせる、リアルで迫力のある映像となっています。どちらもプロの映像クリエイターが主にVeo 3を使って作ったもので、マーケティング観点でもすでに実用レベルになりつつありますが、さらなる進化も予感させます。
他のプロダクトと連携すれば、より簡単により良い映像を作れる

伊豫田:どんどん進化している動画生成AIですが、それをわれわれがどのように活用するのか、という課題もありますよね。餅原さん、制作側の視点から、いい映像を作るためのコツみたいなものはありますか?
餅原:やっぱり「プロンプトをどこまで的確に書けるか」だと思います。ただ、僕自身も、自分の持っているイメージを言語化できないことはあります。例えば「ドローンショット」という単語は、映像制作のプロでなければなかなか思い浮かばないですよね(笑)。ツールがどんなに進化しても、やはり使う人間によってアウトプットには差が出ます。
そういうときは、チャット型のAIアシスタントであるGeminiなど、他の生成AIにVeo 3用のプロンプトを作ってもらったりしています。また、Veo 3はテキストのプロンプトで指示を出す「Text to Video」だけでなく、他の画像や動画を読み込ませることで対象物を正確に再現できる「Image to Video」や「Video to Video」も有効で、私たちも動画生成に当たっては他のGoogleプロダクトを活用しています。そうすれば、制作経験がない人でも比較的簡単に動画生成ができると思います。
特にGoogleはクリエイティブのエコシステムがあり、VeoとGemini、まだアメリカのみですがGoogleフォトの画像からも動画生成できるということで、豊富なプロダクトを生かした制作環境が整っている点が魅力ですよね。
ランディ:「Text to Video」「Image to Video」といった制作プロセスは、生成AI時代にはじめて生まれた新しいやり方ですから、Google社内でも「Veoの使い方ガイドライン」が頻繁にアップデートされています。「こういうふうにプロンプトを書けばこれができる」というふうに、制作におけるノウハウを蓄積している最中です。
生成AIは進化のスピードが速いので、もし今後Veo 4、Veo 5が発表されたとして、今積み重ねたガイドラインやノウハウがそこで使えるかはわかりませんが(笑)。
餅原:自分たちで作ったプロダクトに関してのガイドラインを、実際に使いながら作っていくのって珍しいですよね。それが生成AIの大変さでもあり、面白さでもあるんだと思います。そして、進化の方向性としては、「ガイドラインが要らなくなる未来」を目指して進んでいるんですよね?
ランディ:そうですね、「ヒューマンクリエイティビティの拡張」を目指し、人間のクリエイティビティをより容易に、最大限に引き出せるように進化していくと考えています。Veoのプロンプトガイドラインについては、Googleクラウドのオフィシャルブログから定期的に公開していますので、興味のある方はご覧になってください。
https://deepmind.google/models/veo/prompt-guide/
https://blog.youtube/news-and-events/made-on-youtube-2025/
SNS戦略、今後のキーワードは「たくさん」と「映像の多様性」

動画生成AIがビジネスの領域に登場することで、企業のSNSマーケティングにおける投稿戦略なども変わってくると思いますが、いかがでしょうか?
ランディ:まず制作面については、動画生成AIによって予算や時間など、さまざまな制限が解決され、提案の数や幅が大きく広がるでしょう。
従来の映像作りとの違いについて、Veo 3でトヨタの動画をプロトタイピングしてくれたクリエイターは、
「場所や時間、天気など、いろいろな制限を気にせずに、『どう見せるか』『どう伝えるか』に注力することができる」
と言っています。予算的・時間的制限がなくなることで、これまで以上に多彩な映像表現が期待できるのではないでしょうか。
伊豫田:私も「映像の多様性」はキーワードになってくると思います。AIによって、これまで作れなかったものが簡単に作れるようになり、制作過程に存在するあらゆる制限がクリアになる。そういう環境の中で制作していると、「この発想はなかった」と思わされるものが出てきやすいんです。つまり、「誰でも作れる」ようになったからこそ、感性の部分で「その人にしか作れない」ものに価値が出てくる。
そうしたクリエイターのユニークな感性と、SNSのトレンドを掛け合わせ、動画生成AIが制作をサポートすることで、すごくいいものが作れるなと感じています。
また、動画生成AIによって映像制作のプロセスが短縮されることで、企画を重視し、より多くのアイデアを出すことができるようになるでしょう。その際に、膨大なアイデアをどう選定するか、どう管理するかは、今後考えていくべき部分です。1つ挙げると、スピード感が重要なSNS領域に関しては、「クライアントに企画を提案する工程」も簡略化を目指すべきなのではないかと考えています。
餅原:SNSにおいては、やはりショート動画が重要になっていくと思います。「短い動画をたくさん見る」という生活者行動が浸透している中で、企業も「短い動画をたくさん作る」という方向に動いているんです。
私たちが運用を担当しているトヨタのグローバルSNS施策では、365日SNSを運用していく上で、フォロワーの方とコンタクトにコミュニケーションを取り、よりブランドを知っていただくために、ある程度の投稿数の担保が必要になります。戦略的に本数と投稿頻度を計算しながら、 年間150本くらいショート動画を制作しています。
伊豫田:過去に「なぜそんなにたくさん作るのか?」と聞かれたことがあるんですが(笑)、個人的な答えとしては、単純にいろんなコンテンツがあった方が見ている人が楽しいから。そういうエンターテインメント性は、やはり数があってこそ成立するものだと思うんです。「数を作る」という部分では、制作効率の良さも含めて、動画生成AIの存在は大きいです。
餅原:それに加えて、「ヒューマンクリエイティビティの拡張」という面でも、生成AI活用は重要になってきます。SNS施策の目的として、動画を見た人に、ブランドやプロダクトのファンになってもらいたいという思いがあります。そのためには、そもそも見てもらえるような面白いコンテンツが必要ですよね。動画生成AIだからこそ実現できる、ユニークなアウトプットに期待しています。
伊豫田:ただ、先ほど挙げたように、「誰でも作れる」ことで映像が普遍化・陳腐化してしまうことは避けられません。そこにどうエッジを付け、個性を出していくかが、制作側としての課題です。先ほどランディさんがおっしゃっていたヒューマンクリエイティビティにわれわれも目を向け、生成AIで効率化をした分、人間はアイデアや企画の部分に時間を割いていくことが、今後重要になってくると思います。
ネガティブな面ともポジティブな面とも向き合いながら、AI時代の制作プロセスを模索

伊豫田:最後に、これからの動画生成AIの在り方、そしてわれわれの関わり方についてお話をできればと思います。まず、Veoの今後の展望についてはいかがでしょう?
ランディ:今日何度かお話ししたように、Googleはより多くの人が自由な発想のもとで多彩なクリエイティブを生みだせるよう、より良いツールを提供していきます。
そのうえで、Veoについては、ビジネス領域だけでなく一般ユーザーにも使っていただきたいという思いから、アクセシビリティの向上と、ユーザーベースの拡大を進めています。
また、電通をはじめとする企業やクリエイターから、使用感、機能面などについてフィードバックやインプットをいただきながら、Veo 4、Veo 5と進化させていきたいです。
餅原:動画生成AI全体としては、「たくさん作る」という今のSNSの環境と、「制限を気にせずいろいろなものを簡単に作れる」という動画生成AIの特徴がうまく掛け合わさって、いろいろ試せる時代になったなと思います。今後、動画生成AIを使った映像制作はさまざまな領域で増えていくと思います。その未来がすごく楽しみですね。
ただ、生成AI活用における著作権や肖像権といった権利の問題は非常に重要で、クリエイティブ業界全体の課題だと思います。Veo 3では、企業用には権利関係の保証が用意されていますよね。そういった部分にも企業としてきちんと向き合いつつ、面白いものを作るためにどうバランスを取っていくか、考え続けていきたいです。
伊豫田:私は、とある海外クリエイターが言っていた「この時代に生まれてよかった」という言葉がすごく印象に残っています。広告業界にとって、動画生成AIはネガティブな存在に見えるところもあるかもしれませんが、効率やヒューマンクリエイティビティなど、ポジティブな要素がとても多いんです。
そこをいかに理解して、パートナー企業と手を組んで前向きに進めていくかといった制作プロセスを、電通としてもしっかりと考え、適切なやり方を模索していきたいですね。
AI主導型SNSソリューション「VERTICAL」
電通、電通ライブを含む、複数企業によるコンソーシアム型プロジェクト。SNS領域の本質課題に向き合い、強力なプレイヤーと、クライアント、ユーザー、コミュニケーション観点を深く理解しながら、垂直統合型で瞬発力をもって一気に推進する取り組みです。
関連記事:
「いいね」すらタップしないユーザーが増加中!?ショート動画の“三原則”を知る
「AI×SNS」で世界中のファンを獲得する!SNSグローバル戦略、最前線
※掲載されている情報は公開時のものです
この記事は参考になりましたか?
著者
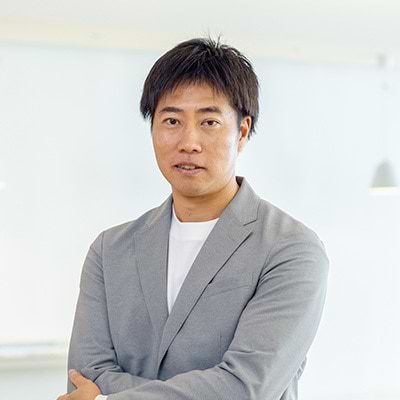
伊豫田 敏広
株式会社 電通
第1ビジネスプロデュース局
電通東京での海外スポーツエンターテインメント事業と海外メディア事業の経験を生かして、駐在したタイとインドの電通拠点で同領域のビジネスを開発。帰任後、トヨタ自動車のグローバルSNS施策やスポーツ施策を中心に取り組む。
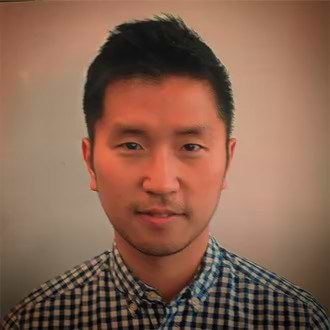
ランディ・ハン
グーグル合同会社
Googleでは欧州、韓国、日本を中心に、CPG(消費財)、ファッション小売、テック、自動車など幅広い業界のグローバルトップクライアント向けにAI、テクノロジー、メディア領域のパートナーシップ推進に携わる。Googleの主要30社のグローバルクライアントとの協業を通じて、ビジネス成長とイノベーションをけん引し、パートナーシップの構築・拡大を中心に取り組む。