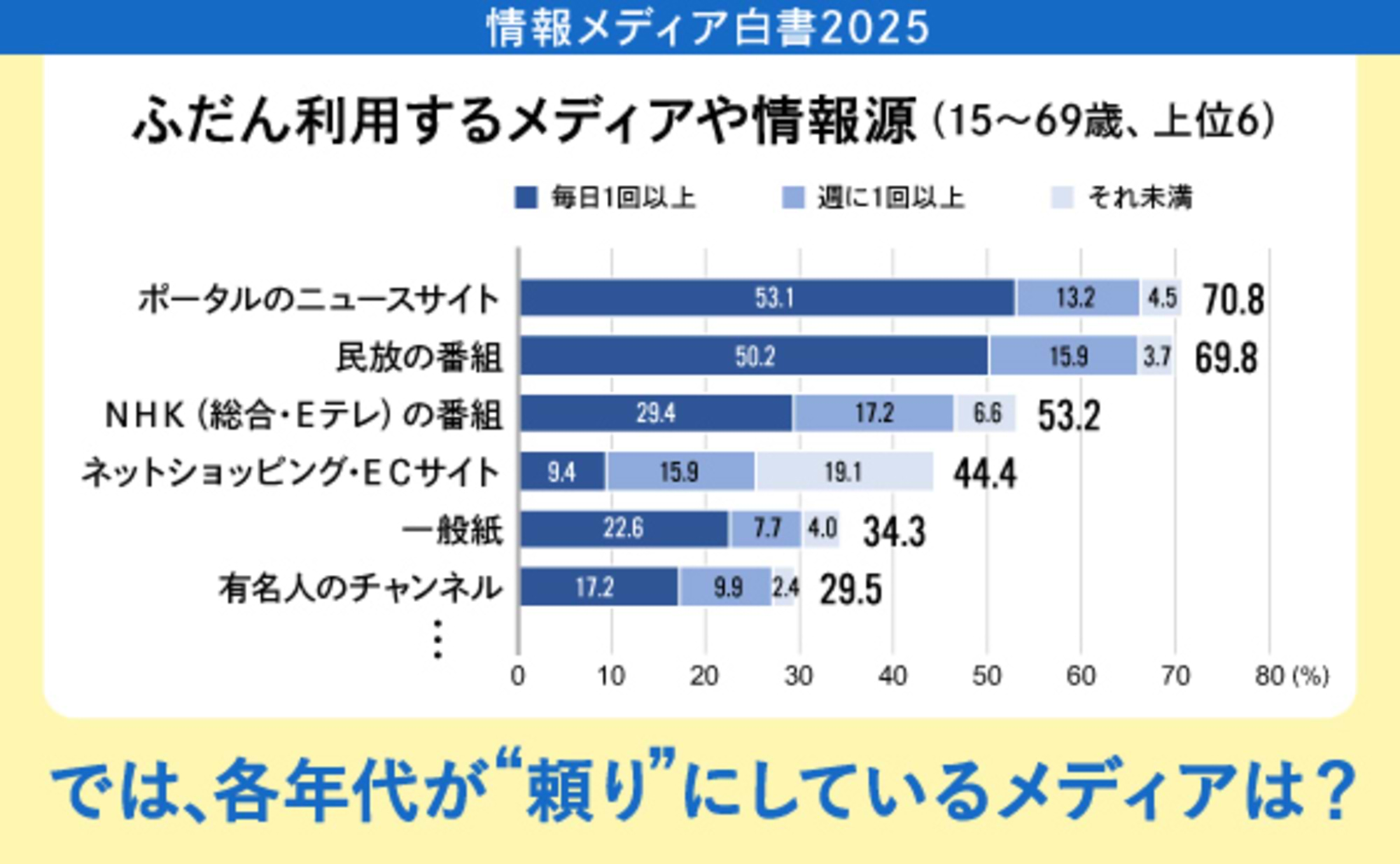約半数に“推し”がいる時代、広告・マーケティングに必要な視点とは?
「情報メディア白書2025」(電通メディアイノベーションラボ編、ダイヤモンド社刊)が4月23日に発行されました。情報メディア産業の全貌を明らかにするデータブックとしてまとめられた本白書の発行は、今年で32年目となります。
巻頭特集の「メディアの大変革期、未来を形作る新たなコミュニケーションの地平」では、情報メディア市場や人々の行動のトレンドを解説。本連載では、この巻頭特集の内容を一部を紹介します。
本稿では、2024年9月に電通が実施した「推し活」とメディア利用などに関する調査結果とそこからの示唆を解説します。「推し」の存在が与えるメディア接触への影響に加え、消費全般やウェルビーイングなどの生活への影響をひもときます。
さらには「推し活」を取り入れた広告などのマーケティング・コミュニケーションがどのような効果があるのか、またそれらの「推し」のジャンルによってどういった差異があるかなどについて考察。メディア、クリエイティブ、プロモーションなどの広範なプランニング領域で有効と思われるデータを、電通メディアイノベーションラボの長谷川想が解説していきます。
約半数に“推し”がいる!「推し活」の広がりの実態
近年注目を浴びている「推し活」。近頃はコンテンツやキャラクタービジネスの視点だけでなく、推し活の熱量に期待し、消費の拡大などを目的とした、マーケティングの観点やウェルビーイングの観点からなどでも語られることが多いと感じます。
「推し活」が広まりつつある背景のひとつとして、動画配信・共有サービスやSNSの利用普及など、メディア環境の変化がよく指摘されます。動画配信・共有サービスの多くは自らの趣向に合った動画をいつでもどこでも視聴可能にしています。またSNSは、「推し」に関するコアな情報を日々アップデートすることを可能にし、さらには自己表現の場や、同じ「推し」の仲間とのコミュニティ的な役割を果たしています。
このようにメディア環境の変化と「推し活」は密接に結びついていると言え、特に若者のメディア利用行動の理解を深める上で、「推し活」の実態を知ることは重要になりつつあります。
今回の調査ではまず、「推し」の有無を質問し、無いと回答した回答者にはさらに、「ファンや応援している人・もの」の有無を質問しています。その際に対象として、アーティスト、アイドル、スポーツ選手やチーム、芸人、タレント、俳優、YouTuber、インフルエンサー、VTuber、作家、映像作品、漫画、小説など広く例示を行っています。
その結果、「推し」があるとの回答率は37.8%となりました。また「推し」はいないと回答したものの、「ファン・応援している人・もの」(以降「ファン」と記載)はあると回答した回答者を加えると、合計では47.0%となり、「推し+ファン」は、全体の約半数に及ぶことがわかりました。
図表1は、性年齢別に「推し」と「ファン」の有無を示したものです。

図表1を見ると男性より女性、中高年層よりも若年層が、「推し」、「推し+ファン」ともに多くなっています。特に女性15~29歳では、4分の3以上が「推し+ファン」があると回答し、最も少ない男性50~69歳でも3分の1弱があると回答しています。「推し」や「推し活」という言葉そのものは若年層により浸透している状況もあり、前述の通り動画配信サービスやSNSなどのメディア接触状況と密接に関係しているとも考えられます。
“推しジャンル”の上位はアーティスト、スポーツ関連、日本のアイドル。年代で傾向に差も
図表2は、性年代別の「推し」のジャンル(複数回答あり)をまとめたものです。(以降、「推し+ファン」を統合して、「推し」と表記)

全体では、「アーティスト・ミュージシャン・音楽家」「スポーツ選手・チーム(野球・サッカーなど)」「日本のアイドル」の3つのジャンルで回答率が高くなり、3つとも複数回答ありで13%を超えました。(「最も推し」としての単一回答でもいずれも7%超え)
それ以降には、「アニメ・漫画のキャラクター」、「日本の俳優、女優、タレント・モデル」、「YouTuber・VTuber」、「アニメ・漫画・小説などの作品」、「国内外で人気のキャラクター、ゆるキャラなど」、「海外のアイドル(K-POPなど)」が続きました。
「推し」の名前について自由回答で質問したところ、ベスト10に、「日本のアイドル」が5つ、「スポーツ選手・チーム(野球・サッカーなど)」が3つ、「海外のアイドル(K-POPなど)」、「キャラクター」がおのおの1つ入りました。
その中で「スポーツ選手・チーム(野球・サッカーなど)」「日本のアイドル」は特定のチームやグループに回答が集まり、反対に「アーティスト・ミュージシャン・音楽家」は回答が大きく分散する傾向となりました。
なお1位はプロ野球の大谷翔平選手、2位は阪神タイガース、3位はSnow Manでした。
性年齢別でもう少し詳しく見ていくと、女性15~29歳は多くのジャンルで「推し」の回答率が高くなっています。また「アニメ・漫画のキャラクター」「ゲームのキャラクター」「ゲーム実況者」「YouTuber・VTuber」などは特に若年層で高く、中高年齢層では低くなるなど、年齢による傾向の違いが明らかとなっています。
一方、男女50~69歳では、「スポーツ選手・チーム(野球・サッカーなど)」や「アーティスト・ミュージシャン・音楽家」が高くなっています。このように性別による違いよりも、年齢による違いが顕著となりました。
“推しとの出会い”は「テレビ番組」が最多。「推し活」とメディア利用
以降は、特に女性15~29歳の支持を集めた8つの「推し」のジャンルを抜粋し、解説を行っていきます。図2の薄黄色で網掛けした6ジャンルに加えて、一定のサンプル(回答)数を確保した分析のために、「ゲーム関連(実況を除く)」(薄緑色2カテゴリー分)と「配信者・インフルエンサーなど」(薄青色7カテゴリー分)という合算したジャンルを設定した上での分析結果となります。
図表3はこういった「推し」を最初に知ったメディア(情報源)について尋ねた結果です「最も推し」として単一回答した結果に基づく)。

「テレビ番組」が最も多く、8ジャンルの中で比較すると「日本のアイドル」がテレビ番組で知った「推し」としてもっとも高い数値になっています。
テレビ番組での露出の多さが強く影響していると考えられますが、それ以外でもテレビ番組を通じて知ったとの回答が最多のジャンルが複数あり、テレビ番組が「推し」に出会うきっかけとして強い影響力を有していることがわかります。
一方「ゲーム関連(実況を除く)」や「配信者・インフルエンサーなど」は、インターネット動画がテレビ番組を大きく上回っています。さらに「海外のアイドル(K-POPなど)」も同様にインターネット動画が高くなっています。図表2で明らかになったような各ジャンルを「推し」としている年代構成ごとのメディア接触状況の差異や、当該メディアにおけるコンテンツの流通量が、「推し」を最初に知るメディアの違いに影響しているとも考えられるでしょう。
「国内外で人気のキャラクター、ゆるキャラなど」をはじめとして、SNS(タイムラインやトレンド)、口コミ(家族・友人・知人の紹介)が多くなっているジャンルもあります。SNS上では、トレンドやフォロワーの投稿、おすすめ投稿で知るケースも考えられますし、「推し」の口癖やダンスなどをまねた、いわゆる「ミーム」を通じたものも多く含まれていると考えられます。
また書籍、DVD、グッズなどとの相性が良いジャンルは、会話に登場しやすく、リアルな場での口コミを通じて知るケースも多いと考えられます。これらのデータは、コンテンツビジネスだけでなく、「推し」を使ったキャンペーンのプランニングに際して、有効なヒントになりうるでしょう。
「推しあり」と「推しなし」で、メディア接触時間には顕著な違い
「推し」の有無によって、メディア接触時間がどのように異なるのか、ジャンルごとにまとめたデータが図表4です。
集計の区分は、「マスメディア合計」、DVD・ブルーレイ、書籍(写真集も含む)などの「パッケージメディア合計」、音楽配信、動画共有、動画配信、SNSなどの「インターネットメディア合計」の3種類。この3区分について、1週間あたりのメディア接触分数を示しています。また、比較対象として「推しなし」の回答者のメディア接触時間も掲出しています。

図4に示した8つのジャンルすべてで、「推しなし」よりも、メディア接触時間が多くなりました。グラフを見て分かるとおり、接触時間の伸びの多くはインターネットメディアになっています。図表には示していませんが、この傾向はジャンルを問わない年代別の「推し」の有無による差異でも同様です。例えば最も差異が顕著な女性15~29歳では、メディア接触時間合計が「推し」ありでは3487分、「推し」なしでは1188分、インターネットメディア接触合計ではおのおの、2693分と775分になっています。
この傾向は今回掲出した8ジャンル以外でも同様です。おそらく多くの人が自宅外であっても、スマートフォンを通じて好きな時に「推し」の動画やSNSにふれられることから、インターネット接触時間が長くなり、結果としてメディア接触時間全体が長くなっていると言えるでしょう。
マスメディア合計では、「アニメ・漫画・小説などの作品」「アーティスト・ミュージシャン・音楽家」「日本のアイドル」を推す人々の接触時間が多くなっています。この結果はテレビ視聴とやや距離がある若年層の含有率が比較的高めのジャンルであっても、「推し」が登場することでテレビ番組の視聴が促されるという仮説の信ぴょう性を高めるものです。
一方インターネットメディア合計では、「配信者・インフルエンサーなど」と「海外のアイドル(K-POPなど)」が多くなりました。ライブ配信が多い、長時間のコンテンツが多い、視聴可能な動画コンテンツ種類が豊富なことなどから、インターネットメディア合計の接触時間が増えていると考えられます。パッケージメディア合計については、大方の想定どおり「アニメ・漫画・小説などの作品」が最も多い接触時間となりました。
では、具体的にどういったメディアの接触時間が伸びているのでしょうか。図表5は、全ジャンルにおける「推し」の有無で区分集計した、主なメディアの1週間あたりの接触時間となります。

「推し」の有無に関わりなく、テレビ(地上波・BS・CS)が最も長く、YouTubeがそれに続く接触時間となりました。一方「推し」の有無による接触時間の伸びを確認すると、X(旧Twitter)の伸び率がほぼ4倍と、最も高い結果になりました。
また、本図表では示していませんが、図表4で取り上げた8ジャンルをそれぞれ個別に分析した結果でも、X(旧Twitter)の接触時間はすべて「推しなし」の2倍を超える伸び率になることが分かりました。これは他のメディアにはない結果で、本稿の冒頭で立てた仮説を証明するものです。X(旧Twitter)は日々のコアな情報のアップデートやコミュニティ形成のための鍵となるメディアとして、大きな役割を果たしていると考えられるでしょう。
時間とお金の消費率が圧倒的に高いのは、「日本のアイドル」を推すファン
本調査では自由に使える時間とお金のうち、どれくらいの比率を「推し活」に投資しているかについても調査しています。その結果を「最も推し」のジャンル別にプロットしたものが図表6になります。

X(横)軸が時間、Y(縦)軸がお金となりますが、一見してわかるように「日本のアイドル」が他を圧倒して時間も金銭も投資している比率が高いとわかります。この結果を分析すると、下記の影響によって、時間比率が突出していると考えられます。
・さまざまなメディアに多くのコンテンツがある
・コンサートや握手会などのイベントといった過ごし方のオプションも豊富にある
また消費に関しても、コンサートやイベントなどへの参加費に加え、パッケージメディアやさまざまなグッズの購買も考えられます。ビジネスとして成熟した結果、そのすそ野が広がっていると想定され、消費額比率も高いのではないでしょうか。
時間比率の優位(グラフ右下方向)ジャンルとしては、「配信者・インフルエンサーなど」、「海外のアイドル(K-POPなど)」がプロットされました。これは、前節で述べたとおり、インターネットメディアの接触時間の長さが寄与していると思われます。
一方金銭比率の優位(グラフ左上方向)ジャンルには「アニメ・漫画のキャラクター」がプロットされました。これにはフィギュア、アクリルスタンド、クリアファイル、缶バッジ、ぬいぐるみなどさまざまなグッズなどを扱うマーチャンダイジングのすそ野の広さが影響していると考えられます。
時間比率優位なジャンルは、「推しと同じ空間・時間を共有したい」「あの瞬間の感動が忘れられない」「ファンの一体感を味わいたい」といった気持ちが強い傾向があり、いわば“フロー型推し活”と呼べるでしょう。
一方金銭比率優位なジャンルは、「自分の好きな空間を推しで満たしたい」「コレクションが増えていくのがうれしい」といった気持ちが強い傾向があるとみられ“ストック型推し活”と呼べます。
また「いつでも推しを感じていたい」といった心理は、インターネット動画の視聴のような時間消費で満たされることもあるでしょうし、グッズを購入して手元に置くような金銭消費で満たされることもあると言えるでしょう。
“推し”の広告起用がファンにもたらす影響の実態は?
図表7は、「推し」が広告に起用されることで、その商品やサービスに関して、どういった気持ちになるかの質問に対する回答結果になります。

8ジャンル以外も含めた全体を通して、「商品・サービスの広告をすべて最後まで見聞きする」、「商品・サービスを意識するようになる、目にとまるようになる」、「商品・サービスに興味・関心がわく」などの認知や興味喚起のスコアが高くなりました。これはわかりやすい広告効果と言えるでしょう。
「日本のアイドル」は、「推し」のすそ野も広く、広告の視聴や注目に効果があると確認できます。一方「アニメ・漫画・小説などの作品」は、「商品・サービスを詳しく調べたくなる・問い合わせたくなる」に加え、「商品・サービスを欲しくなる・利用したくなる」という項目で特に高くなりました。アニメ作品などとの企業のタイアップキャンペーンが多く実施される今日、調べたい、購入したいなどの行動喚起にきちんと効果があることが確認できました。
さらに、キャラクター関連のジャンルについては、多くの項目で上位になっています。日本はかねてよりキャラクター文化が根付いており、自治体などの「ゆるキャラ」も含めてキャラクターが多くの場面で活用されていますが、広告やマーケティングにおいても、幅広い効果があると言えるでしょう。
今回の調査では、「推し」が起用されたキャンペーンや広告などについて、印象に残ったものを、その理由とともに自由回答で質問を行っています。「推し」が起用されている商品やサービスへの好意度が高いことはもちろん、熱量のある回答の中には、トラブルがあったときでも「推し」の広告起用を中止しなかった企業に対して、企業そのものに感謝するような回答も複数ありました。
SNS上では、個人のものも企業からのものも、その投稿などは同じタイムライン上に表示されますが、企業のスポンサーシップも「推し活」と同じように考えることもでき、自らの「推し」を推す企業は、“同志”や“同担”のような見え方になっているとも考えられます。
生活者の興味関心やメディアが細分化し、商品の多くがコモディティ(汎用)化する中、マーケティング・コミュニケーションを展開していく上では、リーチだけを追求すれば良いという時代は過去のものになりつつあります。
その状況に対するひとつの解として、企業自体が「推し活」の視点を取り入れてみてはどうでしょうか。広告に起用するといった視点をアップデートし、企業として「推し活」に参加するという考え方でプランニングを行うということです。それが単発ではなく持続的であれば、企業への共感が誘発され、さらにはその共感がSNSなどを通じて好意的に拡散していくかもしれません。
冒頭にも述べましたが、「推し」もしくは「ファン」がいるとの回答率は47.0%となりました。また「推しがあることで、日々の生活が楽しく、充実して感じられるようになった」という人は、65.5%に上ります。つまり、生活者の3分の1が、「推し」によってポジティブな生活を感じているということです。
今回「推し」に注目した理由のひとつに、一部で広告が嫌われ者になっているような風潮がある中、「メディア、コンテンツ、広告との幸せな関係」を再構築する役割を「推し活」が果たしうるのではないかとの仮説がありました。まだまだ検証の途上ですが、紹介してきたデータなどを、マーケティング・コミュニケーションやコンテンツビジネス領域などでのプランニングのヒントにしていただければ幸いです。
【調査概要】
調査時期:2024年9月
調査手法:ウェブ調査
調査エリア:全国
サンプルサイズ:4,925(SC調査)、1,374(本調査:「推し」あり)、720(「推し」なし)
対象者属性:男女15~69歳
分析における各ジャンル(「最も推し」)のサンプルサイズ
日本のアイドル:232
海外のアイドル(K-POPなど):88
アーティスト・ミュージシャン・音楽家:216
アニメ・漫画のキャラクター:113
アニメ・漫画・小説などの作品:41
ゲーム関連(実況を除く):51
国内外で人気のキャラクター、ゆるキャラなど:55
配信者・インフルエンサーなど:109
※掲載されている情報は公開時のものです
この記事は参考になりましたか?
著者

長谷川 想
株式会社 電通
電通メディアイノベーションラボ
メディアイノベーション研究部長
国内通信キャリアにて、情報メディアサービスの開発・運用などに従事後、株式会社電通に入社。主にメディアプランニング、デジタルマーケティングを担当したのち現職。 情報行動、メディアビジネス、広告媒体開発、ローカルメディアなどに関心がある。 学際情報学修士。日本マーケティング協会マーケティング・マイスター

電通メディアイノベーション・ラボ
株式会社電通
電通の長年のメディア・オーディエンス研究実績を背景に、2017年10月に発足。多様化する人々の情報行動の変化を捉えメディア社会の全体像を見通すための調査研究・情報発信や、その中で求められる企業のコミュニケーション活動の在り方について提言やコンサルティングなどを行っている。