電通発行の書籍『表現の技術』(髙崎卓馬著)、『発想の技術』(樋口景一著)、『言葉の技術』(磯島拓矢著)。CMプランナー(髙崎)、コミュニケーションデザイン・ディレクター(樋口)、コピーライター(磯島)と専門分野の異なる書き手による“技術シリーズ”3作は、広告関係者以外からも普遍性のある技術論として評価を築きつつある。著者3人に共通しているのは、「考えること」の重要性を伝えている点。今回、「考える技術」をテーマに、各々の著作を振り返りながら鼎談を行った。
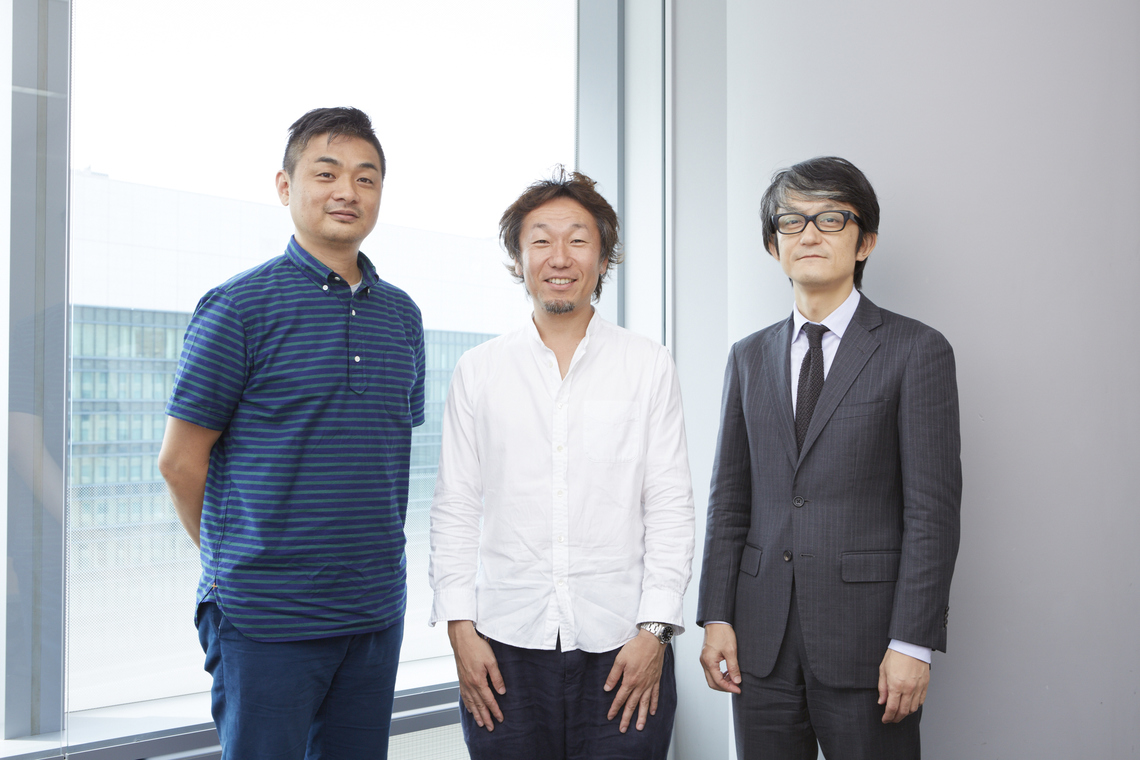
ある一点に向かって、3人とも登っている
髙崎:この本をつくるときは、こういうシリーズになることはあまり想定していなかったんです。だから間口を狭めたくなくてタイトルを大きく構えてしまいました。ここまでラインアップができると僕の本は「映像の技術」でよかったですね。技術というタイトルにしたのは、広告関連の書籍って何年かたつと猛烈に古くなるものがほとんどで。そうならないようにしようという思いが大きかったからです。メディアや世の中の変化にナーバスになってしまう僕らの弱いところをくすぐるだけではなくて、そういうものに動じない芯のつくり方を書きたかったんです。そういう意味では普通のことを書いています。普遍なものに近づきたかったからあえて。
樋口:なるほど。
髙崎:3冊読むと、不思議と似ていますよね。読後感が。映像というルート、樋口君は戦略のルート、磯島さんはコピーライティングのルート。それぞれルートは違うけれど、やがて山の標高が高くなると見える風景が基本的に似てくる感じというか。
 磯島:そうですね。
磯島:そうですね。
樋口:2人の本と恐ろしく似ているなと思ったのは、「結局、考えるしかない」ことに尽きるところです。戦略や企画の研修では、箱を埋めれば企画になるというフォーマット発想がよく見られるのですが、そこからいい企画は生まれない。企画そのものを考えずに、ショートカットして早くゴールに着こうとする状況を一度壊したくて、『発想の技術』ではアンチフォーマットな発想や企画の立て方を書きました。
磯島:コピーライターの場合、細かな技術は確かにあります。異性を誘うとき「デートに行こう」より「ピザとパスタ、どちらが食べたい?」の方が良い。なぜなら女性はどちらか選んでしまうから、とか(笑)。「白いスニーカー」は当たり前でも、「光るスニーカー」などハレーションを起こす単語を組み合わせると何かが生まれる、とか。こういう技術は具体的で使い勝手がいいけれど、それだけでは少し寂しい気もする。だから、考えを深めていった先に言葉がある、という思考の過程をたどる技術を『言葉の技術』では伝えたかった。
髙崎:『言葉の技術』のサブタイトルは、「思いつくものではない。考えるものである。」ですが、猛烈に共感します。客観力を持てるかどうかがこの仕事のスキルの背骨になる。どのルートで登ろうと、どういう表現手段を使おうと、それが実は全てだったりします。100%主観で作ることが許されるのは本物の天才だけですから。
作った人間にしか書けない技術がある
 髙崎:いろんな場面で講義を何年もやっていると、「あ、わかった!」という顔を相手がしてくれる瞬間があります。「人が理解した瞬間に自分もいろんなことが分かる」という感覚。プレゼンでも感じることがありますが、相手に伝わったという感覚が自分の思考を瞬時に深めてくれる時があるんです。僕の本は比較的そういう感覚があったものを整理して、一冊の読み物としての流れをつくるという宿題を自分に与えてまとめました。だからこの本のためにひねり出したものはひとつもなくて。
髙崎:いろんな場面で講義を何年もやっていると、「あ、わかった!」という顔を相手がしてくれる瞬間があります。「人が理解した瞬間に自分もいろんなことが分かる」という感覚。プレゼンでも感じることがありますが、相手に伝わったという感覚が自分の思考を瞬時に深めてくれる時があるんです。僕の本は比較的そういう感覚があったものを整理して、一冊の読み物としての流れをつくるという宿題を自分に与えてまとめました。だからこの本のためにひねり出したものはひとつもなくて。
樋口:同感です。僕は、一般企業の事業部などで研修を行っているのですが、それが勉強になっています。例えば、商品企画のノウハウは、あまり確立されていない。方向性のない中でブレストを行い、それぞれが勝手に発散しながら進めてしまいがちです。発散は必要だけど、“飛ばす”だけではなく“深める”方法論がないのは危険。どう方向付けをして、意味のあるアイデア出しをするのか。それを教えてきた経験が、『発想の技術』の元になっています。
磯島:研修や講義は大変だけど、引き受けた方がいいですね。先日、社内でクリエーティブ・ライティングというテーマをもらって、長い文章の書き方を教えたのですが、自分も予習をするでしょう? あれがいい勉強になる。ちょっとアドバイスするだけで劇的に良くなると、自分でも確信が持てるし。
髙崎:ずっと前に、長い文章を仕事で書いていたら「髙崎の文章は読みづらいなあ。時々単語をポンと入れてみたらいい」とコピーライターの伊藤公一さんに言われたことがあって。そのとき僕、開眼したんです。言葉を並べると文章にリズムをつくる必要が生まれる。そのリズムを使って人を引きつけていくことができるって。今も相変わらず悪戦苦闘はしていますが、それはずっと意識している。それ以降「リズム」は僕の仕事で大事な尺度になりました。映像の編集も同じ。人の目をつかむレイアウトも同じ。ページをめくる本もそう。2時間の映画の構成も。そう気が付いてから大きな武器になった気がします。そういう啓示を唐突にくれる先輩が周囲に結構いたんです。
 樋口:昔の方が、無茶苦茶な先輩がいましたよね。「今、書いているもの見せて。うーん、全然駄目」みたいな(笑)。ああいう“乱暴”さって、何かしらの経験に裏打ちされた技術的なバックグラウンドがあるからこそ言っていたように思います。“乱暴”な人がいなくなると、技術は意外と継承されないものなのかもしれない。
樋口:昔の方が、無茶苦茶な先輩がいましたよね。「今、書いているもの見せて。うーん、全然駄目」みたいな(笑)。ああいう“乱暴”さって、何かしらの経験に裏打ちされた技術的なバックグラウンドがあるからこそ言っていたように思います。“乱暴”な人がいなくなると、技術は意外と継承されないものなのかもしれない。
髙崎:そういう先輩たちのくれた啓示も、今の自分が言語化できる範囲で本の中に書いている気がします。
(中編に続く)



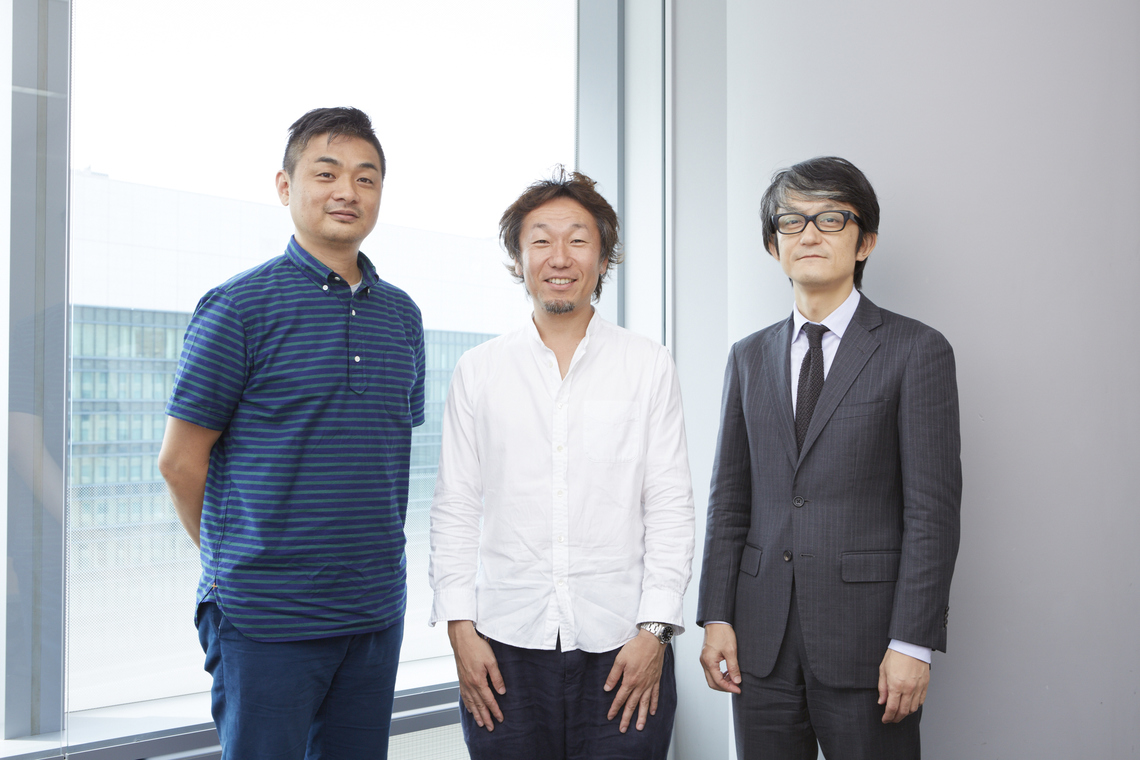

 髙崎:
髙崎: 樋口:
樋口:


