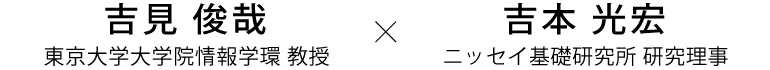(※所属は「アド・スタディーズ」掲載当時)
1964年の東京オリンピックは、日本の戦後復興と社会インフラの飛躍的な向上をもたらし、 先進国への仲間入りをアピールした。
本対談では、2020年東京オリンピックの文化プログラムにも深く関わっておいでの吉本光宏氏と都市論や文化社会学(カルチュラル・スタディーズ)などの研究をしてこられた吉見俊哉教授のお二人が登場。
すでに成熟期を迎え新たな課題をつきつけられている5年後の東京オリンピックには何が求められるのか、歴史を振り返りながら、その文化的な面からあるべき方向性をご提示いただいた。
1964年東京オリンピックの記憶
吉見:私と吉本さんは同年代で、幼い時に1964年の東京オリンピックを体験していますが、どのような記憶が残っていますか。
吉本:開催されたのは小学校に入学する前の年でしたが、私より1つ年下になると記憶がない人がほとんどですから、覚えているギリギリの年代と言えそうです。その中で、鮮明に覚えているのは徳島の田舎で母親と聖火ランナーを見に行ったということと、その時に配られたオレンジ色の冊子などですね。
吉見:私は円谷幸吉やバレーボールの「東洋の魔女」も覚えていますが、それは、あとから刷り込まれたものかもしれませんね。でも、脳裏によみがえるのは、テレビで見た閉会式です。いろいろな国の選手が入り乱れて入ってくる風景に驚きました。予想していた画面と実際の画面が違い、ものすごくカーニバル的な雰囲気がありましたから、ある種のナショナリスティックな固定観念がぐらつく経験をしていたような気がします。
吉本:それは、すごい記憶ですね(笑)。
吉見:私は東京育ちですが、同じ時期にできた駒沢競技場のことが思い出に残っています。代々木のオリンピック競技場はモニュメントとして注目されましたが、この駒沢公園は地域住民とのインターフェイスがとても良くできていたと思います。当時は高度経済成長に向けた開発一本やりという状況でしたが、駒沢で地域に親しまれる次の時代を見据えた公園が造られていたことは記憶しておくべきだと思います。
さて、1964年のオリンピックは、今から見ると必ずしもポジティブではなかった点を含んでいたと思います。その点についてはいかがでしょうか。
吉本:オリンピックを契機に高度成長の波が押し寄せたという印象が強く残っています。私の父親は徳島の県庁勤めでしたが、当時は四国の人にとって本四連絡橋を造ることが夢でした。徳島といえば阿波踊りですが、県庁の踊り連の名前は「夢のかけ橋連」で、浴衣や提灯にも大きな吊り橋が描かれていました。結果的には徳島と香川と愛媛に連絡橋が3つもでき、念願がかなったわけです。
もう一つは原子力発電所の誘致についての記憶です。夏休みの宿題で、父親が持ち帰ったパンフレットを見て、原理もわからないまま加圧水型原子力発電の絵を描いて提出したことがありました。結局、四国には愛媛県の伊方発電所しかできませんでしたが、原発や本四連絡橋はこれからの社会にとって負担は小さくない。時代の流れとはいっても、いい面ばかりではなかったのではないでしょうか。
吉見:日本で最初の敦賀原発や美浜原発が稼働したのは1970年で、その電力は全部大阪万博に供給されました。原子力発電の歴史はオリンピックに向かう時期に誘致等の動きが加速して大阪万博の前後に実際に動き始めていますから、オリンピック、万博、原発がまさしくセットになって動いていたと言えます。
東京も土木工事が圧倒的に突出していた時期でした。私は環状8号線の近くに住んでいたのですが、子どもの頃は空き地に土管や建築資材がいっぱい置いてあり、そこは格好の遊び場になっていました。当時は交通渋滞が最大の課題でしたし、羽田に降りたお客さんを都心や代々木会場まで速く運ばなくてはなりませんから、東京の河川の上は高速道路で埋め尽くされ、日本橋の風景も台無しになっていきました。このマイナス面がオリンピックの開催と表裏をなしていたことを忘れてはならないと思います。
吉本:地方都市に住んでいた身からすると、オリンピック以降、東京への憧れがどんどん刷り込まれ、上京することが暗黙のうちに目標のようなものになっていった気がします。高校2年生のとき、初めて東京に行ってその圧倒的なすごさにただただ驚くだけでしたが、そうした時代の空気の中で、結果的に地方都市はみなミニ東京のようなものを目指すということにもつながっていったように思います。
東京モデルの意義と限界
吉見:1964年の東京オリンピックでは、東洋の魔女に日本中が熱狂しましたが、彼女たちはいったい誰であったのかというと、日紡貝塚の女子労働者です。当時、戦後復興の中で急成長した紡績産業の労働者のためのレクリエーションシステムとしてバレーボールが導入されたのですが、その中から、特に運動能力のある女性たちが選抜され、大松監督のスパルタ式トレーニングによって世界一になっていきます。
円谷も、貧しい福島の農村から出てきて自衛隊に入り、オリンピックで栄冠を勝ち得ました。つまり、東洋の魔女も円谷もいずれも貧しい日本の地方から選び抜かれてオリンピックという晴れの舞台でヒーローやヒロインになっていくという60年代のストーリーそのものだったと思います。しかし、円谷はやがて自殺し、東洋の魔女たちはわりと平凡な結婚をしていきます。つまり、彼女たちの夢は普通の会社勤めの旦那さんと結婚して主婦になることだったわけですが、まさに、こういう時代に東京オリンピックがあったのです。そしてその後、1988年のソウルや2008年の北京オリンピックのモデルになって韓国や中国で同じような流れが繰り返され、アジア全域に広がっていったと思います。東京オリンピックには、ある種の世界性とそのモデルそのものの限界みたいなことがあったのではないでしょうか。
吉本:オリンピックには、いろいろな意味があったと思います。女子バレーがその典型で、決勝でソビエトという大国に勝つわけですが、その時、国民の間に一致団結感のようなものが無意識のうちに生まれ、国をあげて高度成長という目標に向かって走っていくわけです。その後、万博によってそれが加速されたと思いますが、オリンピックによって、日本人全体が同じ価値観を共有する体験ができたというのは幸せだったと思います。しかし、そのことで結果的に地域の特性や多様性が軽んじられるようになった気がします。当時、国の全国総合開発計画では国土の均衡ある発展と言いつつ、あらゆるものが東京に集中していったことからもそれがわかりますね。
吉見:国民が一丸になるというのは広告の世界でも似たような形で起きていました。1960年前後から広告の中で繰り返し現れてくるキャッチフレーズが“メイド・イン・ジャパン”で、例えば、松下電器は「誇り高きメイド・イン・ジャパン」という広告を大々的に出していますし、いろいろなメーカーが“メイド・イン・ジャパン”を冠した広告を積極的に打ち出してきます。
こうした広告業界を含めた大きな流れとオリンピックのプロモーションがある種のイメージ面で一致し、1945年でクラッシュした日本のナショナルアイデンティティーが再構築されたとも言えます。その柱になっていたのが原発や本四架橋、首都高などの巨大な開発事業、あるいはさまざまな新しい製品をつくる技術開発でした。つまり、スポーツの身体的側面に限らず、人々の能力とか技術力を徹底的にトレーニングしていく中で世界の一流国になろうという流れが出来上がっていったと言えるのではないでしょうか。
吉本:まったくそうだと思いますね。
ロンドン・オリンピックの教訓
吉見:1964年と2020年のオリンピックは同じ東京で開かれるわけですが、何が変わらなければならないのか。ざっくり言うと、1964年のオリンピックはある種、キャッチアップ型と言いますか、日本が復興と経済成長に向かっていく時期の国際イベントでした。一方、2020年はそうしたフェーズに日本社会があるわけでは決してありません。よく言えば成熟社会で、人口が減少に向かっていく時代状況にあります。
吉本:非常に漠然とした表現になりますが、1964年のときはとにかく未来を見据えて前進しようと気運に満ちていた。でも2020年はそれとは逆で、日本の近代化の歴史は何だったのか、これまで私たちが築いてきたものを振り返り、それを再構築しながら次のあるべき姿を見いだしていくターニングポイントにしなければならないのではないでしょうか。
吉見:そういう意味で言うと、ソウルや北京のオリンピックではなく、2012年のロンドン・オリンピックが大変参考になると思いますが、このロンドン・オリンピックの文化プログラムとはどんなものだったのでしょうか。
吉本:2012年のオリンピック招致レースでは、当初パリが圧倒的に有利だといわれていました。それに対してロンドンは東地域の再開発を大きな目標として掲げ、文化プログラムに関しても積極的な提案を行いました。
パリでは自国での開催が決まったと思い、IOC総会前に祝勝パレードをしてしまって、IOC委員を不快にさせたということもあったらしいのですが(笑)、ロンドン誘致で中心的な役割を果たしたジュード・ケリー(Jude Kelly)さんは、オリンピックはスポーツだけの祭典ではなく、人間の祭典なんだということを繰り返し関係者に説いて回ったそうです。彼女は今、サウスバンク・センターという英国最大の国立文化施設の芸術監督をなさっていますが、オリンピック憲章に「スポーツを文化と教育と融合させる」とあるように、とにかくクーベルタンの精神に戻るんだということを強く訴えたわけです。
その考え方に基づいた提案が立候補ファイルに書き込まれ、実際に招致が決まると、北京五輪の終了後すぐにカルチュラル・オリンピアードを始めます。それは4年間行われ、オリンピックの期間中には12週間にわたりロンドン2012フェスティバルという大規模な国際芸術祭が行われました。その間に行われた文化イベントの総数は18万件、新しくつくられた新作委嘱の作品が5,400点という大規模なものでした。
重要だと思うのは、それがロンドンだけではなくて英国全土1,000カ所以上で行われたということです。中には自然環境や世界遺産のような場所も含まれていて、有名なのはピースキャンプというプロジェクトです。全英の8カ所の浜辺に2,000のテントを張って、その中で環境音楽や愛の詩の朗読を聴きながら平和を考えるという作品でした。文化プログラムによってオリンピックが全国民の催しであり、英国のこれからを考えるうえで重要なイベントだということをアピールしたわけです。
吉見:オリンピックが、人間の祭典であるという原点に戻るというのはすごく共感しますが、カルチュラル・オリンピアードでとても重要なことは、ロンドンだけではなく地方都市でも展開したということですね。
求められる地方との回路
吉見:2020年の東京オリンピック誘致では、東北の震災復興、あるいは福島の問題をアピールし、カルチュラル・オリンピアードを全国展開する可能性を示唆してきたように見えますが、具体的にオリンピックと地方の文化再生をリンクさせることはできるのでしょうか。
吉本:文化ということを考えたとき、大震災のあとにオリンピックがあるということにはとても重要な意味があると思います。というのは、東北は芸能やお祭りの宝庫といわれながら、一部の観光以外では日本人の記憶からは遠いものになっていました。それが震災後、住む家や働く場所もない中でも祭りをやろうとか、獅子頭や装束が津波で流されても郷土芸能は続けるんだというように、東北の伝統文化の豊かさを呼び覚ましてくれたと思います。
文化プログラムを全国展開するためにも、東北や被災地では伝統芸能やお祭りにフォーカスしてほしいですね。結局は祭りは人々の絆というか、人間の祭典でもありますから、オリンピックの理念にも通じる部分が多分にあると思います。
たまたま、8月に三陸国際芸術祭が大船渡で行われました。これは大船渡や岩手県内の伝統芸能が一堂に会したものですが、特に金津流浦浜獅子躍は感動的でした。それまで7つの地域ごとに別々にやっていたらしいのですが、獅子躍の総まとめの方と京都のNPOの呼びかけで7団体が同時に踊る群舞が初めて実現したんですね。雨上がりの屋外だったこともあり、本当に大地と天がつながるようなすごい体験でした。
芸術祭ではバリ島の舞踊や韓国の伝統芸能も加わりましたが、まったく違和感がありません。やはり、アジアには共通する文化やリズムがあって、文化や芸能の持つ「つなぐ力」にはすごいものがあることを実感しました。
吉見:2020年に向けて観光客や海外からのツーリストなどが増えてくるとすると、大都市や観光地だけではなく、そういう現場にもできるだけ多くの人々を誘うことが大事になります。短期でもいろいろな現場を見てもらえれば、日本に対する見方が決定的に変わる大きなきっかけになると思います。しかし、そのための具体的な方法はあるのでしょうか。
吉本:日本文化ミシュランのようなものを2,020件、各都道府県で約50件セレクトしたらどうでしょうか。そこでは、海外にぜひアピールしたい地元の文化的な資源、それは伝統的なものでもB級グルメのようなものでもいいのですが、そのサイトを整えてアクセスできるようにし、かつ、すべての国々の人に対応できる言語でおもてなしするというアイデアです。そうすれば、各地域の人たちは地元の文化についてより真剣に考え、とにかく見に来てほしいという行動につながっていくと思います。
一方で、日本を訪れる人はオリンピックを見るのが目的で文化を見に来るのではないという意見もあります。実際ロンドン五輪でも、世界初演など一部のものを除いて、観客のほとんどは地元、つまり英国の方だったという調査結果があります。しかし、五輪の文化プログラムは、日本人自身が自国の文化の豊かさに気づく好機になり、アイデアや仕組みを工夫すれば、文化の国としての日本の姿を世界にアピールする絶好のチャンスにできると考えています。
吉見:同時に目を向けなければならないのは、東北の三陸なりローカルな地域で起こっていることが戦後を通じて東京でも起こっているということです。その東京で何を体験するのか、東京の先に何を見るのかということと、地方と回路でつなぐ仕組みをどうつくるかが必要なのではないでしょうか。
〔 第2回(最終回)へつづく 〕
※全文は吉田秀雄記念事業財団のサイトよりご覧いただけます。