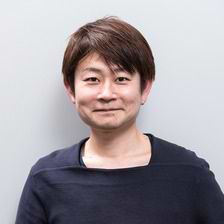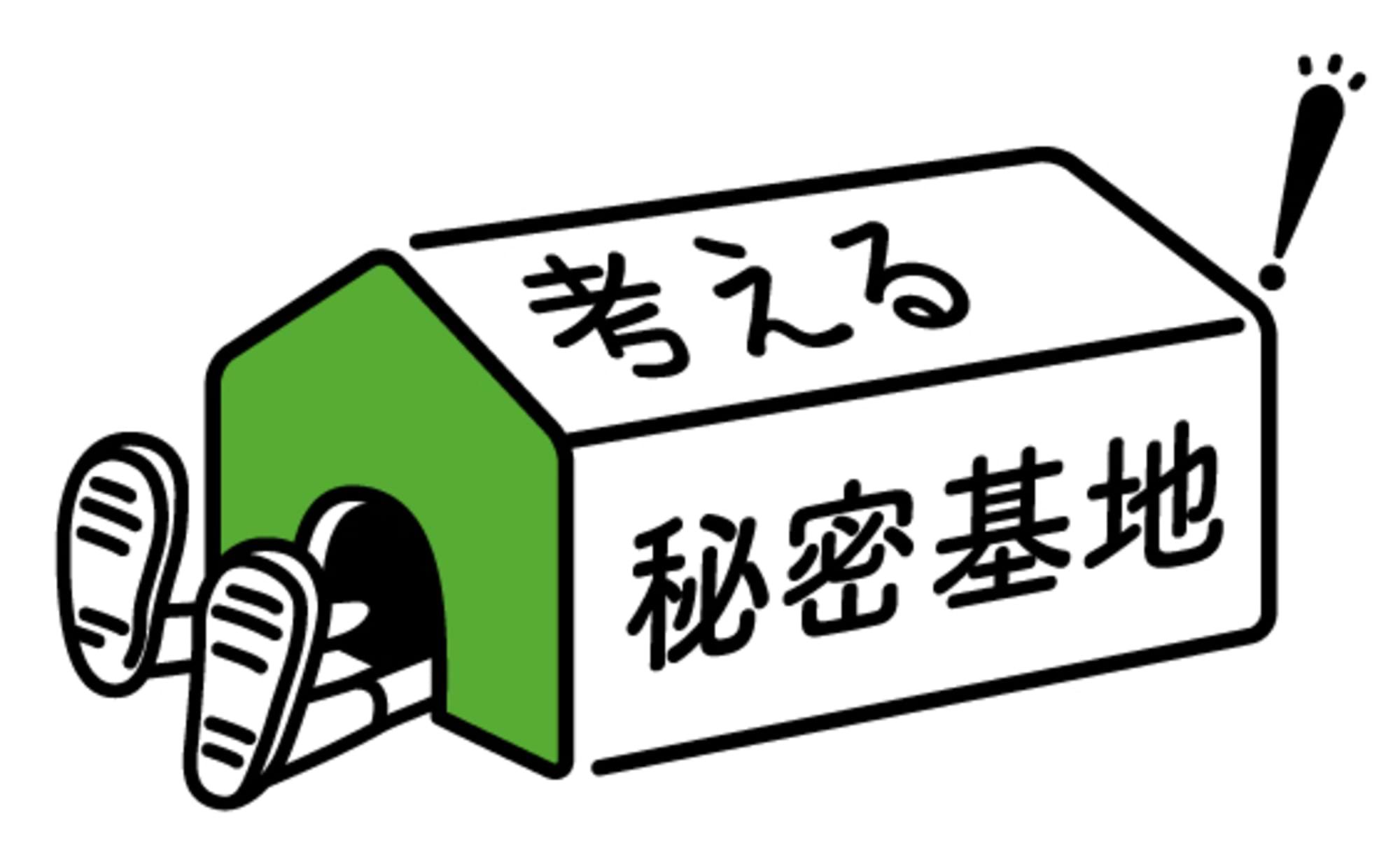電通総研「アクティブラーニング こんなのどうだろう研究所」は、学校教育におけるアクティブラーニングの本格的導入を控え、2015年10月に設立されました。同研究所は、自ら課題発見・解決し、実社会で活用できる汎用的な能力の育成を目指すアクティブラーニングに使えるノウハウを提供し、「ラーニングのアクティブ化」のサポートに取り組んでいきます。
この連載は、同研究所のキリーロバ・ナージャ研究員のコラムと、研究所メンバーでもある大熊雅士先生とメンバーらによる対談でお送りしています。
第3回の対談テーマは「日中プロジェクト」です。
電通は20年に及ぶ「日中プロジェクト」の中で、広告業のアクティブな授業を行ってきました。中国の多くの学生たちに対し、最初は広告の手法を座学中心に教えていましたが、最近ではビジネス自体のデザインに取り組みながら、次世代の人材育成を行っています。
大熊先生と日中プロジェクト担当の電通・池田京子氏、そして研究員の森口哲平氏がファシリテーターとなり、日中のアクティブラーニングについて話し合いました。

左から、大熊氏、池田氏、森口氏
『大衆創業』とは「一人一人スタートアップしよう」という意味。『万衆創新』とは、「一人一人イノベーションをやりましょう」という意味で、共に中国が掲げる国策。
【日中プロジェクト】
正式名称は「電通・中国広告人材育成基金プロジェクト」。1996年に中国の江沢民国家主席と電通の成田豊社長(共に当時)の間で、中国の広告教育および人材育成への支援、日中友好の増進を目的に開始された中国の国家プロジェクト。
中国からの要請を受ける形で、電通のCSR活動の一環として開始され、今年20周年を迎えた。中国の広告教育界への長期にわたる支援が認められ、昨年に続き中国教育部(日本の文部科学省に相当) から最優秀パートナーズ賞「MVP」(Most Valuable Partner)を受賞しました。
アクティブラーニング化していった中国での教育プロジェクト
森口:池田さんは日中プロジェクトを20年前の最初から担当しています。電通の関わり方を教えてください。

MVP(Most Valuable Partner)トロフィー
池田:この20年間、電通では延べ2000人以上の社員がこのプロジェクトに関わってきました。中国では、広告学部または学科が設けられている大学が多く、これまで電通の広告講座を受講した学生は1万人を超えます。
また、電通本社では、毎年中国の大学から6人の教師を研修員として受け入れています。研修期間は当初6カ月という長いコースもありましたが、ここ10年は3カ月です。この研修に参加した中国の大学教師は155人になりました。
大熊:日本の大学には広告学部というようなものはありませんが、中国にはあるのですね。
池田:昔はありませんでした。広告人材の育成が急務だということで、1990年代の前半から設置大学が増え始めましたが、電通のプロジェクトがスタートした96年ごろは、まだそんなに多くはありませんでした。
しかし、増え方が早く2000年ごろには中国全土で広告学科のある大学数は一気に300以上になりました。数は増えましたが、教材の不足や教員の質や量といった課題もクローズアップされました。そうした中で、電通のこの支援プロジェクトに対する期待がとても大きかったのです。
森口:この20年間で教え方の変化があったようですね。
池田:最初の10年は広告講座といった座学が中心でしたが、最近の10年はフォーラムやワークショップなど、いわゆるインタラクティブなプログラムが導入されるようになりました。最初のころが「教え」に重きを置いたやり方だったとすれば、後半はお互い刺激し合える「学び合い」のスタイルにだんだん変わってきました。
大熊:その変化は興味深いですね。中国で10年くらい前から、アクティブラーニングの手法が必要とされていたということですからね。
政策はあっと言う間に現場で実現化される
森口:教え方の変化の原因として、一つには、中国の経済成長の速さがあります。日本が高度成長期から40年かけてきた変革を、中国はここ10年で成し遂げています。
マーケティングに関しても、日本では広告の文化が長い時間をかけて醸成されてきた歴史があります。ところが中国はその時間が短く、あっと言う間にソーシャルネットワーク中心のコミュニケーション文化に様変わりしました。電通は広告の会社として、最初の10年は広告の話をしていたわけですが、中国の成長スピードがそれを追い越して、ニーズが乖離してきたわけです。
池田:それに加え、中国では教育政策が出されれば、学校は直ちにそれに従って実行しなければなりません。2010年ごろから「カリキュラムの見直し」が始まり、それに呼応するかのように、アクティブラーニングのような授業が増えました。
森口:2012年には実践的にやりましょうということで、アクティブラーニングこんなのどうだろう研究所の倉成英俊所長がまず上海で授業を担当しました。3カ月実践的な授業をやったら「こういう授業を受けたことがない。ぜひ続けたい」ということになり、翌年は北京で私が担当して、以降深圳や北京で徐々にバージョンアップさせてきました。
大熊:話が早いのに驚きますね。日本の場合には「アクティブラーニングやらなきゃ」って文科省が言ったのに対してようやく「アクティブラーニングって、1週間に1時間の授業をやればいいんですか」と言う教師がいるような状況なのです。中国では国の方針によってカリキュラムがドーンと変わる圧倒的なスピード感があります。この差は大きいなあ。
池田:中国で常に感じるのは、スピードだけでなく、学生の意欲の高さですね。中国教育部の幹部は「この国を前進させるのは学習への貪欲さ」と言っています。それがあるからこの国は動いていく。しかも人口が多いから、生存競争が厳しいんです。
森口:大学は午前8時から午後10時近くまで授業をやっています。しかも全寮制でずっと勉強をしている。資料をつくるにしても訓練されてるから、速さも質も高いですね。こちらの授業もそれに巻き込まれるように変わっていきました。
「広告」から「創業」へ、「ティーチング」から「ディレクション」へ
池田:2014年に中国は新たな国策として、国民的な創業とイノベーションを提唱し始めました。そのスローガンは「大衆創業」と「万衆創新」というものでした。この流れの中で、昨年北京で森口さんチームに10大学の学生チームを集めて「イノベーション・キャンプ」をやってもらいました。
森口:僕がリーダーをやらせてもらっている「XDS」(電通エクスペリエンス・デザイン・スタジオ)というチームはクライアントの宣伝やマーケティングの部署ではなく、R&D部門や事業部門を相手に、事業・サービスのプロトタイピングにチャレンジしています。
簡単にいえば、広告以外の分野で、電通の事業の可能性を探るチームです。ちょうど中国の方針も「広告」から「創業」に変わり、スタートアップしたい学生や、イノベーション起こしたい学生が増加しました。そこで、私の部署で取り組んでいるやり方が、授業にぴったりはまったわけです。
この時の授業の内容が『EXPERIENCE DESIGN』として中国で出版されています。
池田:中国の大学は出版社を持っている場合が多く、森口さんが講義を行われた大学の出版社から講義内容を本にしませんかと提案され、出版が実現しました。現在では8000部売れているのですが、このジャンルの本としては異例の売れ行きだそうです。
大学の先生はスタートアップとかイノベーションをどう教えればいいのか分からず、イノベーションに関するノウハウを満載したこの本はまず先生たちに大歓迎されました。
大熊:「大衆創業」というスローガンがあれば、学校が即刻動き出す。しかも生徒の側も貪欲なのがすごいですね。
森口:電通の中でも、私たちのチームが何をやっているのか、特に広報してないので、電通社内より中国の大学が「XDS」のことを知っているという現象が起きています。別に日本国内で教えないということではありませんが、結果としては、中国の方々が学びに貪欲なのに引っ張られている形です。
日本にもLINEのような会社はありますが、中国はその成功の数と規模が経済に与えている影響がとても大きい。BATといわれるスタートアップ企業があり、Baidu(百度/バイドゥ)、Alibaba(阿里巴巴/アリババ)、Tencent(騰訊/テンセント)が世界的にも有名になっています。
世界的な規模に成長したテンセントは、学生時代からの仲間で起業しています。中国の学生は、自分たちが「次のテンセント」のファウンダーを目指している。だから、そのためのノウハウを知りたがっています。これはもう、切実なんですね。
大熊:学ぶ側がアクティブなら、教師もそれに対応していく。中国では教師の評価方法も優れているそうですね。
森口:授業に対する評価がきちんと出てきます。授業のどの回が良くて、どこが分かりやすくて、何がいいのか、もっとこうしてほしいという要望も、こちらが生徒のスコアを提出するタイミングで全部説明を受けました。
私は授業以外のリアルなミーティングを重視したのですが、その時には学生に対して、ディレクターの目線でダメ出しをしていきました。こうなると仕事と同じで「教えてやっている」のではなく、学生と一緒にやっているチーム感が出てくる。どんどん彼らが企画を出してくると、そこからはティーチングではなく、仕事のディレクションになる。これこそが中国のアクティブラーニングだと思いました。
大熊:教えるのではなく、共に考えるチームとなるわけですね。評価をきっちりやるのは素晴らしいけど、日本の教育では、評価が次の意欲につながっていないのです。何が違うのでしょうか。
池田:中国の人は精神的にタフですから、評価されることにわりと慣れているのかもしれません。それに、中国の大学の先生は終身雇用ではないので、きちんと評価されないと逆に危機感を覚えるかもしれません。
森口:教育界がビジネスに近い感覚です。中国の教師は常に競争していて、自分が変わっていかなければ置いていかれるのではないでしょうか。
分からないことは専門家にすぐ聞く積極性
大熊:こうした取り組みは、これから日本がアクティブラーニングを取り入れていくとき、とても参考になります。
今、日本で学習指導要領はウェブでいつでも見られるようになり、今や文科省の人が今後の学習指導要領はこう変わると、YouTubeなどで説明している。こうなると情報が伝わる速度は保護者だろうと教員だろうと同じです。
中国ならば「学習指導要領が変わったのに先生なにやっているんですか」となるはずでね。日本の教師もこのような状況になるのでしょうね。
森口:中国の人たちは「分からないことはすぐに専門家に聞く」という積極的な学びの姿勢があります。日本人は奥ゆかしすぎるのではないかと思います。
中国の生徒は授業の流れに関係なく、強引に質問をしてきますし、解決できないとイライラする。言いたいことがあるとガンガン来ますね。そういう競争原理に私たちも取り込まれるので、授業をしていると、真剣勝負になります。
大熊:話を聞けば聞くほど、日本の授業のやり方がまずいのではないかと胸騒ぎがしてきます。
教師の話ではなく、生徒の生んだアイデアこそが成果
森口:今私たちが中国で教えていることの「成果」は何かといえば、それはしゃべったことや「講義メモ」ではないんです。大切なのは、生徒たちがつくり出したビジネスのアイデアです。
私がどれだけいい授業をしたのかをアピールしなくても、生徒がどれだけのものをつくり上げたのかを見れば、その授業の質はおのずと分かるというわけです。
大熊:日本の教育では、指導内容や教科書の内容をどれだけ理解したかが大切ですが、中国では、学生がつくり上げたものこそが教育の評価になっているわけですね。中国では、アクティブラーニングが10年先に進んでいるということですね。
池田さんはこれから先はどうなると考えますか。
池田:この20年間のプロジェクトを通じて私たちと中国の教育部、さらに中国の大学との間で相互理解が深まり、信頼関係もできました。中国ではこれからも新しい政策が出てくるでしょうし、新たなニーズが出てくるでしょうが、私たちとしては、常に中国の人々とのコミュニケーションを心掛け、真に必要とされるプロジェクトにしていかなければならないと思います。
大熊:話し合いで進めてくとおっしゃいましたが、これがすてきですね。イノベーションはこちら側が「いい」と思うものを伝えるだけではできません。僕らもそういう気持ちでこれからの教育を語っていきたいと思います。
森口:そうですね。今後もチャンスがあれば、日本とは全く違うフィールドで、どんなことができるのか学生と一緒に探っていきたいと思います。