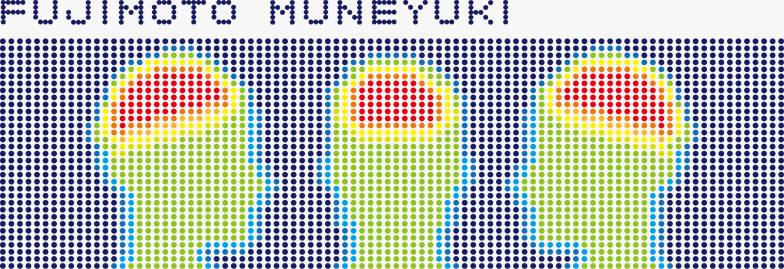公開日: 2013/07/18
そもそもどんな思いで本をつくったんだっけ?
この記事は参考になりましたか?
著者

廣田 周作
Henge Inc.
CEO / Director
1980年生まれ。放送局でのディレクター職、電通でのマーケティング、新規事業開発・ブランドコンサルティング業務を経て、2018年8月に独立。企業のブランド開発を専門に行うHenge Inc.を設立。英国ロンドンに拠点をもつイノベーション・リサーチ企業「Stylus Media Group」と、米国ニューヨークに拠点をもつ、大企業とスタートアップの協業を加速させるアクセラレーション企業の「TheCurrent」の日本におけるチーフを担当。独自のブランド開発の手法をもち、様々な企業のブランド戦略の立案サポートやイノベーション・プロジェクトに多数参画。また、WIRED日本版の前編集長の若林恵氏と共同で、イノベーション都市・企業を視察するツアープロジェクトのAnother Real Worldのプロデュースも行なっている。自著に『SHARED VISION』(宣伝会議)、『世界のマーケターは、いま何を考えているのか?』(クロスメディア・パブリッシング)など。

八木 彩
電通では企業や商品のブランディングを、コンセプト構築・商品開発からコミュニケーション設計まで、デザインを軸に、トータルで手掛ける。2023年10月末に電通を退社。

藤本 宗将
株式会社電通
CDC
1972年生まれ。1997年電通入社。コピーライターとして広告のメッセージ開発を手がける。主な受賞に、TCC最高新人賞・TCC賞・ADCグランプリ・ACCグランプリなど。論文に『拡散するクリエイティブの条件』(JAAA入選)。