社会にはいま、解決すべき課題があふれている。課題を解決するプレーヤーは、かつて行政や市民が中心だった。しかし、いまや企業もその役割を担い、多くの企業がソーシャルグッドな活動を展開している。ソーシャルへのより踏み込んだ関わりが求められる時代に、企業はどのように振る舞い、広告はそれをどうサポートできるのか。社会活動に実績のある2人のクリエーターに、ソーシャルグッドな活動と広告の可能性について語ってもらった。

慈善活動から、事業としての社会貢献へ
──日本でもソーシャルグッドな活動が目立つようになり、企業の関心も高まっています。
白土:ソーシャルな領域における企業活動は、寄付やメセナ、慈善活動といったものが起源にあります。その後、環境問題など社会的な課題が浮かび上がってきて、これらの課題に配慮しないと企業は活動しにくい時代になりました。いわばリスクマネジメントとしてのソーシャルグッド活動です。さらにこの10年で一歩進んで、社会に課題があるなら、それを本業として解決しようという動きが出てきて、企業が経営戦略としてソーシャルグッドな事業を始めたり、ソーシャルアントレプレナーと呼ばれる人たちがベンチャーを立ち上げるようになった。世界も日本もおおよそ同じ流れですが、世界のほうが15年くらい先にこの流れが起きているという印象です。
本田:僕も同じ見方をしています。特に最近の変化は注目で、それまで企業は純然たるCSR的なものばかりやってきましたが、いまは「いいことをやって堂々と儲けましょう」という空気に変わってきました。これは見逃せない変化です。
契機になったのは、やはり3.11の東日本大震災でしょう。僕は26年前から環境マンガの「エコノザウルス」を描いてきましたが、当時は具体的な活動をしている人がほとんどいなかった。ところが3.11の後、たくさんのfor GOODメッセンジャーが出てきました。日本人って、本当はこんなに社会貢献意識が高かったのかと驚いたくらいです。
白土:阪神淡路や中越地震で、すでにボランティアをしたいという意識の土台はできていたのでしょう。ただ、以前は経団連が企業から物資を集めてトラックで届けるとか、そのときに運送会社が手伝うというように、ボランティアの主力がプロ集団でした。それがインターネットやSNSの発達で、いまは一個人、一市民が自分で調べて、ピンポイントで行動するようになってきた。以前とはボランティアへの参加形態は大きく変わり、それにともなってfor GOODを発信する人も増えてきたのかもしれません。


ソーシャルグッド広告の歴史
白土:コミュニケーションに限っていうと、アメリカでは1960〜70年代から公共的なコミュニケーションが盛んでした。いまカンヌCMフェスティバルはクリエーティビティのコンペになっていますが、もともとは商業部門と公共部門があって、2つの部門の賞を獲らないと一人前ではないと世界では言われてきました。アメリカの広告業界でも、広告会社ごとに地域の活性化や教育といったパブリックなテーマにフォーカスして取り組んできた歴史があります。そういう意味では、コミュニケーションの世界でソーシャルグッドなものは以前から当たり前に存在していました。
日本もその影響を受けて、1980年代には公共広告的、あるいは社会的な広告が数多くつくられました。印象的だったのは、トヨタの「あなたの車を凶器にしないでください」キャンペーン。いまだと驚かれるかもしれませんが、かつてはメーカーさんが真正面から交通安全メッセージを発信していたのです。四半世紀の近代広告の歴史を研究していくと、ほかにももっといろいろなものが出てくるはずです。
本田:最近は社会貢献と儲けることは両立できるという流れになっていますが、その方向でのfor GOOD広告を僕が最初に認知したのは、ボルヴィックの「1ℓ for 10ℓ」でした。これはボルヴィックの商品が1リットル買われるたびに、企業がアフリカにきれいな水を10リットル送るというもの。それまでも企業の儲けにつながるfor GOOD広告はあったかもしれませんが、これほど上質というか、鮮やかなものは見たことがなくて、「社会貢献しつつWin-Winになることができるんだな」と教えられた気がしました。
白土:ソーシャルな領域における広告で私の原体験になっているのは、1970年代にニューヨーク市観光局が始めたビッグアップルキャンペーンです。当時のニューヨークは、ビッグアップルどころか腐った林檎といわれていて、世界一危険な都市でした。私もロケでよく訪れていましたが、地下鉄で降りる駅を一駅間違えると強盗に遭って身ぐるみはがされるし、ホテルにいてもパトカーや救急車が一晩中走り回っていて眠れない状況でした。
この状況に危機感を持った広告代理店の若手たちが始めたのが、このキャンペーンです。ニューヨークは楽しいことがたくさんある街だから、少しぐらい危険でも外に出て面白いことをやろうよ、という広告を大々的に展開したのです。ブロードウェーの大スターも賛同して、CMに無料出演。おかげでニューヨークのイメージが変わって、観光客も戻ったそうです。
私が現地で体験して感じたのは、ビッグアップルはキャンペーンというよりムーブメントだったということです。日本だと、メディアを使って上手に表現しようとか、いい言葉を乗せて人々を動かそうと考えますよね。確かにそれも大事なことですが、ビッグアップルキャンペーンには、イベントを入れ込んで仕組み全体で社会を動かしていくダイナミックさがあった。パブリックのアプローチとしてこんなやり方があるのかと、衝撃を受けたことを覚えています。
その活動はGOODなのか、BADなのか
本田:日本のfor GOOD広告に関して僕が気になるのは、企業が踏み込む深さです。海外だと、オピニオンや政治を変えることを明確に打ち出しているものが多いけど、日本の場合、企業が具体的な意見を持って旗幟を鮮明にしてはいけないという雰囲気があって、みんな足踏みしている。これは残念です。
白土:それを裏付けるような象徴的な事件が、ホワイトバンド騒動ですね。ホワイトバンドはアフリカの貧困に目を向けようというプロジェクトで、寄付活動ではなくアドボカシー(政策提言)のための啓発運動です。アフリカの貧困を多くの人に知ってもらうことで、行政に働きかける圧力にすることが狙いですが、日本ではバンドを買ったお金が支援金としてアフリカに送られると勘違いされて、バッシングの対象になりました。
実はホワイトバンドのプロジェクトの人たちが日本に来たとき、フィルムをつくるなどしてお手伝いしたことがあります。コンサートをやりたいというから、「9,000人集められる」と言ったら、「10万人以上じゃないと話にならない」と呆れられました(笑)。つまり、それくらいの大きな数を集めないと政府に提言する力にならないというわけです。世界を仕組みで動かすというのは、まさにこういうことなのですが、日本ではそれが理解されずに叩かれる対象になる。協力していたタレントさんも含めて気の毒でした。
本田:日本人って細かいところまでチェックして、少しでも何か欠けていたら一斉に叩くようなところがあるじゃないですか。まさにホワイトバンドもそうでした。こうしたバッシングを目の当たりにすると、企業はせっかくfor GOODなことをやってもディフェンシブなことしか言わなかったり、最初から炎上しないような当たり障りのない分野でしか仕掛けなかったりする。いまもまだfor GOODを身だしなみ程度にしか考えていない企業がほとんどじゃないかな。
白土:それでも、この10年で変わった印象はあります。2003年ごろにCSR(企業の社会的責任)がブームになって、日本では3,000社以上の会社がCSRレポートを出しました。どんなことが書かれているのだろうと気になって50社ほど取り寄せてみたら、どの会社も環境問題への取り組みとして植林をしていました(笑)。
最初はそのレベルでしたが、さすがに企業自身もこれはおかしいと気づいて、自分たちなりの価値観で、つまり自分たちの事業のポテンシャルで解決していこうと考え始めました。とはいえ、一朝一夕には変われません。言い方は難しいですが、CSRの担当者は、よくいうと人柄は良くて真面目な人、悪くいうと無難なタイプが多くて、新しい視点でソーシャルグッドなことをするのに向いていないのです。ソーシャルグッドなことを事業としてやっていくには、人材の入れ替わりが必要です。それに少し時間がかかりましたが、最初のCSRブームから十数年経って、いまようやくその成果が出始めてきたところではないでしょうか。
本田:白土さんはファーストリテイリングのCSR活動に関わっていらっしゃいましたよね。あの会社のソーシャルグッドな活動はどうなのですか。
白土:2005年にファーストリテイリングの「社会貢献室」がCSR部になった際に、私は社外委員として参加させていただきました。最初に取り組んだのは、環境問題です。我々は洋服をたくさん作って売っているけど、最終的に燃やしてCO2になるのは問題だよね、それならリサイクルして困っている人たちに届けよう、という取り組みです。実際、世界には、洋服がなくて困っている難民が6,500万人以上います。そこでUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)と一緒に配りに行きました。
ここまでは、よくあるCSRの一つです。ところが、ファーストリテイリングは配って終わりにはしませんでした。世界各地の難民キャンプに、役員や社員が訪れました。そして視察するだけでなくリサーチを行いました。洋服を配ったら、もらった人は喜ぶかもしれませんが、現地で洋服を売る人たちの邪魔になるのではないかなど、いろいろと考え、アンケートを取ったのです。


白土:その結果、難民の人たちにも「洋服をもらえて嬉しいが、本当に欲しいのはミシンと布きれ。自分たちが生きる糧は自分たちで稼ぎたい」という自立への願いが強いことを知り、さらに新しい事業を打ち出しました。具体的には、バングラデシュでマイクロファイナンスをやっているグラミン銀行グループと組んで、グラミンユニクロという会社を立ち上げた。この会社は、現地の人を雇用した、現地のための洋服会社です。よくある環境問題への取り組みから一歩踏み込んで、ソーシャルグッドを事業化するというところへ進化していったわけです。
もちろん、その過程で人も入れ替わりました。昔なら国連とかNGOで働きたいといっていただろう若い学生が、いまは入社してきていきなり「CSR部に入りたい」と押しかけてくる。これも10年前には見られなかったことです。
本田:現場で確かめることは大切ですね。僕は国連WFP(世界食糧計画)の理事をやっていますが、いま白土さんに紹介いただいたような事例はWFPの支援先でも起きています。例えばソマリアからの難民がエチオピアに集まっているので、そこに食糧支援をする。すると、エチオピアにもともと住んでいる現地の人たちより難民の生活のほうが豊かになって、現地の人から反感を買ったりするのです。
そこで最近は現地のことをしっかり調査して、難民の方にただ食糧支援をするだけでなく、灌漑施設を造り、自立できるようにする取り組みも始めています。灌漑施設を造るときにはお金を渡します。WFPに寄付してくれた人は「お金を配るのではなく物資で支援しろ」と眉をひそめるかもしれませんが、外から見て適切だと思う支援が必ずしも現場から見て適切ではなかったり、その逆もあるのだということは、もっと知られていい。
白土:同感です。中国の思想家、は「歴史の進化と退化は併進する」と言いましたが、GOODの裏には必ずBADがあります。例えば先ほど本田さんが挙げられた「1ℓ for 10ℓ」キャンペーンも、水を汲んで先進国の消費地まで運ぶのにどれだけCO2を排出するのかという批判もありました。視点を変えると、GOODだと思ってやっていたことも容易にBADになりえます。もちろん、だからといって萎縮するのは良くない。大切なのは、いまよかれと思ってやっていることは本当にいいことなのか、もっといいやり方はないのかと、絶えず見直し続けること。それが新しい知のあり方です。

プレゼン偏重の風潮に異論あり!
──ソーシャルな活動の一翼を担うNPOと企業との関係はどうでしょうか。
白土:日本国内のNPOの数は5万を超えています。正直、すべてが素晴らしい団体とは言えず、中には反社会的団体がやっているようなものもあるといわれます。だから付き合いには注意が必要ですが、一方ではコンサル系の人の流入が増えているという現象も起きています。実は近年、ビジネスの世界ではMBAホルダーが飽和状態になって、MBAを持っているだけではあまり評価されなくなっています。そこで優秀な人はNPOやNGOに入ってマネジメントの経験を積み、それを自分個人の能力の差別化に活用するという動きがあるのです。
コンサル系人材が入ったNPOは、ただボランティアではなく、活動を継続させるために事業化を進めているし、プレゼンが上手で巻き込み力も強い。ソーシャルグッドな活動を社会に広げていくうえで、歓迎すべき流れだと思います。
ただ一つ心配なのは、みんなスティーブ・ジョブズみたいなプレゼンになっていること(笑)。一団体だけ見るとスマートで説得力のあるプレゼンなのですが、みんな同じようなスタイルだから、何団体か集まるとみんな同じに見えます。その結果、志や動機、あるいは課題意識が相対的に曖昧になってきて、悪い意味で営利団体化している印象を受けます。もちろん儲けることは悪くないのですが、ややバランスが危ういなと。
本田:確かにNPOのプレゼン力は、ここ数年でグッと高まった気がします。ただ、僕はそれをポジティブに受け止めています。社会企業の事業プランコンテストである「みんなの夢AWARD」という大会があります。最後は日本武道館で6人の起業家がプレゼンするのですが、彼らは情熱的で、発するエネルギーがすごい。もちろんプレゼンのスキルにも長けているのですが、やはりそれだけで人は動かない。彼らがいい表情で聴衆に訴えることができるのは、社会をよくしたいという情熱が根底にあるからだと思います。
広告に関わるクリエーターも同じですよ。普通のコマーシャルのキャンペーンをやっている人は、産みの苦しみでつらそうな顔をしている人が多いけど、ソーシャルグッドをやっている人たちは、みんなどこか嬉しそうな雰囲気なんだよね。だから志や動機は、とても大事。心が充足されていることが、プレゼンやクリエーティブの質につながっていくのだと思います。
白土:私は少し慎重な立場です。いま「TED」という講演会が注目されていますよね。TEDでは事業家や社会起業家が登場して、7〜8分で世界をひっくり返すような感動的なプレゼンを行います。見ているとなるほど心を動かされるのですが、どこかプレゼンのショーと化しているところがある。世の中には、プレゼン受けする派手なこと以外にも大事なことがいろいろあるはずです。しかし、プレゼンが偏重されると、即効性があってわかりやすいものばかりに光が当たり、プレゼンのフォーマットに乗らない「地味だけどいいこと」が陰に隠れてしまう。ソーシャルグッドな活動を地に足が着いたものにするためにも、そこは問題意識として持っておいたほうがいい。
本田:2014年にバケツに入った氷水を頭からかぶるアイスバケツチャレンジが流行りましたよね。あれはALS(筋萎縮性側索硬化症)の認知を広げるために始まったキャンペーンですが、翌年は誰もやらなくなって、一年だけの花火で終わってしまいました。白土さんがおっしゃるように、わかりやすくて派手なものはプレゼン映えするけど、持続力に問題がありますよね。
もちろんソーシャルグッドな活動にプレゼン上手な人が入ってくるのは悪いことではないし、どんどんやればいい。ただ、昔から地道に続けてきた企業やNPOが脇に追いやられている状況はどうなのかな、という気はします。
白土:急に熱くなったものは冷却も早いですからね。そうした活動ばかりではソーシャルグッドが根づかないので、参加するほうも、課題が解決されるまでやるんだという覚悟を持つべきです。その点、ファーストリテイリングの柳井正さんはさすがで、洋服のリサイクルを始めるときに「みなさん、いいですか。いいことは一回始めたら二度とやめられない。その覚悟はありますか」と、従業員みんなでよく考え、決めて、主体的に行動することを促した。この問いかけは大事です。
本田:ソーシャルグッドな活動を持続的なものにするには、誰に評価されるのかというところをもう一度、考え直したほうがいいですよね。キャンペーンを広告の場やプレゼンの場で評価されたいのか、それとも現場で困っている人たちに評価されたいのか。そこをはき違えると、表面的なものを追いかけて中途半端に終わる気がします。
ソーシャルグッドに求められる広告像
──企業がソーシャルグッドな活動をする上で、消費者との関係はどのように考えればいいのでしょうか。
白土:企業は最初から100%のものを打ち出さなくてもいいと思います。ネット社会は、まず30%くらいのものを出して、みんなで直しながら3年後に90%になればいいという発想をしますが、ソーシャルグッドな活動も同じです。企業がいきなり正解を出すより、みんなで意見を出しながらつくっていく、いわゆるピープルデザインやコミュニティデザインのほうが向いています。そして、企業はそのお手伝いをするというスタンスがいい。
本田:昔の広告は力業で、いいものをつくって大量にスポットを打ち、たくさん消費してもらうというやり方をしていました。しかしいまはそうしたコマーシャリズムに対して一般の人がうさんくささを感じていて、広告を必ず一回は疑うようになった。この商品はいいぞといわれても、もう踊らされたくないという気持ちが強いし、そもそも欲しいものがないからモノを買わないのです。
では、いま消費者が何を求めているのかというと、つながりです。昔はモノを保有することが満足に結び付いていたけど、いまは人とつながっていることで安心を感じて、その安心にお金を払うようになりました。いまfor GOODキャンペーンがウケるのも、それに参加することで、社会とのつながりを感じられるからでしょう。
さらにいうと、企業がfor GOODキャンペーンをやるのも、つながりを求めているからです。自分たちがいいと思うものをつくって売るだけでは不安なんです。ソーシャルな活動を通して社外とつながりを持つことで、安心したいのです。
白土:消費者というより、生活者として捉えないとダメですよね。消費者は「買う人」というイメージですが、生活者には「買わない」という選択肢もあって、それでも企業と関係が続いていく。
本田:そうそう。企業と消費者は「売る人」と「買う人」でしたが、いまはお互いに「仲間」が欲しいんですよ。だから必ずしも売り上げにつながらなくてもいい。
それにともなって、広告の評価も当然変わるでしょう。昔は何千GRP打ったということが評価の指標の一つになっていましたが、つながりの時代はSNSでどれくらい「いいね!」をもらったとか、どれくらいの人にシェアされたのかといった評価が大事になります。通常の商品でもそうだし、for GOODキャンペーンなら、なおのこと評価基準は変わるでしょう。
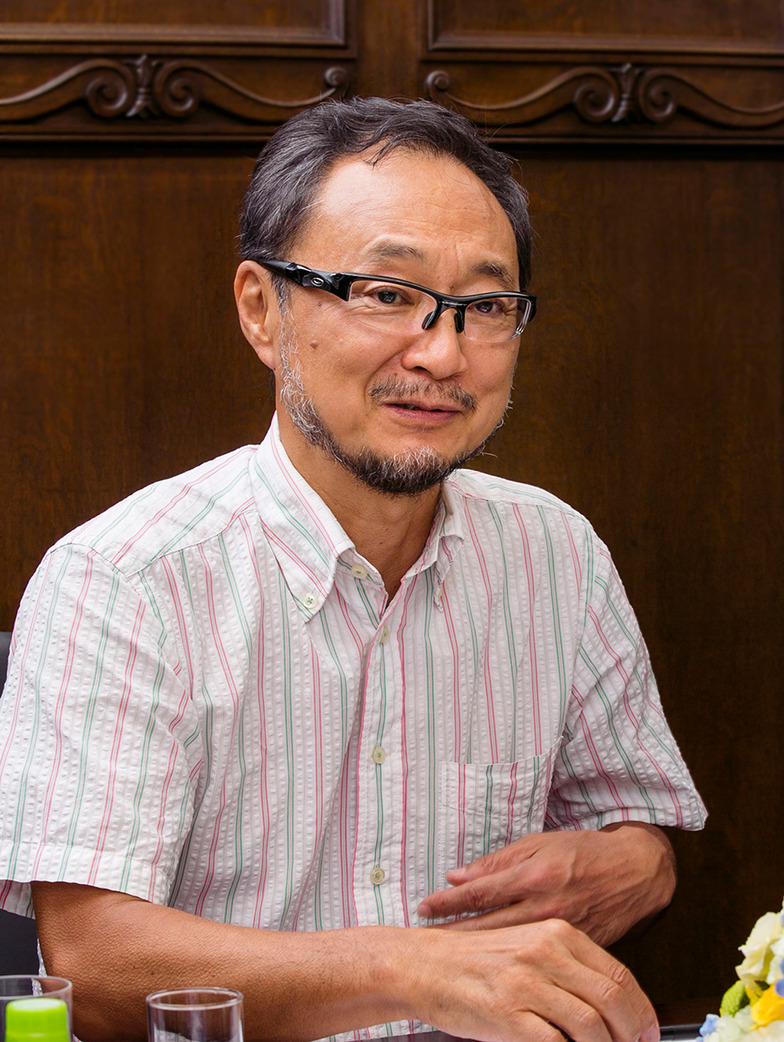
──企業と消費者の関係が変わると、ソーシャルグッドな広告の表現も変わりますか。
本田:昔は社会的なメッセージを出すとき、「脅し」が中心でしたよね。このまま放置しておくと、社会はこんなに悪くなりますよ、というような。脅しの表現はインパクトがあって問題提起するにはいいのですが、一方で共感を呼びにくいという難点があります。
いま求められているのはつながりなので、広告も脅しより柔らかい表現が多くなっていますね。Facebookを見ていても、ショッキングな映像より、かわいらしい動物の映像のほうが「いいね!」がついて広がっています。ソーシャルグッドな活動は共感を呼んで寄付など具体的なアクションにつなげなくてはいけませんから、手法としては後者かなと。
白土:そうですね。昔は難民支援のメッセージも、子どもたちの悲惨な状況を切り取ったショッキングな写真を使うことが多かったですが、いまは逆に幸せそうな写真を使って、「みなさんの協力で子どもたちは幸せになれるよ」という打ち出しをしています。あまり幸せそうだと、「幸せなら支援は不要じゃないか」となるので難しいところですが……。
本田:そこに広告クリエーターが活躍する余地があるんじゃないでしょうか。そのままストレートに表現すると脅しになってしまうものに、広告的なアイデアやユーモアを入れて、心に引っ掛かりつつも心地よく共感できるものにしていく。そこは広告の得意分野であり、社会問題が難しければ難しいほど広告クリエーターの出番は増えるはずです。
〔 完 〕
※全文は吉田秀雄記念事業財団のサイトよりご覧いただけます。
この記事は参考になりましたか?
著者

AD STUDIES
吉田秀雄記念事業財団
<a href="http://www.yhmf.jp/index.html" target="_blank"><span style="color:#336699">http://www.yhmf.jp/index.html</span></a><br/> 公益財団法人 吉田秀雄記念事業財団では、研究広報誌「AD STUDIES」を年4回発行しています。毎号、広告・コミュニケーションおよびマーケティングに関する特集を組んでいます。当財団ホームでは創刊号から最新号までのバックナンバーをご覧いただけます。
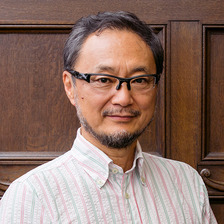
本田 亮
作家、アーティスト
1953年東京都生まれ。76年日本大学芸術学部卒業。同年4月電通入社。以後、「ピッカピカの1年生」(小学館)から「こだまでしょうか?」(AC)に至るまで数多くの広告キャンペーンを企画制作。クリエーティブ局とソーシャルソリューション局のECDを務める。同時に環境マンガ家としても活動し「エコノザウルスの環境マンガ展」を全国展開。カヌーイストとして世界中を旅し、アウトドア雑誌に多くのエッセイを掲載してきた。2011年、電通を早期退社し、現在はフリーランスとして多方面で活躍中。主な著書に『40歳からの仕事で必要な71のこと』『僕が電通を辞める日に絶対伝えたかった79の仕事の話』(ともに大和書房)など。

白土 謙二
思考家、元電通執行役員
1977年電通入社。クリエイティブな発想力で、企業の経営・事業戦略から新製品開発、イントラネットからCSRの領域まで、多様な課題を統合的に解決する独自のコンサルティングで活躍。「伝えるコツ」立ち上げメンバーの一人。2015年3月末で、電通特命顧問を辞し、現在フリー。

