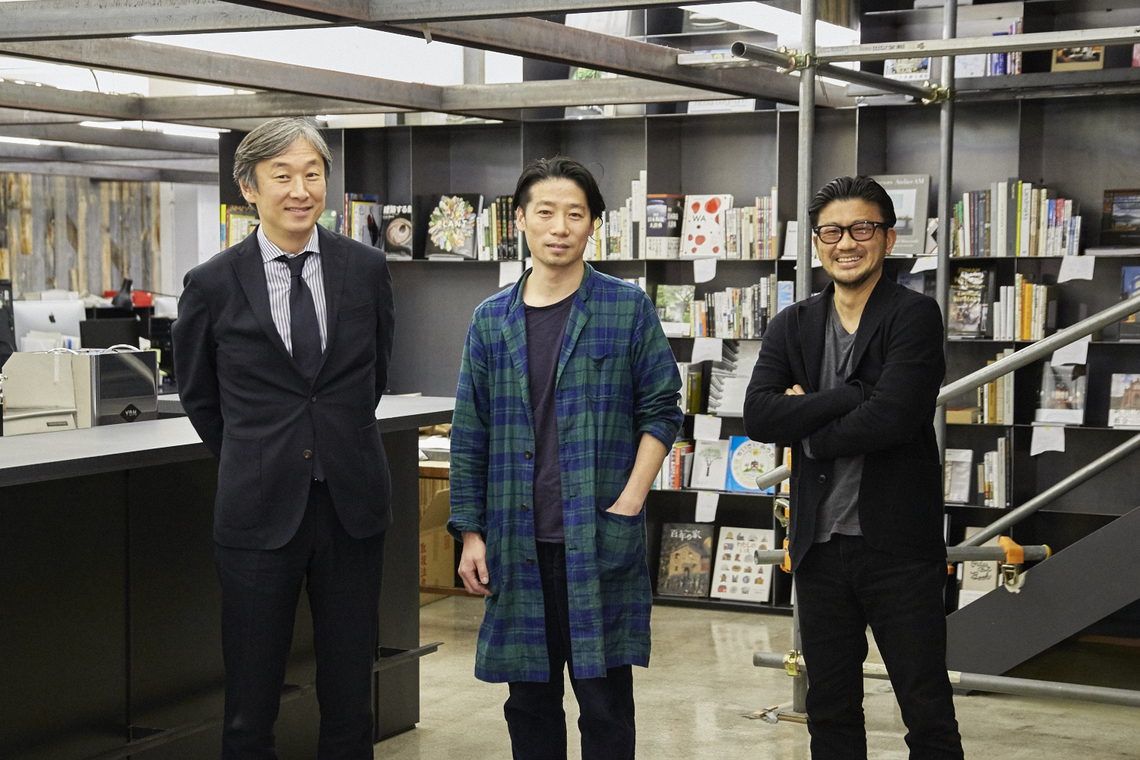電通ライブが掲げる「MOMENT OF TRUTH=真実の瞬間」をテーマにしたこの連載。今回は、電通ライブ執行役員の石阪太郎さんが、普段から仕事や遊びでお付き合いがあり、最高にすてきな空間をつくるお二人、ジョージクリエイティブカンパニーの天野譲滋さんとサポーズデザインオフィスの谷尻誠さんと深く語り合いました。場所は、谷尻さんがまさに建築中のサポーズの新東京オフィスです。
取材・編集構成:金原亜紀 電通ライブ クリエーティブユニット第2クリエーティブルーム (左から)石阪氏、谷尻氏、天野氏
撮影協力:サポーズデザインオフィス 新東京オフィス
瞳孔が開くような、「驚きの瞬間」を提供できるか
石阪: 電通ライブのコンセプトは「MOMENT OF TRUTH=真実の瞬間」なんですが、お二人もいろんな局面で、自分たちの仕事や作品を通じて「これは人とつながった! 人が動いた!」という瞬間を、たくさん感じてきたでしょう?
電通ライブ 石阪氏
天野: たしかに、僕も谷尻くんもリアルな「瞬間」で勝負するのは得意分野ですね!(笑)
石阪: 人は結局、情報だけでは動かない、仕組みだけでも動かない。人はいつだって感動とともに動く、心ふるえる一瞬があればこそ動く。そして、人は変わる。その決定的瞬間を、全てのマーケティングのエンジンだと考えるという意味なのです。
リアルな実体験は、その後の自分の行動の起点ともなるし、自分がその体験情報を他者に発信もする。個人の体験自体が着火点となって、逆にデジタルだとかマスメディアに広がっていく。われわれはそれを「ライブマーケティング」と呼んでいて、電通ライブではそういうことを常に意識していきます。
過去に自分の仕事で感じた「真実の瞬間」を、まずひとつのエピソードとして紹介させてください。これはJTの「海の家」です。みかんぐみと一緒につくりました。数年前です。
日本たばこ「Paradise-AO」 鎌倉由比ケ浜にオープンしたブランドの世界観を体現した海の家
谷尻: ああ、懐かしいですね!
石阪: 「当該商品は『最高の居心地』を提供してくれるブランドである」ということを伝えるのがこの時のミッション。でも「居心地がいい」というのは、解釈が難しい、とても生理的な感覚だから。リアルな体験じゃないとできないですよね。
場所は由比ケ浜ですが、海の家というとそれまでは、着替えをする場所、ビーチでの食事の場所、ナンパの場所というイメージだったけれど、ここで過ごす時間そのものに価値を感じてもらえるような場にしたいなと考えました。自然と共生できるような。なので、日本建築物の特徴を積極的に取り入れました。外と内の境目をなくす。壁をやめて潮風や海への眺めを取り込む。ピクチャーウィンドー効果も積極的に狙いました。壁がないので風が気持ちいい。本当は壁をやめると営業上の不都合も発生するんですけど。雨がどんどん降り込んでくるから。でもそれよりコンセプトの体現を優先しました。
「Paradise-AO」夜の景観
谷尻: きれい!
石阪: 実際にこう見えるんですよ。由比ケ浜って、朝、潮が引いて、夜になると満ちてくる。夜の7時以降はサーフィンができる。サーファーが海の家のすぐ近くまで来てサーフィンをやっている。キモチの良い風、眼下に広がる夜の海、そしてサーフィンをしている人々の幻想的なシーン。制作者としての狙いや想像を超えたサプライズで、この場所にしかない強い「真実の瞬間」を感じました。
人の感情が強く動くときって、それが怒りであれ、悲しみであれ、その直前にまず「驚き」があると、ある電通のクリエーティブディレクターが言っていました。まあ、近頃よく使われる「WOW!」ということかもしれません。それをどれだけしっかり設計しておけるかということが空間では大事だと思うんです。
サポーズに「社食堂」をつくったのは、細胞をデザインしたいから
天野: 僕らがやっている仕事ってリアルな売り場だから、1日に来る人は何百人とかで、広告のKPIでいうとマスメディアとは桁が違いますよね。比較にならないというか。
石阪: デジタルの進化が、対極にあるリアルの価値を押し上げてくれていますよね。これまでは、リアルは深く体験を伝えることができるけれども、リーチは取れないと言われてきた。デジタル技術がそれを補ってくれるようになった。故に空間開発を含め、リアルなエクスペリエンスがコミュニケーション視点でも非常に重要になってきた。
天野: 僕は家業が家具屋さんで、リアルに小売店出身なので、来てもらって買ってもらうところまでが僕らの使命で、伝えるだけじゃなくて「どうしたら買ってもらえるのか」がずっと重要だった。なので、今のリアル回帰は至極当然の流れだと感じています。
谷尻君もまだまだ住宅設計をやっているし、この谷尻君の新事務所には社員のための食堂があるけど、僕は谷尻君がそういうことやるのがすごくわかります。リアルな生活とつながっていたいという欲求がずっとあるのだと思います。
谷尻: 僕の根っこにあるのは、細胞のデザインなんですよ。
サポーズデザインオフィス 谷尻氏
天野: 細胞のデザイン?
谷尻: 結局みんな、一日に二食なり三食食べるじゃないですか。食べたら、その食べ物が自分たちの細胞をつくっている。その細胞が自分の脳に指令を下す。考えることも眠ることも、あらゆる細胞が、どんな食べ物でつくられているかがすごく重要で、人は忙しくなればなるほど不摂生でいいかげんな食事をし始める。そうすると、だんだん体調を崩しやすくなったり、ちょっとうつむきかげんになったりするので、みんながちゃんと健康的な細胞をつくれる環境をデザインしておけば、いい会社がつくれるんじゃないかというトライアルです。
石阪: なるほど。細胞のデザインは、会社のデザインでもあると。
谷尻: はい。だから、名前は「社食堂」。あくまで社員の食堂が前提にあって、内側を考えることが社会を考えることなので。僕はブランディングというのは、インナーブランディングが最も大切なブランディングだと思っているので、まず自分たちの会社をブランディングしています。
天野: 社員の人の身体をつくれば、良い仕事もつくれる。
谷尻: 社員をブランディングする。その細胞形成がうまくいけば、絶対いいチームになるし、「同じ釜の飯」と昔の人が言うように、みんなが同じ細胞を形成し始めると、東洋医学みたいに思考が整うわけです。根っこはやっぱり体ですからね。細胞をデザインするのが一番根源的で、後から効いてくるんじゃないかな。
天野: 同じものを食べれば、同じうんちが出るからね(笑)。
谷尻: 社食堂を社員以外にも利用してもらうのは、もちろん外の人とコンタクトしたいというのもあるんですが、ここに来て建築の本を手にとってもらって、建築家に頼みたいと思う人が、一人でも世の中に増えてくれたらいいなということもあるんです。
僕らは、人間のことを考えてずっと建築をつくっていた。過去の建築家って、建築作品を目指して、建築をつくっていたと思うのです。でも「事」と「物」が一体にならないと、ソフトとハードが乖離して「箱物」という言葉が生まれたように、箱はあるけど機能しないという建築が日本にたくさん生まれてしまう。特に震災以降は、「人と建築は絶対に切り離せないよね」というのが、21世紀の建築家の在り方になっているんじゃないかな。
ジョージクリエイティブカンパニーは店をつくるだけじゃなく、「経営」まで一緒につくる
天野: 僕は時代に合わせたリアルなお店を「買ってもらってなんぼ」という観点からつくっています。
谷尻: そこをちゃんと考えているから、譲滋さんのつくる店は物が売れるんですよ!
天野: 店舗は完成よりも、オープンしてからがむしろ大変。僕たちが企画したりデザインさせてもらったりするお店は、必ず半年から1年は、「経営が安定するまで一緒にやりましょう」というところまで責任持ちたい。企画して携わったところが、すぐにつぶれちゃったら嫌だし。自分たちにとっても、子どもみたいなものだから。
谷尻君も、個人の住宅とかやっていると手離れが悪いじゃないですか。どこかが水漏れしたらすぐ電話かかってくるしね(笑)。
ジョージクリエイティブカンパニー 天野氏
谷尻: だから、建築家は有名になると、個人住宅をだんだんやらなくなりますよね(笑)。
天野: 会社の経営的には、効率悪いものね。
谷尻: 利益も絶対出ない仕組みなので、個人住宅は。でも、みんながやめるからこそ、僕はやるんです。逆に言うと住宅をずっとやっていたおかげで、今は店舗でも「リビングっぽい感じをつくってほしい」と言われる。時代が安らぎを求めているから。
天野: 人の「営み」をきちんと感じることが大切ですね。時代ごとに人々の「営み」も変わってくるし、震災後も、一瞬で「営み」が変わったしね。
石阪: ところで、僕が初めて天野さんと仕事したのは、アスクルの仕事です。家具のショールームがお台場にあって、クライアントからはもうちょっと使用シーンを想像できるように演出したいというリクエストがあったときに、アスクルの商品を中心にライフスタイルグッズを加えスタイリングを整えてもらった。すると見違えるようになったんです!
天野: リアルなオフィスで使っているように見せてあげただけで、「ああ、こうやって使うんだね」というシーンがイメージできた。
石阪: それが衝撃だったんです。天野さんのアプローチは、僕ら広告会社のデザインチームとは全く違うアプローチだったから。
谷尻: ジョージクリエイティブカンパニーは、編集能力が高いですからね。
天野: 自分たち自身がリアルな店をやっていたからだと思う。「CIBONE」だったり「GEORGE’S」だったり。お客さんの顔を見て商売していたからかな……。
<了>