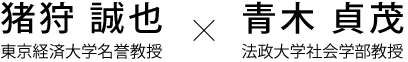(※所属は「アド・スタディーズ」掲載当時)
前回に続き、日本における広報を草創期から理論的・実践的に主導され、『日本の広報─満鉄からCSRまで』という記念碑的著作でも知られる猪狩誠也氏をゲストにお迎え し、企業のコミュニケーションやブランド研究を通して企業の文化力を提案されてきた青木貞茂氏と、これまでの歴史を振り返りながら、企業コミュニケーショ ンとしてのパブリックリレーションズの重要性と理論的な再構築に向けた課題と展望を話し合っていただいた。
コミュニケーションとは何か
青木:ドイツの哲学者ハーバーマス(Jügen Habermas)がコミュニケーション的理性とか、対話的理性という言い方をしています。熟慮して討議することが大事だということですね。
猪狩:熟慮して討議したものが跳ね返って、また熟慮してという1つのスパイラルになることが大事だろうと思います。例えば企業でも、会議がコミュニケーションではなくパソコンに収めたデータや新聞情報を持ち寄る報告会議になっているところも多いようです。ある中小企業の社長が「パソコンを会議に持ってくるな、もっと議論しろ」と言ったという話もありました。
青木:アップル創業者のスティーブ・ジョブズがアップルに復帰したあとで最初にやったことは皮肉なことに、パワーポイントでのプレゼンを廃止したことでした。特に製品会議で白熱した議論を起こすときにスライドではまったくの一方通行になってしまうので、彼はホワイトボードを持ってきて、製品のデザインを模型にしたモックアップ(mock-up)を目の前において、論議したそうです。
連絡会議というのはまさに軍隊の報告と同じで、あることを一方的に伝えたらおしまいという発想です。マーケティングや経営でもやはり軍隊的な発想が強く、言葉としてはインフォメーションやストラテジー、ターゲットといった用語を使っています。上になればなるほど、軍隊の幹部会議的になり、報告が承認されて終わりみたいなことになっているようです。これでは広報部門が対話を司るコミュニケーションの要にはなかなかなれないですよね。
猪狩:昔、ある官庁の方に聞いたことがありますが、上部の会議になればなるほど、本来の会議というより、"この間はこちらが譲歩したから、今度は言い分を通させろ"というようなお互いの貸し借りの論議になるということでした。本質的な議論ではなく、"顔を立てる、立てない"ということになりがちだということです(笑)。
青木:ベンチャー精神は、別にアメリカのシリコンバレーの専売特許ではありません。ソニーやホンダは、小さな町工場から世界を見据えてイノベーションを起こして日本の礎を築いたと思いますが、イノベーションの原動力になったのは、基本的には対話や会話だったのではないでしょうか。
猪狩:産業資本主義が金融資本主義に変質したことで情報が決定的なものになり、問題を議論する世界ではなくなってしまいました。優秀な情報通と鋭いトップがいればそれで済むという感じですね。一方、ものづくりの産業資本主義では集団の力を発揮させるための会話や対話が原動力になっていました。
青木:ソニーにしてもホンダにしても、組織に経営者の人格や生きざまなどが滲み出てきて、システム化しようにもそこをはみ出るような人間臭さみたいなものが絶えずあったと思います。インフォメーションとコミュニケーションが違うのは、人間のキャラクターだとか生きざまだとかいったものが、あるかないかではないでしょうか。
言語哲学では、コミュニケーションにはコンスタティブ(constative)、事実確認的なものと、パフォーマティブ(performative)、行為遂行的なものの2種類あるとされています。事実確認的というのがインフォメーションに対応し、パフォーマティブは人と人との関係性や感情的・精神的な絆のやりとりと解釈されていますが、企業のコミュニケーションにも当てはまるような気がします。リレーションズというのは、顧客と企業の間で価値の共同体みたいなものができるということだと思いますが、それを可能にするのは、やはり、行為遂行的なものではないでしょうか。
猪狩:かつてはソニー文化、トヨタ文化とかいったものがなんとなくありました。ところが、世の中がだんだん無機的になって、どこの会社の人と話をしていても同じ言葉が出てくるような感じになっています。個性というか人間臭い温かいコミュニケーションがなくなってしまいました。
見田宗介さんが『現代社会の理論』の中で、生産至上主義は公害や資源の問題を引き起こすが、情報化と消費化によって解決できると言っています。これはボードリヤール(Jean Baudrillard)なども言っていますが、対話文化みたいなものが消費化社会の基盤にならなければならないということだと思います。
コミュニケーションの生産性
猪狩:今や、ツイッターなどでのコミュニケーションは非常に短いものになっていますが、これで本当の対話ができるのか、非常に疑問ですね。
青木: IT化はコミュニケーションを育てるというより、インフォメーションの流通の効率化やコンビニエンス化には効果があると思いますが、それが非常に極端な形で進んでいます。最近の若い人のLINEを見てびっくりしたのは、もう文字すら書かないでスタンプでやりとりしていますから、それを対話と言えるのか、考えてしまいます。
猪狩:ツイッター文化はある種のデモクラシーを育てるという人がいますが、僕はツイッターというのは、プロパガンダの手段にはなっても関係性を形成するツールにはならないという感じがしています。
青木:もちろん、頭から全部否定するつもりはありませんし、いろいろ使いこなしてTPOを考えてやってくれればいいとは思います。フェース・トゥ・フェースで話す、メールでもパソコンと携帯を使い分けるといったように、モードやルール、マナーといった一種の生活知が伴わないと、コミュニケーションは成立しないはずですが、今の若い人たちにはなかなか理解してもらえません。
猪狩:どうしたら対話の文化を世の中に醸成できるかということは非常に難しいことですが、場づくりが重要だと思っています。私事になりますが、近所の人たちと、自分が読んだ本を持ち寄ってみんなで話をしようというブッククラブをつくりました。1回目は6、7人、2回目は10人ほど集まりましたが、けっこう和気あいあいで話が弾んでいます。白熱した議論とまではとてもいきませんが、そういう会話がなんとなく地域の中でも起こるということが大事なんだと思います。
会社やいろいろな集団の中でも同じで、ある種のゆとりあるコミュニケーションができていくような工夫は可能です。広報というのは、社会貢献といった問題だけではなくて、そういう空気をつくりだすひとつのコミュニケーションの発生源にならなければならないのではないでしょうか。
青木:まさに、ER(Employee Relations)の基盤をつくる基本中の基本です。広報室をつくって、あとは社内メールで回して、情報は伝達したから終わりという話ではなく、社員同士のさまざまなバリエーションのあるコミュニケーションのやり方を広報部門が中心になって仕掛けていくということですよね。
猪狩:4、5年前だと思いますが、ある大手企業が中止になっていた新入社員の全寮制を復活させたところ、社内の雰囲気にも影響したと聞きました。もう1つは社長の発案で月に1回、金曜日の夜6時ぐらいから食堂でビールパーティーをやることにしたそうです。社長が出てくるから敬遠するのではなく、こういう席で一丁言おうかという若い人たちも来て、非常にいい効果が出ているという話も聞きました。
青木:どんなにIT化が進んでも、人と人とのつながりは最後にはフェース・トゥ・フェースですよね。サイバーエージェントの社長の藤田(晋)さんが『起業家』という本で、終身雇用を目指す日本的経営を取り入れた結果、すごくうまくいったということを書いていました。価値観を共有し、ある1つの方向に向けて社員が一体化するためには古い人事制度が機能したわけです。同社は、最先端のアメーバブログで大きな利益を得てメディア企業に変わりましたが、あるステージにおいては日本的経営が実は普遍的な法則としていまだに有効だったというわけです。
猪狩:僕はコミュニケーションがもっている生産性をもっとしっかり捉えて、組織文化の中に入れていくということが非常に大事だと考えています。小さいところでも大きなところでも、いつも対話が行われていれば、実は大きな生産性につながっていくと思っています。
青木:PRを担当する社員がそういう熱を持って、わりと厭わず対人的なコミュニケーションを積極的に仕掛けていけば、その雰囲気とか、感情的なものとか、イメージみたいなものがいつの間にか社内に滲み出てきますよ。
猪狩:それが企業文化というものになっていくということです。あそこの会社の社員は気持ちがいい、話をしていると楽しくて役に立つといったことが伝われば、自分の会社もそうなりたいということになってくるはずです。あまり難しいことを言うということではなく、会話や対話から生まれるある種の文化を育てるということが非常に大事なんです。
青木:それはソーシャルメディアを使う場合にも言えますね。
猪狩:そう思います。
青木:ローソンのシンボルキャラクター「あきこちゃん」がすごい人気で、ソーシャルメディア上に千何百万人の友達がいるようです。まさに社内外の人との対話を意識したもので、デビューしたときは後ろ姿だけで顔がなかったそうですが、ローソンの女性店員はどんな顔なんでしょうと投げかけて対話を交わすことで顔ができ、人気者になったわけです。
これは硬直化した官僚的組織ではできません。有名なあのデザイナーやイラストレーターを使おうということになってしまうからです。
猪狩:しかも、企業文化というのは、いろいろなところに染み出てくるものですが、こうした企業の個性は、それぞれ違うはずです。
青木:逆に、違わなければ私たちは選ぶことができません。各企業の提供する価値がトップ企業とまったく同じだったら気持ちの悪い全体主義社会です。企業はみんな違う価値を主張してほしいですね。英語ではインテグリティ(integrity)で、私は「尊敬すべき一貫性」と訳していますが、信念なり、目標、ビジョンと行動が一致しているということが、企業の魅力になるのだと思います。
〔 第3回へつづく 〕
※全文は吉田秀雄記念事業財団のサイトよりご覧いただけます。