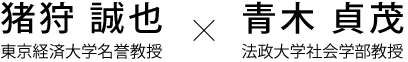(※所属は「アド・スタディーズ」掲載当時)
前回に続き、日本における広報を草創期から理論的・実践的に主導され、『日本の広報─満鉄からCSRまで』という記念碑的著作でも知られる猪狩誠也氏をゲストにお迎え し、企業のコミュニケーションやブランド研究を通して企業の文化力を提案されてきた青木貞茂氏と、これまでの歴史を振り返りながら、企業コミュニケーショ ンとしてのパブリックリレーションズの重要性と理論的な再構築に向けた課題と展望を話し合っていただいた。
信頼こそ企業存立のキーワード
猪狩:以前、「戦略的パブリックリレーションズ」という言葉が話題になりましたが、戦略的ということをそんなに安っぽく使ってほしくない、基本のところで人間をばかにしているという感じを持ちました。
青木:人間が操作対象になっていますからね(笑)。戦略PRもそのやり方が目的ではなく、顧客やステークホルダーに自分たちの心情や真情をしっかり伝えることが目的のはずです。最近の若いネット系の人たちはそこがなかなかわからず、効果と目的が逆さになっているような気がします。
猪狩:両方がイコールになれば一番いいのですが、効果ばかりに目を奪われると、人と人との関係性を壊してしまいかねません。あくまで、対話になっているかどうかということで効果を測ることが大切です。
青木:私は戦略的というより統合的という言葉のほうが好きです。戦略的というと手段や効果に目が向けられがちですが、本当の意味で企業と顧客あるいは従業員やステークホルダーたちと相互の信頼性を築くためには、感情的なもの、感性的なもの、精神的なものと、理性的なもの、論理的なもの、便益的なものが一体化した統合的なアプローチが必要なのではないでしょうか。
猪狩:やはり、信頼性がひとつのキーワードです。なぜなら、パブリックリレーションズにおける関係性というのは、お互いに信頼性をどうつくり上げていくかということが前提になっているからです。
青木:日本人は、アーカー(David Allen Aaker)の理論とは関係なく、企業の信頼性を象徴する暖簾とか看板が大切だということを知っていたはずですが、その重みはいつの間にかなくなってしまったような気がします。目先のことに目を奪われ、今ここで多少損しても、この商売が100年後でも社会的な存在価値を失わないようにする、という発想が希薄になったのではないでしょうか。
猪狩:社会の流れはなかなか変わらないでしょうから、少なくとも逆にそうした趨勢に影響されない人間集団や組織をどうつくっていくかが重要になっているというのに、経営者はグローバル金融資本主義の中で儲けることに頭が行き過ぎ、ブレーキを忘れているようです。四半期ごとの業績で自分の地位も決まるとなれば、近視眼的にならざるをえませんが、今求められているのは、まさに長期的な視点ではないでしょうか。
コーポレート・コミュニケーション・オフィサーとは
青木:企業におけるコーポレートコミュニケーションを担う広報のセクションは、歴史的には広告宣伝部や総務系、あるいは社長室の中の小さなセクションなどと、別になくていいような扱いをされ続けてきましたね。
猪狩:企業によってかなり大きな違いがあります。企業文化や企業の社会的責任というテーマがクローズアップされ、コーポレートコミュニケーション本部とか広報本部がスポットを浴びた時代もありましたが、結局、お金を稼ぐことこそ企業の使命だということになり、広報の価値が下がってしまったのです。
しかし、いい会社は社内にも社外にもきちんと目配りをしています。例えば、社内報は人事部の片隅でつくっていればよかったようなものですが、企業によっては社内広報の重要度は上がっています。一方で、紙の社内報は時代遅れだと、どんどんメールに切り替えたりしていますが、メールの洪水に社員たちが困ってしまうという状況もあるようです。
僕は社内広報は非常に重要な役割を担うと思っています。今の企業環境を考えてみると、実はコミュニケーションの役割が大きくなってきているからですが、トップがなかなか気がつかないというのが実情ではないでしょうか。
青木:先生はコーポレート・コミュニケーション・オフィサーという担当を役員で決めて、統合的にマネジメントできる人を置くべきだとおっしゃっていましたね。
猪狩:これは、ある意味で権力や権限を持った人間でないとできません。しかも、マーケティングを含めコミュニケーションの重要性をしっかり理解している人でないといけませんから、非常に難しい立場ですね。
青木:どうしてもコーポレートコミュニケーションというと、いわゆるマーケティングや営業とは切り離され、ある種、企業イメージのことだけ考えていればいいみたいなことになっていたと思いますが、ツイッターやフェイスブック、ホームページなどで簡単に生活者がコンタクトしてきますから、マーケティングのことなのか、コーポレートレピュテーションのことなのか判別できません。そういったときに従来の縦割り的なコミュニケーションスタイルの組織が対応できるかどうか疑問です。しかし、最終的には企業のブランド価値がどれだけ向上するかということになってくると思いますから、コーポレート・コミュニケーション・オフィサーは、コーポレートブランド全般にわたる価値に関わるコミュニケーションを統括する重要な役割を担うはずです。
猪狩:現実的にはそうした人が適切に配置されているケースは極めて少ないのではないでしょうか(笑)。
青木:当然、広告とも連動しますね。
猪狩:まさに統合です。しかも、情報はフォーマルな形だけで入ってくるものではなく、外の世界ともいろいろな意味でつながっていなければいけませんから、統括する人はスーパーマンといった感じです。しかも、かなりトップと近いところに本部があり、その下に広告がわかる、あるいは何々がわかるという人が何人かいて、年がら年中コミュニケーションをやっているというイメージです。
青木:まさにフォーマルとインフォーマル、表と裏の両方に通じていないとハンドリングできませんから、確かにスーパーマンです。要は、報告とか書類ではなく、本音や実情を簡単に出してもらえるような人間関係をつくっておかないといけないし、パブリックリレーションズで関係づくりをするためには、企業の中にプロフェッショナルなグレートコミュニケーターを持たなければいけないということです。その人がまた人材を育成して、自分の分身を増やしながらそのサイクルをしっかりつくるということですね。日本の企業の中でも、業績が不振なところは、本来の意味でのグレートコミュニケーターなり、パブリックリレーションズの重点の置き方や資源の割き方が弱いのではないでしょうか。
猪狩:やはり、広報学会やパブリックリレーションズ協会でも、コミュニケーションと組織論をもう少しきちんと勉強し、理論的に再構築しなければならないと思いますね。
青木:先生に音頭をとってほしいですね(笑)。何でも物事を動かすためには顔が必要だと思います。具象シンボル的な人がいて、そこにドラマのあるシンボルストーリーがあるといったシンボル連鎖のような形ができないと、ムーブメントは起きませんからね。
「文化力」が決め手
猪狩:去年の6月にイギリスのボーンマス(Bournemouth)というところに行ってきました。そこでは「パブリックリレーションズの歴史」(International History of Public Relations Conference)という会議が毎年1回あります。出席してびっくりしたのは、23カ国ほどから60人ぐらいの人が集まっていたことです。日本の広報学会も、これまでのように実務的なことだけではなく、歴史的なことも勉強をする必要があるのではないでしょうか。
青木:日本に入ってきたパブリックリレーションズのパラダイムは矮小化された不幸な歴史を辿ってきましたからね。
猪狩:私がダイヤモンド社に入ったのは1957年で、58年にヴァンス・パッカード(Vance Packard)の『かくれた説得者(The Hidden Persuaders)』を担当したのですが、訳者の東大教授、林周二さんがその本に刺激されて『イメージと近代経営』『企業のイメージ戦略』という本を2冊お出しになって、イメージドクターというあだ名をつけられました。企業には非常にショッキングだったようでしたが、それから4年ぐらい後に、南博先生と石川弘義さんに翻訳いただき『浪費をつくり出す人々(The Waste Makers)』という本を出しましたが、そこでは当時のアメリカの成熟した大衆消費社会の姿が批判的に描かれています。しかし、当時の日本にとっては学ぶべき教科書になってしまいました(笑)。
青木:非常に皮肉だと思います。例えば、ドラッカーの処女作が『経済人の終わり』ですよね。ヒトラーのファシズムがなぜ成立したのかを分析しています。「自由」と「民主主義」が経済の成功と一体化し過ぎたために、いざ恐慌になると民衆は民主主義に絶望して全体主義になびいたと言います。ドラッカーは、経済哲学、社会哲学的な人だったのが、いつの間にか経営学の神様になっているというのも不思議です。
本田(宗一郎)さん、井深(大)さんや盛田(昭夫)さんにしても、世界一の大金持ちになるために事業をやっていたわけではありません。ジョブズもそうです。彼は日本や禅が好きで、世の中を変えるすごい商品を出して世界を変革したいという熱い思いを持ち続けていました。
私は、本当にブランド価値を上げ、長期的な信頼関係を上げる最終的なリソースは文化力だと思っています。組織の中にコミュニケーション文化をしっかりビルトインすることが生産性を上げることにつながるはずです。しかし、1カ月後には成果を出せとか、四半期ごとに数字を挙げろと言われてしまうと、なかなか文化は育ちませんよ。
猪狩:企業の雇用状況を見ても、近視眼的になっていて労働の文化みたいなものを壊しています。社内競争と淘汰では組織が硬直化し、長い目で見たら国そのものが疲弊していくかもしれませんね。
青木:野中(郁次郎)先生がよく暗黙知と言われていましたが、労働文化というのは、カルチャーということだけではなく、インフォーマルな知識やノウハウ、規範などの蓄積も含んでいるはずです。そういうものを失うことこそ大きな損失です。
猪狩:80年代に企業文化ということが盛んに言われましたが、それは企業のイメージアップのためで、外部と一緒に育てていくという視点がなかったのかもしれませんね。
青木:以前は、正式なビジネスが授業だとすると、放課後には研究会や同好会といったクラブ活動をすることがよくありましたし、飲みニケーションなどの中で、形式知ではないインフォーマルなノウハウや規範、マナーやモードといったものが伝授されていましたが、今は残念ながらこうした機会も少なくなってしまいました。
猪狩:文化というのは、オフィスの中だけでは育ちませんよ。さまざまな人との対話、豊かな関係性から生まれるものですよ。
青木:もちろん、会社としての規範やコンプライアンスがありますから、仕方がない面もあると思いますが、そういう枠がありつつ、いかにコミュニケーションを活性化するかという知恵を絞ってもらわないと、組織は活性化しないと思います。
猪狩:コミュケーションの生産性を考えながら、TPOによって会議室を使い分けている会社もあります。会話しやすい身近な場づくりからやったらどうでしょうか。
青木:そうですね。本日はありがとうございました。
〔 完 〕
※全文は吉田秀雄記念事業財団のサイトよりご覧いただけます。