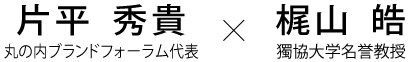(※所属は「アド・スタディーズ」掲載当時)
調査にまつわる情報や技法が複雑・多様化するなか、マーケティングの世界では何が求められているのだろうか。
今回は、長年にわたってアカデミズムと実務の世界で調査に携われた梶山皓氏と、データ解析からブランドまで幅広くマーケティングの世界を主導してこられた片平秀貴氏に、リサーチの世界の大きな流れとそこに生まれている問題点や課題をご指摘いただくとともに、 調査とは一体何なのか、その原点を探りながら、今後のマーケティング活動における調査の思想、位置づけ等についてお話しいただいた。
調査にまつわる2つの流れ
片平:私は最近、調査会社の人からいろいろな話を伺いましたが、調査という世界が今までになかったさまざまな課題に直面しているのではと感じています。今日は、調査やリサーチというキーワードを広くセットして、梶山 さんのお考えを述べていただき、調査の世界を深く掘り下げてみたいと思います。
梶山:実は今日の対談のために、片平さんの著書を読み返してみました。80年代に書かれた定番の『マーケティング・サイエンス』、90年代の『パワー・ブランドの本質』、そして最近の『世阿弥に学ぶ100年ブランドの本質』です。『マーケティング・サイエンス』を今改めて読むと、アメリカの論理実証主義とオペレーションズ・リサーチの理念を融合して書かれたような印象を持ちました。その後の『パワー・ブランドの本質』では気づかなかったのですが、『世阿弥に学ぶ100年ブランドの本質』では推論の仕方が大きく変わり、世阿弥の芸術論とブランドを重ね合わせながら類推によってブランドの本質を探っておられるようです。
これは、解釈学的なアプローチの1つではないかと思いますが、演繹でも帰納でもない、まったく予想もしない類推を用いてブランドを論じているわけで、『マーケティング・サイエンス』の科学的な方法とどのような関係にあるのか、とても興味を持っています。
片平:ありがとうございます。
梶山:まず、調査に関する考え方を少し話させていただきます。本日の「調査の思想」は大きなテーマですが、その前に調査とはいったい何なのかを考えてみました。私が勤めていた大学にはかつて市場調査論という講座があり、他にも調査の講座が置かれている大学があるように、調査論はアカデミズムの中にある領域学で、学際的な応用科学として存在し、アメリカのプラグマティズムの風土の中で生まれた学問と考えられます。
調査論をどう定義したら良いのか、とりあえず最大公約数的にまとめると、「個人と集団の意識や行動を説明し、理解し、予測するための方法を研究する学問」ということになるのでしょうか、プラクティカルな価値を期待されている学問と言えますね。
片平:そうですよね。
梶山:中心にあるのはやはり調査の実施と関わる実践的な部分です。大きく分ければ実査、分析、評価があり、具体的にはサンプリング、質問作成、モデリング、分析方法、検定などさまざまな問題がありますが、こうした調査体系の根幹が今大きく変わろうとしています。それはまず調査の理論的な柱である「統計学」で起きています。
われわれはこれまで推計統計学を唯一の拠り所にしてきました。とくにマスサーベイはダニエル・スターチ以来、80年以上にわたる伝統があります。推計統計学では何はさておき「真の値」を持つ母集団の存在を仮定し、得られたデータを確率変数とみて元の母集団の姿を想定して、その平均と分散を求めていろいろな統計量を出します。大学ではこうした統計学だけを習い、そのあり方に何の疑いも持ちませんでしたが、ベイズ統計学が現れて事情が変わってきました。ベイズ統計学はそうした母集団の存在を仮定せず、データを不確実な情報とみてその平均や分散の確率分布を求め、ベイズの定理を用いて統計量を出します。理工系の分野でかなり前から使われていたようですが、それが社会科学にどんどん入ってきました。
もう一つの大きな変化は「調査の方法」です。これまでは実証的な方法が中心で、思想的にはデカルト以来の数量化と要素還元を暗黙の前提にしていました。それに対して近年は解釈学的方法が広がっています。いろいろな考え方があってひとまとめにするのは難しいのですが、人間のリアルな姿を描いていくとか、テキストに隠された作者の心象を解読していくやり方です。もともとはヨーロッパのポストモダン哲学の影響によるものでしたが、80年代になるとアメリカのマーケティング・サイエンス論争を経て解釈学的な流れが入ってきました。この方法は興味深いことに日本の精神的風土としっくり合っていて、学界の中でも確かな位置を占めています。
人間行動への着目が希薄化
片平:もう少し、続けてお話しいただけますか。
梶山:さらに調査の「推論」についても動きがあります。調査の世界では確率論を使った帰納的推論が主流ですが、歴史的にはガリレオ、ニュートン以来の演繹という考え方があり、理系は今もこちらがメインです。19世紀は実証主義の時代で帰納が力を持ちましたが、20世紀になって論理実証主義が出てきて演繹と帰納が並び立ち、哲学上の論議はともかく、研究領域によって役割を分ける形で今日まで来ました。
それでは演繹と帰納だけでいいのかというと、これだけでは大きな発見が出てこない。そこでアブダクション(abduction)、すなわち仮説形成によるブレイクスルーが求められています。この概念はもともとはパース(Charles Sanders Peirce)の提唱したものですが、たしかに演繹は新しい発見を生みませんし、帰納も観察された事実を超えた発見はできません。最近、研究の仮説がおもしろくないという話を聞きますが、仮説がつまらないと検証がいかに厳密でも成果がありきたりになってしまいます。
少し前にシャピロ(Gilbert Shapiro)がセレンディピティという、創造的な発見の意外な一面を示して話題になりました。偶然がもたらす幸運やひらめきのことで、ノーベル賞の受賞者などに多くあるそうです。調査でも何か新しい発見をしようと思うと、まず魅力的な仮説が必要になります。
こうした調査プロパーの動きに加えて、ICTの発達によって高度ネットワークと高性能コンピュータが現れ、大量データの蓄積と複雑な計算ができるようになってビッグデータが登場しました。ビッグといっても大きさも性格もいろいろですが、いずれにしてもビッグデータ時代に対応した新しい調査の形が求められています。このようなさまざまな変化の中で、改めて調査とはいったい何かが問われていると思います。
片平:僕は、実務家の立場からお話ししたいと思います。もともとわれわれの恩師が勉強し始めた終戦直後ぐらいから、アメリカにはマーケティングリサーチがあり、日本では統計学の伝統というか、いわゆる推測統計学が主に自然科学のほうで発達し、教育学や社会調査論といった領域で推論の精度を上げるために培われてきましたが、この2つがそのままマーケティングの世界に入ってきました。いまだに緊張感があるのは自然科学で、例えば原子に関する仮説をどう測定してどう検証していくかとか、新薬の効能についてみんなが納得する形で判断を下す材料をどう提供するかといったことは、まさに調査の真髄みたいなことになっています。
マーケティングも、もともとこうしたもののアナロジーで、消費者の価格感度がどうなのかとか、あるいは自民党が優勢なのか民主党が優勢なのかといったことなど、基本はそういうところで成立してきました。しかし、消費財メーカーがこういうことにお金を使うようになっていきます。例えば、大手広告会社がプロポーザルのときに「あなたのブランドはこんなふうに危ない」みたいなことを立証する材料として使うとか、「今の消費者はわれわれが考えている商品の方向性とは違うところを求めている」みたいなことを社内に説得するために使うといったことで調査市場ができ、同時に調査会社が大きく成長していきました。
こうした流れの中で、頑健な仮説を精度高く検証しようという研究分野のウエートが減り、本当に検証しているのかどうかがわからなくなっているような気がします。
方法論的にも、共分散構造分析とか、その前だとロジット分析や回帰分析といった分析主導型の研究が非常に多く見受けられ、サンプルのクオリティは大丈夫かといったことにはあまり注意が払われていません。サンプリング、回答者をどう確保してくるか、その構造が違えば結果も全く異なってしまいます。
先ほど仮説がつまらなくなったという話がありましたが、その原因は2つあると思います。1つ目は研究者の問題です。仮説といっても、それは人間が対象です。自然科学は自然が対象で、われわれは人間行動を相手にしているわけですが、生きた人間に触れて感じて何かメッセージを出そうという研究者としての姿勢が希薄になっていることです。
2つ目は手法的な問題です。論文でも、共分散構造分析や何々分析を使ったとか、何々モデルと何々モデルを比較したといった3次的、4次的レベルでの議論が中心になっています。そこの一番コアにある人間行動とは何なのかというところが抜け、人間体験も非常に乏しいのではないでしょうか。家族との触れ合いや人間としての触れ合いが少なく、上司や部下、あるいはクライアントとして表面的に付き合っているだけでは、すばらしい研究ができるはずがありません。実務家についても同じようなことが言えます。まさに応用科学の先の応用ですが、本来、日本の強みといえるセレンディピティには多くの学ぶべき点があると思っています。
梶山:何か、日本のセレンディピティに関する事例はありませんか。
片平:例えば、ハインツのケチャップ、あの逆さに置くチューブです。今、世界的に使われていますが、大本のストーリーは花王です。花王は、ユーザーのお宅を訪問して台所や洗面所、トイレなどを見せてもらい、主婦から切羽詰まった話や苦情を聞きながら論議しているということです。あのチューブは、調査した台所や洗面所が狭くて物がみんな縦に置いてあることから偶然に思いついたんです。要は人間の行動の中からユーザーが気がつかない新しい仕組みを見いだしてくる作法を知っているということですが、日本の研究者はそれをなかなか理論化できません。アメリカの研究者たちがポストモダンというようなことを言い出し、それを売りにしてクリエーティブアイデアを出す会社がありますが、彼らがやっている様々な手法は花王の手法そのものです。
〔 第2回へつづく 〕
※全文は吉田秀雄記念事業財団のサイトよりご覧いただけます。