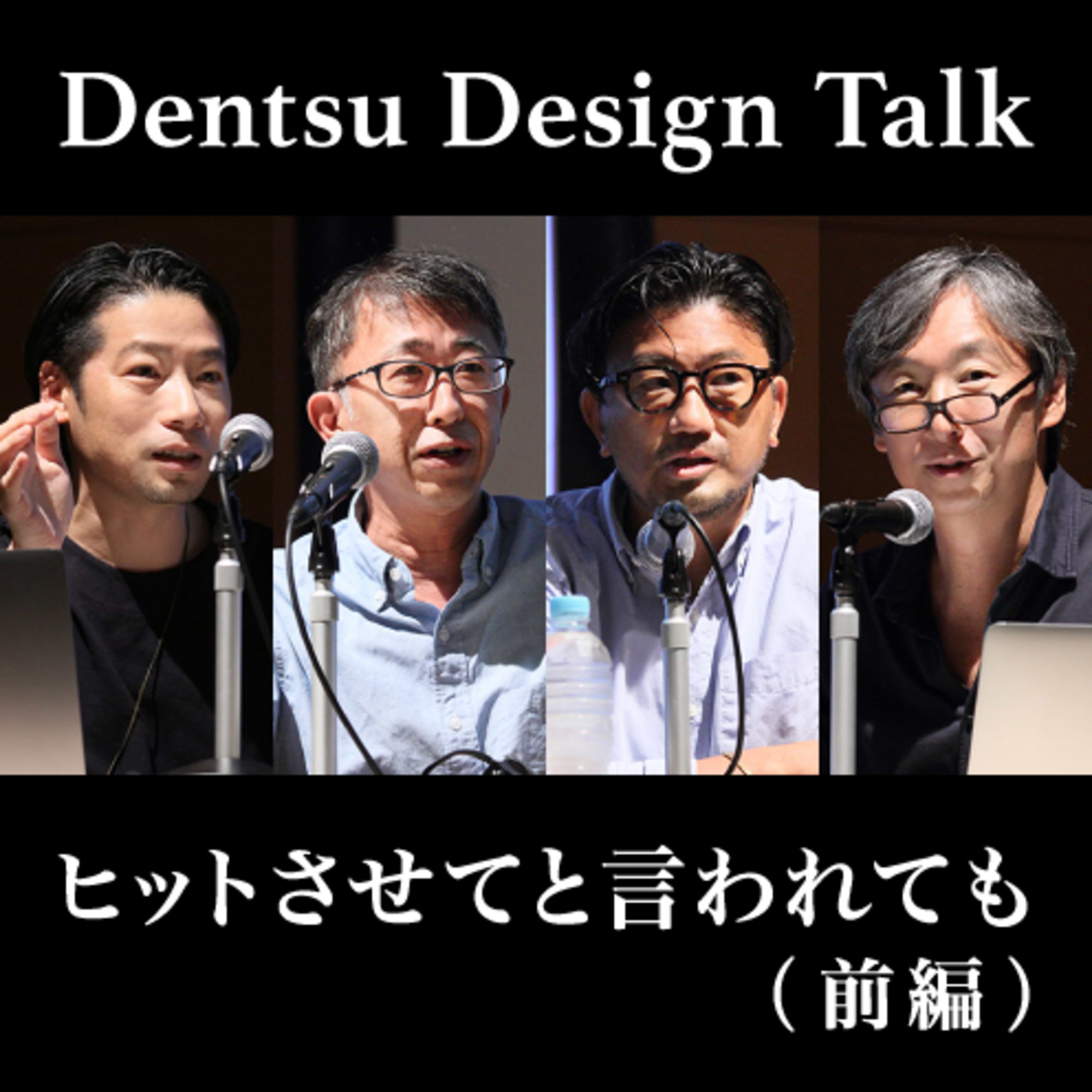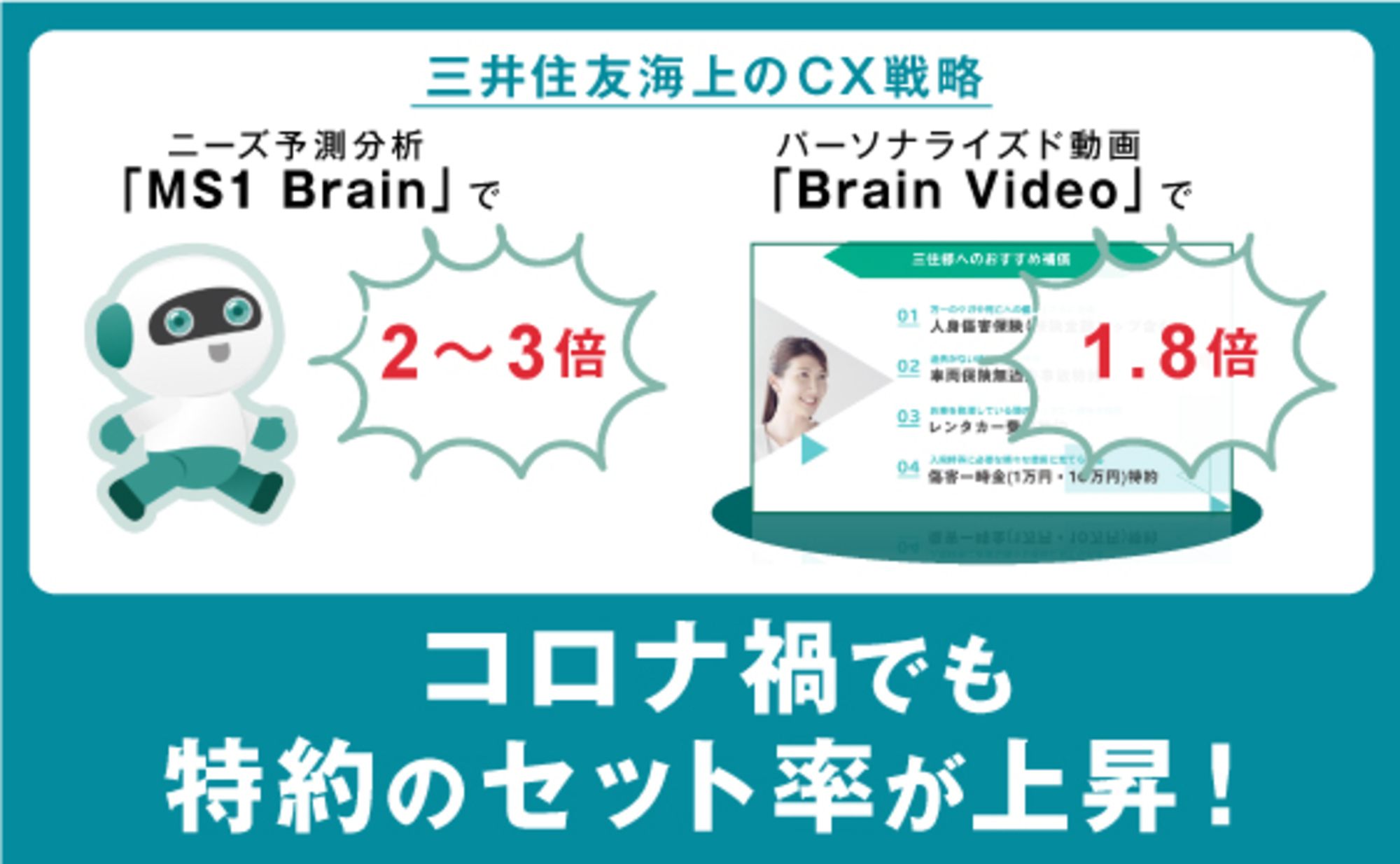グローバル化とデジタル化が同時に進む社会の中で、ビジネスにおけるビジュアルの力はますます重要になっています。今回のデザイントークは、電通ビジネスデザインスクエア未来創造室とビジュアルコンテンツ企画制作・提供のアマナのコラボ企画です。具体的には「ビジュアル×クリエーティブPR」「ビジュアル×新規事業」「ビジュアル×テクノロジー」「ビジュアル×インナー活性化」「ビジュアル×デジタルマーケティング」の五つのテーマをオムニバス形式で、電通とアマナのプロデューサーやクリエーターが“ビジュアルの持つ力”の本質に迫ります。
ビジュアル×クリエーティブPR
小柴:電通 未来創造室の小柴尊昭です。今回の電通デザイントークのテーマは、「ビジュアル・ブレークスルー・パワー!」です。ビジュアルはアートであり、歴史を語るメッセンジャーであり、想像を育む舞台でもあります。
最近は、ビジネスシーンにおいても、直観的で効率的なコミュニケーションをする上でビジュアルの重要性が認知されてきました。さらに、人と人との関係性や絆を確認する時にも、重要な役割を果たします。このようにビジュアルは、私たちのあらゆる活動と表裏一体で存在しているわけです。
片岡:アマナの片岡圭史です。直近の2、3年はストックフォトやCG、撮影など、アマナの持つさまざまな技術を組み合わせた事業を開発することに注力しています。当社は、400名を超えるクリエーターを抱えており、表現力もあり、実行力のあるプロデューサーがいます。今日は、当社が企業のビジネス拡大を支援する“武器”になることをお伝えできればと思います。
小柴:最初のテーマは「ビジュアル×クリエーティブPR」です。電通第3CRプランニング局 アートディレクターの川腰和徳さんと、アマナ プロデューサーの里見勇人さんから、ユニークな事例を紹介してもらいます。

(左から)電通 川腰和徳氏、アマナ 里見勇人氏
川腰:最初の事例は、Yahoo! JAPANの20周年記念企画「ヒストリー・オブ・インターネット」です。この企画は、1969年から始まったインターネットの歴史上の事象を、全てビジュアルで表現するものでした。
まずは事象を調べるところからスタート。合計で1300件ぐらいあり、特にインターネットが爆発的に伸びた95年以降は、膨大な量になりました。そういった事象を全てプロットして、ビジュアル化していきました。
アマナの里見さんには企画段階から入ってもらい、クライアントとも直接やりとりしながら、長い時間をかけて進めていきました。制作期間は約1年かけています。
里見:事象のリサーチ段階から、自分たちで行いましたからね。
川腰:そうですね。専門家の方に監修を依頼して、歴史の教科書としても使えるくらいに綿密にカテゴリーを分けて、それを半年間かけてビジュアル化した大作です。イラストを描き、それを写真で複写した上でレタッチして、組み合わせていきました。かなりの手間がかかっています。
最終的には18メートルに及ぶ巨大な展示物と、ウェブサイトにまとめました。ウェブサイトは、それぞれの事象をクリックすると、説明文が出てくる仕掛けにしています。
里見:表示されるディテールまでこだわっているので、どんどん見たくなります。
川腰:「ヒストリー・オブ・インターネット」は、ニューヨークADC賞で金賞を受賞しました。二つ目の事例は、北國新聞との取り組みです。金沢市で行われる高校生相撲の全国大会を盛り上げるためのPR企画で、「相撲ガールズ82手」という映像とグラフィックをつくりました。これは、相撲の応援サポーターの2人の女性が、相撲の全82手を再現する企画です。
新聞社がクライアントのため、新聞上だけでなく、動画もあることでPRにおける拡散力が全然違ってくるんです。実際、多くのテレビ番組で取り上げられました。
この企画は、「相撲ガールズ」のキャスティングに苦労しました。何度もオーディションを行い、ようやく柔道の有段者2人に出会えたのです。この2人には、500回を超える立ち合いをしてもらいました。
小柴:最初に川腰さんからアイデアを聞いた時に、内心で「無茶言うなよ」とは思わなかったんですか。
里見:はい、正直なところ「マジか?」と思いました(笑)。ただ、プロデューサーとしては、「楽しいことをやりたい」と熱意を持って言われると、ワクワクするんですよね。
川腰:信頼しているから、お願いできたんです。ビジュアルのクオリティーとアウトプットを担保した上で、限られた予算の中で最大のパフォーマンスを出すことはすごく重要ですからね。今後は、CGやARなどで、平面から飛び出したバーチャルな企画も実施してみたいです。
ビジュアル×新規事業
小柴:続いてのテーマは、「ビジュアル×新規事業」です。アマナ ビジュアルコンサルティング・スーパーバイザーの片岡圭史さんからお話ししていただきます。

アマナ 片岡圭史氏
片岡:現在、大手企業の新規事業部やベンチャー企業の多くが、消費者への情報伝達に課題を抱えています。自分たちの事業に対して自信を持っているがゆえに、一方的なコミュニケーションになりがちで、強みがうまく伝えられないのです。これから紹介するのは、こうした課題をビジュアルで解決した事例です。
まずは、JAXA(宇宙航空研究開発機構)との取り組みです。ご存知のように、JAXAは素晴らしい技術を持っています。しかし、世の中には「宇宙に関する技術は、自分たちに関係ない」と思っている人がほとんどではないでしょうか。その技術を、どう民間にプロットしていくかを共同で実施しました。
例えば、JAXAの衛星データを使って、絶対に衝突しない車をつくるといったアイデアが生まれたとします。しかし、それを言葉で共有しようとしても、人のイメージはそれぞれバラバラで共通認識を持つことは難しいでしょう。そこで、ビジュアル化することが求められたわけです。
別の例では、JAXAの持っている黒潮に関する数値データ。専門知識のない僕らが見ても理解できません。しかし、潮流をマッピングして動画にすると分かりやすくなり、理解できるようになります。これがデータをビジュアライズする技術「データ・ビジュアライゼーション」です。
ベンチャー企業のサウンドファンが開発した「ミライスピーカー」は、難聴者にも聞き取りやすい音を出すことができます。しかし、なぜ音が遠くまで、はっきり聞こえるのかという技術的な裏づけが人に伝わりにくく、誤解をさせてしまうことが課題でした。そこで、ミライスピーカーがどのように音を伝達できるのかというポイントをまとめたムービーを制作したところ、肝となる技術「曲面サウンド」に対する理解が得られるようになりました。
小柴:ここから学べるポイントは、「未知なるものを可視化すると、強力な共通言語になる」ということですね。人それぞれが違う解釈をしている技術を、ビジュアルとして定着させることで、意思統一が図れたり、関心を持たせたりできます。
ビジュアル×テクノロジー
小柴:続いてのテーマは、「ビジュアル×テクノロジー」です。電通グループの横断組織「Dentsu VR Plus」代表の足立光さんと、アマナ VR Contents Team 執行役員の岡本崇志さんから、VRの最新事例を紹介してもらいます。

(左から)電通 足立光氏、アマナ 岡本崇志氏
足立:現在のVRの世界は、グーグルやフェイスブック、アマゾン、アップル、マイクロソフトなど、多くの企業が参入しています。例えばフェイスブックは、コミュニケーション活性化ツールとして、「Spaces」というアプリケーションのベータ版を提供しています。これは、違う場所にいる友人と、まるで目の前にいるかのように話をしたり、一緒に場所を移動したりできるアプリです。
これはVRの次の領域として注目されている、ARとVRを融合させた「MR」(ミックスドリアリティー)の第一歩になります。このMRはもはや遠い未来の話ではありません。3年以内には実用化されるのではないかと言われています。
岡本:われわれアマナの持つ、撮影やCGに関する技術とストックフォトなどの経営資源に表現力を組み合せれば、新しい「体験」を生み出すVRコンテンツをつくることができます。
伊勢丹新宿店のイベント「JAPAN SENSES(ジャパン・センシズ)」でも、VRによって店舗内で屋久島を体験してもらいました。VRによるリアルな体験を、物販につなげる試みです。制作期間や予算が限られる中、われわれamanaimagesで取り扱いを始めたVRストック素材を使うことで、低コスト・短期間で制作できました。
もう一つ「リアルタイムレンダリング」での事例を紹介したいと思います。これは、CGを活用することで、自分自身が空間を自由に移動できるんです。物の裏側を見るような体験も可能で、これまでの受動的な映像体験と違い、能動的な体験が可能になります。
例えば、これまでは自動車の販売店でカタログやウェブブラウザなどを見ながら、グレードや色、オプションをカスタマイズしていましたが、「リアルタイムレンダリング」であれば、CG上で実物サイズの理想のクルマを体験することが可能になります。このように体験を購買につなげていくことができるわけです。
足立:ショールームにいながら、車を運転する体験もできるんですよね。
岡本:はい。コントローラーを使えば、運転体験だけではなく、自分の手で物をつかんで投げるといった体験もできます。他にも、未来世界のような実在しない世界を体験させたり、住宅やインテリアのシミュレーションも可能です。
現時点では広告やプロモーションに加えて、建築現場の安全体験や新入社員の育成にも活用されています。とても可能性のある技術ですから、今後は、もっといろんな動きが出てくるのではないでしょうか。
足立:2020年に向けて、これまでと違うスポーツの見方を提案しようという動きが起きています。KDDIの自由視点技術では、自分がフィールドに入ったような感覚でスポーツを観戦できます。そういう時代の到来を見越して、VR素材やコンテンツを入れておくプラットフォームをアマナと一緒に構築していくことを考えています。
小柴:VRは個人的に遠い未来のものというイメージを持っていましたが、お話を聞いているうちに「自分ごと化」されてきました。
足立:今はスマートフォンが出始めた頃と似ていると思っています。発売当初は「何に使うの?」と思っている人が大勢いましたが、いつの間にか便利なツールとして普及しました。VRも同じで、あっという間に生活に浸透していくでしょう。
※後編に続く
こちらアドタイでも対談を読めます!
企画プロデュース:電通ライブ デザイン&テクニカルユニット キャンペーンプランニングルーム デジタル&アカウントプランニング部 金原亜紀