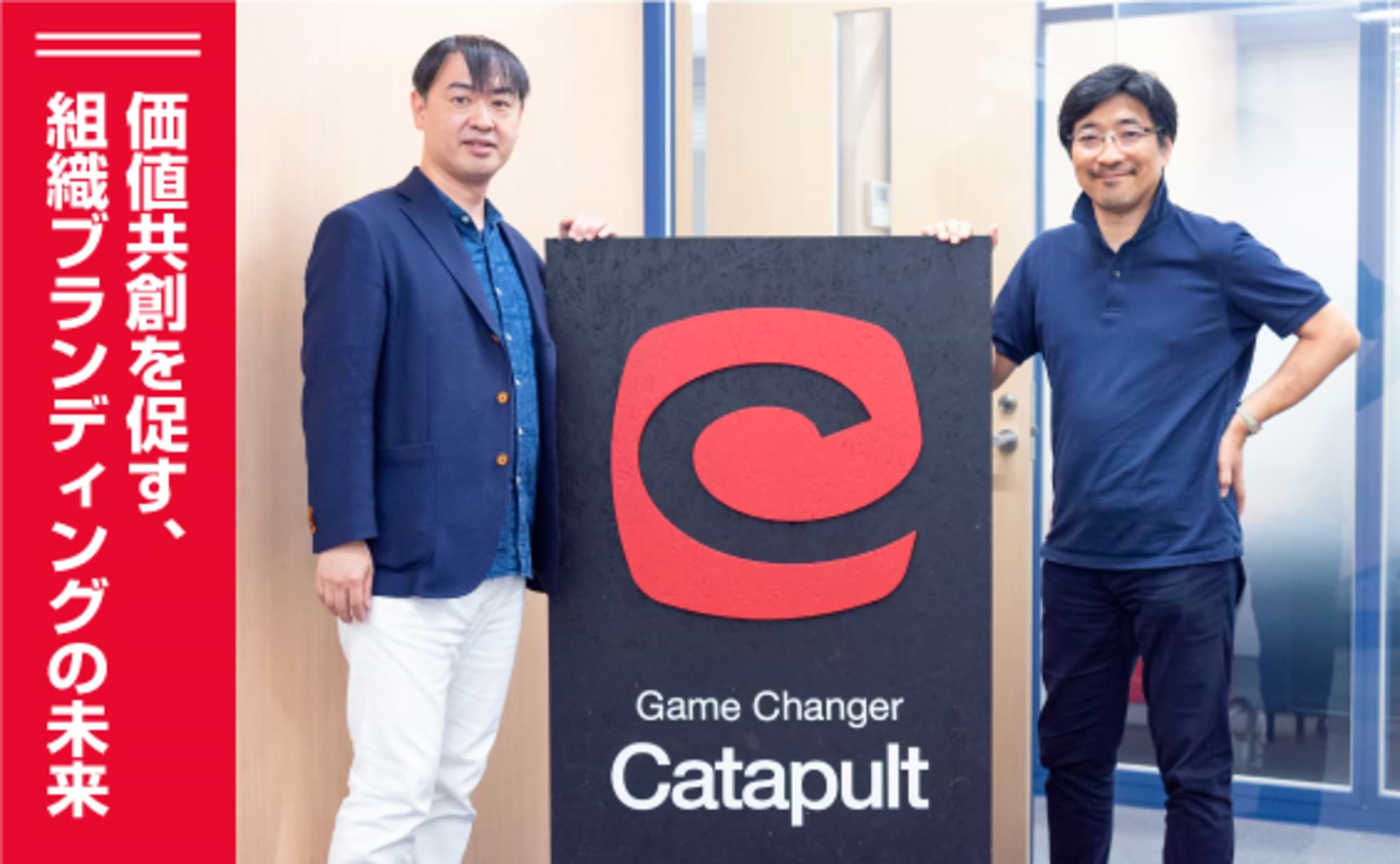インターネット社会が進み、社会や文化、人間にとっての価値を考えることが求められている現代。ポスト資本主義社会のブランディングと価値共創はどうなっていくのか?前回 に続き、インフォバーン(※1)CVOの小林弘人氏に話を聞きました。

インフォバーンCVOの小林弘人氏(右)、電通の小西圭介氏(左)
ポスト資本主義の「価値」と「お金」の関係の変化
小西:私がそもそも“ブランド”という概念に興味を持ったきっかけは、それが人間性を中心に、「意味」や「価値」をどのように作るのかという方法論を示していたからです。そして、インターネットは価値の作り手や作り方に本質的な変化をもたらしてきました。一つの大きな変化は、個人を中心とした情報発信や価値創造の民主化ですよね。またデジタル化で価値をコピーして無限に再生産することが容易になり、フェイク(偽物)やコモディティー化が起こるようにもなった。
そしてもう一つ、価値交換の手段や前提である「お金」や「信用」についても大きな変化が起こりつつあります。ウェブ3.0の中核となるブロックチェーン技術は、国家や企業などの中央集権ではなく、個人主導のつながりが軸となった、分散型の信用システムを実現するテクノロジーとして注目されています。
小林:ウェブ3.0については、単にウェブ1.0とか2.0に続く新しい技術コンセプトとして捉えるのは間違いだと思っています。極端にいうと新しい「私有」や「専有」の概念を、法律の代わりにツールが生み出しつつあるんですね。コード(プログラムによる命令規則)が新しい価値と社会改革の機会を創発しています。
それは今の資本主義システムに取り込まれたウェブ世界に対する、反動的な思想と民主的なテクノロジーを伴った大きな流れだと認識すべきですね。インターネット黎明期では、世界に張り巡らされたウェブは公共のものであり、その上で寡占的に儲けるなんてあり得ないという議論がありました。今聞いたら笑い話ですが、本当にそのような議論がされていた時期があります。
しかし、今支配的な考え方は、その企業のやり方が多少荒っぽくても時価総額が高ければ周りを黙らせられるし、株主のために資本を最大化すればそれでよいという思考停止状態に陥りがちです。
企業は短期的な利益確定を求める株主のために存在し、ガバナンスという言葉も株主や市場向けにしか聞こえない。働いている従業員とその家族、また、「社会」や「公益」がすっぽり抜け落ちたまま、集金マシンとしての価値しか検分されないように思えます。
小西:なるほど。今の資本主義社会は、「価値」が「お金」と結びついて交換される社会ですが、いつの間にかマネー資本主義みたいになって、昔は「物」と「お金」という交換構造があったのが、お金だけが回っていくみたいな。むしろ今、「価値」と「お金」が切り離されてしまっている時代だと思うんですね。社会や環境に悪いことをするほど儲かるような。社会や人間にとっての「価値」と、その適切な交換システムを取り戻す必要がある。
しかしウェブ3.0時代には、お金にコードで「色」がつけられる。どういうお金の使い方や、どういう価値に対して、それを報酬として交換し合うかのような。今まで“匿名”の通貨経済ではお金として換算しにくかった、個人や特定の文脈で意味を持つ、多様な価値をやりとりする新しい手法が出てきている。だからお金も個別性を持った意味を付与されて「ブランド化」できるし、そこにすごく可能性を感じるのです。
小林:私がしっくりきたのは、ベルナルド・リエター(※2)という経済学者の提示した論です。今使っている通貨システム自体が、「負債」(お金の貸借)から始まり、人から利子を取ることが前提となっている。
一つのパイの中から利子を取るので、誰かからその利子分を持ってこないといけない。だから、基本的には、人に分け与える思想設計じゃなくて、人の競争を促す設計になっている。このメカニズムは国力を向上させることや競争を促すことには効果があるのですが、コミュニティーに持ち込むとどんなことが起きるかというと、コミュニティーが持つ「地縁」を壊す力があるわけですね。
ここを何とかするには補完通貨が必要だということを、ブロックチェーン以前から唱えていたのがリエター氏です。そのような補完通貨として、有名なシルビオ・ゲゼル(※3)というドイツの経済学者の「減価するお金」といった考え方があります。
いわばある期間までに使わないと腐ってしまう。ゆえに早期に経済を循環させ、貯め込ませないために設計された「腐るお金」(※4)ですね。今だったら、ブロックチェーンを使えばそのような設定が可能なので、期限限定や用途限定型のお金とか、試論されていますよね。

「意味」を提起することで、共創コミュニティーをつくる
小西:価値を共有するコミュニティーの仕組みを支える経済システムですよね。実は2013年に私は『ブランドコミュニティ戦略』(ダイヤモンド社)という本を書いたのですが、ブランドというのはこれからコミュニティーづくりになり、企業や組織がお客さんと直接つながって一緒に価値をつくっていく、というコンセプトを提唱しました。でも、今考えるとまだ大企業中心の目線だったなと思ってしまって。
圧倒的に個人が中心の社会を前提に、これからはブランド主導のコミュニティーではなくて、個人やコミュニティーが中心の価値をつくっていく。そのために企業やブランドがどう支えていけるのか、支えるプラットフォームを形成していけるのかという発想で考えないと、5年、10年後の価値を共創していくような社会に対応できないんじゃないか、という気がするんですね。
小林:それはまさにおっしゃる通りだと思います。僕はコミュニティー形成こそ、常に過去から未来に向けたブランディングの軸になっていると思います。例えば地域発のクラフトビールを作るスタートアップが増えていますが、彼らは、クラフトビール文化や地域の独自価値を生み出す「想い」をユーザーと共有して、一緒に発信しています。コンシューマーを巻き込みながらエバンジェリストやプロシューマーを育てている。
ただ一方で、コミュニティーをつくるには、「意味」を提起することが必要だと思うんです。ミラノ工科大学のロベルト・ベルガンティ氏(※5)は「意味のイノベーション」を提起していて、これはポスト・デザインシンキングですね。
デザインシンキングは、ユーザー視点の価値設計の方法論を理論化して、カリスマやクリエーターが暗黙知でやってきたことを、みんなでできるようになった。でも、それは改善にはつながるけれど、新しい「意味」の提案に果たして向いているのか、という疑念が残ります。
「意味」の提案には責任が伴うし、社会のグランドデザインになってくる。従来のやり方でいいのかという、ポスト・デザインシンキングの問題提起が起きることは必然だと考えていたので、ベルガンティ氏の思想に触れ、合点がいきました。私も「エディトリアル・シンキング」という考え方をここ数年喧伝してきたからです。そこでは、リサーチだけではあぶり出せない、異なる領域同士の接合やアイデアの跳躍方法に加え、いかに新しい価値を基軸とした社会変革の意志を込めるのかといったことを中心に話してきました。むしろ、アイデアのテンプレート化に対する批判です。
小西:新しい「意味」を提起して、その価値を共有するコミュニティーを通じて共創する運動を、私も「動詞のブランディング」という言葉で表現しています。その主体としてのリーダーシップが企業なのか個人なのかは分かりませんが、世の中を変える大きな力を生み出せないかと。

小林:インフォバーン社内に、企業や行政内のイノベーターたちをネットワークするUnchainedを創設したのは、まさにそういう目的からです。ブロックチェーンの社会実装プログラムや領域横断型のイベント、勉強会、海外視察を行っています。
最初、私たちが企画するベルリン視察ツアーに参加される方は、渡航前に「すごいテクノロジーを持っているスタートアップがあったら、出資したいので教えてくれ」と依頼されます(笑)。でも、参加した後は、「そもそもうちの会社、何がやりたいの?」と意味を考えだす。そして、その意味に基づいて実現したい理想の社会像が描けてこそ、共創相手が見つかることに気づかれるわけですね。
どんなに歴史のある企業でも、無数の「How」ばかりで、たった一つの「Why?」が欠けていることが少なくありません。私が「イノベーションごっこ」と揶揄するのは、流行りに乗って「アジャイル」「コ・ワーキング」「デザインシンキング」などと「How」に振り回され、「Why?」を見つけようとしない状態のことです。それでは本質的なイノベーションを生み出せないし、コミュニティーもつくれないと思います。なぜなら、何の価値を提供しようとしているのかわからないし、A社ではなく、B社でも展開できそうなことに誰も共感はできません。
小西:私もまさにそれを体感しました。今回は本質的で、非常にインスピレーションに富むお話をありがとうございました。
(対談を終えて)
マーケティング手段を超え、社会や文化、人間にとっての価値を考える
今回は、ポスト資本主義のブランディング、価値共創の未来という大きなテーマで小林氏に伺いました。その中で、テクノロジーと社会の大きな転換点に当たって、人や社会にとって意味のある「価値」を生み出し、増やしていく経済システムをどのように実現していくのか、という本質的な問いに至りました。ブランディングも、企業にとっての経済価値を増やすマーケティング手段にとどまらず、より大きな視点で社会価値を共創していく仕組みや手段として、新しい視野と方法論を持つ必要があると確信しました。
※1 インフォバーン:国内外企業のデジタルマーケティング全般からウェブメディアの立ち上げ・運用などを支援。コンテンツ・マーケティング、オウンドメディアの先駆として知られる。2016年からベルリン最大のテック・カンファレンスTech Open Airの日本公式パートナーとなる。
↑本文へ
※2 ベルナルド・リエター:ベルギー生まれの経済学者(1942-2019)。新しいマネーの仕組みを提唱した、補完通貨(地域通貨)研究の世界の第一人者。主著に『マネー崩壊―新しいコミュニティ通貨の誕生』(日本経済評論社)など。
↑本文へ
※3 シルビオ・ゲゼル:ドイツ人の実業家・経済学者(1862~1930)。主著『自然的経済秩序』など。自由貨幣の概念を提唱した。
↑本文へ
※4 腐るお金: 愛知県豊田市で発案されたコメと交換できる地域通貨「おむすび通貨」などが有名。時間がたつほど価値が減る仕組みを持つ。
↑本文へ
※5 ロベルト・ベルガンティ:イタリア・ミラノ工科大学教授。専門はリーダーシップ論、イノベーション論。「意味のイノベーション」と呼ぶ考え方で多くの企業から注目され、欧州委員会のイノベーション政策にも関与している。著書に『デザイン・ドリブン・イノベーション』(クロスメディア・パブリッシング)、『突破するデザイン』(日経BP)など。
↑本文へ