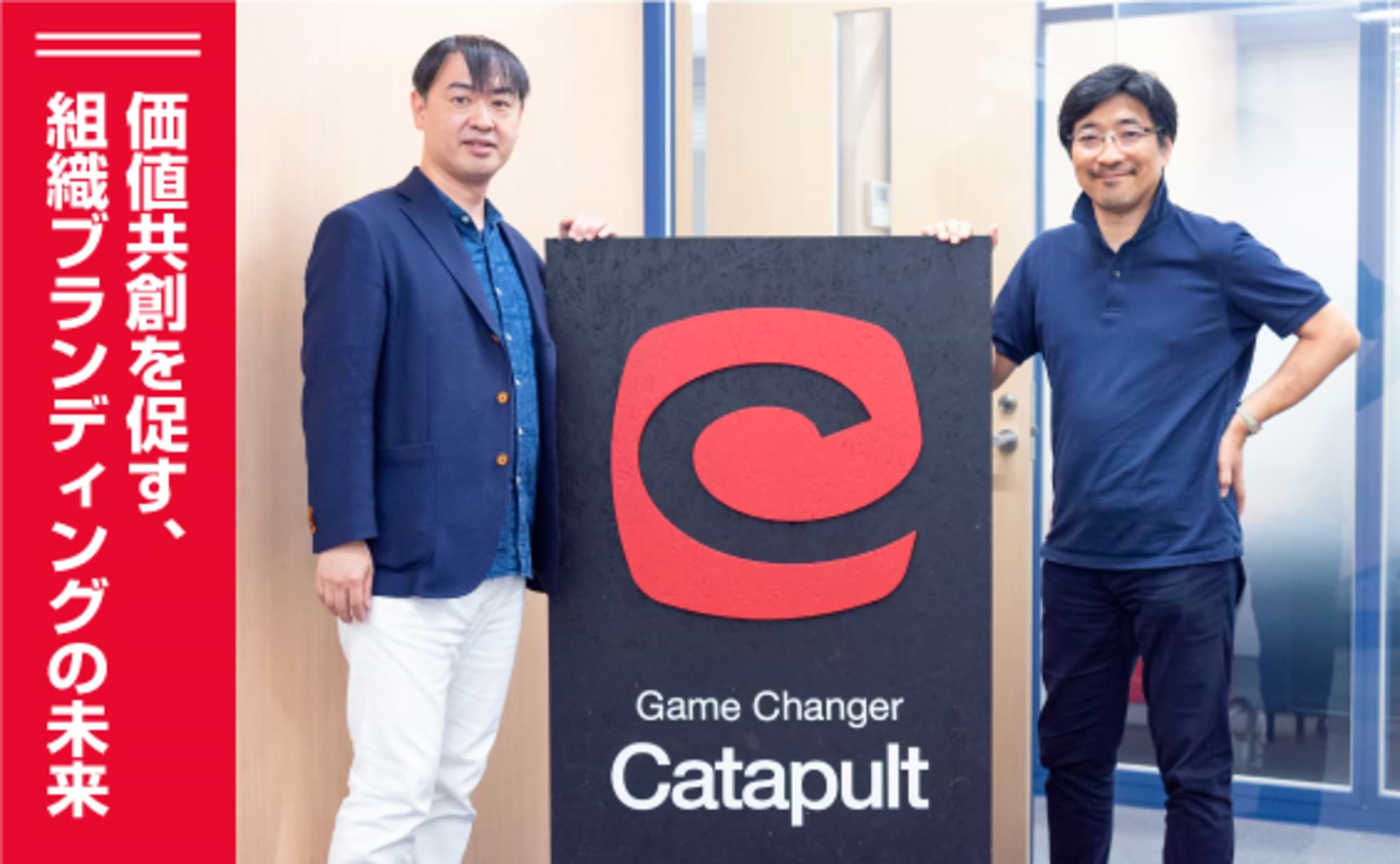ポスト資本主義社会のあり方が議論されるようになり、またGDPR(一般データ保護規則)(※1)の制定などインターネット社会が大きな転換点を迎える中で、ブランディングと価値共創はどうなっていくのか?インフォバーン(※2)CVOの小林弘人氏に話を聞きました。

インフォバーンCVOの小林弘人氏(右)、電通の小西圭介氏(左)
ポストGDPRのデジタル社会の動向は?
小西:小林さんには、ぜひ一度、話を伺いたいと以前から思っていました。今回は、「共創の時代のブランディング」連載企画の最終回として、「ウェブ3.0(※3)時代の価値共創」というテーマでご意見を聞かせてください。
小林さんが1990年代に日本版の初代編集長をされていたメディア「WIRED」は、われわれの世代にとっては新たなインターネット時代のカルチャーの先導者というか、時代の熱狂を伝え、読者や社会の価値観を変えるような大きな影響力を持っていました。小林さんは、現在の成熟・進化したインターネットの状況をどのように捉えていますか。
小林:アメリカの連邦議会がインターネットの商業接続を許可したのが1992年で、93年に米国で「WIRED」が創刊されました。翌94年に郵政省(現・総務省)がインターネットの商用接続をわが国でも認可し、その年に日本版を立ち上げましたが、当時は、インターネットがこれからのニューフロンティアだ、という空気がありましたね。しかし、多くの人たちがそれに気づくには、時間がかかりましたが。
そのインターネット黎明期に多くの理想論が散見されました。例えば、世界はピア・ツー・ピアのノード(※4)でつながっていって、さまざまな可能性や多様性、多様な価値観というのが担保されるだろう、と言われていました。
そこから30年近くたったわけですが、実際にはそうはならなくて、ソーシャルメディアのアルゴリズムが価値観の分断を促進していたりする。そして、インターネットビジネスの儲けの手段は、結局何だかんだいっても今も広告なんですよ。決して広告が悪いと言っているのではなくて、ビジネスモデルの多様性という観点では、インターネットがなかった時代とあまり変わらない。
無料サービスを通じて取得された個人データが、高精度なターゲティング広告手段としてマネタイズされる。データ主導の広告モデルが、自動化テクノロジーやAIなどで爆発的に成長しました。そのため個人データを占有したフェイスブックやグーグルなどのプラットフォーマーが、広告というモデルにおいてはものすごい力を持つようになった。
小西:ネットのフリーで、オープンで、自発的なカルチャーが称揚されていたものが、いつの間にかユーザーやパブリッシャーのコンテンツへのフリーライドや、サービス利用を前提に個人情報を取得する仕組みが発明され、結果的に世界を支配する寡占的なデータの巨大産業を生み出してきたわけですね。しかしこの流れに、ヨーロッパからGDPRという形で待ったがかかった。
個人データの主権回復は、マーケティングの“Me Too運動”だ
小林:プラットフォーマーの広告ビジネスに便利に使われていたデジタル上における個人データが、本来の主権者、すなわち個々のユーザーに帰属する権利なのだということを、ようやく突きつけてきたわけです。GDPRやeプライバシー法(※5)なども含め、僕はアメリカ主導だったデジタル・エコノミーの歴史的な大転換点だと思っています。
「忘れられる権利」(※6)というのもヨーロッパから初めて問題提起されましたが、人間性に関する思想や哲学のブレークスルーというものは、常にヨーロッパから来ています。
日本の企業や日本人の多くは、まだあまりそこまで重要視しておらず、遠い国で起きている現象という感じですが、端的に言えば、今後起きるであろう可能性はマーケティングにおける“Me Too運動”だと思っています。国家が突きつけたものがGDPRだとしたら、今後は個人からも起こり得る。つまり、これまで大手を振るっていた商慣習にクエスチョンマークがついて、各個人が意見できる土壌が生まれつつあります。マーケターも、前提概念が変わったことに気づくべきです。
小西:もはやマーケティングというレイヤーではなく、デジタル社会のあり方や人権をめぐる根本的なルール変更ですよね。GDPRはあくまでもその端緒であり、EU主導の「デジタルシングルマーケット戦略」(図1)に示されるように、eプライバシー法やデジタル著作権法なども含めて、今後デジタル情報の活用をめぐる社会ルールが、世界的にも大きく変わっていく転換点であると。
小林:日本の企業や行政の中でも、個人データの統合を進める中国を見習うべきだといった議論を見かけます。それは国民を管理するという話ではなく、コマースや行動履歴を分析してマーケティングを高度化するうんぬん、みたいな議論ですね。これはすごく怖いなと思っていて。社会学者のジグムント・バウマン(※7)は、著作の中でプライバシーというのは、他人と自分が違うということを区分できる最後の領分であると述べていますが、そこを放棄することは自己を放棄することであると思います。
このような議論になると、日本人の中には「自分はやましいことをしていないから、いくら盗聴されても結構」という人が少なからずいますが、冷戦時代の東ベルリンでシュタージ(秘密警察)が行なっていたことや、それにより市民生活が制限されていたことを鑑みても、他者にプライバシーを委ねることは政治参加や自由意思の放棄につながりかねません。
本当に個々人にとって幸せなことは何か?それはAIによってメールの会話まで抜いて利便性を図ることなのか(グーグルはGmailでやっています)、Alexaに話しかけた言葉を全て解析されることなのか、プラットフォーマーの社内だけで密かに議論されるべき事柄ではなく、社会全体の設計思想に関する問題です。
ゆえに一方的に利便性のためにプライバシーを犠牲にしなさいと言った押し付け型のマーケティングも変わっていかないと。実際には誤ってクリックした広告を何度も見せられるようなリタゲ(リターゲティング)広告など、出稿した側にもあまりメリットがあるとは思えません。
小西:分かります。インターネットが人をより簡単につなげるようになって、企業やブランドにとっても、お客さまとつながるというのは非常に容易になりました。データは、21世紀の通貨もしくはオイルであるといわれていますが、データとして人を見るようになってないか?その結果、広告も変質して嫌われてしまっているんじゃないか?と思います。
小林:だから、これからはマーケターも、自分たちのビジネスの領域の中だけで、視野が狭くなってはいけないと思います。イノベーター向けの教育では、領域横断型で物事を理解し、各専門分野の識者の話を聞いたり、ユーザーへのフィールドワークを行ったりします。マーケティング業界ももっと多面的にブランド価値を考える局面にきていると思います。
テクノロジーや利益主導で行き過ぎた資本主義システムが、環境や社会、人権などについて軋轢を生み出しています。GDPRもその流れの一つですが、米民主党のエリザベス・ウォーレンが公約に掲げるフェイスブック解体が支持を得たり、シェアリング・サービス事業者の高い手数料や無責任さへの反発から協同組合が発足されるなど、世界的な揺り戻しが起こっていることに気づいている日本のマーケターはどのくらい多いのでしょうか。今こそもっと社会や文化、人間にとっての価値を考える必要がある重要な局面かと思います。
私が毎年ベルリンのTOA(Tech Open Air) (※8)ツアーを主催しているのも、こうしたヨーロッパ発の価値観や行動に触れることで、本質的な問いを持ってもらいたいと考えるからです。
※後編に続く。
※1 GDPR(一般データ保護規則):2018年に施行されたEUの法規制で、EU市民の個人情報に関する権利を取り戻すことを目的に、データ収集・利用目的への同意義務や、仮名化、データ侵害の法的義務、消去権、データ可搬性などを定めた包括的な規則。
↑本文へ
※2 インフォバーン:国内外企業のデジタルマーケティング全般からウェブメディアの立ち上げ・運用などを支援。コンテンツ・マーケティング、オウンドメディアの先駆として知られる。2016年からベルリン最大のテック・カンファレンスTOA(Tech Open Air)の日本公式パートナーとなる。
↑本文へ
※3 ウェブ3.0:分散型ウェブと呼ばれる概念で、オープン・個人主導の分散型データ管理、非許可型・デバイスフリーなどの特徴を持つ。ブロックチェーン技術の活用により、近年さまざまなサービス、プラットフォームが登場して注目を集めている。
↑本文へ
※4 ピア・ツー・ピア(モデル):コンピューターの複数の端末間で通信を行う際のアーキテクチャーのひとつで、「対等な立場で情報共有を行う端末」という意味があり、ネットワークに接続している端末(または参加者)のことを「ノード」と呼ぶことが多い。
↑本文へ
※5 eプライバシー法:EUの法規制で、メールやクッキー、メッセンジャーや音声データ通信などを取り扱う民間企業などに対し、EU市民のプライバシーの順守を義務付ける法案であり、2019年中の施行を目指して審議中。
↑本文へ
※6 忘れられる権利:ネット上の個人情報や誹謗中傷を削除してもらう権利のこと。欧州から提起されたプライバシー保護のための新しい権利として、GDPRでも「消去権」として明文化されることとなった。
↑本文へ
※7 ジグムント・バウマン:ポーランド出身の世界的な社会学者(1925~2017)。イギリス・リーズ大学およびワルシャワ大学名誉教授。『個人化社会』(青弓社)、『リキッド・モダニティ―液状化する社会』(大月書店)、『アイデンティティ』(日本経済評論社)など著作多数。
↑本文へ
※8 TOA(Tech Open Air):2012年に開始され、毎年ドイツのベルリンで開催されるイノベーションをテーマにしたカンファレンス。テクノロジー業界を超えた社会・文化的な視点を持ち、世界中のさまざまな業界から多彩なスピーカーが登壇することでも知られる。
↑本文へ