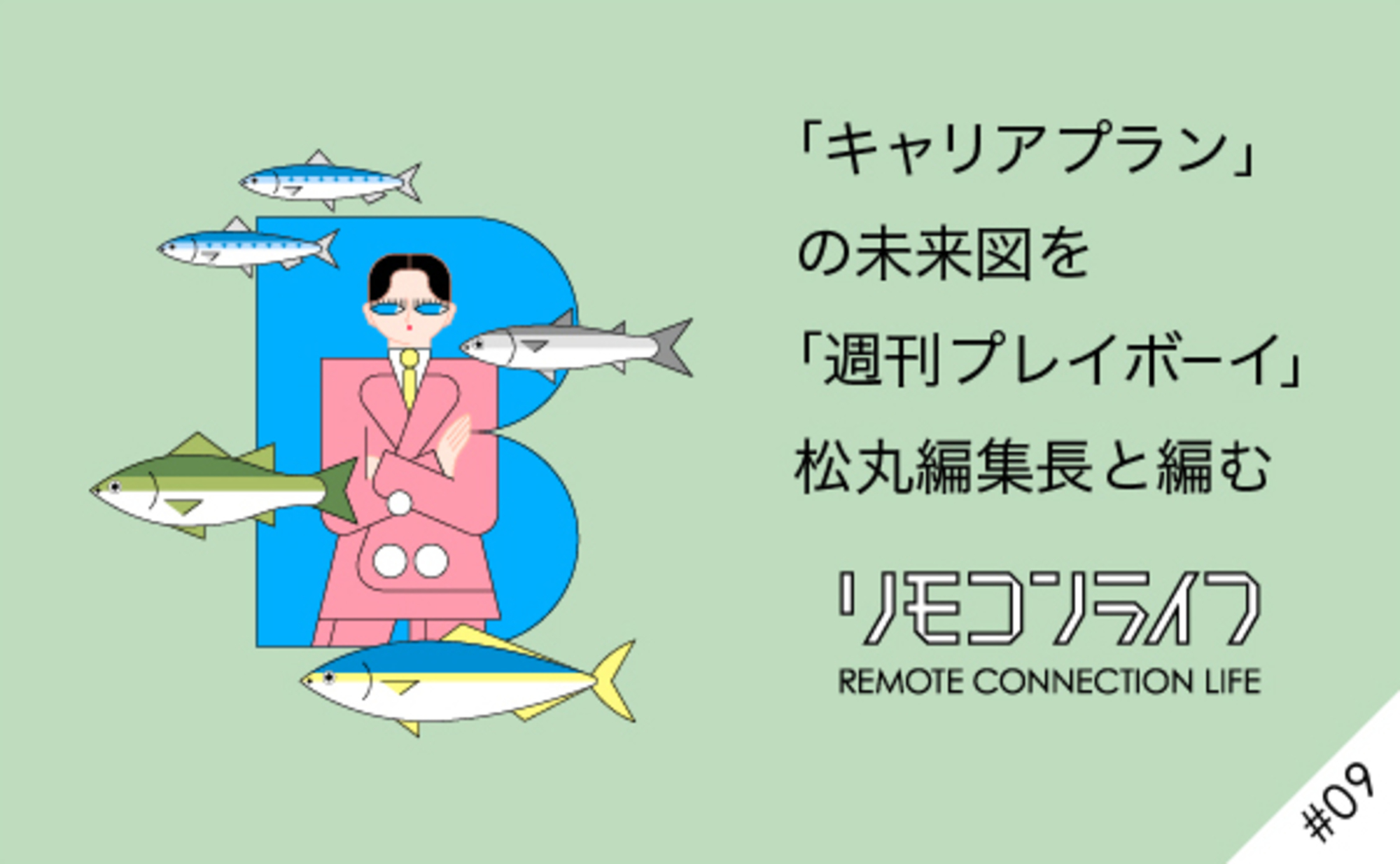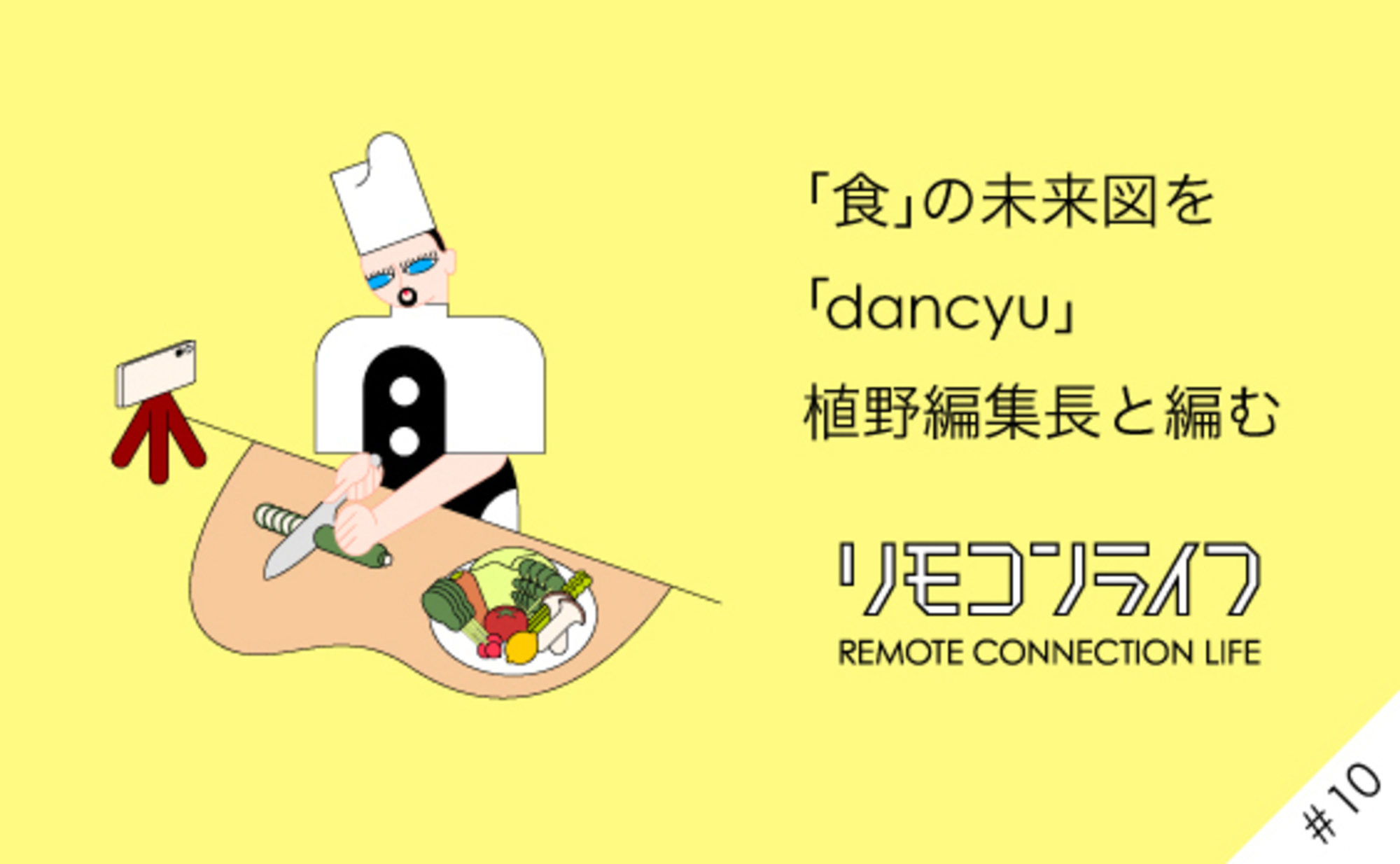お互いの距離は離れていても、テクノロジーを上手に使うことで、今までよりも近くに感じられる。ちょっとした発想の転換で、まったく新たなつながりが生まれる。新型コロナをきっかけにして始まりつつある新しいライフスタイルは「リモコンライフ」(Remote Connection Life)といえるものなのかもしれません。リモコンライフは、Remote Communication Lifeであり、Remote Comfortable Lifeも生み出していく。そうした離れながらつながっていくライフスタイルの「未来図」を、雑誌の編集長と電通のクリエイターが一緒に考えていく本連載。
10回目は「dancyu」の編集長・植野広生さんに伺いました。
<目次>
▼【リモコンライフストーリー#10 知識は最高のソースになる】
▼ 根強い「ファン」のいるお店は強い
▼「チカバ」と「イツカ」のバランスが大切
▼ 日本の食文化を救う「ちゃんと欲求」
▼ 対価の感覚のズレを戻すために
▼ “普通においしい”が最高においしい
新型コロナの影響による外食産業へのダメージは計り知れません。そうした危機の中にあっても、実は客足の変わらない店、むしろお客さんがいつも以上にお金を使うようになったお店があると植野編集長は語ります。その差は、何か?植野編集長によれば、今まで来ていたお客さんが「ただのお客」だったのか、その店の「ファン」だったのかの違いだと言います。
「リモコンライフ」で「食」、特に「外食」はどんな変化を遂げるのか?「食文化」の進化のためにはどんなことが必要なのか?植野編集長の示唆をもとに、ちょっとしたストーリーにまとめてみました。
野澤友宏(電通1CRP局)
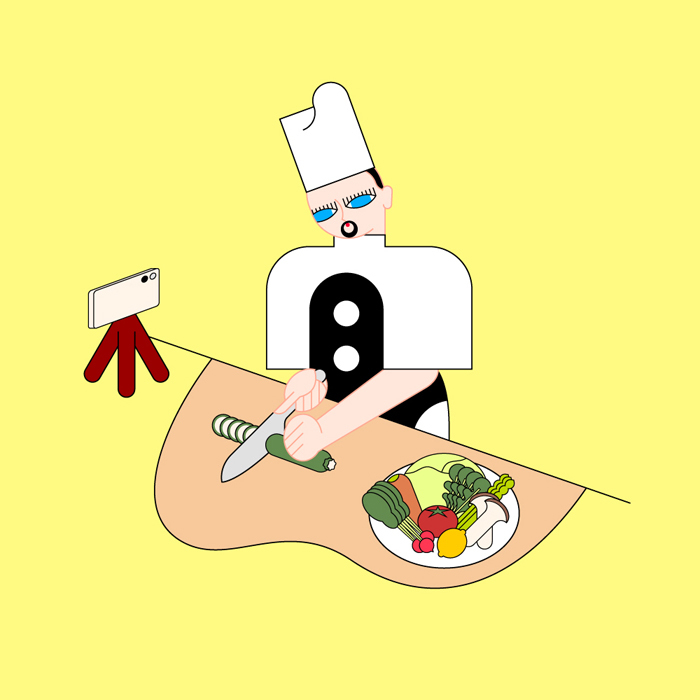
イラストレーション:瓜生太郎
【リモコンライフストーリー#10 知識は最高のソースになる】
(カツミ アヤコ/メーカー勤務/33歳の場合)
「じゃあ、そろそろ始めますので、皆さん厨房が見えるところにお願いします」
店中にシェフのバリトンボイスが響き渡ると、それまでテーブルに座っていたお客さんたちが一斉にカウンターの前に並んだ。リストランテ「conoscenza(コノシェンツァ)」では、ランチタイムとディナータイムの間に「仕込みタイム」というものがあり、シェフが週に1度、その日のディナーに出す料理の仕込みを解説付きで見せてくれるのだ。
アヤコが最初に住宅街の中にひっそりたたずむこのリストランテを発見したのは、ステイホーム期間中、遠出ができない代わりに近所を当てもなく散歩していた時だった。「conoscenza」は、イタリア語で「知識」という意味で、その名の通り、食事の際にはその料理の素材や調理方法について他のお店では味わえないほど丁寧な説明をしてくれる。「知識は最高のソースになる」。それがシェフのモットーだ。カウンター席が六つとテーブル席が四つ。もともと大きい店ではないが、アヤコが訪れる時はいつも満席だった。知る人ぞ知る名店らしく昔からの根強いファンが多かったようだが、コロナ以後、人気はどんどん高まっている。
「仕込みタイム」に集う客も、コロナ前までは勉強目的の料理人たちが多かったが、外出自粛期間中に動画配信したのをきっかけに一般の人も見に来るようになった。半年ほど前に「仕込みタイム」を初めて体験して以来、アヤコは月に1度は参加するようになった。今日は、ちょうど休みだった夫も一緒だった。
「今日のメインは、羊でして……」といって冷蔵庫から塊肉を取り出したシェフがカウンター越しに話しかける。「これは『やながわ羊』と言いまして、岩手の内陸部の奥州市にある10軒くらいの農家さんが自分の庭先で育てている羊で、本当に愛されて育っているせいか非常にピュアで美しい味わいなんです」
シェフはしゃべりながら、手際よく肉にナイフを入れていく。しゃべりながら手を動かすのも大変だとは思うが、シェフの性分なのだろう、実に楽しそうに話しながら作業をしている。厨房全体を見渡せる位置に1台、シェフの手元を撮るように1台カメラが置いてあり、ライブ配信も同時に行っている。
「羊の肉って鮮度がいいものは臭みも全くありませんし、柔らかいので、ぜひ国産にこだわって探してみてください」。料理にそこまで興味がないと思っていた夫も、シェフの話に深くうなずきながら聞き入っている。
羊肉の処理が終わると、三浦港で水揚げされる白魚、栃木県でしか採れないルッコラなどなど、次から次へと仕込みが進んでいく。どの食材にも、生産者がどのように作っているのかという物語があり、シェフがそれを選んだだけの理由があって、実に面白い。
「実は全部、別に特別高いものでもなければ、特別手に入りにくいものでもないんです」とシェフが大ぶりのエビを客の顔に近づけながら言った。「普段何げなくスーパーで目にしている食材にだって物語はあるはず。ただなんとなく食べるか、情報を知りながら食べるか。もちろん、おいしいものは何も知らずに食べてもおいしい。けれど、おいしいものは『知ること』でもっとおいしくなるんです」
「conoscenza」に食べに来るようになってから、アヤコの買い物の仕方も変わってきた。もともと料理は好きだし得意だったが、子どもが生まれてからは作るだけで精いっぱいで食材の一つ一つを厳選する余裕なんかなかった。それが、「仕込みタイム」の時に土鍋を使ってリゾットを作っているのに興味が湧き、家でも土鍋でちゃんとご飯を炊くようになった。そうすると、必然的にお米をちゃんと理解したくなり、研ぎ方もちゃんと知っておきたいと思うようになる。いつしかシェフにお薦めの農家を教わって、家族とドライブがてら田んぼを見にいくまでになっていた。
「料理人は、食材をつくる人と食べる人をつなぐ役目があるんです」と一連の仕込みを終えたシェフがにこやかにお客さんに語りかける、「ある意味、翻訳者といってもいいかもしれません。食材についていろんなことを知ってなくちゃいけないし、どんどん足を使って食べにいかなきゃいけない。そして、どんどん発信していかないといけないと思っています」
シェフの話は聞いているだけで、どんどんおなかがすいてくる。と同時になんだか食べた気になっておなかいっぱいになってくる。
「さて、今夜は何にしようかなぁ」。アヤコは、アヤコの料理熱のおかげですっかりボリュームを増した夫にほほ笑んだ。
(このストーリーはフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません)
根強い「ファン」のいるお店は強い
上記の「リモコンライフストーリー」のヒントにさせていただいた「dancyu」編集長・植野広生さんのインタビュー内容を、ぜひご覧ください。

「食」に関して、改めてコロナ禍を通して分かったことのひとつは、予約が取れないような“人気店”はテイクアウトをやっても人が殺到するし、町場で地味にやっている食堂などは近所の人が普通に食べに来ているということ。もちろん、通常の営業はできませんが、コロナになっても人が向かう先はあまり変わらなかったと改めて気づきました。そして、「客」ではなく「ファン」が付いている店は強いということも。
ファンが付いている店っていうのは、営業時間が短くてもお客さんが入っていますし、むしろ、こういう時だからこそお客さんがお金を使うようです。普段グラスワインしか飲まなかった人が、店のためにボトルを入れたり、飲めなくても「これ飲んでね」って置いていったりとか(笑)。その店を愛する人はその店を守ろうっていう感じになっているので、そういうお客さんが付いているお店はおそらくまだ大丈夫です。
「チカバ」と「イツカ」のバランスが大切
外出自粛になったあたりから特に、SNSで「#チカバとイツカ」をつけるようにしました。「こういう時だからこそ近所のおいしいものを探せるチャンスだよな」って思って、いつも会社に行くときに素通りしていたお肉屋さんに入ってみたら、おいしいコロッケが実はあったとか、逆にいつも通らないような道を通ってみたら小さなお惣菜屋さんがあっておいしい煮豆を売っていたとか、そんなことに気付くチャンスが増えたと思います。その一方で「でもやっぱりいつかあの店に行きたいよね」「いつかあれを食べに行きたいよね」っていう妄想を膨らませることによって、その店がもっと好きになるだろうし、その店に行ったときの喜びも増える気がします。
だから、「チカバ」と「イツカ」をバランス良く考えていると、コロナの時代も食いしん坊的には楽しみが増えるのではないでしょうか。 でも、コロナに関わらずどんな時代でも「チカバ」と「イツカ」っていうのをみんながバランス良く感じていれば、日本の食文化っていうのはきちんと守れて進化していくはずです。
日本の食文化を救う「ちゃんと欲求」
個人的には、今「日本の食」は進化しているけど「日本の食文化」は退化しかねない状況にある、と不安に思っています。例えば、人気店の1年先の予約を頑張ってとったり、2時間待ちのラーメン屋に並んだりとか、本質的な「食の楽しみ」とは異なる部分がフォーカスされることが多かった。けれど、コロナの時期を経て、そういう人たちが、実は自分たちが無理していたとか、そんなことにちょっと疲れていることに気づき始めているような気がします。
そういう人たちが「じゃあ、本当の『食の楽しみ』ってなんなの?」って見つめ直し始めたところから、「素朴なもの」とか「プリミティブなもの」に食の流れが大きく動いているように思います。人間って、世の中が不安になったり、危機を感じるとそういうプリミティブな方に戻るようなところがあります。例えば、ステイホーム期間中、女性はお菓子を作り始め、男は煮込みに走ったみたいなことがありました。
あれは「ヒマだから」っていうのももちろんあると思いますが、粉からお菓子を作るっていうことは「食」の原点みたいなところがありますよね。塊の肉を煮込むというのも「食」の原点。そこから、それまで何も考えずにスーパーで買ってきたお米を炊飯器で炊いていた人たちが「土鍋で炊いてみたらおいしいし、なんか楽しい」という方向に向かい始める。
それからは「ちょっとお米を変えてみようか」「あ、お米を選んで買ってみたらすごくおいしい」「じゃあちょっと研ぎ方をちゃんと調べてみよう」というように、根本を見つめ直すところからどんどん自然に選択肢が広がっていって、能動的においしさを求めていくようになっていきます。
コロナ禍に入ってから「ちゃんと和食」という特集をしたのですが、この「ちゃんと」が効いたと見えて、読者から高い評価を頂きました。今、みんなフラストレーションが溜まっているわけですよね。思い通りに行けない、食べられないっていう。フラストレーションというのは上手に使うとパワーになるので、「ちゃんと欲求」に応えるものは、すごくみんなに受け入れられやすいように思います。これからコロナが収まって平穏になったとしても、「ちゃんと向かい合おう」「ちゃんと食べよう」「ちゃんとしたものを買おう」「ちゃんと参加しておこう」っていうのは潜在的なパワーとして残ると思いますね。
対価の感覚のズレを戻すために
コロナの前から対価っていうものの感覚がちょっとズレてきてるところもあって、町場の居酒屋では1杯100円とかすごい安いものをやっていて、その一方で銀座の寿司屋では1人4万とか5万とかっていうのがあって。デフレとかインフレではなく、物事とか食とかサービスに対する対価という感覚がすごくおかしくなっていたんです。特にコロナ禍にあって安くしないと売れないという感覚が当たり前になって、コロナが落ち着いてもこの感覚が残ってしまうわけですよ。
そうするとホントにいいもの、ちゃんとした食材を使ったものが高く売れなくなってしまうかもしれないということを懸念しています。そうすると、変な話、真面目にやっている店がはやらなくなって、安いか高いかどっちかの極端な店に人が集まるということにもなりかねません。このアフターコロナの問題のひとつとして。
対価の概念を正常に戻していくには、当たり前に真っ当にやっている店がきちんと評価されることしかないと思います。小さいですけど「dancyu」のような媒体がきちんと取り上げていって、ホントに普通のおいしさ、普通の楽しさ、適正な対価みたいなことを提案できると思っています。
“普通においしい”が最高においしい
「dancyu」のコンセプトは、「『知る』は美味しい。」です。が、いわゆる「グルメ情報誌」ではありません。「dancyu」とは何か?を聞かれたときには、「食いしん坊のための、食いしん坊がおいしく楽しくなるためのプランを提案したい雑誌です」というふうに言っています。それがある意味、紙の使命だと思っています。
例えばお店にしても、ネットとかだと数値化とかランキングするのは得意だと思いますが、「dancyu」ではランキングできない「普通においしい」っていうのをご紹介したい。 そのときどき「だけ」の流行とかではなく、もうちょっと普遍的な、「普遍性のある普通のおいしさ」みたいなものが、われわれの究極の目指すところだと思っています。編集長は簡単に「普通においしい店を探してこい」とか言えますけど、うちのスタッフは大変ですよ。「普通においしい店」を探してこなきゃいけない(笑)。
これからは「普通」というのがホントに重要な言葉になる。「普通」の良さに改めて気付いたというか、向き合えるようになったってことは個人的にすごくいいことだと思っています。
今は、「食」に限らず文化全般において基本的なところの価値観を見直すきっかけになったと言われる時代かもしれないですね。 もし、この先コロナ以上のことが起こったとしても、普通に生活することを心掛けていれば、そんなにアタフタしなくて済むのではないでしょうか。
【リモコンライフチームメンバーより】
植野編集長のお話の中から見えてきた、
リモコンライフをより楽しむためのキーワードはこちらです。
◉ 近場のおいしい店
◉「知る」はおいしい。
◉ 食の見つめ直し
◉ ちゃんと欲求
新型コロナウイルスで、私たちのライフスタイルはどう変わるのか──人々の暮らしの中にまぎれた、ささいな変化や日々の心の変化に目を向け、身近な “新常態”を未来予測し、新たな価値創造を目指したい。この連載では「リモコンライフ」という切り口で、そうした可能性を探ってきました。皆さまにとって、これからの暮らし、これからのビジネスを考える上でのヒントとなることを願って。
この記事は参考になりましたか?
著者

植野 広生
プレジデント社
dancyu編集長
編集長
1962年、栃木県生まれ。法政大学法学部卒業後、新聞記者を経て、出版社で経済誌の編集を担当。2001年、プレジデント社に入社。以来「dancyu」の編集を担当、2017年4月に編集長に就任。「情熱大陸」(毎日放送)、「プロフェショナル 仕事の流儀」(NHK)、「アナザースカイ」(日本テレビ)、「人生最高レストラン」(TBS)、「世界一受けたい授業」(日本テレビ)、「和牛町×ごはん」(BS日テレ/レギュラー)、「日本一ふつうで美味しい 植野食堂」(BSフジ/レギュラー)、「食べるラジオ」(TOKYO FM/パーソナリティ)などテレビやラジオの出演多数。著書に「dancyu “食いしん坊”編集長の極上ひとりメシ」(ポプラ新書)。

野澤 友宏
株式会社 電通
第1CRプランニング局
クリエーティブディレクター
栃木県宇都宮市生まれ。コピーライター、CMプランナーを経て、クリエイティブ・ディレクターに。コーチングの資格を多数保有し、現在はHRMディレクターとしてクリエイティブ局の人財育成にも力を注ぐ。葉山在住。4歳男児のパパ。趣味は茶道(江戸千家)