コミュニケーションの力で、医療を変える。
「オリジナリティー」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく本連載。第7回は、AIやITといったテクノロジーを駆使して医療の現場を変えていこうというスタートアップ企業「MICIN(マイシン)」です。
コロナ禍で医療の現場が逼迫する中、注目されているスタートアップ企業がある。ヘルステック企業のMICIN(マイシン)という会社だ。医療現場におけるテクノロジーといえば、すなわち医療技術を指すと思いがちだ。ところが、この会社が高めようとしているテクノロジーとは、そういうことではない。AIやITといった最新の情報テクノロジー、言うなればコミュニケーションの力を使って、医療の現場、ひいては患者を救おうというのだ。
瞬時には理解できない。理系の最先端といってもいい医療の技術と、文学にも近いイメージのコミュニケーションの技術。これらがどう融合していくのか、いくべきなのか、そのあたりを探ってみたい。

2015年11月創業。「すべての人が、納得して生きて、最期を迎えられる世界を。」をビジョンに掲げ、オンライン診療サービス「クロン」、オンライン服薬指導サービス「クロンお薬サポート」などを手掛けるアプリケーション事業、医薬品の臨床開発向けデジタルソリューション事業、診療・患者生活を支援するデジタルセラピューティクス事業などを展開。
今回話を伺ったのは、MICIN代表取締役の原聖吾氏。東京大学医学部卒業後、国立国際医療センターで医師として従事。そこでの経験を経て、臨床医ではなく医療の仕組みを変えるために日本医療政策機構に勤務。その後、米スタンフォード大学でMBAを取得してマッキンゼーに入社。医療分野のコンサルタント として4年間働いた後に起業するという、医療業界では異色な経歴の持ち主だ。
まず、MBAと医療が、パッと結びつかない。医療といわれてイメージするのは科学技術の最先端、あとは「白衣の天使」に代表される慈善的な行為。でも、昨今の報道を見てみると、そればかりではないと思う。マーケティングだったり、コミュニケーションだったり、経営だったり、人材の育成といった、一般企業が頭を悩ませていることが医療の現場でも当然、起きているはずだから。そのあたりをぜひ、原代表に尋ねてみようと思う。
文責:電通 CDC荒木俊哉
テーマは、「納得のいく」最期
「われわれの会社のビジョンは、すべての人が納得して生きて最期を迎えられる世界にする、ということなんです」と、冒頭、原氏は切り出した。医療のビジョンとは、人の寿命を延ばしていくこと。それが、僕らが信じきっていた唯一無二、最大の目的だったように思う。戦地での医療もそうだし、長期の入院を強いられている患者さんだってそうだ。でもそこに原氏は「納得」というワードを持ってきた。ドラマなどでよくある、主人公が病床で涙を浮かべながら「ああ、いい人生だった」と逝く場面を想像してしまった。

原氏は、続ける。「納得のいく最期を迎えるためには、納得のいくデータが必要なんです」。データ?そこが、最初の驚きだった。言われてみれば、確かにそうだ。人が何をもって物事を把握し、「納得」するのか?それは、データだ。医療の世界で「データ」といわれると、ドイツ語で書かれたカルテ、素人には分からない数値などを想像してしまうが、原氏が言うデータとは、どうやらそういうことではないようだ。
オンライン化されると見えてくる医療
「医療の現場で、データが生かされていない。そこが、一番の問題だと思ったんです」と原氏は言う。医療の現場といわれると、リアルの極み、オフラインの世界の極致と思ってしまうが、原氏は「オンライン化されることで、望ましき未来が見えてくる」のだと言う。「新型コロナによって、その動きは加速された」とも。確かに日々、感染者の数などのデータは入ってくる。でも、具体的になにをすればいいのか、が分からない。
原氏は言う。コロナに関わらず、知見や診断技術といったものは、日進月歩で進化している。ただ、そのデータがいまひとつ共有されていない。ここを何とかできないか、というのが起業のきっかけだったのだ、と。オンラインの可能性については、世の中の多くの人が気付き始めていると思う。ああ、このテの作業はオンラインで十分なんだな。むしろ、オフラインよりも効率がいい、といったように。医療の現場で、それを先んじて行ってきた原氏の着想には驚かされた。

オンライン診療、そのとき問われるドクターの資質とは?
「オンライン診療は、あくまで手段であって、ゴールではないんですよ」と原氏は言う。オンライン化は目的ではなく、理想の医療へ向けた長期的な取り組みのひとつ、という意味だ。そこで重要なのは「予防」への考え方なのだそう。新型コロナで私たちは改めて「予防」の大切さを知った。原氏によれば「より健康な生活を」という従来の考え方から一歩進めて「自分の価値観に基づいてライフデザインをしていく」ことがなにより重要で、その際には単なる「予防」ではなく、一人一人の価値観や人生観と向き合う姿勢が問われるという。
酒がなにより好きだ、という人はその価値観のもとでライフデザインをしていけばいい。ドクターは、その価値観に寄り添う。ただし、後悔をさせてはいけない。ものすごく単純にいうなら「あんなに飲み過ぎなければよかった」というようなことだ。そうした後悔をさせないために適切なデータを提示する。「その納得のいくデータを提供するのも、私たちの仕事だと思いますね」

臨床医を辞める、という決断
いわゆる医者、臨床医というキャリアを手放すことに抵抗がなかったいえばうそになる、と原氏は言う。周囲からも反対があった。「神の手」ではないが、自身が培った技術で、患者を治療する。そこに、医師としてのやりがいがあったからだ。でも、さまざまな経験を積む中で「医療現場の仕組みそのものに、これまでとは違うアプローチをかけられないか?」という思いに至った。医療の現場にコミットしたい思いに、変わりはない。そう考えると、聴診器やメスを持つことや論文を発表することだけが、目的を達成するための手段ではないはずだ。その思いを原氏はこう表現した。「輪郭をもって、現場の話をしたかったんですよ」と。
「輪郭」という言葉は、鮮烈だった。木を見て森を見ず、といった格言にあるように、ともすればわれわれは各論にのめりこむ。想像するに、医療の現場などは常識に縛られがちなのだと思う。その世界に、オンラインというテクノロジーを原氏は持ち込んだ。これまでの医療業界の常識からすれば、第一線を退いて裏方に回る、というくらいの決断だ。でも、だからこそ挑戦のしがいがある。「オフラインでは口にしづらいことってたくさんあるじゃないですか」原氏の指摘に、なるほど、と思わされた。

ビジネスとして成立させること。課題の解決は、そこからだと思う
「漠然とした課題意識があって、起業に至りました」と原氏は言う。これからの医療を育てるのは、制度とか、政策とか、事業とか、そんなものではないのか、と。そうしたものを進化させていくには「現場の声を吸い上げて、ビジネスとして成立させる仕組みづくり」が大事なのだ、と原氏は続ける。コンサル会社での経験で、ロジックを積み上げていくこと、整理すること、世の中の声を拾ってビジネスに生かしていくことを学んだ。
そのノウハウを、原氏は医療の世界に持ち込もうとしている。インタビューの最後に尋ねた。「医療とビジネスの理想の関係って、どういうものなんでしょうか」と。答えはシンプルなものだった。「人を治す医療機関に、できるだけ負担をかけないということではないでしょうか。それが、社会全体で健康をデザインしていくということだと思います」
MICINのホームページは、こちら。
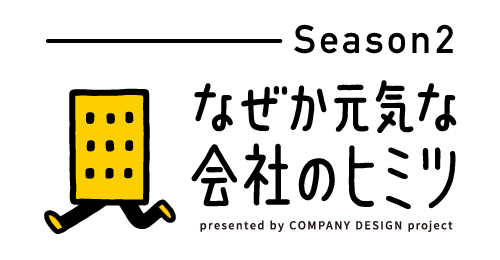
「オリジナリティー」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく連載のシーズン2。第7回は、コミュニケーションの力で医療の現場を支える「MICIN(マイシン)」をご紹介しました。
season1の連載は、こちら。
「カンパニーデザイン」プロジェクトサイトは、こちら。
【編集後記】
医療は、これまでも多くのドラマで描かれてきた題材だ。ジャンルとしては、刑事ドラマと同じくらいメジャーなものだろう。当然だ。人の一生を左右する現場。そこには、ドラマが生まれる。でも、私たちは、ともすれば忘れがちだ。そのドラマを支えているものが一体、なんなのか。そしてなにより、そのドラマはSFでもなんでもなく、リアルな現実なのだということを。
「ビジネスとして成立していなければ、医療は成り立たない」と原氏は言う。一見すると冷たい物言いのようだが、そこには深い愛情がある。医療従事者、患者、家族。すべての人がより幸せになれる仕組みをつくりたい、ということだからだ。
原氏はそこに、AIやITといった情報テクノロジーを持ち込んだ。これは、画期的なことだと思う。医療技術とは、一般企業でいうところのモノづくりの技術を磨くことや、サービスを提供する、ということだ。一方で、情報テクノロジーとはマーケティングやクリエイティブ表現にあたる。この二つがうまく噛み合ってこそ、ものごとは回っていく。豊かな社会に、一歩でも近づける。医療という、いささか身構えてしまうテーマの中に、われわれが目指すべき未来のヒントを見た。
この記事は参考になりましたか?
著者

荒木 俊哉
株式会社 電通
CDC
コピーライター
1980年、宮崎県生まれ。一橋大卒。2005年に入社後、営業局を経てクリエーティブ局へ。コピーライターとして商品や企業、自治体のブランディングに取り組む。主な受賞歴は、ACC賞、TCC新人賞、毎日新聞広告賞、日経広告賞、広告電通賞など。



