「オリジナリティー」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく本連載。第10回は、街の空きスペースと個性豊かなフードトラックとのマッチングで注目を集める日本最大級のモビリティビジネス・プラットフォーム「Mellow(メロウ)」。暮らし方や街そのものの「再編」までを見据えた、斬新なチャレンジに迫ります。
人の流れや、会合が制限されることで、社会を回す原動力は「コンタクト」なのだということに、私たちは改めて気づかされた。どれだけ素敵なモノをつくろうが、どれだけ心を込めたサービスを用意しようが、人との「コンタクト」が断たれてしまっては、どうにも社会は機能しない。
もちろん、オンラインやデリバリーなど、リアルなコンタクトに代わる手段はある。しかし、かつてそこにあったはずの熱量や空気感、高揚感や充実度といったものが、100%再現されることはない。「ふれあい」「ぬくもり」「息づかい」というものは、しばしばリリカルな暗喩として用いられるが、私たちが今、心から求めているのは、リアルなそれではないだろうか。
そうした中、果敢なチャレンジを続けている企業がある。日本最大級のモビリティビジネス・プラットフォーム「Mellow(メロウ)」だ。なじみのない企業名だとは思うが、この文脈で「じゃあ、フードトラックって知ってる?」と言われれば、誰もが「なるほど」と興味をかき立てられるにちがいない。もちろん、本稿のタイトル「社会は今、駆動力を求めてる」の「駆動力」は、暗喩でも、ポエムでもない。正真正銘のリアルな「駆動力」のことだ。
文責:吉田哲史(電通 事業共創局)

2016年2月創業。モビリティの機動力を生かして「なんでもない場所を、うれしい場所に。」をモットーに、街の空きスペースと、フードトラックをはじめとしたショップ・モビリティ(店舗型モビリティ)をマッチングすることで生まれるスペースを、関東・関西・九州を中心に450以上展開。併せて、フードトラック開業支援やイベント運用サポートなども手がける。「あの場所に行けば、会いたいお店がやってくる」。Mellowが手がけるショップ・モビリティの停留所「SHOP STOP」は、人々の暮らしに豊かな体験や環境を提供している。
チャレンジとは、これまでの延長線上にはない仕事に飛び込んでみること
「僕は、原体験のないタイプの起業家なんですよ。例えば震災経験から湧き起こったパッションのようなものがベースにあるのではなく、比較的のほほんとしたタイプ」。インタビューの冒頭、森口社長は穏やかな表情でこう話し始めた。Mellowに参画する以前は「データサイエンス」に取り組んでいた。その反動からか、そのうち人の縁とか、空気感みたいなものに惹かれていった。「チャレンジというと、これまで培った力を今こそ発揮してやる!みたいなイメージがあるじゃないですか。僕の場合、それが全く通用しないところに身をおいてみたいというのが、このビジネスに飛び込んだ理由といえば、理由なのかもしれません」

早稲田大学在学中(2013年)にALTR THINK(株)を創業。データ分析を駆使し100万以上が使うチャットアプリを複数開発後、上場企業へ売却。企業のデータ分析基盤構築など多くのプロジェクトに携わったのち、株式会社Mellowの創業に参画。現在に至る。ビジネス・テクノロジー・クリエイティブ・オペレーション、すべての文脈でショップ・モビリティ市場を成長させるため奮闘している。
「でも、正直、コロナはキツかったですね。短期的には売り上げが半分ほどに落ち込みました」。オフィス街に出没するフードトラック。その街から人影が消えてしまっては、お手上げなことは想像に難くない。ここで早くも森口社長が、冷静な一面を見せた。「そもそもショップ・モビリティとは『需給のギャップが発生している所』を狙ったビジネスなんです。客数が少なくなったということよりも、ビジネスの根幹であるギャップがなくなってしまったのだから、そりゃ、厳しいのは当たり前ですよね」
ピンチを経験することで、組織は強くなる
そうした中、不動産ビジネスといえばあの、と誰もが思い浮かべる大手企業との業務提携にこぎつけた。コロナ禍の波乱のさなかにあって、異例のことである。まさに降ってきた幸運のような話なのだが、ここでも森口社長は至って冷静だ。「これは、『入ったタイミング』と『入った場所』が良かったですね」。それだけですか?という質問にも、「自分たちの努力もありますが、努力はみんなしてますし、特別な理由としてはそれだけです」との答えが返ってきただけだ。冒頭の森口社長の言葉を借りるなら「ご縁は、ご縁として受け止め、何ができるのかを考える」ということなのだろう。
当時の森口社長には、社業への強い危機感があった。持ち前の温厚な性格からは一転、「いかに儲けるか」という厳しい指示を連発した。「それでもメンバーがついて来てくれたのは、それまでの『組織投資の蓄積』があったから、だと思います」。スタートアップ企業の多くが「ある程度稼げるようになった後に、企業内のカルチャーづくりに着手する」ものだが、Mellowという会社はその逆なのだという。「なんで、そんなことができたのか。弊社の場合、会社としての実績がない中でも縁に恵まれ、比較的資金調達を実施できていたからなんです」。ここに、Mellow躍進のヒミツの一端があった。

フードトラックは、絵になる事業
「なぜか元気な会社のヒミツ」を探る筆者としては、Mellowが先述の大企業のほか、官庁や自治体との連携をいかに実現しているのかについて、どうしても聞きたい。それに対する森口社長の答えは、またもや意外なものだった。「実績を使ってPRする。そのために、起業家自身がタレントのような広告塔として機能する。そういったスタイルも昨今多いですが、僕にはあまり向いたやり方ではないと思っているし、しなくても良かった。なぜなら、フードトラックは『絵が撮れる事業』だからです」。
あっ、と思った。フードトラックが停まっている風景そのものが「絵になる」。イマ風に言うなら「映える」。これは、PRの教科書の1ページ目に記載されていることと言ってもいい。商談にも、分厚い企画書などは要らない。写真を一枚見せられただけで、そのビジネスの思想や可能性が瞬時に飲み込める。その上で、森口社長はこう続ける。
「努力は、できるかぎりします。が、その後に大切なのは、確率論です。どの窓から入っていくか。堅い組織や大きな組織であればあるほど、ルートはたくさんある。大事なことは、同じ志を持ってくれる人の窓を探して、ノックをし続けることだと思います」。森口社長によれば、昨今取りざたされる「デジタルとアナログのすみ分け」も同じことなのだそうだ。「大事なのは、張り方×寄せ方の確率ですよね。どちらか一方に特化するのではなく、最適な組み合わせを考えるようにしています」

2000年代初頭、フードトラック事業者の「個の強さ」に感銘を受け、彼らの魅力を社会で持続可能なビジネスにしていくために、プラットフォームの土台を作り上げるなどモビリティの「現場」を誰よりも知る石澤氏(左)と学生起業を果たした森口氏。Mellowで出会うまでのバックグラウンドが全く異なる二人だからこそ、お互いの視点を補完しながら、共通のビジョンを描く。
多様性とは、なにか?
「多様性の本質や可能性とは、一体なんなのでしょう?」との筆者の質問にも、森口社長は意外な角度から答えてくれた。「たとえば音楽業界では、CDの売り上げが下がり続ける一方で、ライブの売り上げは伸びている。その売り上げの逆転が起きる瞬間を、音楽をやっていた大学1、2年の頃、経験したんです。コンテンツの流通が発達する(=流通コストが下がる)ことでマイナーな音楽を発見するコストが下がり、音楽業界全体のコンテンツのバリエーションが増えた。多様性の本質は従来のメジャー主義からの脱却にあり、『はやい、安い、うまい』以外のバリューをアクセラレートしていける感覚が魅力だと思います」
森口社長いわく、便利になるためのソリューションはたくさんあるけれど、豊かになるためのソリューションはまだあまりないのだという。たとえばローカルが抱える問題にしても、エッセンシャルコンテンツの供給だけを考えていたのでは、やがて疲弊する。
都会には都会の、ローカルにはローカルの「不要不急な楽しみ」がある。「多様性と向き合うポイントは、文化的、あるいは人間的なつながりを重視して、お互いにリスペクトし合うことだと思います。その意味では、我々のフードトラック事業も、創業からのポリシーこそ変わっていませんが、そのノウハウを適用できる領域は広がりつつあるように感じています」

ルールは、日々、変わる
「多様性ということでいうと、主体(個人や企業)ごとに豊かさの定義があって、それをさまざまな手段で世の中に訴えることができる、投げかけることができる、今はそんな時代だと思います。その投げかけが多ければ多いほど、個人も社会も豊かになれる。Mellowは、そのプラットフォームとして機能していきたいんです」
森口社長によると、ビジネスを起こすためには「成功をどのように定義するか」が大事なのだという。どういうルールで、世の中が回っているのか。サラリーマンであれば、会社組織というものが、どのようなルールの下で回っているのか。その仕組み、すなわちルールがわかって、物事を理解する上での抽象度をコントロールできるようになれば、どんな仕事でもうまく回せるのではないか、と。
「ただ、『ルールは、日々、変わるものだ』ということも、同時に認識すべきです。企業が失敗するケースの多くは、『ルールが変わっていること』に気づかず、過去の成功パターンを繰り返してしまうことにあります。サッカーで極端にたとえるなら、“手を使ってもいい”というルール改定に気づかず、かたくなに“足だけでプレーしている”ようなものです」。確かにそれでは、勝てるはずがない。自分とまわりを客観視するためには、「ルール」をわきまえているだけでなく、その「ルール」に対して常に疑いの目を向けていることが必要なのだ。
最後に森口社長は、こうインタビューを締めくくった。「大事なことは、『考えること、考え続けることに対する投資を惜しまないこと』だと思います」

Mellowのホームページは、こちら。
SHOP STOPのイメージムービーは、こちら。
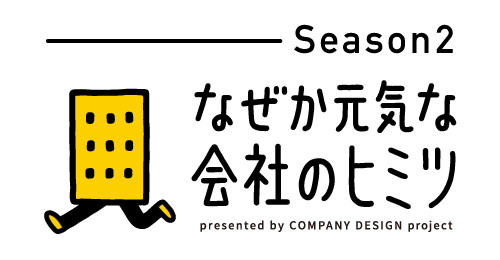
「オリジナリティー」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく連載のシーズン2。第10回は、日本最大級のモビリティビジネス・プラットフォーム「Mellow(メロウ)」をご紹介しました。
season1の連載は、こちら。
「カンパニーデザイン」プロジェクトサイトは、こちら。
【編集後記】
編集部から森口社長へ、あえて小学生のような質問を投げかけてみた。「僕はクルマが大好きなんですけど、森口社長はどうですか?」と。とにかくまず、ワクワクしますよね。と、齢50を超えた小学生に、森口社長は答えてくれた。そこからが、面白い。クルマの持つワクワク感の本質は、クルマだけが提供できる「場の質感」にあるのだ、と。
モノや人、サービスを運ぶという意味では、電車でもリアカーでも同じ。でも、クルマには独特のワクワク感がある。その正体は、クルマというものがもたらしてくれる「場の質感」の、それも「多様性」にある、と森口社長は言う。「自由」や「多様性」の象徴であるクルマが、思い思いのファストフードや野菜や魚を積んで、近くまで来てくれるのだ。誰だってワクワクせずにはいられない。
そしてそのワクワク感は、「行く」と「来る」の中間に置かれることで、爆発的に高まるのだ、と森口社長は続ける。店舗で座して待つのではなく、客のすぐそばまで出向いて「行く」。家やオフィスにデリバリーが「来る」のを待ちわびるのではなく、そのワクワクする対象まで足を運んで「行く」。だからこそ、売る人も買う人も、自然と笑顔になってしまう。難しい言葉で言うなら、「衝動来店」と「目的来店」の中間にフードトラックは位置しているんですよ、と森口社長。「なんの気なしに、出合ってしまった」喜びと「探していたものにやっと巡り合えた」喜びの二つが混在している。それが、あのワクワク感になるのだ。
繰り返し言うが、その「ワクワク」がクルマに乗ってやって「来る」。その場についつい出向いて「行く」。とても自由で、とても開放的で、他では体験できない心地のよさである。「時代が求めている豊かさというものは、画一的なものや、我慢や努力の末にようやく獲得する、といったようなものでは、もはやないのだと思うんです。その象徴が、フードトラックなのではないでしょうか?」森口社長の、あっけらかんと分かりやすく、とはいえ、とてつもなく深い指摘に、齢50超えの小学生は大いにうなずかされた。
この記事は参考になりましたか?
著者

吉田 哲史
株式会社 電通
事業共創局
ニュー・ビジネス・クリエイター
営業(キリンビール、三井不動産、経済産業省、日本郵便)、マーケティング&プロモーション(サントリー等飲料メーカー、官公庁、三菱地所等ディベロッパー、大塚製薬等製薬会社、オリックス生命等生命保険会社、イオン等流通を担当)を経て、2014年に現局の前身であるビジネス・クリエイション・センターへ。4年間に渡り、都市開発を中心に携わる。現在は、社会課題解決を切り口としたビジネス開発をプロデューサーの立場から推進。 【主な社内受賞歴】 2008年度 電通GRANDPRIX(フード・アクション・ニッポンの立ち上げ) 2012年度 ベストプラクティス賞、ベストナレッジ賞(国産食材購入促進のポイントシステム構築) 2019年上期 ベストソリューション賞(TOKYO MID TOWN HIBIYA「BASE Q」立ち上げ)


