「オリジナリティ」を持つ"元気な会社"のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく本連載。第12回は、創業約100年の梅干し屋さん「紀州ほそ川」の、驚くべきサバイバル術に迫ります。
少し年下の細川社長とは、学生時代からの友人だ。彼の留学のちょっとした助言をし、帰国後は就活の助言もちょっとだけした。大手アパレル会社からキャリアを始めた彼は、数年の勤務の後、和歌山で家業を継ぎ、“新人経営者”になった。それからも上京した折に途切れることなく会ってきたが、毎回、土産のように持ってきてくれる仕事の話にはいつも引き込まれた。経営理論より現場、定石より直感で動く彼は、同業者の誰もが生産過程で捨ててしまうものから作り出した商品で、新事業を軌道に乗せてしまった。
働きたい育児中の女性向けの求人では「完全在宅勤務可」とし(実際には「出社可」と書いていた)、周囲を驚かせた。世の中にコロナのコの字もない、2014年のことだ。新規事業開発、サーキュラーエコノミー、働き方改革、地方創生……。今、多くのビジネスパーソンが向き合う課題を、いつの間にか解決してしまっている彼のモノの見方には、きっとわれわれが知っておくべきヒミツがあるはずだ。そんな思いから、今回、取材を依頼した。
文責:薬師寺肇(電通BXCC)

梅づくり約100年、紀州の梅の産地のど真ん中で代々、梅を栽培する梅干し屋さんです。梅研究者だった先代が梅の有用成分に着目し、研究を続けてきた結果、梅の新しい用途開発を得意としています。例えば、梅の抽出成分からつくる不妊治療剤や家畜の肉質を向上させる飼料などです。また近年では、生姜や八升豆の有用成分を利用した製品を研究・開発し、販売するなど、「伝統的な食材の新しい使い道をつくるメーカー」だと自負し、新製品を世に提案し続けています。
紀州といえば、梅。でも、その常識は、まだ日が浅い
「50年前に、偶然発見された南高梅から、紀州の梅は始まっているんです」。インタビュー冒頭の細川社長の発言には、正直、びっくりした。徳川吉宗の時代から梅の産地だったのだろうな、というくらいが世間一般のイメージだからだ。「たまたま畑で発見された南高梅が、おいしいし、皮が薄くて食べやすいということで、その木を接ぎ木、接ぎ木して、いまに至っている、というのが事実です。1本の南高梅がきっかけで、それまで全国ナンバーワンだった群馬県を抜いて、一気に和歌山県が梅の生産地として認知されるようになったんです」
南高梅、皆きょうだいなんてうそでしょう?という話だ。そのうそみたいな話から、今回の取材は始まる。とはいえ、そこまで梅に依存した生活を、そもそも私たちはしてないけどな、という思いを含めて。

1985年生まれ。2009年に中華人民共和国の厦門(アモイ)大学を卒業後、ファーストリテイリングに入社。13年に家業である梅干し屋さん、㈱紀州ほそ川に入社するも、同年、長年の研究データを基にした製品開発を目的とし研究部を分社化、ワノミライカ(現・紀州ほそ川創薬)を設立。現在、両社の社長を務めている。強運だけが自分ができるたった一つの専門分野だと豪語し、従業員の力を最大限に借りて、命からがら生きている、ご機嫌なハートの持ち主です。
「紀州ほそ川は、創業およそ100年。初代は、梅農家。2代目は、梅商人。3代目に当たる父は、大学で生物資源を学んだ梅マニアともいうべき研究者。そして、4代目が私です。この間、着実にビジネスとしてステップアップしてきている。そこが、われわれの強みといえば、強みですね」。そう、細川社長は話す。中でも、梅マニアのお父さまの存在は、自分の親ながらすごい、と言う。「とにかく、梅のポテンシャルを信じて行動していました。口を開けば、もったいない、もったいない。そればかりですから。一時期、余った梅肉で髪を洗ってましたから。これは、ホントの話です。まあ、1年ぐらいでやめましたが、さすがに、梅肉シャンプーは」
梅の良さは、誰もが直感的には分かっている。体に良さそうだ、と誰でも思う。でも、良さそうだ、良さそうだ、と言いながら、梅干しを作る過程で出てくる梅酢は、生産者でさえ、ゴミとして捨てている。しかも産業廃棄物になるので、捨てるのにお金がかかる。個体か、液体か、の違いだけで、梅酢には梅干しと同じ良い部分がそのまま残っているのに、市場価値は全くない。それっておかしいでしょう?3代目の社長は、そのことをあちこちに触れまわったのだという。「もう、手当たり次第ですよ。人が難しければ、牛、豚、鶏、魚、あらゆるものに梅酢を使った飼料を試してみる。子ども心に、この人、すげえな。その情熱は、一体どこからくるんだろう、と思っていましたから」
イケイケ、ノリノリの時にこそ、明日への投資が必要
「梅干し製造業のピークは、2000年。そこから需要が落ちて、年に1%ほど、売り上げが下がり続けています。当たり前ですよね?若い世代になればなるほど、梅干しなんかなくても全く困らないわけですから。実は、製品単価でいうと1997年がピークなんです。つまり、その後の3年、グロスとしての売り上げは惰性で伸びていただけのこと」
ここで先代は、手を打つ。「ものすごく高額な、脱塩のための機械を買っているんです。それも、98年に、億単位で。うちの会社からしたらかなりのことですよ。それも、梅干しの売り上げはまだ伸び続けていたイケイケ、ノリノリのタイミングで。周囲はそれこそ、高いクルマを買ったり、畑違いのビジネスに手を出したりしていました。でも父は、そんなことには目もくれなかった。梅の魅力が伝わっていないことに、我慢がならなかったんです」

「まず、効果が表れたのは豚。おいしい肉質の豚がうまれた。つづいて、鶏ですね。鶏卵。親鶏が健康になる。すると、質のいい卵を、それも長く産み続けてくれる。もちろん、失敗もたくさんあります。牛は、完全に失敗しました。梅酢のパワーで、健康にはなるんですが、健康になりすぎて、マッチョな牛になってしまうんです。つまり、あのおいしいサシの部分が減っちゃった。どうしてくれるんだ?と叱られたりしました」
唐突ですが、暴走族の話をします
梅干しを作る過程で出る、梅酢。そのままでは、産業廃棄物になってしまう厄介モノから塩を抜いた。そのエキスを活用した工夫は、飼料だけではない。完全に塩を抜くと、それは梅果汁たっぷりの梅ジュース(梅果汁には糖分がほとんど含まれないので全く甘くない果汁です。そういう意味で、想像する甘いジュースではないかもしれない)になる。紀州ほそ川では、その梅ジュースに、梅を浸す。「梅を塩漬けして天日干しした段階の塩分濃度はおよそ20%。そのままでは、しょっぱくて食べられたものではありません。そこで、水に浸して半分くらいまで塩分を抜く。でも、そうすると塩分といっしょに、栄養やうま味成分まで溶け出しちゃうんです。そこに梅ジュースを使うことに気付いた。うま味はそのまま、というわけです」
説明を聞けば誰でも分かる理屈だ。でも、誰も気付かず、気付いたとしても誰もやらなかった。その革命をやってのける、揺るぎない信念と行動力には、脱帽だ。「例えば、暴走族っていますよね。俺たちは、社会のルールには縛られない!みたいな。でも、よくよく考えると、不良はバイクに乗って、パラパラと変な音を立てて街中を走り回るものだ、と誰かが作ったルールに乗っかっている。それでは革命でもチャレンジでもありません」。普通と違うだけでは、まだ新しさはつくれていない、ということだ。

便益なきものは、必ず捨てられる
「梅干しは日本の食文化だ。だから、毎日3粒は必ず食べよう」みたいな言い方が昔から許せなかった、と細川社長は言う。「そういうのは、文化の消耗、文化への寄生だと思うんです」
作り手、送り手として一番大切なことは、時代が求める価値を提供できているか、ということ。それには、何かを変化させなければならない。世の中に評価されたり、文化として残っていくかどうかは、自分たちが決めることではない。それはあくまで世の中が、そして後世の人が決めることだ、と。
「便益のないものは、必ず捨てられ、時代から忘れ去られていくんです。だから僕らは挑戦を続ける」。そう言う細川社長は、先代の社長が挑み、一度は失敗した梅酢の人への活用に再び挑戦した。梅酢は必ず人間にも役立つはずだと信じ、粘り強く続けてきた地元医大との共同研究で、不妊治療への有用性が見つかったことがきっかけになった。別会社をつくり、ゼロから始めた妊活サプリメント事業を軌道に乗せ、今は次なる事業開発へと突き進んでいる。
「創薬事業というものは、そう簡単なものではありません。認可が下りるまで、とてつもない時間も労力もかかります。でも、難しそうだから、とチャレンジしなかったら、なにも生み出すことはできませんからね」

森の話と、ドングリの話
細川社長は、何年も前から在宅勤務を取り入れたり、子ども同伴で出社してもいい仕組みを作ってきた。事務所には、オフィス机が置かれている横に、子どもたち用のプレイゾーンが作られている。「経営でも、人との接し方でも、なにかに迷ったときは、その方法は森でも生きていける選択なのか、ということを考えてみます」と、細川社長は言う。森の中へ一人で放り出されたら、人間などあっという間に、野垂れ死んでしまう。環境保全だのなんだのと、聞こえがいいことを言うのは簡単だが、例えばそれを森の神様が見たらどう判断するだろう?ということを考えれば、やるべきことはシンプルだ。
「職場に子どもを連れてくるなど、あり得ないと思われてきましたよね。でも、縄文時代のお母さんは、きっと子どもを抱きながらドングリを拾い集めていたはず。それが、自然ではむしろ当たり前のことだと思うんです。働き方の生産性をあげる、とはそういうことですから」
オン・オフをしっかり区別しましょう、といった最近の風潮も、細川社長に言わせればナンセンスだという。「愛する家族と幸せに暮らしていくために、僕らは生きているわけですよね?であれば、オンもオフもないでしょう」。さらにそれは、社員やお客さまについても同じなのだと言う。
「僕に言わせれば、社員もお客さまも会社との距離感が少し違うだけなんです。例えば、商品だけ買い求めたいというお客さまがいる一方で、こうした方がいいよ、ああした方がいいよと積極的にアドバイスをくれるお客さまがいたり、いろいろな方にうちの商品を勧めてくれるお客さまもいる。やっていただいていることは、社員ともはや変わらないんです。ちなみに、わが社のことを心から愛してくださるお客さまのことを、僕は『お友達さま』と呼んでいるんです。友達、ではさすがになれなれしいですから、お友達さま」
森で生き抜くことに立ち返って考えている細川社長にとって、働き方改革やファンマーケティングといった言葉は、最近そう呼ぶ人もいる、くらいのものでしかないだろう。あるいは、意識すらしたこともないだろう。真に新しいことや、物事のあるべき姿とは、そうした本質価値の森を通り抜けなければ、たどり着けないものなのかもしれない。森とドングリの話の中に、意外な示唆を見いだした。
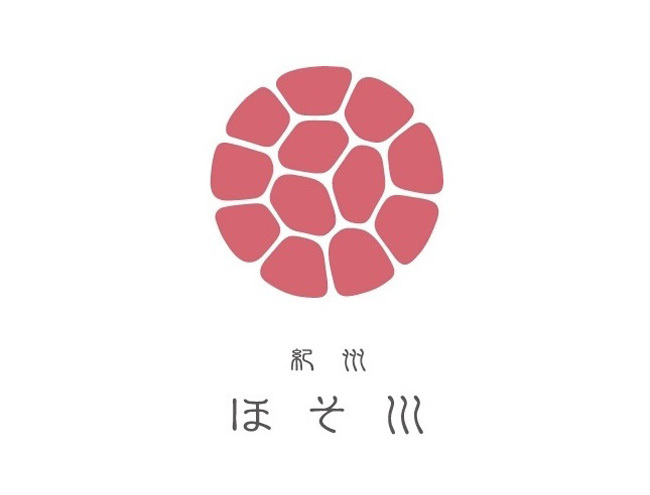
紀州ほそ川のホームページは、こちら。
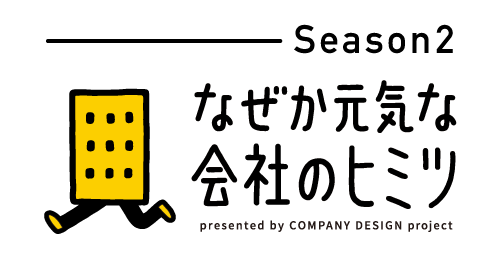
「オリジナリティ」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく連載のシーズン2。第12回は、創業約100年の伝統に甘んじない梅干し屋さん「紀州ほそ川」をご紹介しました。
season1の連載は、こちら。
「カンパニーデザイン」プロジェクトサイトは、こちら。
【編集後記】
取材の最後に、今回、どうしても聞いてみたかった質問を、細川社長にぶつけてみた。「個人的には、梅って、世の中から過小評価されているものの代表のように思えてならないんですよ。そもそも、松竹梅の最下位ですし。和歌で詠まれる花といえば、平安時代から桜のことですよね。でも、おぼろげな記憶でいうと、万葉集では花といえば梅の花のことだったように思うんです。細川社長は当然、梅のことを愛しておられますよね?そこまで梅にほれ込んでいる理由を、お聞かせください」
われながら、意地悪な質問だ。でも、その質問に対して、細川社長は即座に、こう打ち返してきた。「果実としての生の梅の実、食べたことあります?スモモをイメージしてください」と。ああ、そうなんだ。スモモのようにおいしいものなんだ、と早合点したのもつかの間、「そのスモモから、甘さを完全に抜き取ったような、ただただ酸っぱくてまずいものなんです。梅ってやつは」。細川社長の話はつづく。「その、とてつもなくまずいものが、1500年もの間、食べ続けられている。これって、すごいことだと思いませんか?すごいというか、愛らしいというか、こいつ、どこまでかわいいやつなんだろう、みたいな」
かわいいだけ、じゃない。いまだ人智が及ばない、とてつもないポテンシャルを梅は持っている。そうでなければ、奈良時代から現代に至るまで、珍重されてきたことに説明がつかない。その謎を、解き明かしてみたい。自分が生きている間に、できることかどうかは分からないが。そんな気持ちにさせる梅のことが、とにかくいとおしくて仕方ない。
笑いながらそう話す細川社長の言葉に、甘酸っぱい気持ちと同時に、この国に生まれて良かった、という思いが込み上げてきた。梅には、チカラがある。そう言われて納得しない人は、少なくともこの国には、一人もいない。はずだ。
この記事は参考になりましたか?
著者

薬師寺 肇
株式会社 電通
ビジネストランスフォーメーション・クリエーティブ・センター
プランナー
ソリューション・ニュートラルなコミュニケーション設計から、商品開発・事業開発まで担当。ビジネスとクリエーティブと技術の接点を日々探しています。



