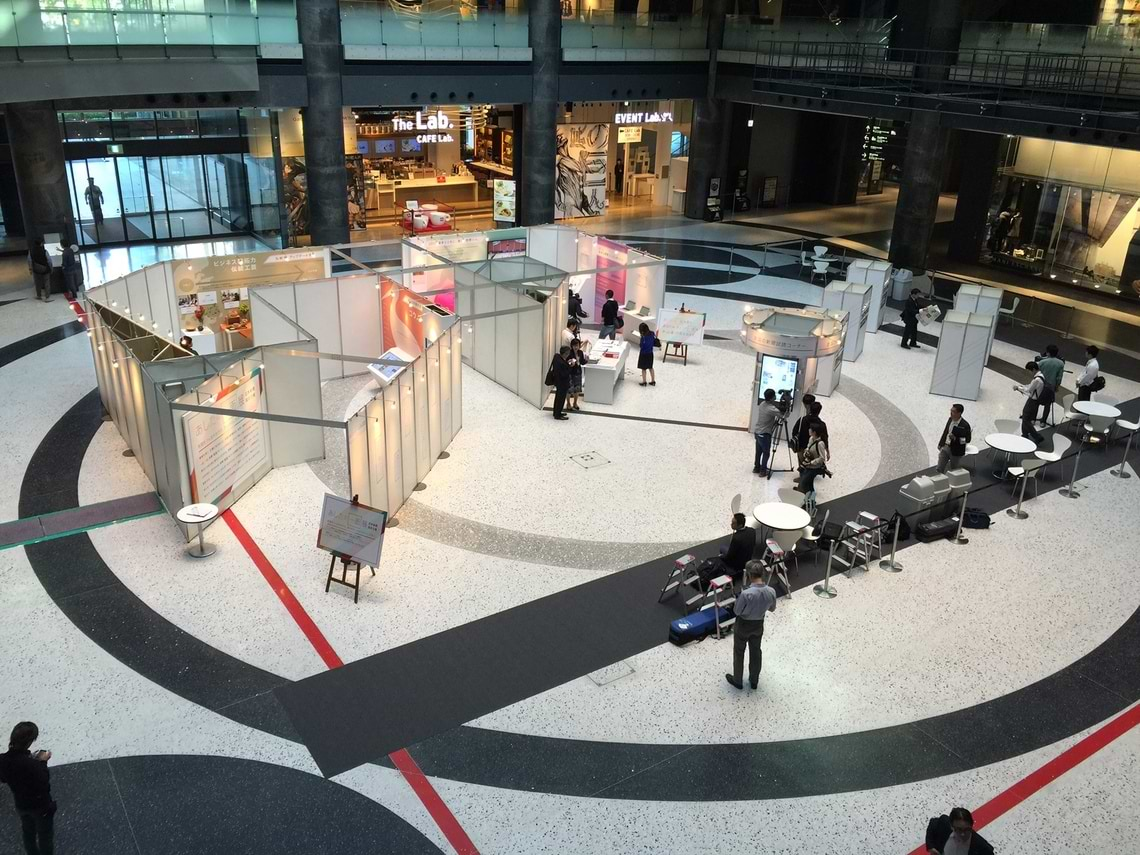前編 新聞メディアの未来を考えよう――欧州各国の事例から学ぶ
ニュースはネットで、いつでもどこでも無料で入手可能な時代。そんな中、ニュースメディアとしての存在意義、更にその拠って立つところのビジネスモデルが転換期を迎えている日本の新聞業界。欧米の新聞社では、いち早く自社サイトのコンテンツを無料で公開してきており、現在は読者とともに記事を生成してゆくオープン・ジャーナリズムの動きが盛んです。世界のメディア事情に詳しい在英メディアアナリスト・小林恭子氏に、欧州における新聞社の施策と、オープン・ジャーナリズムの今後についてお話を伺い、新聞メディアの未来を考えます。

欧州のオープン・ジャーナリズム
――英ガーディアン紙がオープン・ジャーナリズム宣言を行った「三匹の子豚」のCMがカンヌライオンズ2012・フィルムクラフト部門などで金賞を獲りました。ガーディアンをはじめとする欧州新聞社のオープン・ジャーナリズムの動きについてお聞かせください。
小林 あのCMは、ガーディアンがブランド戦略の一環としてオープン・ジャーナリズムを前面に打ち出したときに放送されたものです。その大きな前提として、1990年代半ばに各新聞社がウェブサイトを立ち上げ始めたとき、英国ではウェブ版が無料で閲覧できたという背景があります。当時はあくまで紙の補足という位置づけでしたが。
BBC(英国放送協会)が無料のニュースサイトを設置したこともあって、これに新聞社が対抗する必要がありました。また、「多くの人にあまねく情報を伝えることが社会や国を豊かにする」という考えもあって、新聞社はウェブ版の記事を常に無料で提供するとともに、コメント欄をつけて国民、読者からの意見も取り入れていこうとする試みが早くから行われていました。
「オープン・ジャーナリズム」の顕著な例としては、ガーディアンが、まずは自社ウェブ内に市民、NGO、ジャーナリストたちのブログサイト「コメント・イズ・フリー」を作りました。通常の記事のコメント欄でただ意見を募るだけでなく、サイトの中に彼らが意見を発するスペースを抱えたわけです。さらに、NGOや観光局などが記事データを自由に活用できるように、API(アプリケーション・プログラミング・インターフェイス)を開放して、過去記事の解析、二次利用を可能にするなど、自分たちのコンテンツを公共財のようにオープンにしました。

――市民やNGOがアプリケーションを使って記事を作成したりできるというのは、まさにオープンデータ化されているということですね。市民が利用するガーディアンの記事に広告はつくのでしょうか?
小林 広告がついてもかまわないということであれば無料で利用できます。広告をつけずに利用する場合は有料になるなど、すべてが無料というわけではなく段階に応じてやっているようです。英インディペンデント紙の例では、ウェブサイトの記事は全部無料で読めますが、普通に印刷すると広告が表示されるけれど料金を払えば広告が出ないものが出せるといった試みを過去にしていたことがあります。有料電子版が好調なフィナンシャル・タイムズも一部は無料で読めるメーター制を使っていますし、無料と有料を組み合わせてどうやって利益を生じさせるか、各紙があれこれ試しているという感じです。
各社が展開する「若者対策」
――ウェブを中心としたオープン・ジャーナリズムが進む過程で、欧州では紙の新聞はどう位置づけられているのでしょうか?
小林 紙媒体の最大の価値は、編集室があって、一定の人数とお金をかけて、プロの記者がコンテンツを作っていることからくる信頼性とクオリティの高さであり、そこは今も強く認識されていると思います。ウェブで記事が読まれている時でさえ、そこは意識されています。
――日本では若者の新聞離れが言われていますが、欧州ではどうでしょうか。若者たちに向けて新聞社はどういったコミュニケーションを行っていますか?
小林 若者の新聞離れは欧州も状況は同じです。年齢によらず、読者や広告主が紙媒体よりもネットに向かう傾向がありますよね。でも、たとえばガーディアンは同紙の日曜版とも言える「オブザーバー」と共同で、若者が興味を持ちそうなトピックを扱った記事や若手著名人のインタビューなどをまとめてA4判の小冊子にして街角で配っています。紙の新聞を一度も手にしたことがない若者にも読んでもらえる紙面を作って、広告も若年層向けのものになっています。さらにそこから購読につなげるために、たとえば2週間、ディスカウント価格で新聞が買えるクーポンを付けて、実際に小売店やスーパーに行って新聞を買ってもらうようにするわけです。クーポン券を収納できるミニ・ウォレット(財布)を作ったりもしています。ウォレットの内側に地下鉄の路線図や映画情報など広告も入っています。私自身もこのクーポン券を使って新聞を買ったりしましたが(笑)、2週間経つと、購読という一つの体験になるんですよね。
――そうした販促活動だけでなく、本紙の中身にも若者向けのコンテンツがあるのでしょうか?
小林 あります。たとえばインディペンデント紙は、「i(アイ)」という若者通勤客向けの簡易版新聞を2010年に作りました。1部売りを本紙の5分の1の価格にしたところ、本紙の部数の4~5倍も売れています。さらにガーディアン、タイムズなど一般の新聞には、いわゆる日本の夕刊に載るような軽めの情報を集めた付録冊子が毎日付くんです。20~40代の人が興味を持ちそうなダイエット、旅行、映画、本などに関するコンテンツを中心にした15ページくらいの雑誌みたいなものです。

宅配率の高いドイツ、オーストリアでは
――ドイツやオーストリアは日本と同様、新聞購読率が高く、比較的若年層にも読まれているという話を聞きますが。
 小林 はい。日本と同様宅配率が高く、購読が習慣化している地域です。ドイツの新聞協会では幼稚園に新聞を持って行って授業に使ってもらったり、20~30代の女性が出産する際、産院に協力してもらい、ドクターを通じて本や新聞のセットをプレゼントするといったことをしています。私が以前に取材したドイツのアクセル・シュプリンガー、オーストリアのラスメディアの2つのメディア企業は若い世代へのアプローチもうまくやっています。とくにアクセル・シュプリンガーは高級紙ヴェルトを若者向けに再編集した「ヴェルト・コンパクト」という新聞を発行したり、社内に若者向けの研修・トレーニング制度を持っていたり、テクノロジー系のスタートアップ企業を支援したりと、若者施策に非常に積極的です。
小林 はい。日本と同様宅配率が高く、購読が習慣化している地域です。ドイツの新聞協会では幼稚園に新聞を持って行って授業に使ってもらったり、20~30代の女性が出産する際、産院に協力してもらい、ドクターを通じて本や新聞のセットをプレゼントするといったことをしています。私が以前に取材したドイツのアクセル・シュプリンガー、オーストリアのラスメディアの2つのメディア企業は若い世代へのアプローチもうまくやっています。とくにアクセル・シュプリンガーは高級紙ヴェルトを若者向けに再編集した「ヴェルト・コンパクト」という新聞を発行したり、社内に若者向けの研修・トレーニング制度を持っていたり、テクノロジー系のスタートアップ企業を支援したりと、若者施策に非常に積極的です。
ラスメディアにもやはり若者向けの新聞というのがあり、こちらでは地元の若い人たちを多く紙面に出すということをやっています。若者が集まるイベントに取材に行って彼らの写真を撮って載せると、記事がFacebookでシェアされていくという効果があるようです。
――新聞を読んでほしい層と直接接点を持って、具体的に語りかけ、彼らの意見を反映した紙面が作られているわけですね。
小林 そうですね。それと、編集幹部が若いこともポイントです。実際、インディペンデント紙の編集長が今まだ30代前半です。新聞社で働いている人全員が必ずしも若いというわけではないですが、30~40代が中心ということは言えますね。日本でも新聞を読まない層を取り戻したいならば、できることの一つとして組織面の大幅な若返りもあるのではと思います。
――日本でもまだいろんな施策ができる可能性がありそうですね。最後に、日本の新聞メディアも今後急速に、デジタルシフトに大きく舵を切っていくでしょうか?
小林 実は、日本と欧州の新聞メディアを取り巻く状況は、単純に同列に語ることはできないと思っています。なぜなら、日本では、それこそ米ワシントンポスト紙のように新聞社が全く違う業界の個人に買われるというような大胆な変革が、新聞社に対して望まれているのか。むしろ国民は現状維持、安定を選ぶのではないでしょうか。とくに日本では社会の公器としての新聞に対する期待感がとても高い。欧州では新聞のウェブ版記事にコメント欄があって、新聞社側も読者側も様々なコメントが出ることに慣れていると思いますが、日本の新聞サイトでコメント欄があるところはほとんどないですよね。新聞がある意味公的な存在であるがゆえに、コミュニケーションが一方通行になってしまっているというのはちょっと残念と言えるかもしれません。
(続く)





 小林
小林