カンヌ、審査の舞台裏を語る
「カンヌライオンズ 国際クリエイティビティ・フェスティバル」が、6月19日から23日までフランス・カンヌで開催されました。世界最大規模のクリエイティビティの祭典は、クリエイターの目にどう映ったのか。受賞者、審査員、プレゼンター、さまざまな立場でカンヌに関わったクリエイターたちが、それぞれの視点で、カンヌの「今」をひもときます。
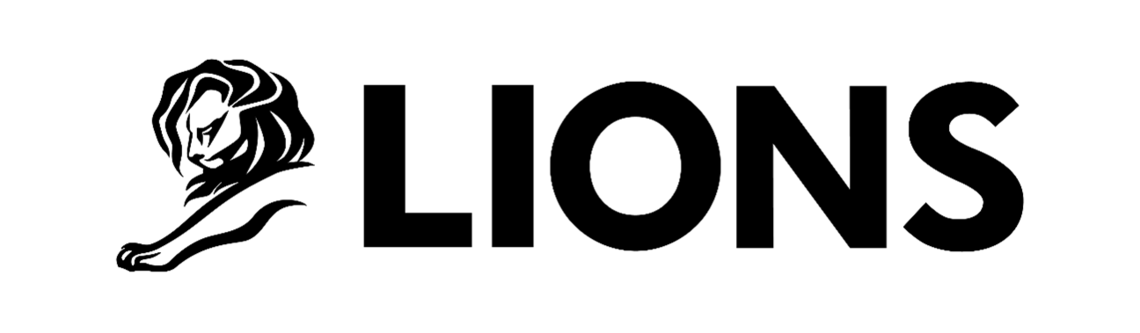
第3回は、インダストリークラフト部門の審査員長を務めた、電通 zero エグゼクティブ・クリエーティブディレクター八木義博氏へのインタビュー。審査する側の立場から、カンヌはどのように見えていたのか。実際の審査の舞台裏はどうなっていたのか。審査員長の役割、審査の過程の様子、日本と世界のクリエイティブの違いなどについて聞きました。
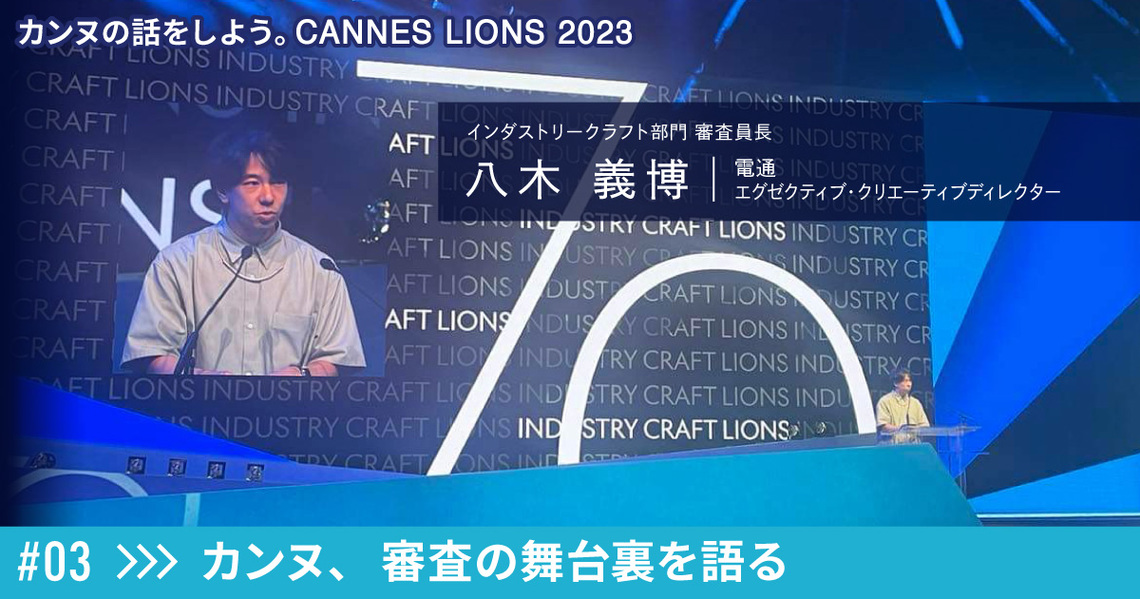
審査結果は、世界に向けてのメッセージ
──今年のカンヌライオンズ、現地の様子はいかがでしたか?
八木:昨年は、コロナ禍を経て再びカンヌライオンズでリアルに集まれることの大きな喜びがあったようですが、今年はすっかり平常運転といった様子で、各国の審査員仲間との再会から始まって楽しく過ごすことができました。
全体の受賞作品を眺めると、どこかリラックスしてのびのびとした仕事、ベーシックでブランドに素直に向き合っている作品が多かったように感じました。この3年間で、遠い国の話が自分たちに大きく影響することを経験し、それがシェアされて、「つながり」や「利他」といった感覚がスタンダードになってきているなと感じました。
──八木さんが審査員長を務められたインダストリークラフト部門とは、どのような部門ですか?
八木:「創造的なアイデアに必要な、美しく遂行されたソリューション、芸術性、才能、技術を称える」──カンヌライオンズはインダストリークラフトをこう定義しています。僕自身は、これまでデザイン部門の審査に2度参加していますが、その審査をする中で、日本で共有されているクラフトの意味は、審査室でなされている会話に比べると、どうしても狭義になってしまうなと感じていました。クラフトのためのクラフトではなく、コミュニケーション産業における、人の心を動かすためにブランドと生活者の接触面において、最後の質感の部分とも言える知覚に大きく影響を与えているのがクラフトです。ブランドが掲げるビジョンの、その声のあり様を評価するカテゴリーであると考えています。
──カンヌライオンズの審査員長の役割について教えてください。
八木:まず、審査員長として、オンラインで事前審査を開始する前にクライテリアについて発表しました。AIが台頭する時代のクラフトのあり方とはどういうことなのか、今の時代にクラフトを再定義したいということから、ブランドとユーザーとの感情的な結びつきを探そうということを提示しました。
クラフトの技術的な資質に加え、考慮したのは、そのブランドが自らの倫理観に従い、世の中のために本当にやりたいことに取り組んでいるかどうか。そして、人々は本当にそれを応援したい、共感したいブランドとして選び、一定の対価を支払っているか。さらに、審査において直感的な視点もあわせ持つために、キーワードも提示しました。審査の現場では、「enrichment > convenience」「emotion > function」「dreams > efficiency 」という3つの基準を会場に掲げました。利便性よりも充実や豊かさ、機能よりも感情や情緒、効率よりも未来やビジョンなどの人間的なことが大事だという基準で審査していこうというものです。
この基準をくぐりぬけるAIの仕事も見てみたいという気持ちもありました。と言っておきながら、少し青臭い内容になってしまったかな?と、審査員に説明する際には一種の気恥ずかしさがありましたが、全員に賛同されて、内心救われる思いでした。やはり、こういった青臭さが求められる時代でもあると思っています。
審査員の面々はクラフト系の審査ということもあって、デザイナー出身で建築にも携わっている人やコピーライター出身のクリエイティブディレクター、エージェンシー(広告会社)のCCO(Chief Creative Officer)クラス、地域もヨーロッパ、北欧、アメリカ、アジアとバランスがよかったと思います。ウクライナから参加している方もいらっしゃいました。みんな聞き上手で優しかったですね。
審査員長は本審査では投票は行いません。決を取る前までの議論によって、質の高い判断材料をいかに机上に並べられるか、ファシリテーションが審査員長の仕事です。議論の質を高いものにするために、審査員のモチベーションが大事だと考え、時間配分を徹底して管理し、メリハリのある進行を心がけました。
そして、審査員長の一番大きな仕事といえば、さまざまな背景を持つ審査員と共に、今年の受賞作品を通じて世界に向けてこのカテゴリーからメッセージを作ることです。そして、アワードセレモニーにて審査員長から贈賞を行います。受賞者と直に触れ合うことができるのも審査員長としてうれしいことでした。心からおめでとうという気持ちで壇上に上がりました。随分と緊張しましたが……。
──今回、インダストリークラフト部門では、八木さんが制作に関わったJRグループ「MY JAPAN RAILWAY」がグランプリを受賞するという、ドラマチックな結果となりました。
八木:とても貴重な体験ですし、すごく光栄なことですが、自分が審査員長であることもあって、審査の過程では、このままグランプリになったらどうなっちゃうんだろう?と、少し戸惑っていました。当然、オンライン審査でも、自分が所属する会社が手掛けた作品には投票できませんし、対象作品を議論する際には、審査員長であっても部屋の外に出されてしまいます。ゴールドに決定していた6つの作品の中からグランプリの候補を審査員から挙げてもらい、議論と投票で決めていくのですが、今年は候補がこの1作品しか現れず、満場一致で受賞が決定しました。それは素晴らしいことですが、審査員長としては少し寂しい気もしていました。でも、ぜいたくな話ですよね……。

ゴールドを受賞した、ある審査員の作品はグランプリ候補に選ばれなかったのですが、カンヌライオンズの事務局から、心理的にグランプリ決定の議論や投票に参加できるかどうか、丁寧に確認が入っていて、まるでボクシングのレフェリーのような厳粛なムードでグランプリが決定されていきました。
その後、自分が議論に参加できていないところをキャッチアップするために審査終了後に座談会を開き、このカテゴリーでの議論の内容について、まとめる時間をもうけ、プレスカンファレンスではその内容に基づいて報告発表を行いました。
デザイン部門やクラフト系のアワードでは大抵、ジャパニーズクラフトなど日本のエキゾチックな要素や細部の作り込みに注目される傾向があります。しかし、審査会場で交わされていた意見は、もっとコミュニケーションの戦略の視点からなされていて、「MY JAPAN RAILWAY」についても、「どこにクラフトの技術を使ったのか?」「公共の施設である駅をどう感情的な価値に変えたのか?」「それらは今後も継続・拡張していけるのか?」といった一口にクラフトという言葉に片づけられない視点が重視されていました。このような視点を作り手側がきちんと認識することで、日本の作品のレベルはもっと引き上げられると感じています。
アワードセレモニーでは自分はプレゼンターであるため、佐々木康晴CCOに受賞者代表として登壇していただきましたが、受賞時の写真だけ見ると、どちらがどちらにトロフィーを渡しているのかわからなくなっていましたね。レアなケースでした。

日本の課題は、世界の課題でもある
──日本の作品がカンヌでグランプリを獲得することは、なかなか難しいとされてきました。日本と世界のクリエイティブに違いを感じますか?
八木:日本と世界の国々で、違いは大いにあると思います。そもそも国が違うわけですから、言語や文化、法律や宗教なども違ってきますし、浮かび上がってくる課題のあり方が違います。その課題の数だけ違うクリエイティブがあるということですよね。
傾向として欧米のほうが本質的でビビッド、ダイナミックなキャンペーンに感じることがあって、日本は常にカンヌから学ぼうというスタンスが見受けられると思います。確かに欧米の事例から学びのチャンスはたくさんあって、自分たちの目の前の仕事に生かせるように努力するべきだと思います。
ただ、日本と海外で環境が違うわけですから、発揮されるクリエイティブの種類も違ってきて当然です。そもそもカンヌライオンズでは、世界をより良くするためにシェアされるべき仕事が、評価され、受賞していると思うんです。そう考えると、僕たちが応募するべき仕事は、日本で生まれる、世界にシェアしたい仕事のはずだと思うんですね。
今回審査を始めるにあたり、インダストリークラフト部門での昨年のグランプリ受賞作「Hope Reef」には当然注目していたのですが、審査員団の中にそれを手掛けたクリエイターがいて、数年前のデザイン部門グランプリである「Trash Isles」という作品を手掛けたのも同じチームであることを知りました。その仕事も尊敬していたので、少しミーハーな気持ちと、そんなすごいクリエイターに対してきちんと審査員長が務まるのか、という複雑な気持ちもあったんですね。ところが、そのクリエイターはクリエイターで「ヤギ(八木)はPockyやPanasonic、JRのクリエイターだよね?緊張するなあ」と周囲に話していたらしくて(笑)。僕らが世界のクリエイターを尊敬するように、世界の同業者たちも僕たちのことは意識しているんだな、と感じました。
日本の課題は、世界の課題でもあると捉えて、尊敬ばかりするのではなく、世界の一員として堂々と目の前の課題に向き合い、オリジナルなアプローチを続けていきたいと思います。

──昨今、ますます多くなってきたテクノロジーとクリエイティブの融合について、今年のカンヌを通して何か感じるものはありましたか?
八木:今年は審査が始まる前からAIが議論の主題に来ることは予想していました。確かにAIによって知的生産の効率は良くなったと感じることができますし、ChatGPTによって言葉を無限に生成することができます。でも、誰でも言語化ができるということだから、逆に「言葉にならないこと」の価値が上がるとも考えられる。新しいテクノロジーが台頭してくるということは、どこかではその反作用が起きると思うので、クリエイティブの性質上、それが次のヒントにもなり得ると思います。
そして人間は時々、論理から逸脱して感情から衝動的に行動してしまうものであり、時にそのような感情に人は心を打たれます。AIのそつないアウトプットは活用次第で人間を解放してくれそうな気がしますが、やはり人間を相手にする以上、人間の心をつかむ行為というのは論理では足りないと思います。クリエイティブというのは、過去のデータの分析から導かれるものではなく、未来にブランドがどうあるべきかを考えることで見えてくる、ブランドにまつわる感情のようなものから生まれるものでありたいと思っています。
なんとかしたい、その衝動がクリエイティビティの源泉
──これからの時代にクリエイティビティが果たす役割について、どう思われますか?若いクリエイターや広告関係者にメッセージをお願いします。
八木:「面白いことをやりたい」「イノベーションを起こしたい」「賞を狙いたい」とかではなく、「目の前の問題をなんとかしたい」「これが実現できたらすごい」というように、頭で考える前に手が動いてしまうような、何か人間的な衝動が起こることを大事にしたいと思っています。そもそも企業やブランドは人々のどうしても見過ごせない問題をなんとかしたいという衝動に駆られて生まれてきたはずです。
今まで関わってきたクライアントを見ていても、例えば、Panasonicの創業者は街を走る電車を見て、「エレキの力を全ての家庭に届けたい」という思いを持っていましたし、HONDAでは、創業者の奥さんが買い物に行くのに「自転車にエンジンがついていたら楽なのではないか?」というひらめきから二輪事業が始まったそうです。それはアーティストが自己満足で絵を描いているのではなく、その人なりのやり方で世の中に問題を提起しようとしていることと同じだと思うんですね。
今、社会における問題の発見と解決がビジネスであるなら、それは同時にアートのようなものだと考えることもできる。だから僕たちの仕事においては、すごく楽しくて美しいものを作っていくことを今まで以上に求められると思います。
報道の真実でさえ揺らいでいるような時代ですが、広告はブランドの真実を伝える手段にもなり得るかもしれない。優れたクリエイティビティは広告業界を誠実なものにし、ビジネスとアートが出会う最も刺激的な場所にしていけるのではないでしょうか。
この記事は参考になりましたか?
バックナンバー
著者

八木 義博
株式会社電通
CDC
クリエーティブディレクター/アートディレクター
1977年京都生まれ。ノンバーバルなビジュアルコミュニケーションで、企業・商品ブランディングや広告キャンペーンなど、幅広いクリエイティブを展開。 主な仕事に、JR 東日本「行くぜ、東北。」、HONDA「Human! FIT」、江崎グリコ「Pocky THE GIFT」、メニコン「Magic-1 day Menicon Flat Pack」など。 受賞に、Cannes Design Lionsグランプリ、One Show Best in Design、D&AD Yellow Pencil×6、東京ADC賞、JAGDA新人賞、ACCグランプリ、佐治敬三賞など受賞多数。東京アートディレクターズクラブ会員 京都芸術大学 客員教授



