2023年クリエイター・オブ・ザ・イヤー(※)に高崎卓馬氏(dentsu Japan/電通コーポレートワン)が選出され、5月31日、都内で贈賞・表彰式が行われました。広告の領域を超え、映画という形でクリエイティブの力を世界に示し、広告業界のすべての人、とりわけ若手に勇気を与えたことが高く評価されました。今回が3度目のクリエイター・オブ・ザ・イヤー受賞となる高崎氏に、映画「PERFECT DAYS」における製作アプローチや製作現場での貴重な体験、さらには広告クリエイティブの現在地について聞きました。
※日本広告業協会(JAAA)主催の賞で、JAAA会員社の中で2023年に最も優れたクリエイティブワークを行ったクリエイター個人を表彰するもの。1989年の創設以来、当該年で35回目を迎える。

「スーパーマリオ化する365日」
──3度目のクリエイター・オブ・ザ・イヤー受賞、おめでとうございます。今回の受賞をどのように受け止めていますか?
高崎:ここ数年の受賞を見ていると、どこか「広告が可能性を求めている」という印象があります。まだまだ何かできるはずだと思っている熱を感じつつ、混乱と模索の状態がまだ終わっていないのかもしれない。正解がないのが広告のすてきなところですから、ある意味正しい状態でもあると思います。僕個人で言うと、年齢と経験を重ねてようやく見えてきている風景もあります。その中をこれから自分の足でどう歩くか、そのことをよく考えます。とにかく丁寧に信念をもって生きていこうと思っています。10年ぶりに選んでいただきましたが、この賞は「スーパーマリオ化する365日」をもらえるものだと思っています。あるいは、「さらにいい仕事をする」責任が生まれただけとも言える。これからの1年で何をやるかが問われているので、とにかく頑張ります。おじさんがしゃしゃりでてすいません、という感じですが。
清掃員の方々への感謝と尊敬の念から出てきたアイデア
──共同脚本・プロデュースを手がけた映画「PERFECT DAYS」は国内外で高く評価されています。映画化の経緯や製作アプローチについて伺えますか?
高崎:映画「PERFECT DAYS」は、柳井康治さん(ファーストリテイリング取締役)が個人で始めた「THE TOKYO TOILET」から生まれました。誰もが快適に使用できる公共トイレをつくるという柳井さんのこのプロジェクトの思いに強く共感して、それから二人で公共意識の問題や、アートとデザインの違い、広告の限界など、本当にいろんな話をしました。何か具体的な課題があって、それをどう解消するか、いつまでにどのくらいの予算で何をするか、というような広告的なスタートは何もなくて。二人の思いを重ねていくうちに、「清掃員を主人公にした映像をつくろう」となったんです。それは清掃員の方々への感謝と尊敬の念から出てきたアイデアでした。その時点でPR的な意識や、広告的な意識とは決別しました。むしろ、そうであってはいけない。僕たちはその頃から頻繁に「利他」という言葉を会話の中で使うようになりました。誰かのために生きている人にどうしてこんなに引かれるのだろう、と。映画の中で主人公の平山は、誰かのために毎日トイレを清掃します。現実の世界でも、誰かのために生きている人たちがたくさんいます。
それから、海外のチームと組んで、できるだけ大きく、みんながおおっと期待したくなる座組みにしたいというのが柳井さんの強い希望でした。僕の頭には経験的にうまく着地できるチームがすぐ浮かんだのですが、それではダメだと言われて。半強制的に新しい原っぱに立たされてしまったんです。節目節目で、柳井さんは僕を想像もしていない新しい場所に立たせるんです。これは猛烈に勉強になる。この数年一緒にいさせてもらって劇的に意識が変わりました。いやが応でもテンションの上がる場所の見つけ方を教えてもらった感じです。

THE TOKYO TOILET ART PROJECT/映画「PERFECT DAYS」
ずっと穴蔵の中にいる気分……でも、それは必要なプロセス
──クリエイティブの観点から、映画製作ではCM制作とどのようにアプローチを変えているのでしょう?
高崎:映画とCMはまったく別のものです。CMでは許される方法も、映画では許されないということはたくさんある。その違いについて徹底的に考えました。それは「頭のOSを切り替える作業」という感じのもので。それから、自分が理想とする映画について考えました。自分は伏線の回収みたいなテクニックには全く心が動かない。では、テクニックじゃない部分をどうやって見つけるのか。当然オリエンもない。自分の中にあるものを手探りでたぐり寄せていくしかない。作っている間はずっと穴蔵の中にいる気分でした。でも、それは必要なプロセスです。その時間と思いが映画の種になるのですから。
──高崎さんは、これまで山田洋次監督やヴィム・ヴェンダース監督といった巨匠たちと仕事をされてきました。彼らからどのようなことを学びましたか?
高崎:本当にすごい人たちは、みんなとてもユーモアがあります。超越しちゃってるんでしょうか。譲らない部分はガンとあるんですが、普段はとても知的でとにかく楽しい。あのレベルの人たちにはそういう人が本当に多い気がします。自分は到底そうはなれないから、憧れます。そして、みんな、延々と考えている。考えることがもう習慣になっている。だから息をするみたいにアイデアが出てくる。ついていくだけで精いっぱいですね。
ヴィム・ヴェンダースという人には、映画とは何かをこの2年の間、徹底的にたたき込まれました。彼の方法論はとてもオリジナルなもので、他に類があまりない気がします。そのうえ、毎回「作り方からつくる」と言っていました。これがとても刺激的で。そうすれば、自然とつくるものはオリジナルになる。人物の見つめ方、ロケ地の探し方、キャストとの会話の仕方、スケジュールの立て方、シナリオの書き方、撮影体制のつくり方、編集の仕方、映画祭との向き合い方、取材の受け方。本当にすべてのプロセスでたくさん学ばせてもらいました。感謝しかありません。

映像は言語でもあると思います。そのことをCMをつくりながら30年、かなり意識して生きてきました。昔の映画に今でも感動できるし、知らない国の物語に心を震わせることもできる。映像を通じて理解しあえるものはとてつもなく大きい。時間も場所も超えることができる。その豊かさに見合う真剣さで向き合うべきだなと思います。
話がそれちゃうんですが、これからもっと分断は進むと思います。そして世代や価値観だけでなく、物理的な関係もきっと今よりも曖昧になるでしょう。そのとき、連帯の大きな要の一つになるのが文化ではないでしょうか。映画、音楽、本、アートにはその力があると思います。同じもので感動した人たちは、新しい連帯の礎になる。そんな気がします。共通の体験は宝物です。
この映画のおかげでたくさんの海外の映画人たちと出会いました。心から愛せる人も、価値観があまり合わない人もいましたが、それでも映画による連帯、その底力は圧倒的なまでに感じます。海外でその連帯に触れると、日本はそこから外れそうになっているように見えました。そうなると、将来的にとても大きな損失になってしまうのではないでしょうか。
余計なことを常に考える。だから奇跡は起きる
──広告クリエイティブが現在置かれている状況をどのように見ていますか?
高崎:僕が広告の世界に入ったとき、テレビという「みんなが見ている土俵」がありました。みんなでCMという文化をつくっているという意識が自然とあったと思います。そこから生まれる流行もたくさんありました。そして先輩の圧倒的な仕事のおかげで、そのカウンターがつくれたりもしました。でも、今は土俵そのものを作るところからやらなくてはいけない。そもそものアイデアを発明し、みてもらうための仕掛けを発明する必要がある。2回企画をしないといけない感覚があります。そのどちらかでカロリーを使い切ってしまったら届かない。今はみんな大変です。
──昨今、「クリエイティブの力を広告以外に拡張していこう」という動きがあります。高崎さんは、そのことを強く意識されていますか?
高崎:拡張を目的にして何かを作ったことはありません。ただ結果を出したくて、そのために何ができるか。できること、思いつくことは全部やりたい、という思いだけでやってきました。オリエンにただ応えるだけではなく、余計なことを常に考えるようにしています。過去の範例に基づいてアウトプットをつくるのは了解をとりやすいのでそうしがちですが、それだと奇跡は起きないと思います。人と企業の接点がどこにあるのか、そのとき、人はどういう動きをするのか。何に関心があって何を欲しいと思っているのか。そういう想像をすることはとても楽しいものです。そこに新しいアイデアがある。やるべきことを思いついてしまったら、もうなんとしてでも実現するしかないんですよね。
【高崎氏の主なクリエイティブワーク】


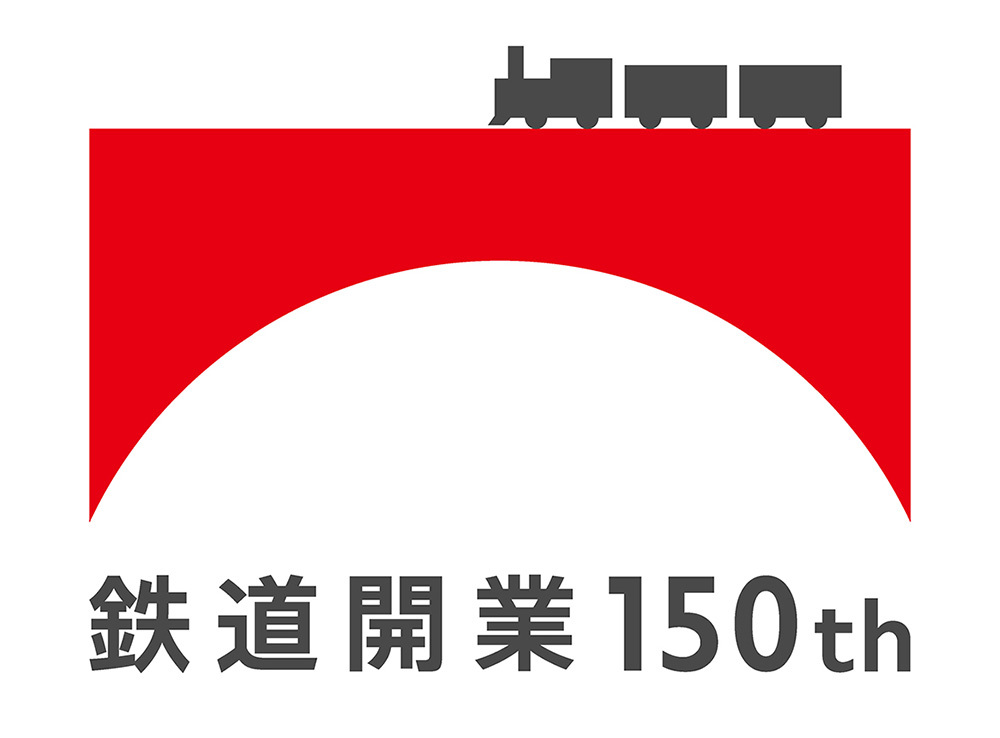
──高崎さんのこれまでの経験から、若手のクリエイターやクリエイターを目指す人たちに今伝えたいことは何ですか?
高崎:自分のキャリアアップだけを目的にこの仕事をすると、その品のなさは伝わってしまう。そして、表現からチャーミングさが消えてしまう。セルフプロデュースに夢中になると暗黒面に落ちてしまいます。賞や評価はもらうとうれしいものだし、安心もするものですが、それは次にいい仕事をするチャンスをくれるものです。ってなんか自分に言ってるような気持ちになりました。とにかく、他人のために生きると気持ちいいものですから、その気持ちを忘れずにいたいですね。
──最後に、高崎さんにとって「クリエイター」とは?
高崎:企画で誰かのテンションをあげられる人、だと思います。仲間がこの仕事をしていて良かったと思うアイデア。クライアントがこの仕事をしていて良かったと思えるアイデア。世の中がその広告があって良かったと思ってくれるアイデア。そういうものを見つけられる人のことだと思います。
何かをつくるのはとても大変なので、どうせ大変ならそういうものをつくるほうがいい。その広告がそこまでいけるかどうかは、「企画」にかかっている。だから、クリエイターにはその責任があると思います。できるかどうかは別です。やる意識があるかどうかです。その意識があれば、たとえできなくても、そこから学んで次なんとかしようと思うはずですし。自分はそうありたいと思います。
この記事は参考になりましたか?
著者

高崎 卓馬
1993年電通に入社。2010、13年に続く3度目のクリエイター・オブ・ザ・イヤー受賞をはじめ、国内外での受賞多数。著書に「表現の技術」(中央公文庫)、小説「オートリバース」(中央公論新社)、絵本「まっくろ」(講談社)など。J-WAVE「BITS&BOBS TOKYO」でMCを担当。共同脚本・プロデュースで参加した映画「PERFECT DAYS」は、2023年のカンヌ国際映画祭で、役所広司さんが最優秀男優賞を受賞。2025年3月、電通を退社。
