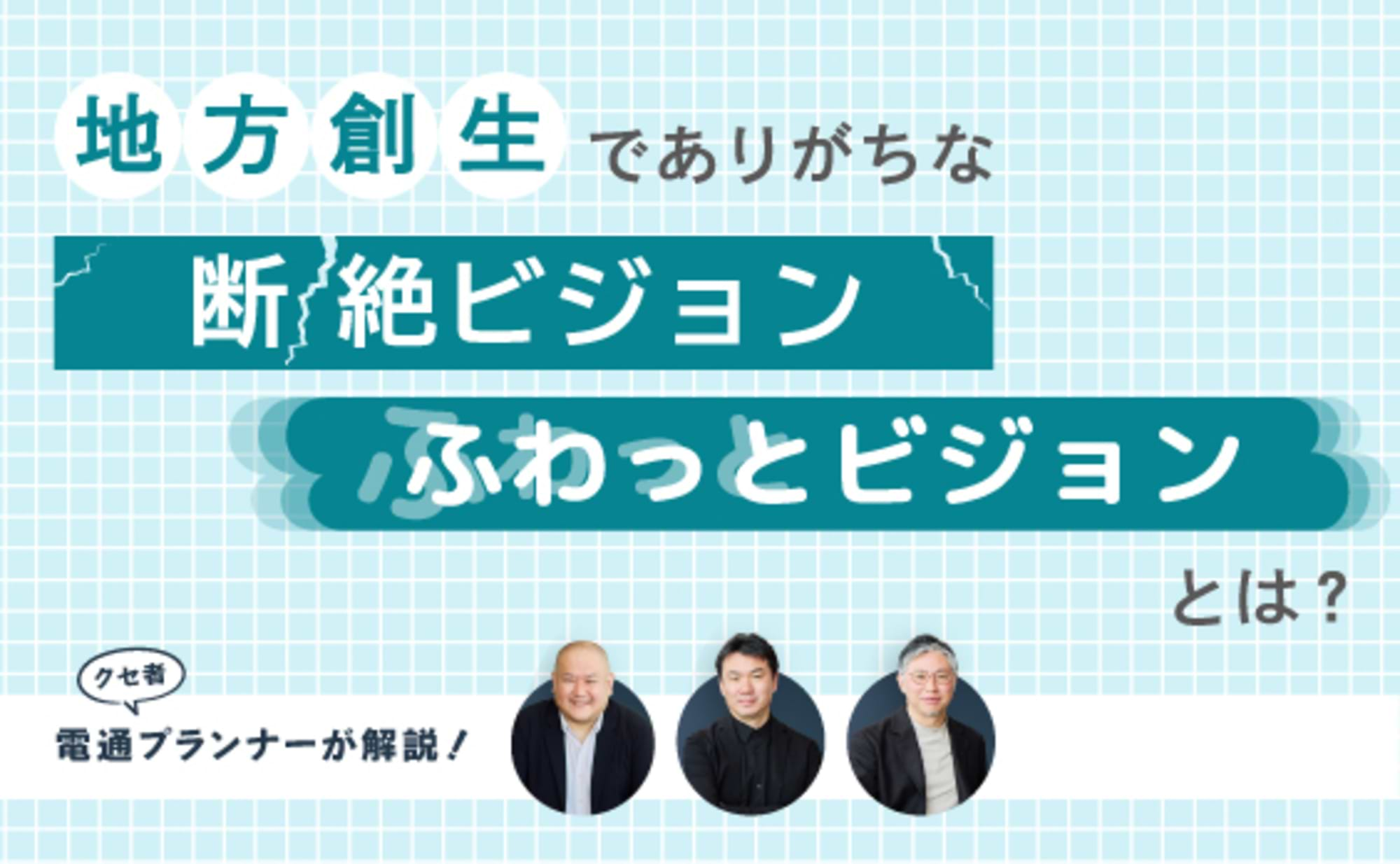創業67年の茶商が巻き起こす、日本茶業界のゲームチェンジ
「オリジナリティ」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく本連載。第37回は、“ボトリングティー”を手に、世代を超えた、国境を越えた挑戦をつづけるカネス製茶を紹介します。
カネス製茶が拠点とするのは、言わずと知れた茶所・静岡県島田(しまだ)市。“ボトリングティーとは、その名のとおりワインボトルのような瓶に、ワインさながら日本茶を詰めたもので、1本2万3000円ほどする商品もある。「そんなに高価な日本茶?」と思われる方も多いかもしれない。でも、次期社長 小松元気氏のお茶への数々の思いに触れ、なによりホンモノを味わってみれば、その考えは一新されるにちがいない。
文責:宮崎暢(電通BXCC)

茶葉のポテンシャルのわずか3割しか味わえていない?
創業1957年。カネス製茶はどんな会社なのか?と、小松幸哉現社長(三代目)の後を継ぎ、いずれは四代目社長に就任予定の元気氏に尋ねると、原料となるお茶の葉を生産者から買い付けて二次加工し、出来上がった茶葉商品を国内海外へ卸す卸業と、自社で直接の小売販売も手掛けている会社だという。茶葉の卸が売り上げの中心だが、小売り販売で2022年に「ボトリングティー」をブランド化して発売したのが「IBUKI Bottled tea」だ。
「ボトリングティー」とは何なのか?「一般的な定義はまだありませんが、ボトリングティーとは、茶葉が持っているポテンシャルを最大に引き出したリキッド状態の日本茶をボトルに入れたものだと僕らは定義しています」。茶葉のポテンシャルとは、どういうことなのか。「お茶とはとても繊細な飲み物で、水質、温度、抽出時間、茶器、原料の茶葉の5つの要素が絡み合います。つまりこの5つを、しかも茶葉の特徴に合わせて設定しないとおいしさの最大化はできないんですよ」
それぞれの要素を特に意識せずに、急須にただ茶葉とお湯を入れるだけのごく日常的な飲み方では、茶葉のポテンシャルはどれくらい味わえるのですか?と尋ねると「そうですね、感覚的には3~4割程度しか味わえていないのではないでしょうか?」。お茶の生産地にあって長らく茶商として目利きをしてきたからこそ、お茶それぞれのポテンシャルがわかる。逆に日々何気なく飲んでいるお茶では、そのポテンシャルに気づかずにいる人が多いということだろう。

「IBUKI」は日本茶を取り巻く現状へのアンチテーゼ
ボトリングティーブランドである「IBUKI」について教えてほしい、とお願いした。「元々は『息吹』といううちの主力のお茶の品名だったんです。それと『生命の息吹』から取っています。生命に息吹がみなぎっている状態、つまり生まれ出た葉っぱ、新茶のことです。これはアンチテーゼなんですよ」
新茶がアンチテーゼとは、一体どういうことなのだろう?「お茶の木が冬を越すために蓄えた栄養分を、春先に一気に開化させるのが最初の葉っぱです。新茶には生命の息吹がこもっているんです」。お茶でいう一番茶、二番茶……というのは取れるタイミングのことで、一般的には一番が春、二番が夏の前、三番が秋となっているという。「同時に、クオリティの高さも順番の通りになることが多いです。お茶といわれてイメージするペットボトルのお茶のほとんどは、二番茶、三番茶が使われています。二番以降がダメということは決してありません。爽やかにノドを潤すには十分です。でも、ボトリングティーはお茶のポテンシャルを最大化することを目指していますから、一番茶にこだわっています」
手に取りやすいペットボトルのお茶が普及するにつれ、二番茶、三番茶が取引の主流となり、最も栄養価がありクオリティも高いはずの一番茶の取引が減少してしまった。加えて本来100種以上あった日本茶の品種も、取引の多い特定品種に偏ってしまったという。そうした日本のお茶業界を取り巻く現状へのアンチテーゼなのだ。

「周りでも茶生産者の方が廃業をしたり、茶畑が荒れていく様子を日々目の当たりにしています。日本茶の低迷を肌で感じている僕たちが、いまの日本におけるお茶の常識を変える『ゲームチェンジャー』が一番茶を使ったボトリングティーなんです」
ボトリングティーをブランド化する
ゲームチェンジを起こすべく、静岡からお茶の価値を広めたい、生産者や地元の人たちに還元したいと、カネス製茶が社の決定事項としてボトリングティーのブランド化へ舵(かじ)を切ったのは、2020年。翌2021年、島田市内に自社のボトリングティー工場を設立する。抽出方法から自社で研究開発し、お茶のポテンシャルを引き出す独自の工程をつくり上げた。
製品づくりとともに、元気さんが大きく変えたいと意識したのが日本茶を飲む体験だという。「鎌倉時代からお茶は嗜好(しこう)品や薬として飲まれていました。大衆に広まったのは江戸時代からで、今ほど広く飲まれるようになったのはごく最近の話です。ただ、手軽に飲めるようになったいまでは、お茶はタダで飲めるくらいに思われているところもある。となると、飲む人の意識から変えていくには飲む体験そのものをデザインしていかないといけないと考えたんです」。嗜好品として、価値ある飲み物として日本茶を飲み手に届けたい。そうすることで日本茶が置かれた状況を、地元を変えていきたい。その思いで生まれたのが「IBUKI bottled tea」ブランドだ。


昨今、海外での人気も出始めたカネス製茶のボトリングティーだが、海外と国内との温度差が顕著だと元気さんはいう。「海外では注目が高まっても、国内ではまだまだ軽んじられている向きがある。そこがとてももどかしいんです」。少しずつ国内でも日本茶の新しい楽しみ方を伝えるプレーヤーが増え日本茶ブームといわれることもあるが、生産者の状況に目を向けるとギャップがある。消費者の反応や反響を、生産者に伝えていくコミュニケーションも、大事な仕事だという。

嗜好品・高級品としてのデザイン
ブランディングについて、元気さんはさらに続ける。「IBUKIのボトル写真をご覧ください。僕が考えるプロダクトデザインのポイントは、①インパクトがあること➁高級感があること③シンプルであること、です。開発時に設定したIBUKIのターゲットは30代後半から40代後半の企業でいえば事業責任者で、仕事やプライベートで贈り物をしたり誰かと飲食をともにする機会の多い人。飲用機会を描きながらとデザインしていきました」
飲料品や食料品にかぎらず、あらゆる製品という製品の「黒色」に元気さんはシンプルさと高級さを感じるという。黒色の瓶に「お茶の葉っぱ一枚」をデザインした。確かに高級ワインや日本酒の瓶が並ぶ中に「お茶の葉っぱ一枚」のラベルが並んだら、インパクトがある。「そこに、ポイントを置きました。手に取るところから、これまでにない日本茶との出会いをつくりたかったんです」。ターゲットの明確さから購入体験の設計まで、製品開発にとどまらない工夫が凝らされている。だからこその冒頭で紹介した価格設定なのだ。

茶産業と地域を元気にするのがミッション
「家業に入る前、プロダクトはもちろんのこと、レストランなどの新規事業、禅や他ジャンルとのコラボレーションなど、さまざまな職で経験したことが生きていると思っています」。自身が身につけてきたブランディング、マーケティングの知見をもとに、家業、地元の産業を再びデザインするプロジェクトが「IBUKI bottled tea」なのだ。
現在、国内外でマーケットが着実に拡大しているという。今後の展開について尋ねると、「海外で買っていただけるお客さまを、生産地に連れてくるツーリズムにも挑戦しています。お茶の産地や品種の多様性は、ワインや日本酒の地域性にも似ています。IBUKIが生まれた場所を訪れて、地元の食と風土を一緒に体験する機会をつくりたい。特に、お茶のもつ“うまみ成分”への感度の高い東南アジアの人たちに提供したいと思って、地域の他のプレーヤーと実践を始めています」
こうした活動をとってみても、低迷する地元の茶産業において、元気さんは頼もしい存在なのではないだろうか。どうしたら元気さんのような発想や行動につながるのかを最後に尋ねた。「あくまで自分のこととしてお話しすると、外の人と話すこと。地域の外の人や業界外の人、海外の人と密に話すことだと思います。自分たちにとっては当たり前でも、外の人からみたら普通じゃなかった、ということに気づけます。お茶をおいしい状態で飲むことは静岡の人には当たり前でも、外の人からはそのおいしさに驚かれる。日本茶の可能性がたくさんあることに気づいた、それが自分にとってとても良かった」
外の人の目を通じて客観視することで強みに気づき、新しい意味合いをつくっていくことが可能になる、ということだろう。国内各地で後継ぎ問題などにより先行きが見通しづらくなっている地域産業が増える中、新しい意味づけをもとに産業や地域が息を吹き返す、そんな未来につながっていく予感がした。

カネス製茶のHPは、こちら。
ボトリングティーブランド「IBUKI bottled tea」については、こちら。
日本茶の知識とビジネスについて発信中のSNSは、こちら。

「オリジナリティ」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく本連載。第37回は、“ボトリングティー”を手に、世代を超えた、国境を越えた挑戦をつづけるカネス製茶という会社を紹介しました。
season1の連載は、こちら。
「カンパニーデザイン」プロジェクトサイトは、こちら。
【編集後記】
小松氏は、農家の視点、経営者の視点、経済学者の視点……あらゆる視座から、こちらが用意した質問に答えてくださった。「最後の最後に、編集者である私からどうしてもお聞きしたいことが、一つだけあるんです。よろしいでしょうか?」とお願いしたところ、「もちろん、構いませんよ。一体どんな、ご質問でしょう?」と小松氏。
というわけで、オホン、と咳払いをした後、幼稚園児の頃から不思議に思っていたことを小松氏に投げかけてみた。「オレンジ色、レモン色、藍(あい)色、藤色、灰色、水色、空色……どの色もその出典が、名前となっていますよね?ところが茶色だけです、イメージに合わないのは。どうしてですか?」。くだらないことを聞くな!あと一つ、すてきな発見で終わりたかったのに!と、おかんむりの読者もおられるだろう。でも、これだけは、いつの日かお茶のプロの方に聞いてみたかったのだ。
以下が、元気氏の答えだ。「それには諸説ありまして、そもそもお茶の液体色は緑色ではなく濁った色をしていたという説もありますし、その昔、お茶の葉っぱというものは、ぐつぐつぶくぶくと荒っぽく煮込まれていたという説もあります。冒頭お話ししたように、繊細なプロセスがあって初めて、お茶はエメラルドのような輝きを放つ液体になります。あくまで私の想像なのですが、繊細とはほど遠い作業の結果として生まれる色になぞらえて、茶色と呼び名が生まれたのではないでしょうか?」
長年の疑問が解決された。色、味、香り……なにからなにまで一切の妥協を許さない。そんな小松氏のような人が育て、つくり、届けてくれるお茶の存在を知らなかったなんて……もったいないことをしてきたものだ、と心から思った。
この記事は参考になりましたか?
著者
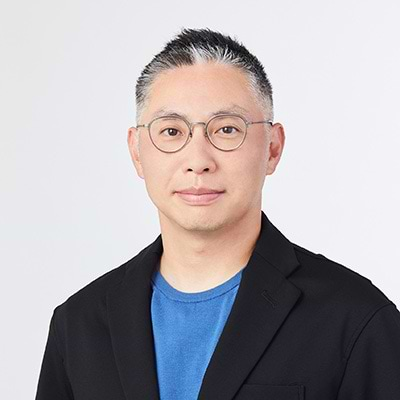
宮崎 暢
株式会社 電通
ビジネストランスフォーメーション・クリエ―ティブ・センター
クリエーティブプランナー
電通入社後、雑誌担当の経験を生かし、編集者との協業により多様な業種のクライアントのコンテンツ開発、キャンペーンプランニングを実施。2018年より地域のブランディングを支援する産学協働プロジェクト「電通abic project」に参加、2022年より代表。北海道から九州まで国内各地の地域資産を再編集し、地域のプレーヤーとの協業・共創によりブランディングするプロジェクトのプランニング・推進を手掛ける。