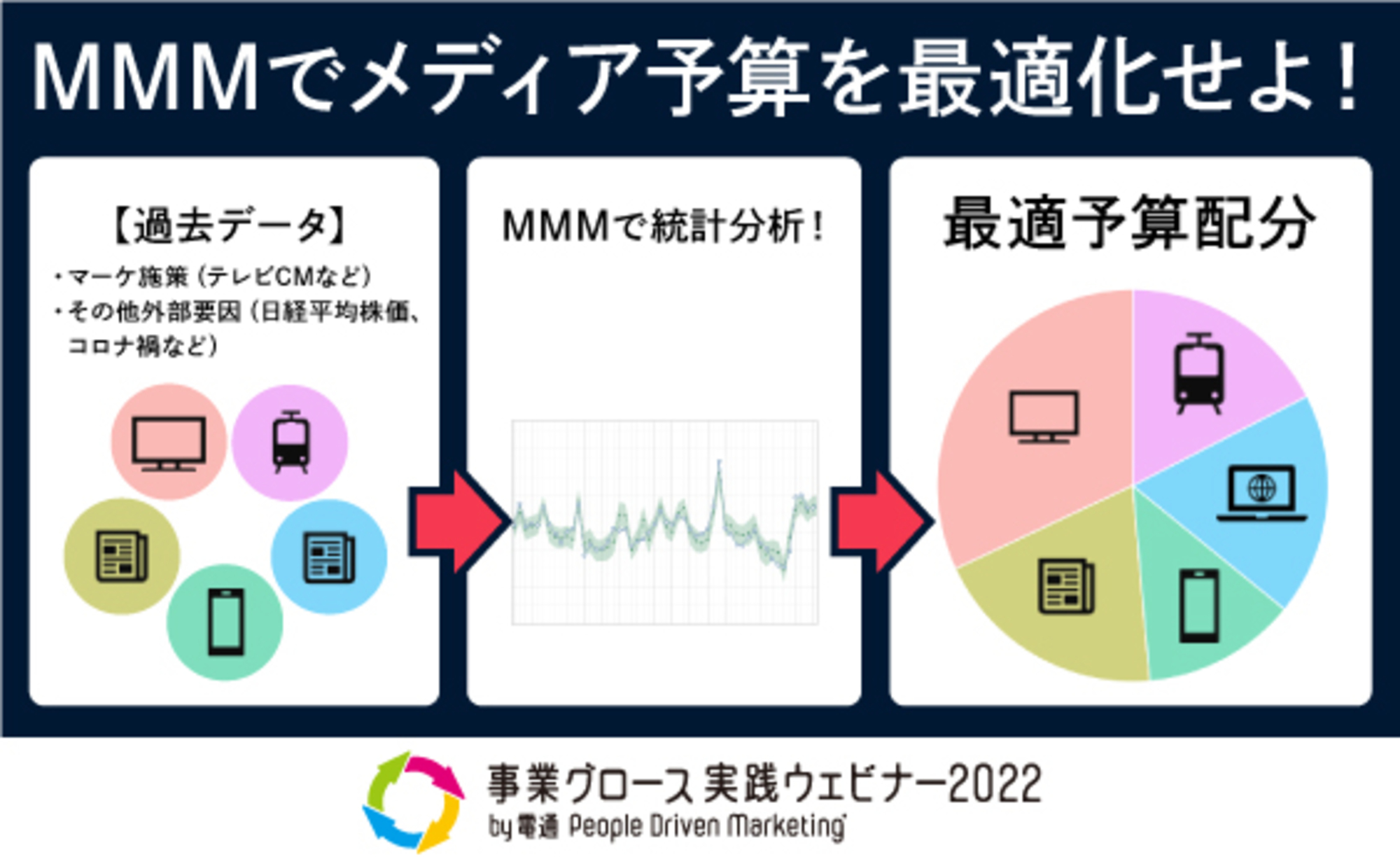授業の企画、実施を行っているプロジェクトメンバー。左から福田博史氏、高山裕基氏、降旗俊介氏、近藤俊平氏。
広告の企画制作で培った「伝える力」を大学生へ──。2024年春から、横浜国立大学では電通が参画し、新たな産学連携の授業がスタートしました。同大学の経済学部の1年生を対象に少人数体制で、課題解決力やコミュニケーション能力の向上にフォーカスした授業が行われています。本記事では、授業を企画・実施した、電通の福田博史氏、降旗俊介氏、高山裕基氏にインタビュー。実施に至った背景や目的、授業内容、学生の反応などについて伺いました。(2024年6月21日取材)
「私たちが学生だったら受けたい授業」をカタチにしてみたい
──電通はこれまでもインターンシップやワークショップの他、社員が講師として授業を実施するなど学生にクリエイティブについての考え方や技術を教えてきました。今回「課題解決力」や「伝える力」をテーマにした授業プログラムを企画したきっかけや背景を教えてください。
福田:電通は「伝える技術」のプロとして、企業の広告活動を長年サポートしてきました。現在は広告領域から発展して、企業や自治体などに伴走しながら、顧客起点の新しいビジネスを開発したり、街づくりにも携わったりするなど、コミュニケーションを軸に「広告以外」の領域でも課題解決をしていこうと変革の最中です。
ただ、簡単に答えが出せる課題は今の社会に残されていません。答えのない課題に対してより良い解決方法を探るためには、さまざまな企業や組織が協働し、アイデアを出し合う必要がありますが、そこで重要となるのが、チーム内で自分の考えを「伝える力」だと思っています。
この「伝える力」は、社会人だけでなく学生にも求められるスキルだと思っています。過去に学生と会話する機会があった時に、彼らの「伝える力」不足を感じることがありました。雑談ではすごくすてきなのに、緊張すると途端にうまく話せなくなってしまう……。これは私自身も学生時代に経験があったので、何とかサポートできないものかと考えていました。
人生は伝えることの連続です。ですから、「伝える力」を学生のうちから身に付けることができれば、大学時代やその後の人生、さらには社会も良いものになるはず――。そんな思いから、教育や学生の育成などに興味のあるメンバーに声をかけてプロジェクトがスタートしました。
──降旗さん、高山さんもそういった思いに共感されて、メンバーにジョインされたのですか?
降旗:そうですね。コミュニケーション領域を得意とする電通では、世の中やターゲットに対して伝えたいことを構造化したり、ロジックを緻密に設計したりすることを社員一人一人が当たり前のようにやっています。実は僕自身、電通にいる時はこの価値に気づかなかったのですが、数年前に他の企業に出向して外から電通を見たときに、誰もがみんなできることではないのかもしれないと気づきました。能力がないということでは決してなく、ただ何かを伝えるためにはロジックの設計や構造化して伝える力、見せ方が重要だということを知らないだけなんです。そういった経緯もあり僕自身、この「伝える力」の価値に気づくまでに時間がかかってしまったので、学生のうちに伝えるスキルを学んで身に付けることができたら、社会を変えていける人材がより多く育つのではないかと感じて、すぐにプロジェクトへの参加を決めました。
高山:学生が「伝える力」を身に付けることに加えて、僕は、大学の授業で学生が社会人と接する機会を持つことにも意義があると思いました。企業で働く中で自分の力を発揮する醍醐味(だいごみ)を学生のみなさんにも、ワクワクしながら感じてほしい。授業を通して、「働く」ことを俯瞰(ふかん)的に見る視野を広げてほしい、そんな狙いも込めました。

──お三方とも「伝える」「働く」といったことにさまざまな思いがあったのですね。では、横浜国立大学で授業を行うことになった経緯を教えてください。
福田:横浜国立大学の関根豪政教授とは、大学時代に同じ法学部ゼミに所属していたので面識がありました。その関根教授から「LBEEP」という教育プログラムの存在を教えていただいたのが今回の出発点です。この「LBEEP」とは、現代社会の課題に対して、さまざまな視点を持って立ち向かえる人材を実践育成していく少数制の授業プログラムで、非常に面白いコンセプトの授業だと思いました。
このプログラムを「伝える力」の授業にできないかなと思いました。そこで私たちの思いを、「私たちが今大学生に戻ったとしたら、こんな授業を受けたい」というテーマで関根教授に相談したところ授業コンセプトに大いに興味を示してくださいました。
そこから、産学連携の一つの実験として経済学部の1年生の授業「導入演習Ⅰ」での実施が決定しました。単発のゲストとして登壇して終了ということではなく、継続的なプログラムとして実施し、学生としては単位も取得できる授業としてスタートすることになったため積極的に学生が参加してくれました。
高山:授業を企画するにあたり産学連携の輪を広げ、電通の他に、日本を代表するシンクタンクの野村総合研究所と、世界を代表するIT企業のGoogleも参画することになりました。より幅広い視点で、学生に対して多様なプロフェッショナルがアプローチするこの授業プログラムは、今までにない授業のカタチなのではないかと感じています。
「推し」をテーマに、伝える力を磨く
──実際に行っている「導入演習Ⅰ」の授業内容について教えてください。
降旗:授業は全8回のプログラムとなっており、できるだけ学生には実践形式で学んでもらうことを意識しています。
また課題解決を図るためには、伝えたいことを構造化して(Structuring)、視覚化して(Visualizing)、相手に伝える(Communicating)というこの3つのスキルを理解してもらうことを目指しています。その一環で、学生には「自分の推しを伝える」という課題に取り組んでもらっています。
──なぜ、「推し」をテーマに選んだのでしょうか。
高山:実はコロナがまん延した時期、電通社内でも同じ企画を行ったことがありました。リアルなコミュニケーションが取れず、社内にどんな人がいるのかよく分からない……。そこで、社員を知ることを目的に、オンラインとオフラインのハイブリッドで「推しの湯」という企画を行いました。これは、参加者それぞれが、自分の推しをプレゼンするというものです。推しというと、アーティストやアニメキャラクターのイメージが強いですが、参加者は、「民俗学」「窒素」「狂言」とか、推しているものはさまざまで非常に盛り上がりました。そこで、「伝える力」の授業の題材に「推し」は最適なんじゃないかとチームで考えたんです。
Day1の授業では、課題解決に必要な伝えたいことの構造化について解説した後に、「推しの湯」に参加した電通社員が登壇し、自身の推しである「民俗学」について学生たちに伝えてもらいました。自分にとって「推し」とはどういうものか、民俗学の何に魅力を感じているのかをプレゼンすると、学生のアンケート結果では「話に引き込まれた」「いままでの授業の中でいちばんおもしろかった」などの感想があり、大変好評でしたね。

コロナ禍に始まった電通社内のコミュニケーション活性化の取り組みの一つ。これまで知らなかった社員の「推し」をきっかけに他部署同士のネットワークが一気に広がるなど、非常に盛り上がりを見せた。
降旗:Day2の授業では、3つのグループに分かれて、実際に学生たちがそれぞれ自分の推しを伝える演習に挑んだ他、Day3の授業では、「Structuring(構造化する力)」の基礎固めをすることを目指し、伝わる文章を書く力を上げることにフォーカス。「聞いた人が会ってみたいと思うように、400文字で自分の友達を紹介してください」という課題を学生に出しました。
福田:400文字の原稿は、大体10個の文章で構成されます。要点を絞りストーリーを構成する構造力と、自分らしい言葉で伝える表現力が求められます。やはり書き方は千差万別。中には、399文字で原稿をまとめてきた人や、完全に400文字をオーバーしている人、読み手に「なぜだろう?」と締め方に考えさせる余韻をたくらむ生徒など、学生たちのさまざまな表現の仕方は、私としても勉強にもなりました。
私たちは「場数は進歩の母」だと伝えて授業をスタートしたのですが、こうした演習や課題などの実践を通して、“打席”に立つことの大切さを実感してもらえたらと思っています。「分からない」という言葉が言えるムードこそが、授業やチームにおいて一番大事だと思っているからです。

実際の授業の様子。グループワークでは、学生同士でとことん議論し合います。講師が声掛けをして対話をしながら授業を進めていきます。
オーディエンスドリブンな授業スタイルを実験
──授業のプログラムを組み立てるにあたって工夫されていることはありますか?
降旗:事前に8回の授業内容をガチガチに固めてしまうのではなく、大まかな方向性だけを決めて、学生の反応を見て改善をしながら授業や課題をつくるアジャイル的な形をとっています。
高山:一般的に大学の講義では、授業の最初に出席をとることが多いと思うのですが、このプログラムでは授業終了時に二次元バーコードを提示して、授業の感想や質問などのアンケートを回答してもらうことで出席確認をしています。このアンケートから、学生の反応や理解度、どこにつまずいているのかがリアルに分かるので、これをもとに改善しながら次回の授業の内容・方向性をチューニングしていくのが特徴です。
降旗:この授業プログラムでは、SVCや構造化などの慣れない言葉に、やる気を失ってしまう学生もいるのではないかという心配がありました。そのため難しい言葉をできるだけ使わない、途中で質問タイムを設けて確認し合う、授業の際は学生たちの発話のきっかけをつくったり、フォローする講師をつけたりする、授業の最後にはアンケート調査で反応を確認して次に生かすなど、学生の様子をつねに把握し、それを次の授業に生かすようにPDCAを回しています。
福田:降旗さんが提案してくれたより良い授業に進化させていくアプローチには大賛成でした。特にC(Check/評価)からA(Action/改善)を行う手段として、二次元バーコードからその場でアンケートに回答してもらう仕組みは簡単に取り入れられる上、DXアプローチとしてかなり機能したと思います。学生のリアルな反応とアンケート結果を合わせてチェックしながら次の授業を考えていくオーディエンスドリブン型の授業は面白かったです。全員スマホを持っているからこそ、授業を進化させていく仕組みはもっとつくっていけそうな手応えを感じましたよね。
しっかり伝わり合うところからイノベーションが生まれる
──ここまでの授業で、どのようなことを感じましたか?
高山:授業を行っての一番の発見は、私たち自身が教わることも多いということです。授業を行うたびに、学生とともに私たちも成長する「共成長」が起きている場だなと感じています。社会人が教育に関わることで自身を俯瞰して観察するいい機会にもなっていると思います。
降旗:学生たちの変化もとても感じますね。この授業に出ている学生たちは1年生でまだ大学に入ったばかりということもあり、授業がスタートした当初は、すぐに答えを求めがちなところがありました。例えば「このフレームを使えば、答えが出るんですか」という具合に。でも、授業の回数を重ねるごとに、確実に質問の内容のレベルが上がっているなと実感しています。
高山:アンケートの回答を見ても、授業に向かう姿勢がより前向きになっているのを感じます。
福田:よく「伝える力」って大事だといわれますが、私たちは身に付けるために大事なことが2つあると思っています。
1つ目は、何度も聞き直せるようなムード
2つ目は、ちょっと緊張する打席の数
この2つが「伝える力」を鍛えていくための成長のカギだと思っています。急成長していく人たちに電通で出会い、本当にそう感じたんです。
今回は、どちらも意識して授業を行いました。
この授業を通して、学生同士が実は面白い人だということが分かったり、相手への興味が出てきて話しかけて一緒に何かしてみようかという雑談になり、「あの時のアイデアなんだけど、実際にやってみない?」というムードに発展したりするわけです。
情報が伝わり合う状態があれば、きっとイノベーションも生まれやすくなります。これからも電通グループのさまざまな「推し」を持つ人たちの力を借りながら、「伝える」を武器にして、学生の未来のために役立つ授業を企画していきたいと思いますし、より良い社会のために貢献していきたいと考えています。
◎次回は、横浜国立大学側の視点からみた本プロジェクトの意義や学生のリアルな声などをご紹介します。