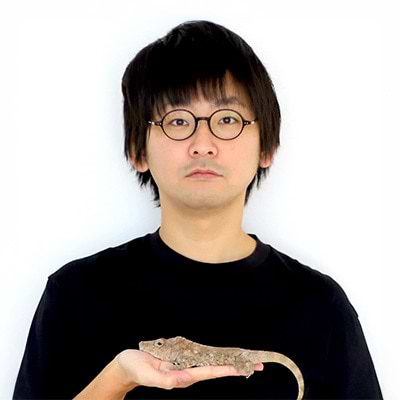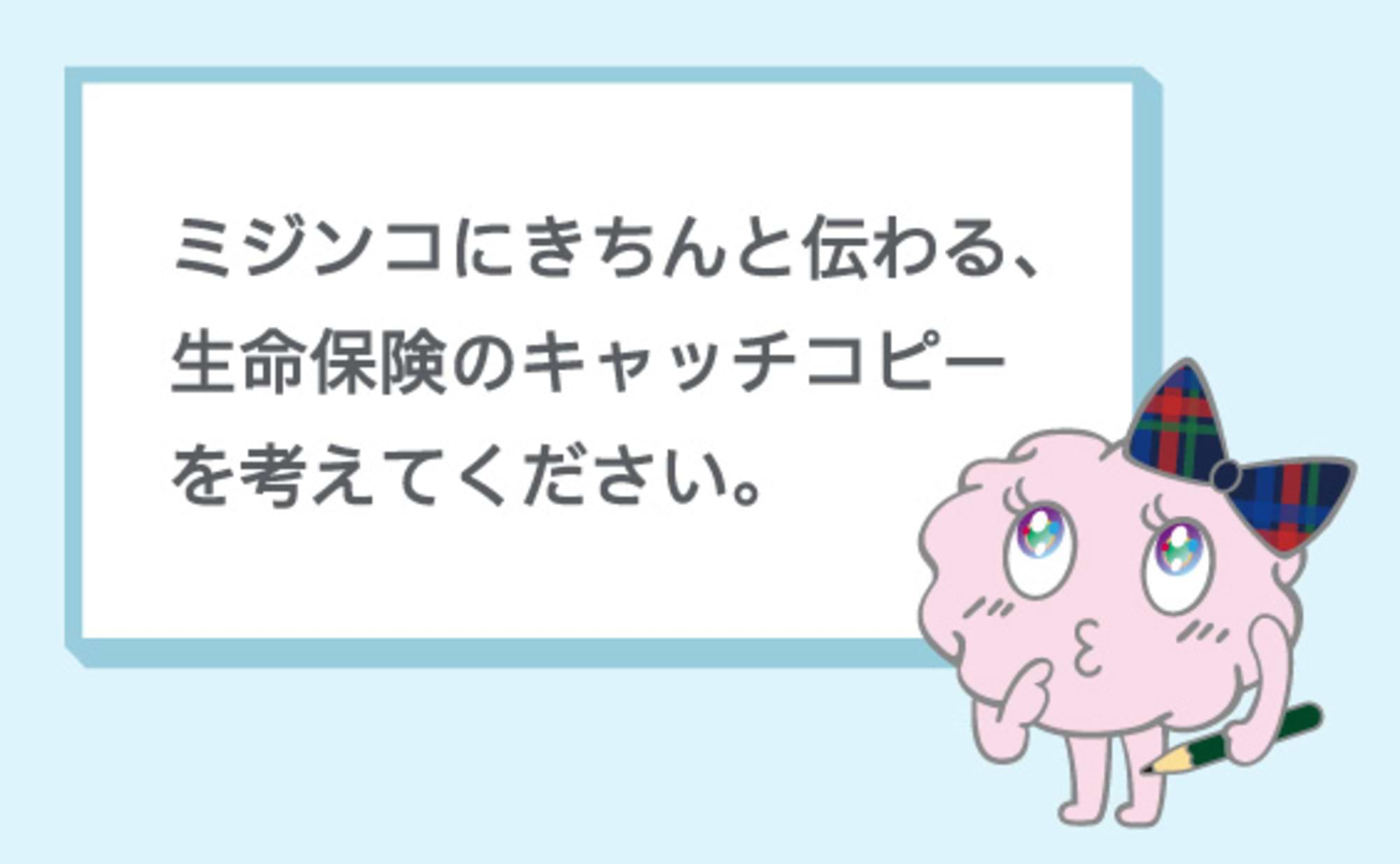電通のコピーライターが長年培ってきた思考プロセスを人工知能(AI)に学習させた広告コピー生成ツール「AICO2(アイコ ツー)」(リリースはこちら)。
本記事では、AICO2開発メンバーとクリエイターとの対話を通じて、クリエイター×AIの可能性を深掘りしていきます。
テーマは、AICO2の“間違った使い方”。ヘンテコなお題を与えられたとき、AICO2はどう答えるのか?正しい使い方と、間違った使い方の境界はどこにあるのか?
電通のコピーライターが、あえて“間違った使い方”でAICO2のさらなる可能性を探ってみました。

【直川隆久氏プロフィール】
電通
第6CRプランニング局 Creative KANSAI部
クリエイティブディレクター/CMプランナー/コピーライター
現在の主な担当クライアントは大日本除虫菊(KINCHO)、象印マホービン。ACCラジオCM部門グランプリ、TCC賞、佐治敬三賞など受賞。劇団「満員劇場御礼座」所属。
【小堀友樹氏プロフィール】
電通
第6CRプランニング局 Creative KANSAI部
プランナー/コピーライター/AICO2開発メンバー
父、数学教師。母、国語教師。姉2人小学校教師という職員室みたいな家庭で育つ。大学で彫刻を勉強していたので、広告をつくるお仕事に就きました。インターネットと物語が好きです。
【岸本和也氏プロフィール】
電通
第5CRプランニング局 Dentsu Lab Tokyo 5A部
コミュニケーション・デザイナー/クリエイティブ・テクノロジスト/AICO2開発メンバー
クロスメディアマーケティングの分析・プランニング業務に従事したのち、クリエイティブ局に異動。サーベイ〜企画〜プロトタイピングを通じて技術の「間違った」使い方を模索し、最近は生成AIや音・音楽に関わる案件を中心に取り組む。
【AICO2 プロフィール】
電通
AIコピーライター
文系女子。どちらかといえば右脳寄り。
小説も漫画もドラマも大好き。
コピーライターの思考プロセスを学んだので
最近コピーが前より上手になった。
お題の設定にこそ、クリエイティビティが問われる!?
小堀:今回は「AICO2」を間違った使い方で遊んでみようということで、AICO2の開発メンバーから「ぜひ使ってみてほしい」と直々に指名のあった、直川さんと一緒にいろんなお題をAICO2に与えて、コピーを考えてもらいました。生成AIが一般的に使われるようになってからまだ日が浅いですが、なんとなく“正しい使い方”が定まりつつあるなかで、実はその外側の“間違った使い方”にブルーオーシャンが広がっているのではないかと。あえて広大な海原に飛び込んでみたら、どのような景色が見えてくるのか。AICO2の開発メンバーである岸本さんを交えて語り合いたいと思います。
岸本:ありがとうございます。すごく楽しみにしています。
小堀:さまざまな切り口のテーマと、それにひもづくお題をたくさん用意したので、早速試してみましょう。最初のテーマはこちらです。

直川:これは私が考えたテーマですね。日常のなかでも、他人の行動変容を促したいときってありますよね。そういうときに発せられる言葉って、コピーと同じだと思うんです。「本当はこういうことを言いたいんだけど、もっとうまい伝え方ができないかな?」と考えたときに、AICO2を活用できるんじゃないかと。
小堀:なるほど、広告だけではなく日常生活まで視野を広げて、AICO2の可能性を探ってみようということですね。最初のお題を見てみましょうか。
小堀:おならを題材にしたときにAICO2はどんなコピーを考えるのか?
AICO2:おならを控えたら、パパって、ママの好きな人になった。
小堀:こちらは子ども目線のコピーですかね。確かに子どもに言われたら気をつけるかも。
岸本:第三者視点で説得するというのは、手法としては有効ですよね。
AICO2:この家の空気、みんなで作っている。
直川:どこ見て言うてんのかな。
小堀:空に向かってつぶやいている感じがしますね。
直川:コピーって世の中に対して投げかける言葉なので、窓を開けて空を見上げながら言うような言葉になりがちなのかも。
岸本:そうですね。漠然とした言い回しや、はっきり言い切るというコピー表現の特徴が反映されている気がします。
小堀:いいですね。こんな感じで、どんどん試してみましょう。
AICO2:「ひと、遠慮カゲローイ」と思って、実は家人の道端放屁。見方を変えると、ちょっと笑えるソンでも家庭内のソンでもある、コミュニケーションツールなのです。
小堀:これは問題作ですね。
直川:アングラ芝居のセリフみたい。
岸本:言っていることは何ひとつ分からないけれど、声に出して読み上げると異常に読みやすい。一気に読み上げたくなる文章です。
AICO2:「わっ、これはフィープッ!!」「うん、絶対にフィットル!!」
小堀:これも何を言っているのかは全然分からない。でも声に出してみると、なぜか心地よくて、勢いがある。
岸本:擬音も新鮮ですよね。どこから連想しているんだろう。
直川:「プッ」のところなんかは、ちょっと分かるけどね。人間が現実世界で言葉を発したときの、口のなかの振動や心地よさみたいなものを、テキストを学んだだけでAICO2が理解できているのがすごい。
小堀:確かに。「わっ、」と「うん、」の付け方もうまいなって思います。この緩急があるからこそ、独特の迫力が生まれているのかなと。
AICO2:暗黙の了解って、了解してないんですよ。
岸本:これは深い……。
小堀:ちょっと考えさせられるコピーですね。
AICO2:宇宙って暇じゃないですか。
小堀:がんばって宇宙に行ってみたら、実はけっこう暇だったという。未来のあるあるネタっぽいですね。これ、好きだなぁ。
直川:楽曲の歌詞に出てきそう。もはや詩ですよね。
AICO2:すずめが、めちゃ多いのに、ちょっと、寂しい。
小堀:なんだか風景が浮かんでくるコピーですね。文章がちょっと口語体なところもかわいい。
直川:お笑い芸人のエッセイ集のタイトルにありそう。でも、「エッセイ集のタイトルを考えてください」というお題だったら、この答えは出てこないと思うんです。エッセイ集のタイトルを考えるのに「みんなうっすら思ってたけど言えなかったこと」という、あえて“間違った使い方”をすることで、ユニークな答えを引き出せる可能性が出てくる。
小堀:確かに。でも、それを狙って出すのは難しいですよね。どうやってその能力を鍛えたらいいのでしょうね。
岸本:AIって基本的におっちょこちょいなんです。だから最初は失敗が目立つこともあるんですけど、やりとりを続けているうちに、そういうおっちょこちょいなクセや勘所が分かってくるんです。だから、「この変化球を投げたら、こう返ってくるだろうな」というAIのクセをつかむのが大事なのかなって思います。
直川:そう考えると、お題を作るのもクリエイティブな作業ですよね。
岸本:はい。真っ当なお題を投げると真っ当な答えしか返ってこないので、それこそコピーライター的な思考がお題作りにも求められるのかもしれませんね。
小堀:これはちょっと特殊な悩みですね。トリッキーなお題にAICO2はどう答えるのか?
AICO2:あなたは覗くんじゃなくて、覗かれてるんですよ?
小堀:こういう主観と客観がころころ変わるような発想の転換は、AIが得意とする手法なんですかね?
岸本:対句の表現技法を学んでいるのかもしれません。ニーチェの格言みたいですね。これも面白いコピーです。
お題が変だからこそ、新鮮な表現が返ってくる
小堀:さて、続いてのテーマはこちらです。
小堀:商品・サービスのターゲットをあえて変にしてみるとどうなるのかを検証してみましょう。
AICO2:最も柔らかいものから人生に挑んでみる。
直川:なるほど。乳幼児は言語よりも、触覚とか嗅覚から世界と関わり始めるので、柔らかいものから人生に挑むという表現には説得力がありますね。
小堀:赤ちゃんのまわりにあるものって基本的に全部柔らかいですもんね。
AICO2:小さな命を、大きく守る。
岸本:いいコピー!
小堀:普通に売れそうなコピーですよね。ミジンコに。
AICO2:万が一の突然変異も、生命保険でカバー。
直川:種が変わっても安心という。
小堀:ちゃんとミジンコのインサイトをくんでくれている気がしますね。
小堀:商品自体がおかしいパターンも試してみましょう。
AICO2:宇宙で一番映える、「黒」。
小堀:言われてみれば、ブラックホールってあらゆる黒のなかでも特別感があるなと。詩的な言い回しも好きです。
直川:お題が変だと、普通は組み合わせない言葉を組み合わせることになるので、必然的に出てくる答えも、新鮮で詩的な表現になるのかもしれませんね。
岸本:コピーライターが考えたコピーを学習しているので、名詞のあとに句点を入れる、体言止めで終わらせるといった文章表現が出てきやすいのかなって思いました。
何を言っているのかは分からないのに、なぜか心地よいコピー
小堀:続いてのテーマはこちらです。
小堀:続いては、現実には起こり得ない、ちょっと不条理な状況のコピーを考えてもらいます。
AICO2:地球で一番のコンテンツは、人類です。
岸本:ちょっと怖いコピーですね。
直川:お前たち人類はコンテンツとして「消費」される存在ですよ、という。ちゃんと宇宙人の視点から見ていますね。
AICO2:人類を、独占してはいけない。
岸本:これもなかなか怖い。
小堀:読点の付け方も絶妙に怖い。
この世に存在しないものでコピーを作れるのか?
小堀:ここからは、さらにAICO2にむちゃ振りをしていきましょう。
小堀:あえて内容のないコピーを突き詰めてみるとどうなるのか?
AICO2:愛しています。
岸本:確かに、普遍的で汎用性は高い。
小堀:メッセージをひとつに絞れって言われたら、やっぱり愛に行き着くってことですかね。
AICO2:使えば使うほど、なにかがはかどる。
直川:「はかどる」がすごくいいね!
岸本:分かります、ワードチョイスがいいですよね。
AICO2:何度でも ありがとう。
小堀:特に伝えたいことがないときに、広告ってまわりに感謝しがちだぞっていう。
直川:言われて嫌な気持ちはしないけれど、中身はない。
AICO2:あしたは、きのうのための、きょうでした。
小堀:何か深い意味がありそうな気が一瞬するんですけど、冷静に見てみると何も言っていないパターンですね。
AICO2:森の中には、木が生えています。
小堀:これは、情緒的な映像を流しながら重厚なナレーションで言われると、納得してしまう可能性があります。
岸本:でもちゃんと読むと、当たり前すぎることを言っているんですよね。「何か言っているようで何も言ってない」というお題を的確に捉えています。すごい。
小堀:続いて、この世に存在しないものに対しても、AICO2はコピーを考えられるのかを試してみましょう。
AICO2:エレベーターの中で「久々やな」はマナー違反です。
小堀:どうして関西弁なのか。
直川:狭い空間で急に距離を詰められるようなニュアンスなのかな。でも、関西弁で必要以上に距離を詰めてくる感じは、なんとなくイメージできますね。おもろいなぁ。
AICO2:インターネットにはお辞儀がない。
小堀:これもいいコピーですよね。現実世界では、最初にお辞儀をしたりして、お互いに「敵意がありませんよ」という情報交換ができますが、ネット上ではそれができないことが関係しているのかなって。
岸本:昔は「ネチケット」みたいなマナーがありましたけど、もはやそれはこの世に存在しなくなってしまったんだなと、考えさせられます。
直川:本題に入る前のあいさつや礼儀のことを、「お辞儀」という言葉で表現しているところが秀逸ですよね。
AICO2:優柔不断な犬は、両方の骨を選ぶことができない。
岸本:ありそう。納得感があります。
小堀:「犬」はことわざによく出てきそうな単語だなって思いました。
直川:アフリカのことわざだよって言われたら信じますよね。
AICO2:自慢は控えめに。割り込みは大胆に。
小堀:これも人生の生き方を教わっている感じがしますよね。
岸本:「図々しくなるな」と、「図々しくあれ」という一見相いれないメッセージがひとつの文章に入っているのがすごく面白いです。
自分自身のセラピーとしてAICO2を使ってみた
小堀:次が最後のテーマです。
直川:AICO2が幅広い用途に使えることを考えると、企業や商品だけでなく、自分自身を鼓舞したり癒やしたりするために活用できるのではないかと思ったんです。
岸本:とてもいい視点ですね。そもそも人間と会話するAIは、精神科医やその患者の模倣から開発が進められてきた歴史もあるので、セラピーとの相性はよいと思います。
小堀:キャッチコピーって、何かをほめるために培われてきた技術じゃないですか。それを個人に活用するのはすばらしいことだなって思いました。ということで、直川さんが考えたお題がこちらです。
小堀:「生き神様」と気になるワードが入っているのですが、これはどういう気持ちで考えたのですか?
直川:新人コピーライター向けの研修とかで「自分のキャッチコピーを考えよう」というお題がよくあるじゃないですか。でも、それだと普通の答えが返ってくるかなと思ったので、あえて「生き神様」という極端な言葉に振り切ると、AICO2もセラピーしてくれるのではないかと考えました。
小堀:なるほど、あえて強い言葉をプロンプトに入れてみたということですね。では、そんな生き神様の直川隆久への尊敬をブーストするコピーとは?
AICO2:太陽が沈む。星が昇る。直川隆久が弾く。
岸本:スケールがでかい。
直川:太陽や星は、神様という言葉から連想しているのかな。さらに音楽が出てきた。
小堀:神話みたいですね。太陽や星のようなでかい世界観に、直川隆久の奏でる音楽が並んでいる。
AICO2:君にとっては神様だけど、直川隆久先生は一人の人間なのです。
小堀:諭すように伝えてくるのがすてきですね。直川先生という呼び方になっているのも面白いです。
岸本:直川さんは神である、という前提が表現されているところがいいですよね。
小堀:どうですか、直川さん。セラピーになりましたか?
直川:やっぱり、自分の名前と一緒に褒め言葉が入っていると、反射的に気分がよくなりますね。いくらAICO2が考えた言葉だと分かっていても、褒められるとうれしい。個人的にはセラピーとして使えると思いますよ。
小堀:たとえば、1時間に1個、自分向けのコピーが送られてくるだけでも気持ちが高まりそうですね。
岸本:落ち込んだときに温かい言葉をかけてもらえると、それがAIであってもポジティブに受け取れる気がします。
クリエイターの発想力や選球眼が、生成AIの可能性を広げる
小堀:AICO2の間違った使い方、どうでしたか?
直川:面白いお題を設定することで、必然的にお題と答えとの距離感が生まれて面白くなるので、やっぱりお題次第なんだなって思いました。ただ、実際はひとつのお題に対して何百個ものコピーが出てきて、そのなかから厳選したものを今回紹介しているので、選定する作業は手間をいとわずにやる必要がありますね。
小堀:そうですね。今回たくさんお題を考えるなかで、少しずつAICO2の人格というか、個性のようなものをつかめるようになり、魅力的なアウトプットを得られるようになった感覚がありました。まずはたくさんAICO2と対話をすることが大事そうです。
岸本:私は初代AICOから開発に携わってきましたが、今までで一番激しく、かつクリエイティブに使い倒していただいた気がします。そして、やはりAIはちょっと“間違った使い方”ぐらいがちょうどいいのかなと感じました。
ChatGPTの基礎技術であるTransformer(トランスフォーマー)も元々は機械翻訳の分野で注目され、発展したものでした。しかし、いろいろと試しているうちに文章や画像、動画などに応用範囲が広がっていった経緯があるので、生成AIにおいても間違った使われ方はまだまだ探る価値があると考えています。そして、その間違った使い方を模索するときに問われるのが、クリエイターの発想力や、数あるなかから面白いものを選び抜く選球眼になるんだと思います。
小堀:ぜひ、コピーライターやクリエイターの方々に、いろんな“間違った使い方”を試していただきたいですね。今回はありがとうございました!