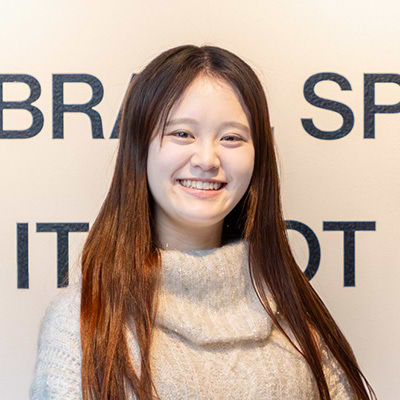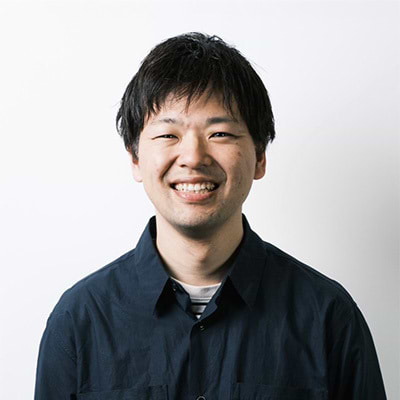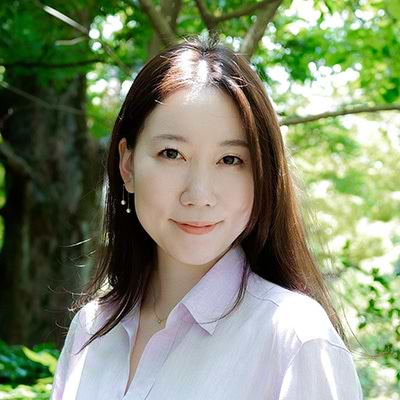2024年秋、青山学院大学総合文化政策学部と電通のフューチャークリエイティブリード(FC)室で、プロジェクトデザインを通じて企業の未来を共創する講義が開講。題して「AOGAKU PROJECT DESIGN CENTER」。プロジェクトデザインという思考回路を用いて、パートナー企業と青学生、電通でどんな未来が描けるのか?新たなチャレンジがはじまりました。

「AOGAKU PROJECT DESIGN CENTER」については
第1回をご確認ください。
パートナー企業第1弾は、静岡県浜松市を拠点に全国的な知名度を持つ“うなぎパイ”の「春華堂」。
創業138年を迎える春華堂は「まちづくり」を事業の根幹に据え、静岡県内だけでなく、日本中の地域、企業、大学などと連携、多種多様なアイデアや想いを束ねてプロジェクトを推進するクリエイティブな企業です。
その事業のひとつが、「遠州・和栗プロジェクト」。お菓子づくりの過程で掛川栗の価値と課題に出合ったことで生まれました。現在、日本中の和栗産地や企業を巻き込むプロジェクトとなり、25年2月に「和栗協議会」として再発足。日本中の和栗の価値を日本中、世界中へと届けていく事業に発展しています。
24年秋、ハラカド(原宿/神宮前)にオープンした「HOW’z(ハウズ)」もこのプロジェクトの想いを受け継いでいます。
クリエイティブなプロジェクトを生み出し続ける春華堂と「AOGAKU PROJECT DESIGN CENTER」との出会いから生まれた物語のはじまりです。
目指す方向が同じだったことが「ご縁」のはじまり
ここからは参画していただいた春華堂の今永栞希さんと、森島ゼミに所属する北爪乃衣さん(青山学院大学3年生)、電通フューチャークリエイティブリード(FC)室の大曽根一平にインタビュー。ゼミでのセッションを経て、どんな発見があったのか、プロジェクトメンバーの舩曵慧美が話を聞きました。

(左から)今永さん、北爪さん、大曽根、舩曵
春華堂が出店する東急プラザ原宿「ハラカド」HOW’zにて
舩曵:まずは、今永さんにお伺いしたいのですが、今回のプロジェクトに参画していただいた背景を教えていただけますか?
今永:電通の大曽根さんをご紹介いただいたのは、2024年の7月頃でした。そこで春華堂が推進する「遠州・和栗プロジェクト」の話をしたところ意気投合して、今回のプロジェクトのお話を伺いました。
青学とのプロジェクトは一過性で終わるのではなく、長く続けていくことを大事にしているとお聞きして。「遠州・和栗プロジェクト」も未来まで続けていくことを大切にしたいと考えているので、ご縁を感じてぜひ参加しようということになりました。
「遠州・和栗プロジェクト」というのは、静岡県掛川市で栽培されている和栗が後継者不足から生産地としてなくなってしまいそうだ、という話を聞き、菓子メーカーとして何かできることはないかと立ち上げたプロジェクトです。質の高い和栗を未来に継承する「持続発展型事業」をつくり上げることを目指して、官民一体でさまざまな取り組みを行っています。
大曽根:春華堂さんはうなぎパイの会社だということはもちろん知っていたのですが、「遠州・和栗プロジェクト」の話を伺ったときに、官民いろんなところを巻き込んで価値をつくっておられることを知りました。私たちFC室がやろうとしていることそのものだと感じ、ぜひ真っ先に春華堂さんとご一緒しようということになりました。
舩曵:地域とのご縁を大切にするプロジェクトを推進されていて、春華堂さんを知れば知るほどファンになってしまいます。北爪さんは今回のプロジェクトに参加して春華堂さんのイメージが変わりましたか?
北爪:やはりうなぎパイのイメージが強かったのですが、お菓子の種類も豊富な上に、お菓子づくり以外にも多くの事業に携わっていることが分かり、春華堂さんのイメージがもっと大きくて広いものに変わりました。プロジェクトを進める中で、春華堂さんの目指しているものや想いに触れていくうちに、私たちも自然とご縁でつながっていけたように感じています。
学生たちのフラットな視点から生まれるアイデアとは?
舩曵:実際に学生たちのプレゼンを聞いていかがでしたか?
今永:私たちがこれまで行っていた施策は、農業や町おこし観点からのものが多かったのですが、学生さんたちからは、「マロンアイ」や「栗持ち運びバッグ」「ビックリオブジェ」など、ファッションの観点からの発想もあって、我々には無い新しい視点からの提案がすごく学びになっています。
舩曵:学生らしいフラットな視点でアイデアを出してくれましたよね。和栗についてここまで真剣に考える機会はなかったと思いますが、プレゼンまでの工程はどんな感じでしたか?
北爪:結構、混沌としていました(笑)。全員が頑張りたい課題だったので、力んでしまったというか、最初は“お利口さん”なアイデアが多く出て、なんか足りないな、という印象でした。でも示し合わせたわけじゃないのに、「こないだ栗のお菓子買って……」とか「春華堂さんのお菓子買って……」という感じで日常の中に和栗が浸透していき、それをきっかけにアイデアが深まっていきました。
大曽根:事前にプロジェクトメンバーのFC室の吉川の講義で、「世の中の課題から考えるのもいいけど、身の回りの願望や違和感、人から直接聞いた話とかを大切にしよう」というインプットをしていましたよね。学生たちのアイデアを見ると「うちに栗の木があって、むいてみたら……」という話とか、身の回りの気づきが集まってアウトプットされている感じがあって面白かったです。
一つ一つのアイデアも「栗の色や形がかわいいよね」というピュアなことから、むきにくいけど、むくと達成感があるとか、崩れやすいけど、いろんなものに加工しやすいとかネガティブな点をポジティブに転換しようとする発想は納得感がありました。
舩曵:そうですよね。私も講義で聞いたことをすぐに吸収してアイデアを出してくれたのには驚きました。ちゃんと準備したことが垣間見える、プロジェクト化につながるプレゼンだったなと思います。

学生たちのプレゼン(写真上)とゼミの様子

プレゼンの当日はグラフィックレコーディングも行われた(グラフィックレコーダー:中尾仁士氏)
対話してアイデアを重ねていく、共創の良い循環ができている
北爪:このプロジェクトが始まって、ゼミの人間関係にも変化がありました。仲の良い子同士でかたまりがちだったのですが、深く話したことのない子とも話すようになって、お互いのバックグラウンドやセンスを知ることができ、ゼミメンバーとしても関係が一歩前進するような機会になっています。今はゼミのメンバーと大学の誰よりも多く話しています。
大曽根:それはうれしいです。企画するプロセスが面白いものになっていますよね。大本には春華堂さんの和栗への想いがあって、学生の皆さんが考えたアイデアを中心に、FC室からもクリエイティブの観点でアイデアを重ねていく。三者が集まってそれぞれの良さを重ね合わせながら何かをつくっていく打ち合わせがとても楽しくて。楽しいから春華堂の皆さんも次回の打ち合わせを楽しみにしてくれているし、学生たちももっと考えようと思ってくれるいい循環ができています。このプロセスを続けていけば、アウトプットも良いものになりそうです。対話しながらアイデアを重ねていくので、誰かのアイデアというより、みんなのアイデアと思える進め方になっているのもいいなと。
それから“寸劇プレゼン”をしてくれましたが、学生たちは楽しい場にするための空気づくりもすごく上手でしたね。
舩曵:森島先生のお人柄やゼミのつくり方もあると思いますが、ゼミの空気感というか受け入れてくれる雰囲気が最初からありました。
今永:私たちもいろんなところでアイスブレークをするのですが、森島ゼミの皆さんは雰囲気が柔らかくて、やりやすい空気づくりをしてくださっていると感じました。
大曽根:あの春華堂さんのアイスブレークも大きく影響していますよね。栗のダジャレも何個レパートリーがあるんだろうってくらい披露してくださって。アイデアを言いやすくする空気づくりをしてくださいました。
和栗を通して学生同士がつながる、長く続くプロジェクトに
舩曵:ゼミでのセッションは終わりましたが、プレゼンで終わってしまうのはもったいないということで、その後も月1回のペースで打ち合わせをするなどプロジェクトは継続しています。HOW’zに学生たちがお邪魔した際には、新作カクテルができたというお話を伺って、そのネーミングも学生たちからアイデアを募集して決めました。

HOW’zで提供されている春華堂の新作カクテル「クリスタルムーン」
舩曵:学生たちとの交流が続いている点についてはどんな感想をお持ちですか?
今永:率直に、学生さんたちが和栗を広げていく方法を積極的に考えてくださっているのがうれしいです。「きっかけがあれば、興味を持ってくれるんだ」と実感しています。私たちは普段地方で活動していますが、東京の学生と関わることで、新たな視点が得られましたし、学生の皆さんには地方に魅力を感じる機会になっているといいなと思います。ぜひ一度、浜松や掛川に足を運んでいただき、栗農家さんを訪れてみてほしいです。
北爪:ゼミでも実際に農業体験をしてみたいよね、という話が出ていました。私たちにとっても、地方の企業と関わる機会は少なくて、インターンでもオンラインのみで終わってしまうことが多いので、本当に貴重な経験をさせていただいていると感じています。
大曽根:知ることも大事ですし、そこから一歩踏み込んで一緒に考えてみることで自分ゴト化できますよね。さらに体験までできるともっといいと思いますが、関係人口を増やすというのはこういうことだと思います。
舩曵:では最後に、それぞれの視点から今後の展望をお聞かせください。
今永:今後は学生さんたちとの連携をより強めていけるといいと思っています。この青学のプロジェクトを大々的に実行していくことはもちろん、「和栗を通して学生同士がつながって地方を盛り上げる方法を考えて発信していく」というところまでもっていけるといいなと考えているところです。
北爪:私たちもここまで一丸となって熱意を持って取り組めることって、滅多にないなと感じています。就活も関係なく、ただ楽しいと思ったことを突き詰めていく中で自分を知ったり、社会がどうなっているのかを知れたりするのはすごく大きな財産になります。森島ゼミにこれから入ってくる下の学年の子たちやゆくゆくは他の学生たちまで広がっていく、長く続く取り組みになるといいなと思っています。
大曽根:これからは、小さくてもどんどんアウトプットをしていきたいですね。1個アウトプットをすると、そこから関わった方や知った方、農家の方などいろんな人を巻き込んでプロジェクトが大きくなっていきます。
企業の課題を解決することはもちろん、社会にも目を向けて、「ワクワクする未来をつくっていくにはどうすればいいのか」を考えていきたいです。「AOGAKU PROJECT DESIGN CENTER」もそうありたいですし、今後もご賛同いただける方や企業に参画していただき、仲間を増やしていきたいと考えています。

インタビュー当日HOW’zに集まったプロジェクトメンバー