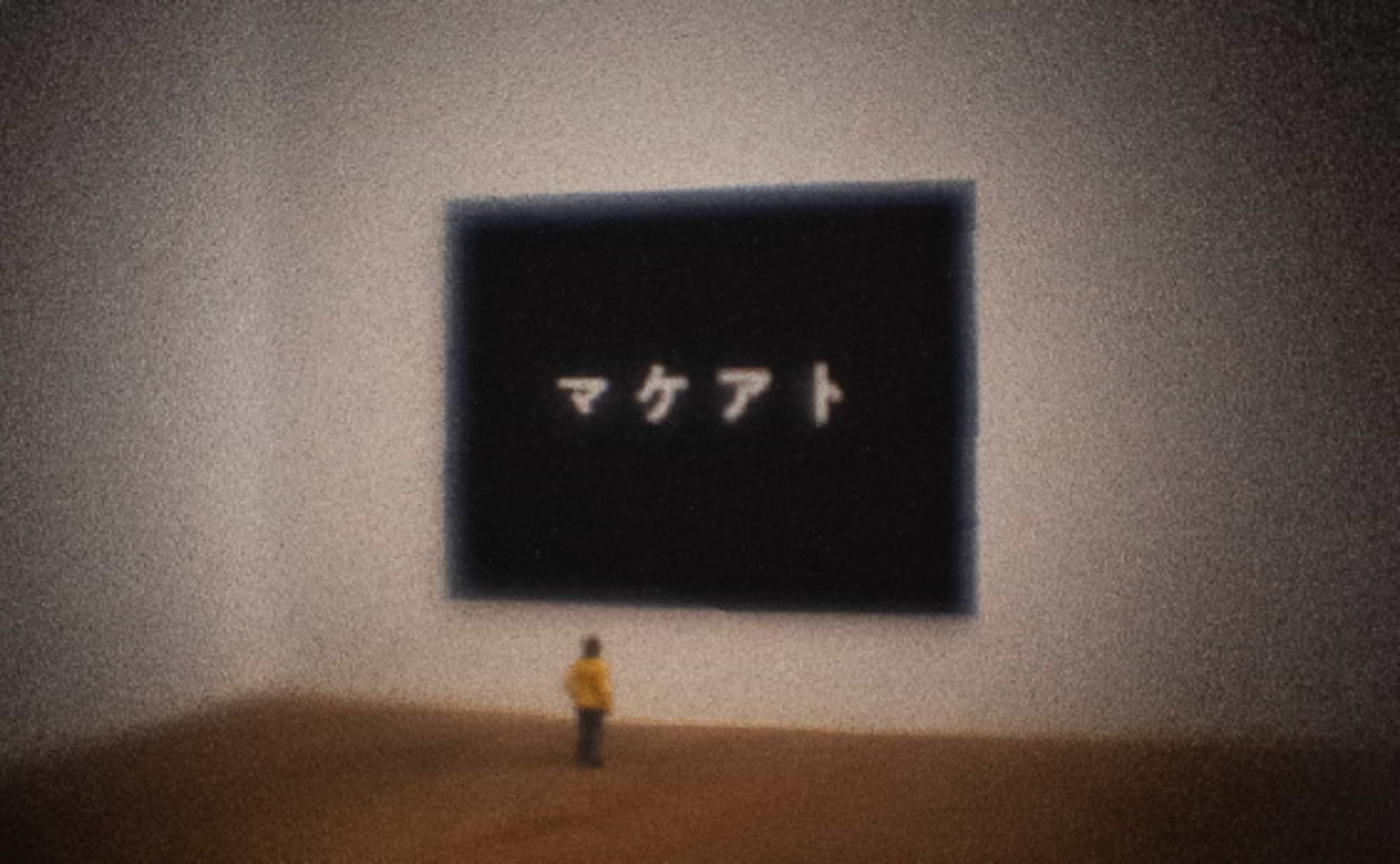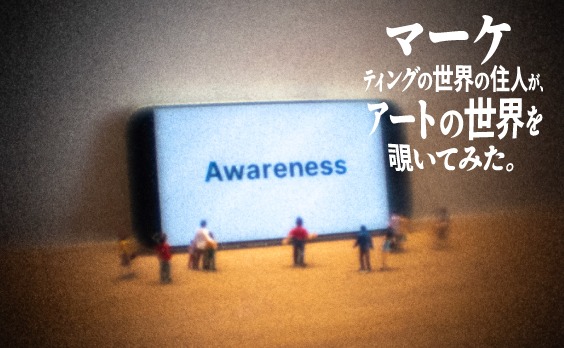電通・宮川裕による連載「マーケティングの世界の住人が、アートの世界を覗いてみた。」
今回対話をともにしたのは南條史生さん。美術評論家・キュレーターとして世界の第一線で活躍し、現代アートシーンを牽引している。南條さんと仕事で初めてご一緒してから、かれこれ10年以上になる。いつも南條さんの語り口に引き込まれ、気付けば「分からないこと」の入り口に立っている自分がいる。自ら考えることを促される。南條さんはとてもチャーミングな人だ。
◆現代アートの魅力
宮川:南條さんは、さまざまな手段を通じて現代アートに詳しくない人でも興味を持てるように入り口まで連れて行ってくださる印象があります。でもその先がミソで、「分かるでしょう?」じゃなくて、「いや、分からないんだよ」というふうにおっしゃる。そのスタンスが素敵だなと感じるのですが、改めて南條さんが考える現代アートの魅力について教えてください。
南條:一つじゃないと思うんです、現代アートの面白さって。社会批評的な作品もあれば、作家が内側にずっと溜めていた個人的なものを表現する作品もありますよね。その多様さこそが魅力で、その中から自分にとってピンとくるもの、響くものを見つけられる。そういう出会いの可能性があることも魅力と言えますよね。
一方で、マーケット的な側面に面白さを見いだす人もいる。価格が急騰する作品があるように、現代アートを資産として捉える視点もある。他にもアカデミックな世界もあれば、歴史的な視点もあるし、本当に現代アートの世界って“玉虫色”なんですよ。
だから「現代アートとは何か?」と問うても、その人の立ち位置や視点によって、まったく違って見える。結局、誰にも本当の正解は分からないという、そこもまた面白さですね。
宮川:南條さんが「分からない」とおっしゃるのなら、きっと誰にも分からないんでしょうね(笑)。
南條:そう、「これが現代アートです」と断言できるような絶対的な物差しは、存在しないんだと思います。マーケットの視点で見ても、現代アートって他の商品と違って供給が尽きないんですよ。不動産にも、ダイヤモンドにも、金にも物理的な限界がある。でも作品は誰かが作り続けている限り、絶えることがない。だからマーケットとしても面白いし、必ずしも価格が上がるとは限らないけれど、常に新しいものが出てくる。そういう意味で、経済的な魅力もあるんですよね。
でも、美術評論家のように、美学的な観点から作品を読み解く人たちもいて、そういった多層的な解釈が入り交じっている。現代アートって、本当に不可解な物体なんです。
宮川:正解を求めがちな時代において、現代アートはまったく逆のベクトルにある、と。
南條:そう。だから、正解を求めるのではなく、「自分はどう考えるのか」という意見表明が大事なんです。それはすなわち、作品が厳然とそこにあるだけではなくて、自分との関係において存在する、ということ。自分で考えない限り、その作品は何かを語り出してはくれない。だからアートを見ることは、「自分自身と向き合う」という人間らしい営みでもあるんです。
AIがここまで発展してくると、人間がやるべきことって、どんどん少なくなっていく。でもそれは、ある意味では素晴らしいことですよね。今までのように苦労しなくていい時代に突入しているのですから。だからこそ、われわれに残された数少ない「人間らしい営み」としての現代アートの役割は、これからますます大きくなるんじゃないかと思っています。

◆日本のポテンシャル
宮川:そうなってくると、やっぱり気になるのは日本の話です。現代アートの世界において、日本はどんなポジションにあるのか?日本の教育や価値観とアートの関係など、いろんな視点があると思うんですが、世界を見てこられた南條さんの目には、今の日本はどう映っていますか?
南條:シンプルに現代アートにおける日本のポジションで言えば、草間彌生、奈良美智、村上隆、杉本博司、名和晃平、加藤泉――トップクラスの名前がこれだけ挙がる国って、実はあまりない。フランスやイギリスで同じように並べられるかといえば難しいし、アメリカでさえ世界的な現代アート作家となると、数は限られます。そう考えると、日本は国際的にもかなり影響力のある“現代アート大国”なんです。
宮川:そうなんですね。多くの日本人は“現代アート大国”という認識を持っていない気がします。
南條:でも、実際はそうなっている。おそらく日本が他の国とは違う文化を持っているからだと思います。違うということが、アートにとってはリソースになる。皆、どこかに“日本的な何か”を取り入れて有名になっているんですよね。村上さんはジャパニーズカルチャーを意識的に取り入れているし、杉本さんも多くは語らないけれど、やっていることは非常に日本的ですよね。
そういう意味では、日本にはまだたくさんの文化的アセット、いわば“レガシー”が眠っていると思います。それをうまく使っていけば、新しい作品がこれからも生まれてくるポテンシャルは十分にあります。
一方で、日本は少しズレているという感覚もあります。欧米では当たり前に議論されているような重要なテーマが、日本では避けられてしまうような空気感もある。そういった切実さの違いが、作品を通しても生じている可能性は高いです。
宮川:今後、変わっていくことはあるのでしょうか?
南條:そこは人びとの好奇心次第、でしょうね。やはり、日本人はもっと世界を“自分の目で”見に行くべきだと思います。最近は世界から日本に来てくれていますが、それだと日本人の意識はあまり変わりません。自ら外に出ていき世界のエコシステムを体感しないと、今起きていることや世界の価値観の全体像が理解できないと思うんです。

◆これまで注力してきたこと
宮川:南條さんは数々の国際芸術祭でディレクターを務めてきた他、著名なパブリックアートやコーポレートアートの監修、森美術館の館長など、本当に幅広い活動をされてきた印象がありますが、ご自身の中で何か一貫した視点はあるのでしょうか?
南條:ひたすら、来た球を打ってきたからなぁ(笑)。ただ昔から、いくつかのタイプの仕事をバランスよくやることは意識していました。たとえば、アカデミックで教育的な側面を持った仕事、しっかり利益を生み出す仕事、社会的な意味やメッセージを持つ仕事など、いろんなタイプの仕事がありますよね。それらのバランスを考えて働くことが、人間のあるべき姿じゃないかと思うわけですよ。
宮川:それって、ビジネスパーソンにも通じる考え方ですよね。どうしても収益ばかりを追求しがちなんですが、南條さんのように社会的な意義も含めてバランスを取るという視点は、今まさに必要とされている気がします。
南條:ビジネスの世界でもよく言うじゃないですか。「Win-Winの関係を作ることが大事だ」って。私の考えも、それと近いかもしれないですね。たとえば、アカデミックなプロジェクトでも、完全に赤字ではやっていけない。社会的な意義がありながら、ちゃんとフィーも生み出せる仕事にすることが大事なんです。新宿アイランドのパブリックアートを手がけたときは大物作家をそろえましたが、翌年のプロジェクトでは日本の若手作家の作品を紹介しました。どちらも学術的・教育的な意義を持ちながら、経済的にも成立しているプロジェクトでした。
1982年に国際交流基金で「行為と創造」というパフォーマンスイベントを開催したときは、演劇関係の予算が原資だったのでダニエル・ビュランなどトップレベルの現代アート作家たちを“パフォーマンス”してもらうというお膳立てで呼んだのです。あれは“ひねった”戦略でした。
宮川:みんながまだその価値を認識していないものに、価値を与えていくプロセスが、まさに南條さん流の企てというか。
南條:そう、みんながあまりにも知らないということが、メリットになっていました。1980年代当時、日本における現代アートの理解って本当に浅かったし、美術評論も情報ばかりが先行して、実物を見ていない人が評論していたんですよね。でも、現代アートって“本物”を見ないと絶対に成り立たない。だから私は、ある時期に、“持ってくる側”に回ろうと思ったんです。展覧会を企画し、本物かつ最先端の現代アートをキュレーションする。そうすれば、きっと日本人も「現代アートって面白い」と思うはずだと信じていました。
宮川:南條さんが森美術館で行われていたようなジャンルを横断する展覧会も、まさに人びとの好奇心を刺激する仕掛けだったのではないでしょうか。
南條:そうですね。最初にも言ったように、現代アートってそもそも規定できないものでしょう?だから、作品を「これは現代アートです」と言ってみせても、それは既成観念の範疇で踊っているだけなんです。そのボーダーを超えて、アートだと皆が思っているものを他の領域のものと一緒に配置していく。「こういうものもあるよね」「この可能性はどうだろう?」という姿勢で、ボーダーレスな状況の中でいろんなものを提示していくべきだと考えたのです。

◆企業と現代アート
宮川:ここまで個人の視点での話が多かったですが、「企業」という視点で、組織が現代アートを活用する意義についてお聞きしたいです。
南條:以前、アートフェア東京の前身となるイベントが横浜で行われたとき、関連書籍に「企業とアート」というテーマで原稿を書いたことがあるんです。その中で僕は、「日本には企業という怪物がいる」と書きました。つまり、利益を増やしても社員や社会に十分に還元せず、そのお金を次の投資に回してしまう。企業という器の中に莫大な利益が留まって、人間は不幸なままでおわってしまう構造があるという問題提起をしたのです。そして本来、企業は黒字になったら文化に貢献すべきであり、そうすることで初めて、企業は社会の中で“意味ある存在”として認められるのだ、と。
宮川:かなり強いメッセージですね。
南條:すると後日、電話がかかってきました。ベネッセの福武總一郎さんがその原稿を読んだらしく、「来てくれ、会いたい」と言われました。それがきっかけで直島の最初の展覧会(1994)を私が手がけることになったんです。福武さんは現代アートをベネッセのブランディングに活用したわけですが、文化への大いなる貢献も実現したことになります。
宮川:とても象徴的な取り組みですよね。
南條:国内外問わず、たまに哲学的な視点を持っている経営者に出会うことがあります。たとえばエルメスの前社長なんかは“哲学者”とも言われていた人で、実際にお会いしてみると、物静かで、哲学者風でした。エルメスは彼によって独自のブランドになっていった。単に物を作って売るという発想にとどまらず、境界を超えて俯瞰的に世界を見るという思考法を身に付けている人が現代アートにも精通している印象を持っています。
宮川:金融機関など、グローバルに活動する企業ではどうでしょう?
南條:そこは確かに進んでいる会社がありますね。たとえばスイスのUBSグループは、アート・バーゼルのメインスポンサーですし、ドイツ銀行やチェース・マンハッタンも大規模な現代アートコレクションを持っています。こうした企業にとってアートは、単なるブランディングではなく、エグゼクティブ層を中心とした顧客とのコミュニケーションや顧客サービスの一環として捉えている側面もあります。

◆マーケター(ひいてはビジネスパーソン)と現代アート
宮川:最後に視点を個人に戻して、「マーケター」という立場から現代アートに触れる意義について伺いたいと思います。この連載を読んでくださる方の中には、「自分の視野を広げたい」「狭義のマーケティングとは異なる教養を身に付けたい」と考えている方も多いと思います。そういった方々に、現代アートに触れることの面白さや豊かさを伝えられたらと思っているのですが、いかがでしょうか?
南條:やっぱりマーケティングって、本質的にはクリエイティブでなければならないと思うんですよ。僕が印象に残っているのが、徳大寺有恒さん(「間違いだらけのクルマ選び」の著者)がおっしゃっていた、メルセデス・ベンツの姿勢です。
普通、メーカーはマーケットのニーズをリサーチして、ニーズに合わせた車を作るわけですよね。でも、ベンツはそうじゃない。「車とはこうあるべきだ」というビジョンをまず持ち、それを実現するクルマを作っている。安全性、快適性、性能……それらを極めた結果、「高いけれど、これが最高の車です」という態度をとる。つまり、自ら価値を定義し、提案しているんです。この姿勢こそ、マーケティングが向かうべき方向じゃないかと思いますね。つまり、マーケットを調査するだけでは足りない。その先に何を提案するのか?そこに本当のクリエイティビティが求められており、現代アートから学べることの一つだと思います。
宮川:まさに、「正解は何ですか?」と問うより、「私はこう考える」と見立てていく力ですよね。先ほどのアートの話ともつながってくる気がします。
南條:あるAIの専門家は、「AIでもゴッホ風の絵は描ける」と言いました。でも、ゴッホの本質って、それまでの絵画の歴史からジャンプしたところにある。浮世絵の影響を受けて影をなくして色面で描いたり。それまで営々と連なってきた西洋の美術の歴史や系譜を切り捨てて、全く新しい表現を生み出したわけです。こういう“飛躍”がAIにできるかと疑問を呈しました。そうしたらその先生は「AIも変なものを作ることはできる。でも、それが“アートかどうか”を決めるのは人間だ」とおっしゃったんです。アートに限らず、判断を下すために必要なのが“自分の感覚”や“価値観”であり、それを磨くことが重要です。そこに現代アートに触れる意義があるのではないでしょうか。
宮川:たとえアーティストでなくても、アーティストたちの先見的な視点をヒントにすれば、一人一人が自己を高めたり、ビジネスの可能性を広げたりすることができるということですよね。
南條:アートって結局、“物の見方”そのものなんですよね。たとえば、千利休からマルセル・デュシャン、そして現代の杉本博司に至るまで、歴史の中には、物の見方をひっくり返す人たちが常にいた。
利休がやっていたことって、デュシャンのコンセプチュアル・アートと同じ発想なんですよ。当時、多くの人が中国から伝来した白磁の茶碗を美しいものとして重んじていた中で、利休は瓦職人が作った歪んだ黒い茶碗、すなわち楽焼に美を見いだした。その時、利休は「美とは何か?」という価値観を完全にひっくり返したわけです。
利休を描いた映画でも、侍が「どうしてこんな茶碗が高値なのか?この茶碗が本当に価値があるのか」と詰め寄るシーンがあるんですが、利休は「私が言えば、そうなります」と答える。これはつまり、「価値は自分で決めるものだ」という強烈な自信の表れなんですよ。それって、現代アートの姿勢とまったく同じですよね。一見すると価値が分からないかもしれない物体を「これはアートだ」という。その信念を貫くことで、それが本当に価値を持ち始め、歴史に残る。
もしアートのコアがそこにあるとすれば、それこそがまさにクリエイティビティであり、柔軟な物の見方を養うための訓練の場とも言えるんです。最近話題の「アートシンキング」も、そうした柔軟な考え方の重要性を語っているのではないかと思うんです。
宮川:アートに触れることを通じて、物の見方や価値を見いだす力を養える、と。
南條:そう。確定した価値なんて、本当はないんです。自分がどう見るかを決めて、そこに自信を持つ。それをできることが、現代アートを面白がれる人の資質なのかもしれません。
それから、現代アートの定義なんて本来存在しないけど、ヨーゼフ・ボイスが社会を変える行為を「社会彫刻」と名付けたように、極めてクリエイティブな仕事を現代アートだと定義するなら、それはもはや絵画や彫刻に限らないですよね。マーケティングの仕事も、日々の業務も、思考のプロセスも、創造的であれば現代アートたりうる。そういう捉え方が、今の時代には必要なんじゃないかな。
宮川:なるほど。現代アートという枠に収めてしまうより、仕事や日常と地続きのものとして捉えることが大切なんですね。
南條:だから言ってしまえば、現代アートって多分、ないんですよ。
宮川:南條さんに「現代アートは存在しない」と言われるとドキッとします(笑)。でも確かに近年、現代アートがいろんなところに越境して溶け込んできているような印象があります。
南條:そう。どんなものでもクリエイティブであれば、現代アートであり得るんです。
宮川:マーケターにとっても、アートに触れることを通じて自分の感性や思想、行動にまで拡張して考えることで、新しい視座が手に入るのかもしれませんね。本日は貴重なお話をありがとうございました!

画像制作:岩下 智
この記事は参考になりましたか?
著者
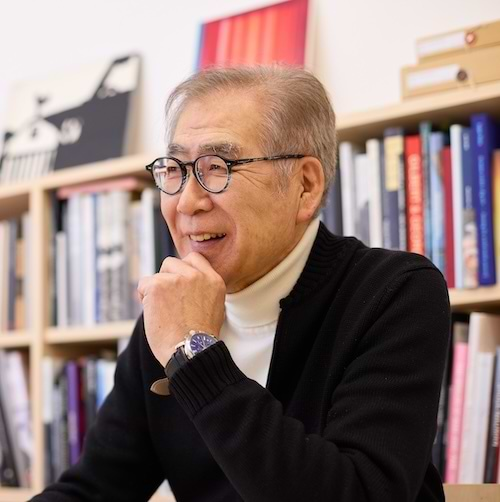
南條 史生
キュレーター、美術評論家
1972年慶應義塾大学経済学部、1977年文学部哲学科美学美術史学専攻卒業。国際交流基金等を経て、2002年より森美術館立ち上げに参画、2006年11月から2019年まで館長、2020年より特別顧問。同年より十和田市現代美術館総合アドバイザー、弘前れんが倉庫美術館特別館長補佐、2023年5月アーツ前橋特別館長に就任。1990年代末より1997年ヴェニスビエンナーレ日本館を皮切りに、1998年台北ビエンナーレ、2001年横浜トリエンナーレ、2006年及び2008年シンガポールビエンナーレ、2016年茨城県北芸術祭、2017年ホノルルビエンナーレ、2021年北九州未来創造芸術祭 ART for SDGs、2021年〜2023年Fuji Textile Week等の国際展で総合ディレクターを歴任。著書として「アートを生きる」(角川書店、2012年)等。