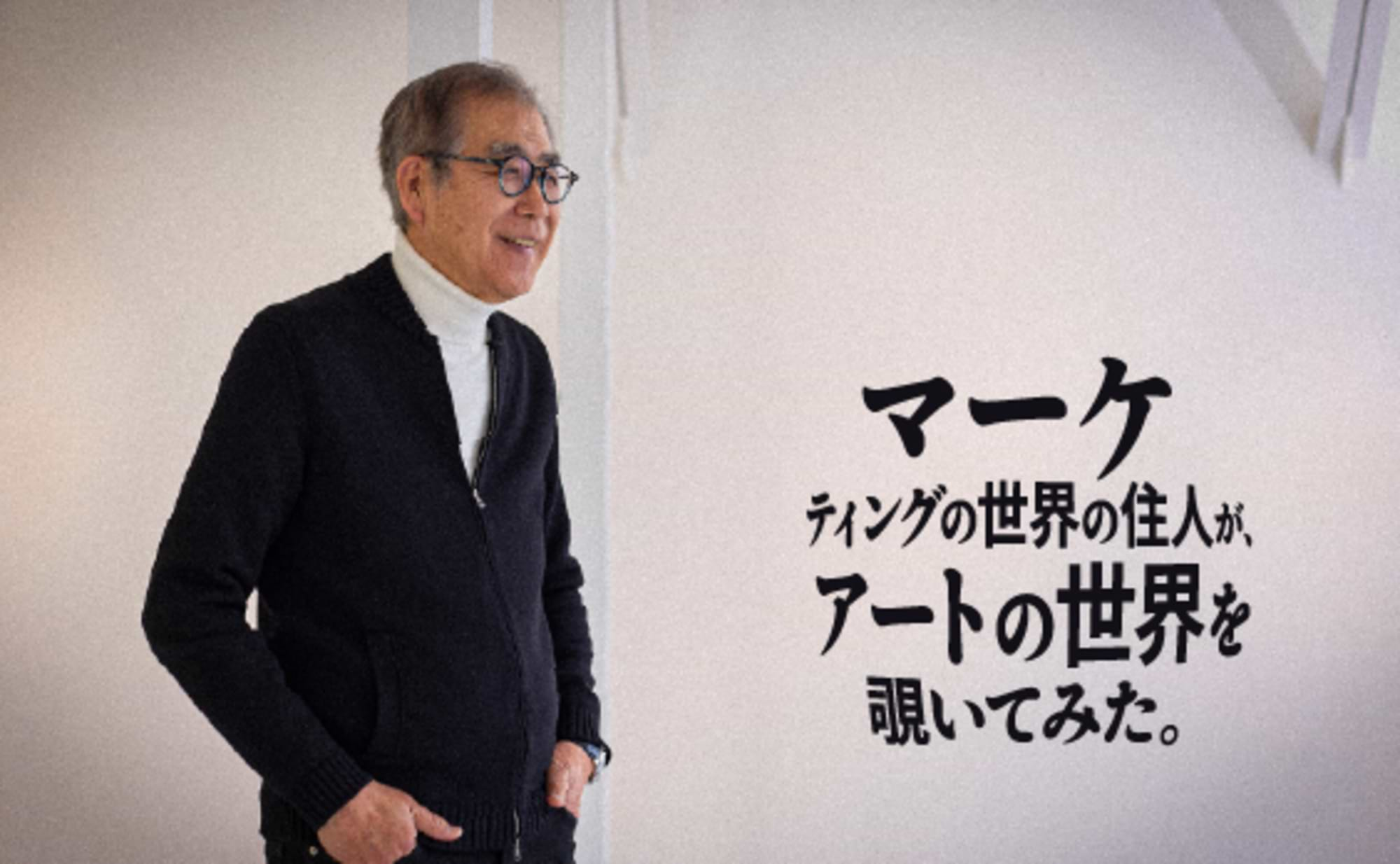もし時間に余裕があれば、ミュージアムに行ってみよう。この手の提案にまったく反対ではないのだけれど、そもそもミュージアムって、なんだろう?という素朴な疑問が僕にはあった。
日本には、博物館と呼ばれる施設が世界の中でも多いらしい。文科省の実態把握調査によると6000施設近くある模様。日本における博物館は博物館法で規定されており、博物館、美術館、科学館、それから動物園や水族館なんかも博物館になる。
2019年、世界中の博物館や美術館、つまりいわゆるミュージアムの関係者を中心とした会議体「ICOM」が京都で開催された。開催前、僕はICOM会場でゲストをお出迎えする俵屋宗達筆の「風神雷神図屏風」と尾形光琳筆の「風神雷神図屏風」(ともに高精細複製品)の設置作業の場にいた。2つ並ぶと壮観だなぁ。満足感とともに東京に戻った。ということで、この国際会議の場での議論の内容は後から記事で知ることに(自分のエピソードを盛り込んだら、妙に言い訳めいた書きっぷりになってしまった)。
で、博物館法や国際会議なんかで提示されている基礎的なこととして、ミュージアムとは有形・無形の資産を「収集」「保管」「調査」し、「教育」するための機関である、ということ。これらの要素を見ると、なんともアカデミックな香りというか、へー、ミュージアムは研究機関なのかぁ、と。僕なんかは展覧会を見に行く、とか、動物園のパンダに会うために行列するといった一般人としての行動の側から認識しがちだから、このミュージアムのアカデミックな顔つきは別人のように思えてしまう。展覧会もパンダを見せることも「教育」に位置付けられており、いわば機能の一部のようだ。
博物館法というのは、1951年に制定されたもので、戦後、博物館を増やしていくために、登録すると優遇がありますよ(博物館登録制度)、そんな特徴も持って誕生したようだ。それにしても、スタートしたのはずいぶん昔だが、その頃の社会ってどんなだったのだろう?
◆
この博物館登録制度について、個人的に興味を持てた点が2つあった。まず、登録されているのは日本全国で1000施設超、ということ。ざっくり計算で1つの都道府県に20以上はあるということか。なかなか多いなぁ、多い?あれ、実態把握調査によると6000施設近くあるらしいのだから、登録しているのは2割程度?
そしてもう一つ興味深いのは、登録の種類が「登録博物館」と「指定施設(かつての呼称は博物館相当施設)」の2種類あること。ちなみに登録していない約8割の施設を便宜上「博物館類似施設」と言うらしい。調べてみて、少し驚いた。日本における博物館の中の博物館としてぱっと思い浮かぶのは、個人的には東京国立博物館(東博)なのだが、東博はなんと指定施設。博物館法が一部改正されたのは割と最近のことなので、それまで東博は博物館相当施設と呼ばれていたということか!博物館オブ博物館の東博が「相当」って(制度設計上そうなってしまうことは理解できたが、言葉の印象ってあるよなぁ、と)。
ちなみに、東京ステーションギャラリーや東京オペラシティ アートギャラリーは「登録博物館」に分類されていた。ギャラリーという名称だけど博物館。言葉は多様だ。
博物館たる美術館(ミュージアム)もまた有形・無形の資産を収集・保管している、つまりコレクションを保有しているということになる、はず。しかし、日本で屈指の集客力がある国立新美術館はコレクションを保有していない。学芸員や教育普及担当、司書など、職員はきちんといる。しかしコレクションは、ない。そういうコンセプトに則し、国立新美術館の英語名称は、「The National Art Center, Tokyo」。ミュージアムじゃなくてアートセンターだと宣言している。そして博物館登録制度には入っていない。
全国美術館会議、というものもある。東京ステーションギャラリーも東京オペラシティ アートギャラリーも、そして国立新美術館も正会員館に名を連ねている。だんだん頭がこんがらがってきた。
◆
新しいミュージアムに目を向けてみる。ソニー・クリエイティブプロダクツによる六本木ミュージアム(2021年からこの名称に)は、博物館登録制度にも全国美術館会議にも入っていない。また、同社による東京駅近くのCREATIVE MUSEUM TOKYOも同様。こちらは2024年開業ということで、できたてだからかもしれないが。両ミュージアムというか両施設ともいわゆるIPを中核に、プロモーション、物販といった連関の中でのビジネスモデル、ということでいわゆるミュージアムというものとはあえて一線を画しているのかもしれない。マーケター・オブ・ザ・イヤー2024をカルチュア・コンビニエンス・クラブの代表の方が受賞していたが、SHIBUYA TSUTAYAは「推し活」を主軸に大リニューアルしており、ソニー・クリエイティブプロダクツによる展開は、どちらかと言うとこちらに近いものを感じる。
ミュージアムという名称での展開について、Immersive Museumというものもある。常設の館でなく、貸しホールを使った期間限定の企画。すごい人数のお客さんが区切られた時間でコンテンツと過ごしている様を目の当たりにしたことがある。これもまたいわゆるミュージアムとは一線を画しているなぁ。
規格外。良い意味で使われたり、悪い意味で使われたり。思うに、良い悪いというよりも、ミュージアムという言葉の使われ方含め今の時代が既存制度の規格にはおさまっていない、もしくは制度はさておき、多様な在り方こそ時代の価値観や落としどころ、そんなものを反映しているのかもしれない。アートの歴史も規格外の登場、規格のアップデートの歴史だし、まあそういうものだよね、と受け入れるというより受け止めるくらいの心持ちがいいかな、なんて思ったりする。
◆
と言いつつ、自分に引き寄せて考えたくなることがある。2026年オープン予定の「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」だ。100年先へ文化をつなぐ、とか、文化財にも対応した大型の展示ができるスペースもあるという話を聞くと、オーソドックスなミュージアムを想起するが、アート、歴史、サイエンス、エンタメなどさまざまな境界を越えてコンテンツを開発するという話からは、まさに型破りで規格外な姿、ヨコイトのような姿が立ち現れる。さらに、デジタル化を通じて「体験をコレクションする」ミュージアムを目指すという。おそらく日本にはなかったような在り方で、新しいミュージアムの形を日本に上陸させてくれる予感。
大学生の頃、教授がやたらと「学際的」と言っていた。なんのこっちゃいな?と思っていた。聞き慣れない言葉の響きだけがずっと残っていた。あれからずいぶん時がたって、こういうことなのねと、ようやく僕にも体感できそう。身近なものとして引き寄せられそう。
ミュージアムって、なんだろう?という素朴な疑問は、ずれたり、はみ出したり、融合したり、膨張したり、ヨコイトのようになったりしながら、より複雑で豊かな問いへ。今なら僕も言ってみたい。もし時間に余裕があれば、ミュージアムに行ってみよう!
画像制作:岩下 智
この記事は参考になりましたか?