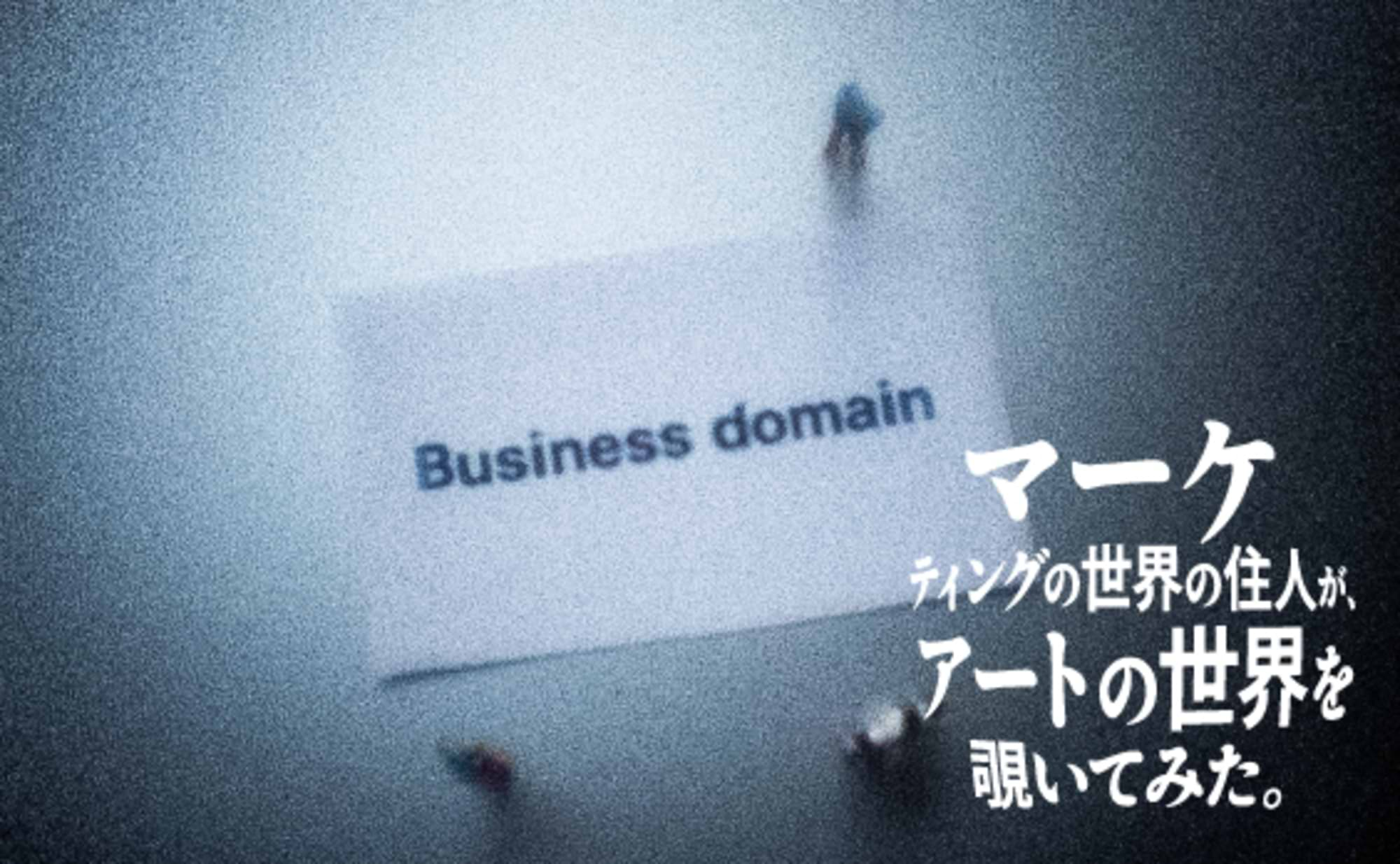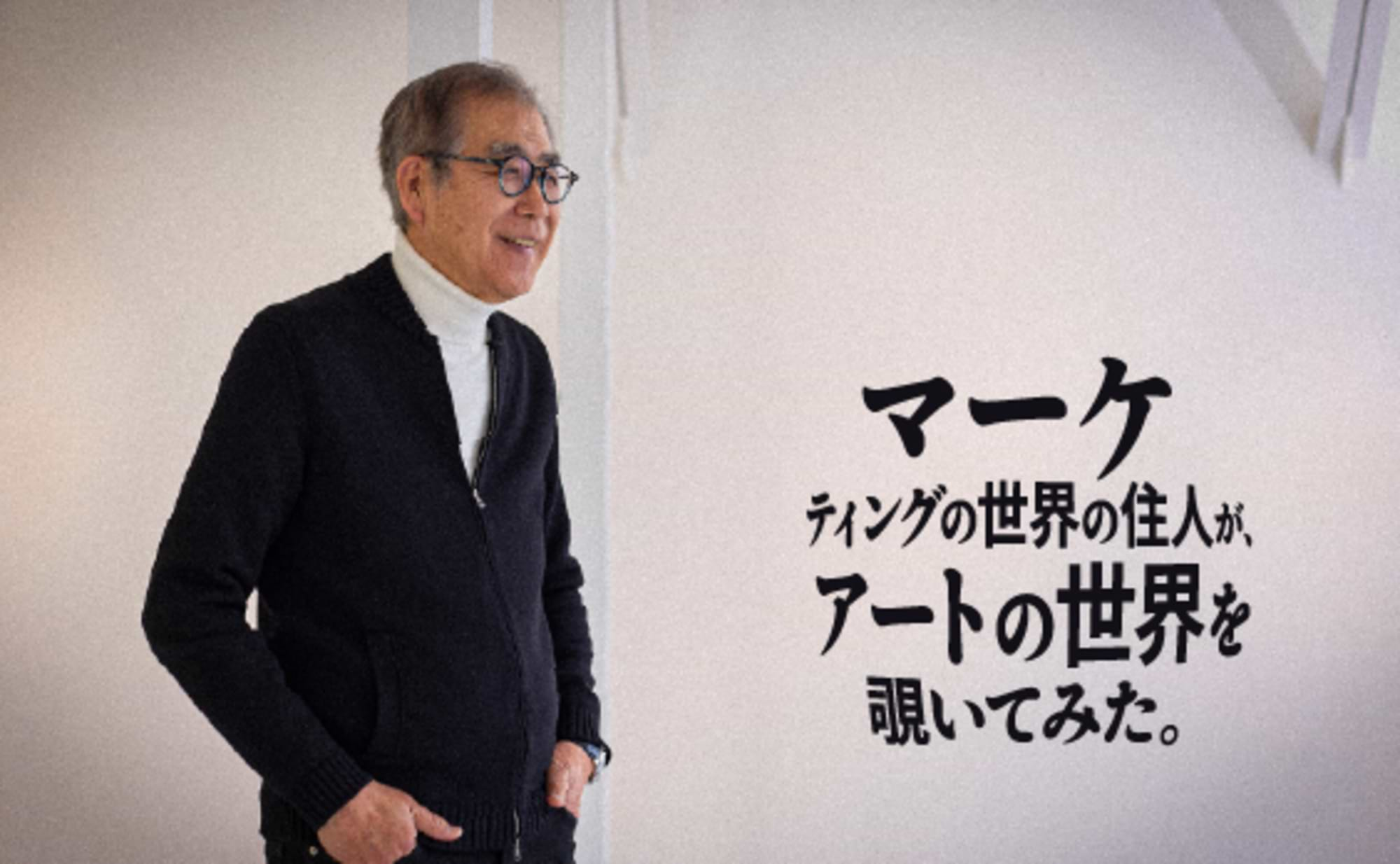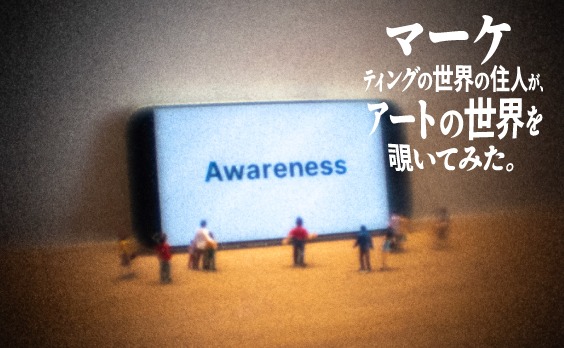電通・宮川裕による連載「マーケティングの世界の住人が、アートの世界を覗いてみた。」
今回お話をうかがったのは、東京国立博物館の松嶋雅人さん。大河ドラマ「べらぼう」の美術史考証を担当するなど多方面でご活躍だが、とにかく懐の深い人、というのが僕の印象だ。数年前に村上龍の小説「五分後の世界」を薦めていただき、以来何度も読み返しているが、松嶋さんは僕には想像できないくらいに広く、深く、世界を捉えているのかもしれない。
◆松嶋さんの価値観を形成したもの
宮川:松嶋さんのお仕事は、すごくアバンギャルドな部分もありつつ価値観に一本筋が通っているようにも感じていて。そういう考え方はどうやってつくられていったのでしょうか?原体験みたいなものがあるのでしょうか?
松嶋:明確なきっかけみたいなものはないんですよね。私自身は周囲の状況に乗っていくタイプのパーソナリティだと思います。流れの中で自分が一番パフォーマンスを発揮できるのはどこか、という合理的な判断で動いてきた気がします。
ただその一方で、自分の中には「好奇心の赴くままにいろんなことを経験したい」という思いが常にあって。そういう意味で、昔からずっと「自分は一体何者なんだ」という自分探し的な感覚を持っていたんだと思います。
宮川:その感覚は今も続いていますか?
松嶋:続いていますね。博物館の仕事をしていても、もちろん目の前の展覧会には一生懸命取り組むのですが、「自分は本当に何を目指しているのか」となると、それは別の話で。若い頃は、まだまだ自分は何者にでもなれると思っていたところがあるんですよ。世界の中心に自分がいる、というようなちょっと90年代のサブカルチャーっぽいというか。でも、だんだん歳を重ねてくると、時間的な限界や身体的、あるいは経済的な限界が見えてくるわけです。
そうなると、限りある人生の中で、自分の考え方や精神を手放すことなく社会とどう折り合いをつけるか、今ある社会に自分の考えをどう合致させられるか。そちらに知恵を絞ったほうが合理的なんじゃないか、と思うようになったんです。
宮川:そのような折り合いの付け方に手応えを感じ始めたのは、いつ頃からですか?
松嶋:はっきり意識したのは、2006〜2007年ぐらいですね。その頃、和紙に墨の質感を再現するような印刷技術や高精細な撮影技術など、印刷会社やメーカーが技術を進歩させていました。世界的に見ても非常にハイクオリティだったんです。
複製技術が飛躍的に向上し、専門家でも本物とコピーの区別がつかなくなってきました。化学的な分析をしないと判断できない、たとえばそういったレベル。高精細複製品の松林図屏風と原本をシャッフルして見せられたら、私でも見分けがつかないと思います。となると、形そのもの、視覚的な構造に意味があるのではないかと。
宮川:それは、アートの本質に触れる問いのような気がしますね。
松嶋:そうなんですよ。そこから「じゃあ、絵を動かしてみたらどうなるか」と思うようになって。日本の絵画って平面的だといわれがちですが、実は動いて見えるんです。たとえば、喜多川歌麿の「ポッピンを吹く娘」。あれ、女性がただ横を向いてポッピンを吹いているわけじゃないんです。振袖がまくれていますよね。つまり、進行方向を向いていた女性が後ろから呼びかけられて、パッと振り返った瞬間を描写しているんです。その動きの勢いで、振袖がひるがえっている。さらに、古典的な約束事から考えると、おそらく呼びかけた声の主は知っている男性で、女性はその声に心が奪われてポッピンを口にくわえたまま振り返ったんです。そのような心情まで読み取れるんですね。
こういう約束事、すなわちコードが日本絵画にはたくさん存在し、それが頭に入っていると、絵が自然に動いて見えてくる。でも、経験や知識がないと動いて見えません。だから私はその取っかかりをつくりたくて、絵を映像で動かすことを考えたんです。今は、プロジェクションマッピングや高精細映像、電子デバイスなどを活用したイマーシブな体験によって、動きを“感じられる”ようになってきた。一度その感覚を経験しさえすれば、ガラスケースの中に入っている本物の絵を見たときにも、自然と動きが見えてくると思うんです。そのような入り口を、テクノロジーが補ってくれる時代になったんですよね。
宮川:コードや約束事は“教養”と言い換えることもできると思うのですが、まさにイマーシブな体験を通じて美術に関する“教養”をアップデートするような試みをされてきたのですね。

◆間口の広さについて
宮川:松嶋さんは乃木坂46や細田守監督とのコラボレーションなど、すごく“間口が広い”アウトプットをされていますよね。そこにはどういう考えがあるんでしょうか?懐が深いなといつも感じていて。
松嶋:細田監督は大学時代の同級生で、約10年ぶりに恩師を介して再会したことがきっかけで「時をかける少女」で東京国立博物館を使ってもらいました。そのときに細田作品を見直してみたら、すごく感性が鋭いなと感じて。特に「見せ方」が欧米のアニメーションとはまったく違う。「あ、これ、日本絵画じゃないか?」って思ったんです。細田作品の特徴として、“異界”に行くんですよ。そしてその異界に入った瞬間に、輪郭線の色が変わる。意図的なのかどうかは分からなかったけれど、その表現手法は日本の絵画の伝統と共通するものがありました。よく浮世絵や絵巻がアニメの原点だといわれるのですが、それって単なる比喩じゃなくて、構造的に本当にそうなんだなと。
そうやって考えていくうちに、「ポップカルチャーが、古美術につながっている」という実感が生まれてきました。そして、現代の文化と古美術を接続することによって、自分の仕事をもっと多くの人に知ってもらう道筋ができるかもしれないと考えたのです。
宮川:「サマーウォーズ」でも電脳空間に入った瞬間にキャラクターの輪郭が赤くなりますよね。それを松嶋さんが「国宝の孔雀明王像と共通しています」って話されていて、もう、ぐっと深みに引き込まれてしまいました。
松嶋:古美術もアニメーションも、本来は“ファンタジー”の世界じゃないですか。ある意味、絵空事ですよね。そこに共感できるかどうかって、物語だけじゃなくて、視覚的な部分の力もすごく大きいと思います。でも、その世界にそもそも興味が向かない人だと、なかなか共感は生まれません。アニメですらそうなんですから、古美術なんてもっと間口が狭いですよね。だから、アニメや漫画などのポップカルチャーを入り口にして古美術に向き合うきっかけをつくることで、いっぺんに両方の世界へと視野を開かせることができるのではないかと思っているんです。

◆日本のポテンシャル
宮川:ここまで、日本の文化やアートが独自のコードや構造を持っていることを教えていただきましたが、改めて世界の中での日本の立ち位置や、日本のポテンシャルについてどうお考えですか?
松嶋:前提として、どんなクリエーションでも、ゼロから何かが生まれることはないと思っています。必ず前の世代のものをアレンジするか、そこを乗り越えようとする。私が専門とする江戸時代の絵画史もそうですが、以前の作品と比較して特色を見いだすのが美術史の第一段階です。それって実は、現代のポップカルチャーにも通じるものがある。同じ国に暮らし、同じ空気を吸い、同じ文化や暮らしの中からつくられたものは、時代が変わっても表現に“らしさ”が立ち現れるんです。
では日本らしさとは何かと考えると、日本って自然環境がものすごく過酷な土地ですよね。地震は一年中どこかで起きているし、山崩れや川の氾濫だって少なくない。何千年も前からずっとそうですよね。
だから日本人は、自然と共に暮らすしかなかった。自然をコントロールできるという感覚ではなく、自然とどう調和するかを常に考え、その感覚が信仰や文化の形をつくっていった。自然と一体化しようとするような想像力や概念の世界がものすごく発達してきたんです。
宮川:なるほど。アニミズムにも通じることのように感じますね。
松嶋:加えて、日本は物理的な資源にも乏しい国です。国土の面積だけでいえば本州だけでもヨーロッパの国と遜色ありませんが、山が多く、川もすぐ氾濫するので、住める場所が少ない。農業も大規模にできません。そのような土地で誰かが何かを独占してしまうと、もう人が住めなくなるんです。だからこそ、“分かち合い”が前提になってくる。歴史を振り返ってみても、日本で大規模な内乱は数えるほどしかないですよね。あとはみんな、どこかで落としどころを見つけながら、共存してきたんです。
困っている人がいたら助ける、自分に余裕があったら少し分け与える、困ったときは誰かに頼る。そういう“共助”の精神が、日本にはずっと息付いてきたんですね。江戸時代なんかはまさにそうで、国内総生産は決して高くなかったけれど、循環型社会が200年近くも成立していました。いわゆる持続可能性を大切にする価値観が、当たり前に日常の中に根付いていたんですよ。もちろん近代的な人権感覚はありませんでしたが。
そのように脈々と続いてきた精神は、今も変わらずに継承されていると思います。たとえばマンガやアニメーションにもそれは表れていて、ストーリーだけじゃなく、表現の手法そのものにもその精神性が宿っています。日本のアニメーターも技術が高まってくると、どうしても欧米的なリアリズムや描き込みに走りたくなる。その気持ちはすごく分かるのですが、日本のアニメが世界で評価されているのは、むしろ“他と違う手法”を確立しているからだと思うんです。その独自性があるからこそ、相対的に価値が上がるし、日本独特のものの考え方が、自然と伝わっていくんですよね。日本が見てきたもの、積み上げてきた知恵や思想を、世界にどう共有できるか。そのような役割の一助となることが文化にも求められていると思います。

◆仕事観
宮川:ポップカルチャーから日本人の自然観、精神性、所作の話にまで広がっていきましたが、こうしてうかがっていると、冒頭で松嶋さんが話されていたご自身の「働き方」や「興味の向け方」とも重なっているような気がします。何かをコントロールしようとするのではなくて、流れに身を任せるような姿勢。日本人が長い時間の中で培ってきた感覚と、松嶋さんの生き方が、自然にシンクロしているんだなと、改めて感じました。
松嶋:言われてみると、確かにそうかもしれませんね。あらがっていないというか、常に波に揺らいでいるような感覚です。私、クラゲが好きなんですよ。水の中でふわふわと漂っているじゃないですか。あれが理想なんですよね。常に自分が行きたい方向に行けるわけじゃないかもしれないけれど、流れに乗っているうちに思いがけない景色が見える。そういう生き方が、好きなんだと思います。
結局、自分が楽しいかどうかを優先しているし、何かを独占したいとか、人を押しのけてやりたいという気持ちもありません。それよりも、みんなが納得してくれたり、楽しんでくれたりしたほうが、生きやすいなって思うんです。組織の中で仕事をするのであれば、いろんな人がいるのだから、その人たちと協力したほうが絶対に早く進むし、楽しい。そのためには、みんなが「面白そうだな」と思ってくれるようにするほうが理にかなっている。だから、現実的なやり方としても、今話してきたことと辻褄が合っているんですよ。そういうスタンスで、今はすごくいいんじゃないかなと思ってます。
宮川:その「一緒にやろうよ」というスタンスは、組織論にもつながる気がします。
松嶋:すぐには理解されないことだってあります。みんなそれぞれに専門分野があるし、関心の対象も違う。私の進め方が全部伝わるなんて、最初から思っていません。でも、私たちの仕事って、医療や消防のように人の生き死にに直結するわけではない。だからこそ、好きにやったらいいと思ってるんです。この先、いきなり東京国立博物館がなくなるわけでもない。だったら、今やりたいこと、未来に向けて可能性があることをやってみたほうが、自分たちにとってもプラスになるんじゃないかなと、常々思っています。
宮川:僕も含めて、マーケティングや広告に携わる人間は、ついクライアントありきで物事を考えがちなんですが、数年前に松嶋さんから「結局、皆さんは何がしたいのですか?」と問いかけられたことがあって。それがずっと僕の中にはあります。「自分はどのような未来を望んでいるのか」を問われている気がしたんです。
松嶋:それはマーケティングや広告の仕事だけではなく、博物館も含めて共通して言えることだと思うんです。本来、枠や制限のないはずの場所が、いつのまにか“こうあるべき”みたいな前提に縛られてしまっている。でも今、世界中の博物館や美術館が変わろうとしています。さまざまな専門性はあれど、みんながミュージアムという場所は「プラットフォーム」だという考え方に向かっているんです。つまり、いろんな人が集まり、いろんな使われ方ができる場所。あるいは、そこで人と人が出会い、思いがけない何かが起こる場所。そういう“場づくり”が求められるようになってきました。
日本の美術館って、どこか“教科書的”な空間で、来館者もそれに慣れてしまっているのですが、本当はもっと多様であるべきだと思います。作品を前にして「私はこう思う」と、誰かと語り合ってもいい。すでに海外の美術館では、そういうやりとりが自然に起こっているケースもあります。東博の裏庭で日なたぼっこしてぼーっとしていてもいい。ルーヴル美術館だって、そうやって何時間もゆっくり過ごしている人、たくさんいますよね。何かに囲まれて静かに没入する時間って、すごく大事なんです。

◆ビジネスパーソンがアートに触れるということ
宮川:今おっしゃっていただいた話に通じるかもしれませんが、ビジネスパーソンがアートに触れることで、何か仕事や人生が豊かになるような感覚って、あると思うんですよね。ぜひ松嶋さんの視点から、その“楽しみ”について教えていただけますか。
松嶋:日本では、アートを見て、それが何の役に立つのか?というふうに、すぐ意味を求めたくなるところがあると思うんです。あるいは「これはこういう意図の作品だから、正しく理解しないといけない」というような、ある種の“脅迫観念”みたいなものがあるかもしれません。学校教育の影響によるところもあると思いますが、作品を自分で“感じる”というところにたどり着く前に、情報だけで完結してしまう。
でも、たとえば海外の方に日本の美術作品の魅力を聞かれたとき、検索すれば出てくるような情報よりも、この作品が自分にとってどういう意味を持ったのかを話すほうが、よっぽどその魅力が伝わると思うんですよ。「小さい頃にお母さんとこの作品を一緒に見に行って、すごく印象に残っている」とか、「自分の子どもとまた見に行きました」とか。そういう“物語”のほうが、相手の心に残りますよね。
宮川:その人の思い出や感情が含まれているほうが、聞いている人もぐっと引き込まれますよね。
松嶋:そうです。「ルーヴル美術館でモナリザの絵は人が多くてゆっくり見られなかったけれど、フェルメールの部屋は誰もいなくて、静かにじっくり見られて良かった」みたいな、そんなエピソードのほうが、その人の感性や人となりが伝わります。アートって、作品そのものよりも、それを見た人が「どう感じたか」「どう考えたか」のほうが、ずっと意味があるはずなんです。
宮川:アートが“答え”ではなくて、“問い”を引き出すものだとすれば、それってすごく重要な価値のような気がします。
松嶋:今は一般的な情報はAIが答えてくれる時代ですから。だからこそ、自分が作品に触れてどう感じたかという部分に価値を見いだしてほしいなと思います。歴史のある作品に触れて、その時代の空気を少しでも感じ取れたら、それだけで“時空を飛び越えた体験”になるかもしれない。先ほども申し上げたように、日本人って、そもそも空想や概念の世界で考えるのが得意な民族だと思うんです。そういう感覚を刺激することが、固定観念を壊すことや、新しい視点やアイデアを生み出すきっかけになるはず。
宮川:それって仕事や暮らしの中でも生きてきますよね。
松嶋:もちろんです。今はいろんな刺激や楽しみがあふれていますが、ただ刹那的に消費するだけではなく、「なんで自分はこれが好きなんだろう」とか、「この感覚はどこから来ているんだろう」とか、そういうところに思いを巡らせると、自分の“軸”が見えてくる。
たとえば、掃除が好きな人だったら、昔の道具を見ながら「この掃除道具って、なんでこの形なのか?」と考えていくと、その時代の暮らしや階級のあり方、四季の過ごし方にまで広がっていく。そういうものの考え方を今の自分の身の回りの物事に結び付けて、自分の“好き”が歴史や文化にリンクした瞬間って、すごく強い体験になる気がするんです。
宮川:好きなものを通して、自分の世界の解像度が上がっていくような感覚ですね。
松嶋:そうです。そのためのヒントは、博物館や美術館にたくさんあります。なにせ人類の知恵・営みの蓄積である文化財の宝庫なわけですから。もちろん、そのような合理的な目的がなくても、「最近ちょっと疲れたな」とか、「なんか楽しくないな」と思ったら、博物館や美術館にふらっと行って、何もしなくてもいい。ただぼーっと過ごすだけで、すごく癒やされることもありますから。歴史あるものに囲まれていると、自分の悩みなんて、ちっぽけに思えてくるんですよ。
宮川:松嶋さんはすごく長い時間軸で物事を考えていらっしゃるなぁ、といつも感じてしまいます。
松嶋:私たちは“歴史の途中”にいるだけなんですよ。そう思えば、自分の今の悩みも、そんなに大きな問題じゃないと捉えることができるかもしれません。人生に悩んだときに、ふらっと立ち寄るだけでもいい。そういう意味でも、人の暮らしに寄り添うプラットフォームでありたいなと思うんです。
宮川:歴史の途中にいるだけ――。その言葉に、ふっと肩の力が抜けたような気がします。博物館がそうした時間の流れを感じさせてくれる場所であり続けることに、大きな意味があるんだと改めて思いました。勇気の出るお話、ありがとうございました。

画像制作:岩下 智
この記事は参考になりましたか?
著者

松嶋 雅人
東京国立博物館
学芸企画部長
1966年、大阪市生まれ。東京国立博物館学芸企画部長。金沢美術工芸大学美術工芸学部美術科卒業、同大学大学院修士課程修了。その後東京藝術大学大学院博士後期課程に進み1997年単位取得満期退学。 日本近世から近代にかけての絵画史を中心に研究。著書に『あやしい美人画』(東京美術)、『細田守 ミライをひらく創作のひみつ』(美術出版社)『蔦屋重三郎と浮世絵 「歌麿美人」の謎を解く』(NHK出版)など。 展覧会企画に「没後400年 長谷川等伯」( 東京国立博物館・京都国立博物館、2010年)、「俺たちの国芳 わたしの国貞」(Bunkamura ザ・ミュージアム、2016年ほか)、「マルセル・デュシャンと⽇本美術」(東京国立博物館、2018年)、「横尾忠則 寒山百得展」(東京国立博物館、2023年・横尾忠則現代美術館、2024年)、「本阿弥光悦の大宇宙」(東京国立博物館、2024年)など。2025年4月に「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」(東京国立博物館)を企画。 またTNM&TOPPANミュージアムシアターでは、VR映像作品「風神雷神図のウラ -夏秋草図に秘めた想い-」(2018年)、「国宝 松林図屛風―乱世を生きた絵師・等伯―」(2020年)ほかを監修。細田守監督のアニメーション映画「時をかける少女」(2006年)の作中に登場する展覧会、同展をバーチャル空間で再現した「アノニマス-逸名の名画-」を監修。