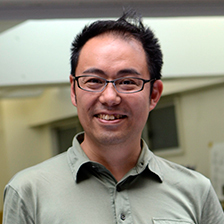2005年よりスタートし、今年100回を迎えたDentsu Design Talk。過去のトークセッションから厳選した内容を、順次1テーマを2回に分けてダイジェストで紹介していきます。
Dentsu Design Talkは毎週金曜日に更新予定です。
(企画プロデュース:電通人事局・金原亜紀 記事編集:菅付事務所 構成協力:小林英治)
<第1回 後編>
前編にひき続き、ゲストスピーカーに、博報堂イノベーションラボ、東京大学i.schoolディレクター(当時)の田村大氏を招き、イノベーションから考える広告会社の可能性について、白土謙二執行役員(当時)が聞き手となってトークが繰り広げられた。
多くの人がイノベーションの基本としているのが、「良いアイデアが新しい習慣や価値観や行動をつくる」という考え。田村氏はこの考えをProspective(前向き)なアプローチと呼び、それに対して、「先に理想の新しい習慣や価値観や行動が思い描かれ、その後にアイデアが生み出される」Retrospective(後ろ向き)なアプローチがあると述べた。田村氏の研究対象はこの「後ろ向きなアプローチ」であり、社会の現実を理解することで、どのように社会が変わっていくべきなのかを先に考え、そのビジョンや理念のシェアによって広がる共感の輪が、新しいムーブメントやマーケットそのものを創り出すことになるのだという。一連のAppleのイノベーションも実はこのタイプで、創業者・スティーブ・ジョブズは理想の世界の構想が明確にあり、その世界をどのように実現させていくかというアイデアがiPhoneやSiriだったといえる。
では、このようなイノベーションを実現するための現代的な戦略とは何だろうか? 田村氏は、「イノベーションは、結果的に社会にインパクトを与えなければ認められない宿命にある」という。科学技術を元にした20世紀型イノベーションでは、資本を中心に置いたスケールアップモデルを戦略とした。しかし、アメリカで発展したそのモデルの最たる金融イノベーションでは、結果的に勝者が富を独占する方向性を生み出すことになった。一方で、20世紀後半にイタリアのブラという町から始まったスローフード運動は、コンセプトのみを共有することで世界に大きな社会的インパクトを与えることができると実証した。田村氏は、このモデルが新しいイノベーションに成り得るのではないかと考える。つまり、ひとつひとつのプレイヤーは小さいが、何かひとつの強いコンセプトを持ち、ある社会的現実に対する共感を軸にして、お互いに連携しながら全体として新しいバリューを生み出すムーブメントを生み出すというものだ。
田村氏が東日本大震災の後に東京大学の学生の有志とともに行ってきた気仙沼市の復興支援では、技術や資材を提供することではなく、気仙沼の人々が世界の魅力的な地域と「丸」を描くように相互交流を進めながら新しい文化や産業を続々と育み、自らの未来を切り拓くことを目指した、プロジェクトMARUを立ち上げた。このように、こうした疲弊した地域にどのようにイノベーションの考え方を持ち込むかを考えた時、必要になるのは「夢をつくること」だという。この地域を出ていった若者が10年後に必ず戻ってきたい、何か面白いことがあると思わせるような、未来に向かって「開いている状態」をつくっていけるか。科学技術に夢を抱けなくなった現代においては、その夢をつくることこそが広告会社の役割、電通のスローガン「Good Innovation.」にもつながるのではないのかと。
それを受けて白土氏は、「オープンで、フラットで、ネットワークな社会である現代で、日本国内に限らずさまざまな人とひとつのプランに対してどのような組み合わせで取り組めば一番良いかを考えていくことが重要だ」と述べた。そして、そう考えた時に、「一業種多社(を扱う)という形態こそが日本で最も可能性があり、21世紀モデルになる」と示唆した。その上で、「イノベーションは何か?」と同じくらいに、「何がGoodなのか?」を改めて考えることも大事だと指摘。世界にとって、社会にとって、会社にとって、われわれ一人ひとりにとって、未来にとって、何がGoodなのか? そのことを全員が考えてみようとオーディエンスに呼びかけ、トークを締めくくった。