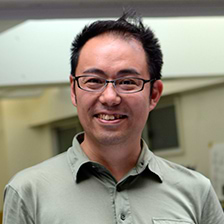角田陽一郎×中村洋基×朴正義×澤本嘉光 「明日のテレビをつくる」会議!(後編)
この記事は参考になりましたか?
バックナンバー
著者

角田 陽一郎
株式会社TBSテレビ
TBSテレビ プロデューサー/ディレクター/映画監督
1994年TBSテレビ入社以来、主にバラエティ番組の企画制作を手がける。現在は、いとうせいこう/ユースケ・サンタマリアMCの深夜トーク番組「オトナの!」プロデューサー。今年10月には初映画監督作品「げんげ」公開。 過去の主な番組 「さんまのスーパーからくりTV」「中居正広の金曜日のスマたちへ」「EXILE魂」深夜ミニドラマ「永沢君」

中村 洋基
PARTY
クリエーティブディレクター/ファウンダー
電通に入社後、初期はバナー広告で大量の作品をつくっていたが、その後、インタラクティブキャンペーンを主として手掛けるテクニカルディレクターとして活躍。 2011年、4人のメンバーとともにPARTYを設立。 人と人とのコミュニケーションに「遊びのルール・しくみ」をひとつ足すことで、単なる日常がエンターテインメントに変わる、という手法に興味を持つ。エンジニア出身であることから、プログラミングやデータが持つ面白さと、SNSなどのコミュニケーションを利用したアイデアを組み合わせてつくる、新しいエンターテインメントを模索している。国内外250以上の広告賞の受賞歴があり、審査員歴も多数。TOKYO FMのラジオ「澤本・権八のすぐに終わりますから。」毎週ゲストパーソナリティー。
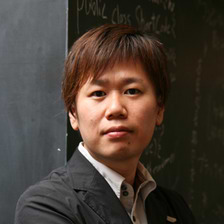
朴 正義
株式会社バスキュール
代表取締役/クリエーティブディレクター
株式会社HAROiD チーフクリエーティブオフィサー。 2000 年にバスキュールを設立後、15 年にわたりトヨタ、コカ・コーラ、ユニリーバ、ソニー、パナソニック、ポケモン、JRAなど、 数多くの企業やブランドのデジタルプロモーションの企画ディレクションを担当。これまでに担当した100以上のプロジェクトで、カンヌ、クリオ、One Show、ADC、Adfest、文化庁メディア芸術祭など、国内外のクリエーティブ賞を受賞。 ここ数年は、テレビ×ネットという領域で多くのチャレンジを行うとともに、既存の枠を飛び越える次世代クリエーターの育成活動であるBAPAに注力している。

澤本 嘉光
株式会社電通
CDC
エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター/CMプランナー
1966年、長崎市生まれ。1990年、東京大学文学部国文科卒業、電通に入社。ソフトバンクモバイル「ホワイト家族」、東京ガス「ガス・パッ・ チョ!」、家庭教師のトライ「ハイジ」など、次々と話題のテレビCMを制作し、乃木坂46、T.M.RevolutionなどのPVなども制作。著書に小説「おとうさんは同級生」、小説「犬と私の 10の約束」(ペンネーム=サイトウアカリ。映画脚本も担当。)、映画「ジャッジ!」の原作脚本や東方神起などの作詞も担当している。クリエイター・オブ・ ザ・イヤー(2000年、06年、08年)、カンヌ国際広告祭銀賞・銅賞、ADFEST(アジア太平洋広告祭)グランプリ、クリオ賞金賞・銀賞、TCC賞 グランプリ、ACCグランプリなど受賞多数。