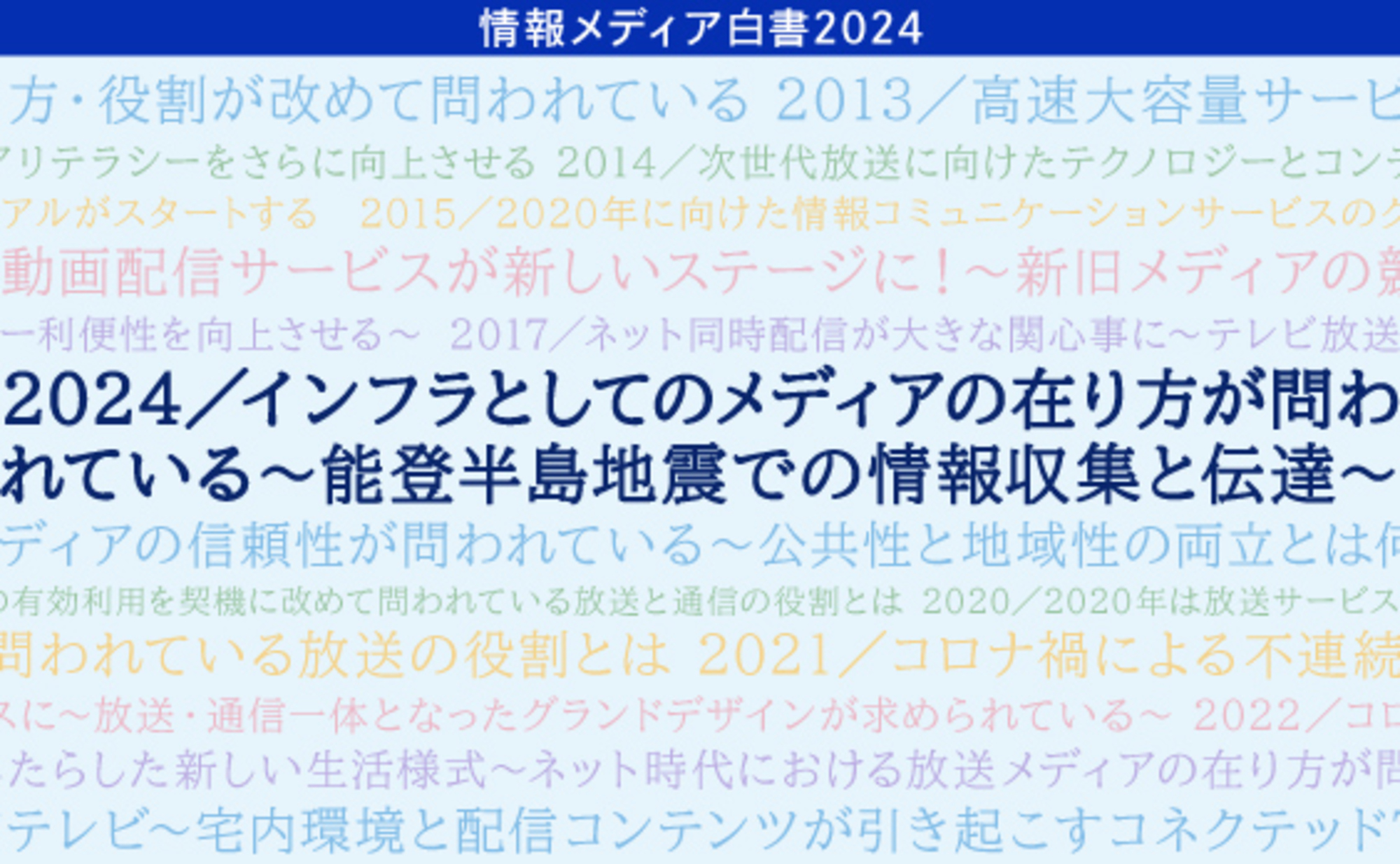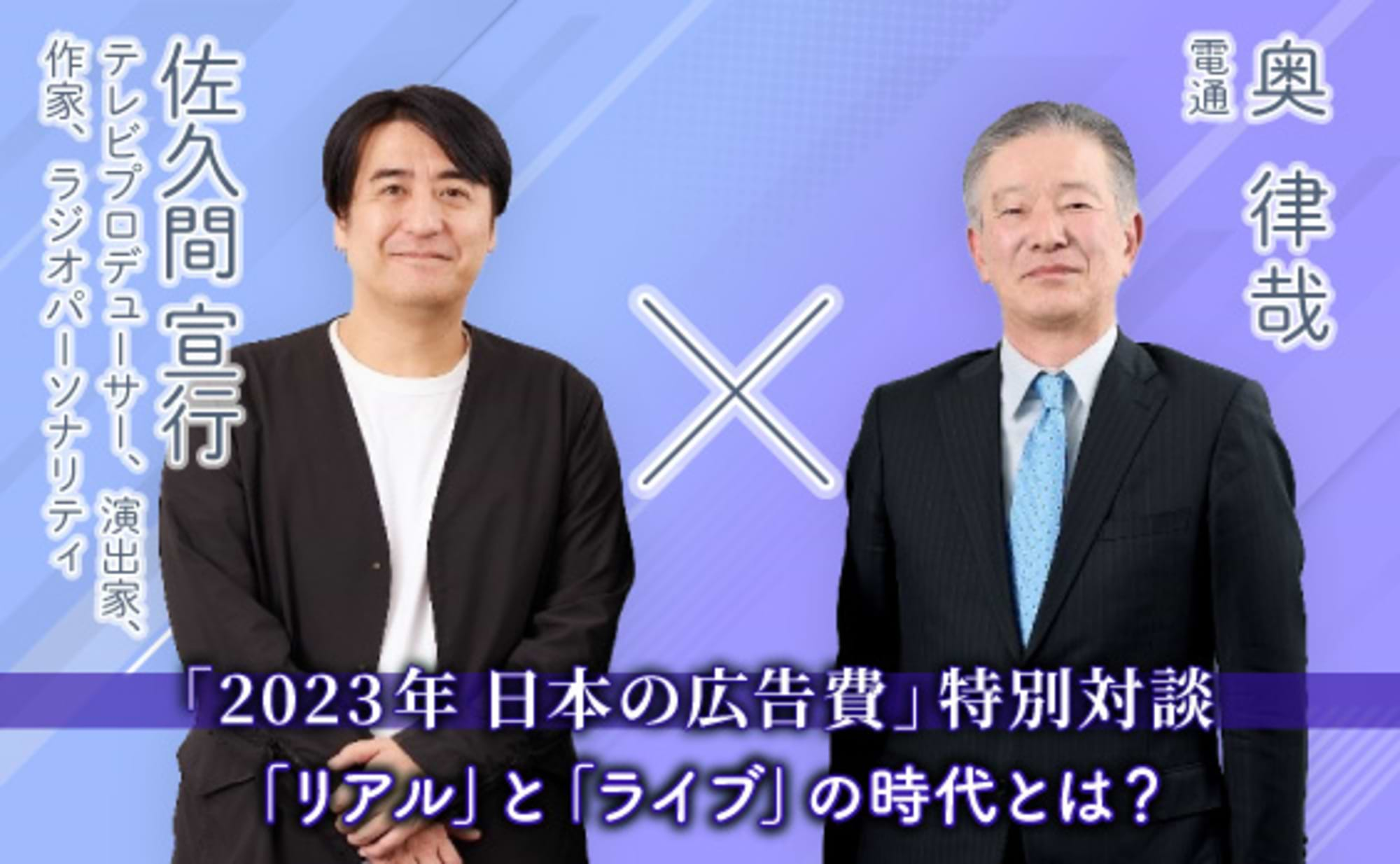スマホやタブレットPCなどスマートデバイスの浸透で、広告コミュニケーション・ビジネスにも地殻変動が起きている。ビジネス、オーディエンス、テクノロジーの視点から研究開発を行う電通総研・研究主席の奥律哉さんと、マスメディアとインターネット両方の業務に精通する電通デジタル・ビジネス局次長、植村祐嗣さんが4回にわたって、これからのメディアの展望と課題を語り合った。
横に拡散していくコミュニケーションの仕組みが必要
奥:マスメディアとネットメディアの連携・融合は、これまではマスの側がネットを使って双方向性をどう高めるかが課題とされてきました。でも、いま双方向性をいかんなく発揮しているのはネットユーザー同士で、テレビ放送を観て「あれはこうだよね」と興味を持った人同士の繋がりがソーシャルメディアでできたりする。そういう中でメディア側は情報発信をトリガーにして、ネットと連動したコミュニケーションをどうデザインしていくかが問われていますね。
植村:マスメディアの話題がソーシャルメディアの世界で広まると、リーチが広がるだけではなく、その各々の場所で話題がクラスター化して集中が起きる。そうなると、広告メディアとしてのビジネスもしやすくなってくるはずですよね。
奥:ただ、4大マスメディアの話題はトリガーにはなりやすいけど、視聴者への対応が必要になる。視聴者側はさらに突っ込んだ関心が生まれて、それをシェアする。それに対してメディア側がもう一回発信する情報の中身は、個々にカスタマイズされるのが理想ですが、なかなかそこまでは対応できない。
植村:放送局が準備したサイトやトピックスよりも、視聴者が勝手に、ソーシャルメディア上にまとめたものが面白かったりする。しかも、ネガティブではなくポジティブな流れができるので、ある程度ユーザー側にお任せしちゃってもいいのではないかという気もします。

奥:でも、広告はどうしてもメッセージを伝えなくてはいけないから、完全には割り切れない。難しいのは、クライアントが広告色を出しすぎると、コミュニケーションにならなくなる。企業のブログでも、担当している社員のキャラクターが前面に立つと人気も出るけど、その社員が人事異動で担当を外れたりすると、ユーザーが離れる場合もありますからね。
植村:法人として情報を発信していたとしても、法人としてのパーソナリティがないと支持されない。法人としてのペルソナづくりが本当に大切な時代になってきました。
奥:ジャーナリズムを背負ったマスメディアと、コミュニケーションが得意なSNSなどのネットメディアがどう重なっていくのか。あるいは役割を分けるのか。放送局などは、いろんな可能性を探りながら進めている印象はあります。
植村:現状は、放送局側もクライアント側も、番組ごとや商品カテゴリーごとにサイトやアプリを作ったりしていますが、消費者からみたら、番組も商品も全部、つながった一つのものなんですよね。好きなタレントは、局や番組を超えて観たいし、商品もメーカーを超えて比べたい。しかし、どうしても発信者側は横には広がらない。それを、何とか横に拡散していくプラットフォームなどの仕組みができないかと思うのですが。
奥:そういう仕組みがあると、ユーザーはいろんな情報がとれて、さらにコンテンツに触れたいという好循環が期待できる。視聴者や読者と情報の出会いの場であるマスメディアの機能と、さらに詳しく知ろうと思えば理解が深められるネットの機能、そのいいとこ取りですよね。そういう仕組みづくりが、ここ数年いっそう求められるのではないかと思います。
独自の領域・ユーザーへのリーチを

植村:ソーシャルメディアのいいところは、放送局や新聞社が発信したコンテンツや情報を、面白いと思ったら簡単に引用して、フェイスブックやツイッターで拡散していくところ。テレビでいえば、「このドラマが面白い」とつながっていく。しかも放映中に、スマホからリアルタイムで拡散する。それが視聴率に反映する。つまり、拡散した話題が放送局の広告ビジネスの場にちゃんと戻るわけですね。でも新聞の場合は、何か事件が起きてサイトに見に行っても、それで終わっちゃう。新聞社の広告ビジネスであるところの部数とか閲読数に貢献しない。その問題は、新聞社側もわれわれも考えなくてはいけないですね。
奥:テレビとネットへのリーチする層が増えれば、テレビだけ、ネットだけ閲覧する層も増えますよね。そこで僕は思うんですが、テレビオンリー層や、ネットオンリー層へのリーチは、将来的にもっと強化すべき流れになる気がします。植村さんは、海外の実情も詳しいですよね。そのへんの実態はどうですか。
植村:テレビとネットの融合や連携という点では、アメリカも今は決してうまくいってない。フェイスブック、ツイッター、グーグルなどのネットメディア業界と放送業界に距離があると感じます。人材のシャッフルもあまりない。結局、第三者が勝手に両方をつないでやっているのが現状です。向こうには、放送局の編成や制作にコミットしてたり、一方でフェイスブックやツイッターの媒体価値や機能向上にコミットしているエージェンシーもほとんどない。だから、メディア側から、どう連携させたらいいかという問い合わせがわれわれのもとにくる。
奥:なるほど。双方をつなぐ必要があるわけですね。
〔 次回へ続く 〕