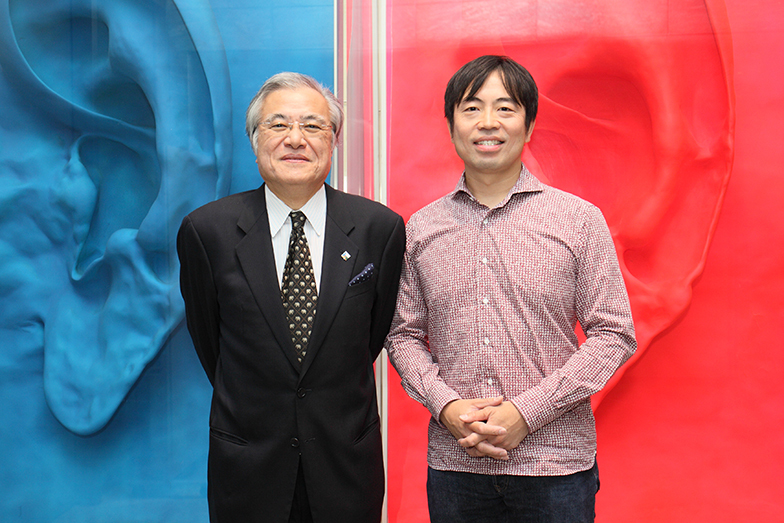彫刻家の名和晃平さんは、彫刻作品のみならず、様々なテクスチャーの素材開発、3Dプリントなど新しいテクノロジーでのエンジニアリング、建築などの空間設計のディレクションや個々のアートワークなど、表現領域を拡張してきた。近年、日本でも「コミッションワーク(委託制作)」と呼ばれる、企業とアートの新しい協働が生まれ始めているが、名和さんはその分野でも活躍している。これまで、アートは企業(ビジネス)と常に反発し、時には連携し、刺激や影響を受け合ってきた。今回は、コミッションワークのプロデュースを行う編集者の後藤繁雄さん、安川電機100周年の仕事を通して、名和さんと共にアート作品制作を企画した電通の阿部光史さんと3人で、未来のアートコラボレーションを語り合う。その後編をお届けする。

(左より)阿部氏、名和氏、後藤氏
TOKYO2020の演出プランを
アーティストから提案する
後藤:名和くんはアートを発展させて建築やデザインに取り組む一方で、オリンピックや都市構想のプレゼンテーションも積極的にしています。オリンピックは、スポーツの祭典であると同時に文化の祭典でもある。グローバルに日本が出していくビジョンやミッションを、アートやアーティストの力を使いながら予感させたり、世界に発信する場になります。
名和:「東京キャラバン」は、東京都のプロジェクトで、野田秀樹さんや日比野克彦さんと一緒に取り組んでいるオリンピックのためのリーディングプロジェクトです。昨年、駒沢公園で1000人前後のお客さんを招待して開催したワークショップでは、演者と観客がフラットな状態になれる時間であるという考えからお客さんが舞台裏を見られるような会場を作り、その真ん中に彫刻を置いて実施しました。
磯崎新さんと妹島和世さんと共に考えた「東京祝祭都市構想」は首都の広場を考え直して、2020年のオリンピックのタイミングに皇居前広場で人類の祝祭の歴史が更新されるくらいの巨大祭典を行い、新しい都市「東京」を全世界に宣言する提案です。
祝祭都市構想で僕は「宇宙花火」の案を出しました。金属の球を成層圏外から落とすプランです。球は燃えながら落ちてきて、炎色反応で花火のように見えます。競技場だけでなく、日本全体から見える花火になるかもしれません。
アン・ハミルトンの作品で、僕がとても好きな作品があるので、紹介させてください。テクノロジーを一切使っていない、ワイヤーと布だけのインスタレーションです。大きな空間の真ん中に巨大な布が壁のように下されていて、無数のワイヤーに接続されています。人が布を触ると、ワイヤーが引っ張られて布の形が変わる。これは時代に対するメッセージかなと思うんです。グローバルの時代になり、みんな緩やかにつながっていて、メッセージはふわっと反映されていく。だけどまだ、もやもやとした壁はあるんだよと。こういう新しい広場が今の時代に求められているのではないか。最先端技術を使わなくても、古い場所や伝統的な表現を使っても作れるんじゃないかと思います。
阿部:圧倒的なクリエーションとアイデアの数ですね…。名和さんにとってコミッションワークは、創作活動とどう分けているんですか?
名和:作りたいものやアイデアは常にたくさんあるけれど、それが作りきれていない状況です。だからコミッションワークは、出されたお題の答えを一から考えるというより、あのアイデアならコンセプトが合うんじゃないか、と考えていくことが多いです。
時代とダイナミックにつながるのが
コンテンポラリーアートの最大の魅力
後藤:ここまでの話で、名和くんは今までのアーティストと違う、と思った方は会場にもたくさんいると思います。今は、会社もアーティストも両方変化している。だから、変化する者同士の幸福な出会いをプロデュースするのが、自分の仕事です。
阿部:後藤さんから見て、日本社会でアートの需要は増えていると思いますか?
後藤:アートは“会社の社会的価値を上げるもの”という認識が生まれてきていると思います。特に安川電機のようなグローバル企業は、世界中の顧客に向けてステートメントをビジュアライズして示す必要がある。そうしたノンバーバルなコミュニケーションにおいて、アートはとても強い。カッコいいアートを置けばいいのではなく、名和くんが話したように、参加できて、生命や絆といったものを広げてくれたり、新しいアイデアを企業にもたらすものとして認識することが重要だと思います。
名和:現代美術は生ものです。今同じ空気を吸っていることがコンテンポラリーということであり、世の中で起きていることや都市を歩いていてふっと感じるようなことがアートの中で花開く。時代にダイナミックにコミットすることが、コンテンポラリーアートの一番スリリングで面白いところです。そのアーティストに実際に会うこともできるし、一緒に作ることだってできる。美術館にあるアートだけがアートとは限りません。人々の中にアートの種があり、それがどうやって実を結ぶかです。それをわかっているアーティストが、今活躍しているのではないかと思います。
阿部:広告もまた、企業がたくさん持つ世の中とのリンクのひとつです。商品ではないところで企業の考えや同時代感を、アーティストを介して表現していくようになるのかなと感じました。
後藤:最近では、企業に「グラフィックデザイナーではなくアーティストにデザインをしてほしい」と言われることもあります。極端な話、「デザイナーは上辺をつくる人」だと思われていて、アーティストの思考の深さに期待が寄せられている。企業には、アーティストの価値観に惚れ込んで、コミッションワークだけでなく、パトロンとなって、様々な形で協業もする…というように、アーティストの活動を末永くサポートしてほしいと思います。
名和:デザイナーも建築家もそうですが、クライアント志向で行う仕事は、表現に問題がないようにソフトランディングするクセが出やすい。よく建築家がアーティストとコラボレーションしたがるのは、クライアントや建築のルールを無視して、アーティストが勝手なことを言い出すからです。それがいいんです。ルールが一気に破壊されて、表現のジャンプが起きて、建築家がやりたいのにできなかったことにトライするチャンスが生まれますから。大阪万博のパビリオンに《太陽の塔》を作った丹下健三さんと岡本太郎さんの関係がまさにそうで、そこがアーティストとのコラボレーションの一番面白いところだと思います。
後藤:アーティストと組みたいというクライアントにいつも言うのは、「アートは太陽と一緒で、離れていると暖かいけど、近づくと焼け死にますよ」、と(笑)。そこを理解すれば、企業はアーティストのエネルギーをうまく使えます。
名和:アーティストはその時代の表現を直観的に感じていて、そこに真実味がある。企業の方にはそこを見抜いていただきたい。コマーシャルの仕事をやり続けると、クライアントの要望に合わせてデザイン的な処理をするのが癖になる。それはアーティストにとって危険なことです。今を生きて、心の奥にある真実味がどろっと出てくる人がたまにいます。そういう人に、ちゃんとその時代の何かを残させることが大事だと思います。
後藤:先ほどのドローンによる空中彫刻など、パフォーマティブなことをたくさんの人に経験させること自体が、アーティストにとって新しいメディアになる。企業は、現代アートは難しくて高いと思わずに、そういう機会をたくさん作っていただきたい。
名和:安川電機のプロジェクトも、僕はまだ終わっていないと思っています。エントランスに彫刻を作っただけでは、普通のお仕事で終わってしまう。例えば、安川のロボットアームを使って作品を作るなど、次のプロジェクトを考えていきたい。
阿部:安川電機以外にも、企業がアーティストと協業するチャンスはまだまだ広がると思います。そういった仕事に今後もチャレンジしていきます。
こちらアドタイでも対談を読めます!
企画プロデュース:電通イベント&スペース・デザイン局 金原亜紀