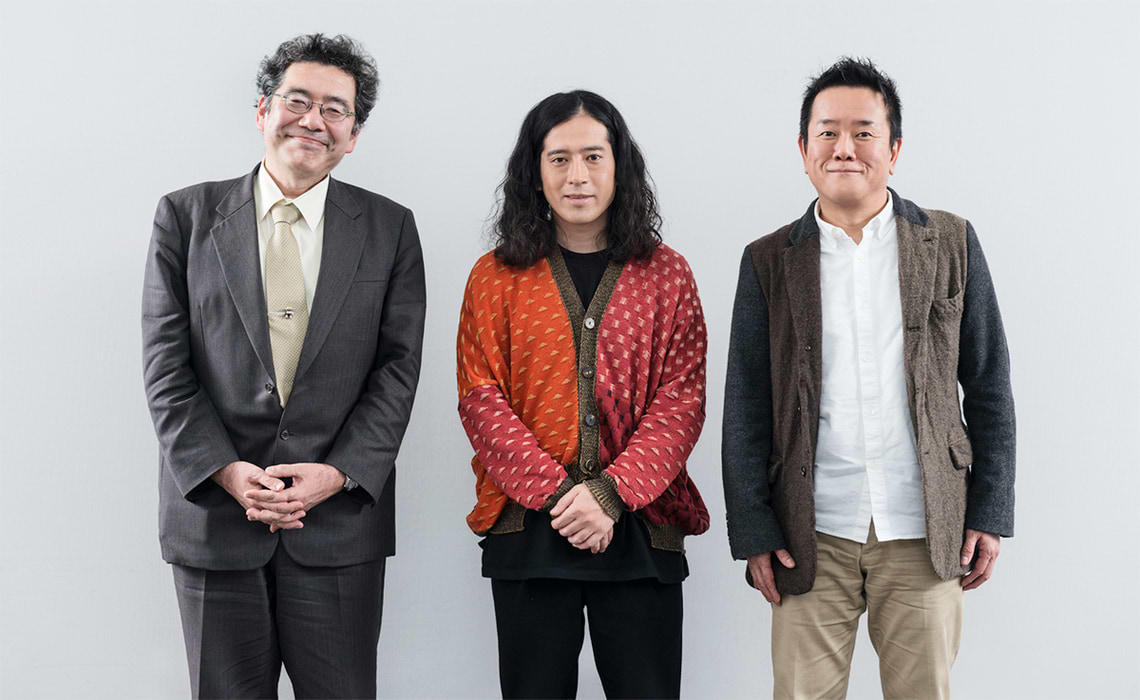AIの特徴はランダム力。人間の創造性を高める期待も?
吉崎:AIの創作研究は他分野でも進んでいますよね。例えば音楽では、コンピューターの作曲とバッハの作品を聞かせて、どちらがバッハの曲かアンケートを取る。すると、コンピューターの書いた作品を「バッハの曲」と答える人が多かったという結果も出たりします。
松原:詩などの研究も進んでいて、過去の有名な詩のワードをたくさんインプットし、その中からコンピューターに組み合わせを任せる。すると、千に一つくらいは「おおっ」というものができます。音楽や詩は小説などより選択肢が少ないので、ランダムに選んでも成立しやすいし、「前衛的」といえば評価できないこともない。
又吉:もしコンピューターがランダムに言葉を選んで俳句や詩をつくったとして、ちゃんとした作品は少ないかもしれないですけど、一見微妙な作品も、作家が創作するヒントにはなりそうですよね。「あ、このワードとこのワードをぶつけて整えたら作品になる」とひらめいたり。そもそも全然違う単語をランダムに持ってきて発想するのは、人間が苦手な作業だと思うんです。無関係なものを持ってくる勇気ってないですから。何か意味を持たせてしまうというか。
松原:又吉さんがおっしゃるように、人間の創造性を高めるというか、補完するようにAIが働くというのは、ひとつのあるべき姿なのかなとは思いますね。
吉崎:又吉さんは、そういう形でAIが手伝うことについてどんなイメージを持ちますか。書いているときにAIが選択肢を出したらちょっと助かるとか。
又吉:選択肢を出してくれたら絶対助かるでしょうね。でも、アイデアを出す方法は、作家の方や芸人って独自に手に入れていると思うんです。新聞を読んでみるとか、辞書を開いて引っ掛かる単語を探すとか。それってアイデアのヒント探しですよね。作家の方がよく散歩するというのも同じで、音が聞こえたり、季節を感じたり、疲れてきたり、変化が起きるから、その変化に対する自分の反応として、いろんな発想が出てくるんでしょう。
吉崎:辞書を開いてみるのとコンピューターがランダムにワードを選ぶのはちょっと似ていますけど、作家の体が伴っているかどうかという違いがあるのでしょうね。
松原:多分そこが、作家の身体性というか特徴が作品に反映されるところで、何らかの変化からアイデアを考えても、やはり作家の作風や統一感が維持されている。一方で、AIは良くも悪くも本当にランダムなものを持ってくる。それが先ほどいった「ズレ」につながるのでしょう。
吉崎:人間には身体性があり、AIはランダム力がある。これは両者の明らかな違いといえそうですが、又吉さんとしては、ランダムの得意なAIが小説の世界に入ってくることには、嫌な感じはしないということでしょうか。
又吉:僕は本を読むのがすごく好きなので、むちゃくちゃ面白い物語ができて、それがAI小説だと聞いたら絶対読みます。興味があるし。極端な話、途中までめっちゃ面白くて、最後の50ページくらいが「あれ、これ夏目漱石の作品とまるまる一緒や」とか。そんなズレのある小説も面白いじゃないですか。もちろんそれは問題になるんですけど(笑)。いずれにせよ、僕はAI小説を読んでみたいと思いますね。