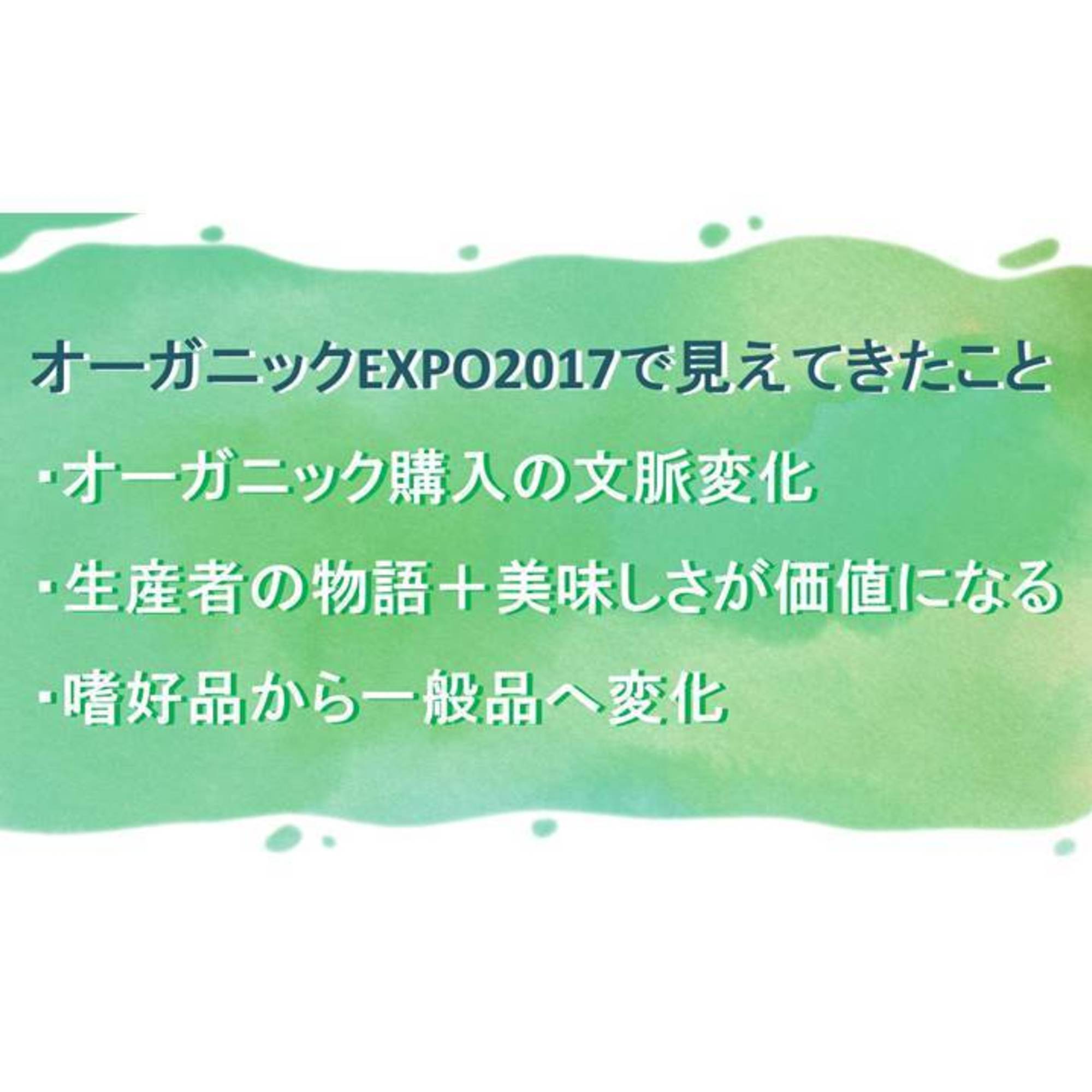8月24~26日に、パシフィコ横浜で行われた「国際オーガニックEXPO2017」に行ってきました。農家がつなぐ物語を探しに、販売+αの価値を生む情報収集の場「オーガニックマルシェ」や、日本の有機のお酒が一堂に会す初めての試み「BioSAKEヴィレッジ」で生産者の方を直撃インタビュー。その様子をお届けします。
「会う、食べる、話を聞く」農業体験
EXPO会場に入ると展示会ではなく、マルシェが開催されていました。
「物語があっても、それが生産者から流通、消費者へとつながらないと価値は生まれません。お互いをつなぐ場が必要なのです」
そう語るのは、オーガニック食材・加工品で埋め尽くされたマルシェを企画した、オーガニックヴィレッジジャパン(OVJ)、季刊「ORGANICVISION」編集長山口タカさんです。
「生産者と流通、消費者がつながるための場づくりには、二つの要素が必要です。①おいしいモノをそろえ、心地いい空間をつくる。②お互いの顔が見える関係をつくる。今回のマルシェでは、ここに気を使いました」。
山口さんに教えてもらい、農家が持つ物語を伝えるには、物語だけでなく「おいしい!」も感じてもらう必要があり、両方があって、初めてお互いがつながる、ということが分かりました。

「おいしい商品と楽しい物語と出そろうと、必然的に商談が始まります」。マルシェというとto Cが通常ですが、今回の企画はデパートやスーパー、商社といったto Bがメイン。to Bマルシェをやってみたら、商談に至るまでの時間が短く、その数も多く「間違いなく、オーガニックの需要は大きくなっている」と感じたそうです。
さらにオーガニック需要は、量もさることながら、その質も変化が出てきているそうです。
「今までは、自分の美容や家族の健康のため、という文脈でオーガニックを購入する傾向が強かったと思います。しかし最近は『地球環境や持続可能な農業のため』という文脈でオーガニックを購入する方が増えている。つまり利己的オーガニックから利他的オーガニックへ変化しているんです」
特に、若い人にその傾向が見えるそう。山口さんはその要因を、若い人が受けてきた環境教育にあると考えます。「利他的オーガニックにおいて、農家の物語はますます豊かになりますし、その果たす役割はますます大きくなります」
山口さんの話を聞き、早速会場にいる生産者にお話を伺うことにしました。
甘い「薬石リンゴ」は腰痛がきっかけで生まれた!?
青森県で留目昌明さんが栽培しているリンゴ「薬石リンゴ」で作ったジュースは、飲んでみると子供用の風邪シロップのような甘みがしました。風邪薬の苦みを消すための甘みでなく、リンゴそのものから出た甘すぎない甘み。どうやってこの甘みが出るか、留目さんに聞いてみた。
「人間の大腸が喜ぶことを、リンゴの樹の根っこに施しています」。
人が喜ぶことをリンゴにしてあげる?
「学生時代患った腰痛をきっかけに学んだ鍼灸で人間の体の構造を研究した時、人の体もリンゴの樹も一緒だと気付きました」。
水分とミネラルを吸収する構造は、人間の大腸もリンゴの根も一緒だそう。
「ミネラル豊富な土壌から作ったリンゴは、一番端の枝先に実ったリンゴまで甘さが行き渡ります」。留目さんが栽培したリンゴの甘みの秘密は、土にミネラルをあげること。東洋医学と農学の両方を学んだ留目さんだからこそ考えついたのです。

「龍の瞳」の物語はミミズから始まりました
岐阜県下呂市で今井隆さんが2000年に偶然発見して、こだわりの栽培方法で作付面積を伸ばしてきた玄米「龍の瞳」は、もちもちっとした歯ごたえで、玄米の荒々しい味といより繊細な和菓子を食べているよう。
「『龍の瞳』は、突然変異でできた米なんですよ」
農水省内で統計官として働いていた今井さんは、おいしい米の品種を探していた。ある日、田んぼの中で周りの稲よりもずっしりと高く伸びた稲穂にオーラを感じ、大切に種を増やして2002年に炊いて食べてみたら、とんでもなくおいしいお米だったそう。
今井さんと「龍の瞳」の物語は、ミミズから始まったという。今井さんが20代のころ、いもち病と害虫の消毒を終えた帰路、ふと田んぼを見ると、大きなミミズが苦しそうにのたうち回っている姿を見たそう。それ以降、農薬を減らして日本の農業が昔から大切にしてきた安全で自然にやさしい米づくりができないか、今井さんはオーガニックの研究を始めました。
「気が付くと、ミジンコやらホタルやらクモ、トンボ、カエルやらで田んぼが賑やかになってしまって。コナギなどたくさんの雑草が生えるようになりましたけどね。食べても美味しいですよ。私は、野菜や山菜のように田に生える食べられる雑草を『田菜』(でんさい)として販売していくのが夢です」
その豊かな想像力と実行力を拝見し、今井さんは突然変異した農家なのではないか、と思ってしまいました。

オーガニックの日本酒に注目が集まっている
今井さんは、「龍の瞳」から、焼酎・どぶろく・日本酒・各種レトルト、雑穀、発芽玄米、米せんべいなどさまざまな加工品製造にもチャレンジしていて、出店ブースは、日本酒を販売しているコーナーにありました。OVJ山口さんから、最近オーガニックの日本酒に注目が集まっていると聞きました。最近の日本酒人気は知っているし、日本酒といえば純米吟醸でしょう、くらいも知っていますが、オーガニック日本酒は知らなかった。
「先進的な酒蔵は、その先を見据え、オーガニック志向の日本酒を製造・販売し始めています。自社酒の付加価値向上という目的だけでなく、『環境保全・地方創生』といった含意もあるようです。このように、地元の自然や農家から紡がれる物語が、オーガニック日本酒への取り組みへと酒蔵のハートを突き動かすのです」。
生産者の物語がオーガニックのポテンシャルを引き出し、マーケットやネットワークの無かったオーガニック日本酒「BioSAKE」の市場を動かしています。
世界の潮流となっている“分かち合い(シェア)”の考え方
「オーガニック白書2016」によると、無農薬・無化学肥料・無添加の国内食品市場は、381.4億円と算定されています。食品市場全体から見るとわずかなシェアです。しかし、2020東京オリパラや地方創生の文脈の中で、食市場のオーガニックに対する関心は高まってきています。
「オーガニックへの意識というより、世界中で“分かち合い(シェア)”という考えが広がっていることが大きいです」とOVJ山口さんは強調する。
「家族だけでない周りの人、地球のこと、自然のこと、自分や家族に向けてきた目が、Social(社会)やFuture(将来)など、もっと全体像を見ようとする意識が多くの人に芽生えてきています」。
何がきっかけなのだろう。
「食のことでいえば、ここ10~20年、草の根的に進めてきた食育や環境教育が、マーケットではなく消費者の意識の上で発酵してきていることにあると思います。それが、今度はマーケットにおいても発酵しようとしているのではないでしょうか」。
当たり前にオーガニック、気が付いたらオーガニック
「“嗜好品”から“一般品”へ」。ORGANIC SHIFTは間違いなく起こっており、それは、「オーガニック」という言葉がなくなる方向に行くのだ、と感じました。
われわれの食は、ことさらオーガニックを叫ぶわけでなく、当たり前にオーガニック、気が付いたらオーガニック、ということになるということ。
「そのためには、より正確にオーガニック市場の動向を観察し、そして消費者だけでなく、流通も今一度、食育を見つめ直すことが大切です」とOVJ山口さんは語ります。to C向けの食育から、to E 、 to B向けの食育へと進化していく必要があります。
取材を通じて、「食材のおいしさ」と「農家の物語」は、これからのわれわれの食や暮らしに重要な役割を果たすと感じました。両方とも食卓にのせた時、食卓には会話が生まれます。会話のある食卓は、きっと人々を幸せにします。だから、食卓に農をのせよう。
この記事は参考になりましたか?
著者

杉村 慶明
株式会社電通
CDC
事業開発ディレクター
1998年電通入社。現在は、本社CDC Future Business Tech Teamに所属。事業開発アイディアを核に、ITからバイオテクノロジーまで、さまざまな先端技術を活用して社会的課題を解決する取り組みにチャレンジしている。