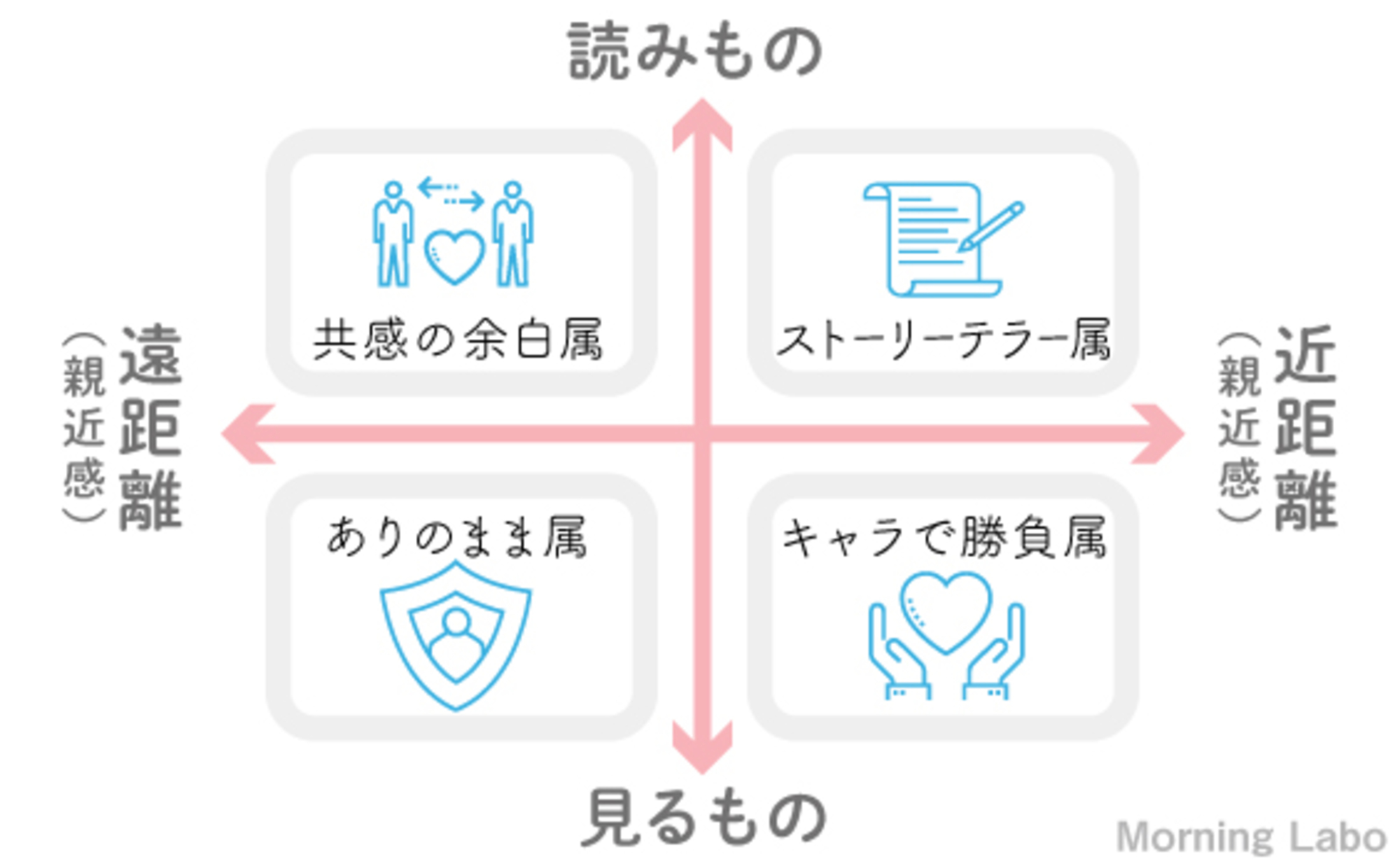前回に引き続き、シェアをキーワードに現代のメディア環境を立命館大学産業社会学部准教授の飯田豊先生と電通メディアイノベーションラボの天野彬で考察していきます。
前半は「シェアとイベント」にフォーカスした内容となりましたが、後半ではよりインターネット上の映像カルチャーに的を絞って議論を交わします。
ライブストリーミングと「テレビ」カルチャーの連続性
飯田:著書の中で、天野さんは、「マス型」「インフルエンサー型」「シミュラークル型」という三つの型が、単線的に移り変わっていくわけではないことに注意を促しています。
当たり前のことですが、プロがUGC(ユーザー生成コンテンツ)のプラットフォームに参入することで、牧歌的だったアマチュアのコミュニケーションが周縁化してしまう半面、それによってプロフェッショナリズムの在り方自体も変容せざるを得ないんですよね。ネットの動画文化が、アイドル業界やゲーム業界に与えた影響は計り知れませんし、これまで放送が担ってきた役割との境界もあいまいになってきました。
ライブ配信のプラットフォームのひとつに「SHOWROOM」がありますが、近年はAKB総選挙ともタイアップしているように、長年にわたってテレビが培っていたリアリティー番組との親和性が高いですね。ライブ動画の視聴者を「リスナー」と呼ぶことが定着しているのも、ラジオが培ってきた擬似的な双方向性を継承しているからに他なりません。
また、ビデオゲームのプレー画面を、解説や雑談を交えて楽しむゲーム実況は、日本に限らず世界中で白熱しています。動画サイトで若年層になじみがある著名な実況者は、ゲームイベントで多くの観衆を集めます。しかしゲーム実況は決して、UGCのプラットフォームで自生した文化とはいえません。
日本のゲーム実況は、遅くとも1990年代から複数のゲームセンターで行われていましたし、2003年に始まったフジテレビCS放送の人気ゲームバラエティー番組「ゲームセンターCX」から多大な影響を受けています。
僕が子どものころには、ビデオゲームを主題的に扱う番組は地上波にもありましたが、今ではすっかりなくなってしまいました。テレビ(=マス型)に見限られつつあった周縁的な事物が、ネット動画文化(=インフルエンサー型)の中心に反転したように見えます。
天野:昨今盛り上がりつつあるライブ配信文化のリサーチも進めているのですが、ラジオが培ってきたコミュニケーション作法の継承など、改めて意識して首肯しました。そのような日本特有のメディア文化の経路依存性の問題は、新しいメディアがどんどん生まれている今こそ問われるべきテーマですね。
飯田先生はテレビの文化史もご専門にされていますが、そのような視点から、最近のYouTuber的な映像コンテンツやAbemaTVのような新しいテレビ的なコンテンツの在り方をどのように見ていますか? テレビ的な文化や方法論の継承線もそこにはうっすらと見いだされるようにも思うんです。
飯田:「新しいテレビ的なコンテンツ」とおっしゃる通り、今では「テレビ」はもとより、「放送」や「視聴者」といった概念が軒並み自明性を失っているわけで、電波を介して放送されている/いないという差異は、ほとんど意味がないですよね。
僕は『テレビが見世物だったころ』(青弓社、2016年)という本の中で、テレビジョン技術の考古学的研究を通じて、「テレビ」と「放送」は元来、必ずしも不可分なものではないことを指摘しました。こうした長期的な歴史観に立てば、YouTubeやAbemaTVなど、放送法上の放送局に含まれない映像配信事業も、大局的には「テレビ」と地続きです。
社会学者の加藤秀俊さんは今から半世紀以上前、『見世物からテレビへ』(岩波新書、1965年)という本の中で、見世物をはじめ、影絵や写し絵、パノラマや絵はがき、紙芝居や活弁といった視聴覚文化の伝統が放送文化に継承されていることを多角的に論じました。
また、批評家のマーシャル・マクルーハンさんも、人間は全く新しい状況に直面すると、一番近い過去の事物や様式にしがみつくものだと言いました。われわれはバックミラー越しに現在を見て、未来に向かって後ろ向きに進んでいるというわけです。マクルーハンが活躍した60年代、成熟期を迎えていたテレビが、映画や演劇の世界から多くのことを学んでいたように、新しい技術の中には必ず、一つ前のメディアの特性が組み込まれていきます。
先に挙げたとおり、長年テレビによって培われてきた番組文化や放送文化は、その姿を変えながらも、多くの部分がインターネットに受け継がれています。広告業界の論理もそうでしょう。インターネットの歴史の中で、さまざまなウェブサービスの「マスメディア化」がたびたび指摘されるのも、無理のないことだと思います。
このように言うと、かなり保守的に受け止められるかもしれませんが、天野さんの言葉を借りれば、「文化や方法論の継承線」こそが新しい技術やメディアの強度につながり、それとの比較を通じて、初めて真の「新しさ」を評価できるのだと考えています。
私たちはメディア的な「オムニボア」である
天野:「バックミラー越しに現在を見て、未来に向かって後ろ向きに進んでいる」という表現はとても興味深いですね!
また、おっしゃっているようなメディアの連続性の視点は、テクノロジーが一気に新しくなったとしても、オーディエンスはそのスピードとは異なる受容の仕方をするという捉え直し方もできるでしょうか。かつてインターネットがあらゆる情報メディアを駆逐してしまうだろうという言説がありましたが、現実にはそうはなっておらず、さまざまなメディアが併存し続けています。
その意味で、私たちはメディア論的にオムニボア(雑食性)な存在なのかもしれません。
ここまでの議論を振り返りながら伺い直してみたいのは、YouTubeやAbemaTVなど放送法上の放送局に含まれない映像配信事業も大局的には「テレビ」であるという論点を提出いただきましたが、その一方でこうしたプラットフォームはインターネット上でのシェアを通じて広がっていく側面もあると思っています。本当に感動したコンテンツ、人に教えたくなるコンテンツをユーザーはシェアするからです。
そのとき、シェアはマスメディアとは異なる同時性を伴うという先のご指摘との兼ね合いが大変興味深いと感じました。このあたりに、新しい映像プラットフォームの性格を考えるためのひとつのヒントがあるのではないでしょうか。
飯田:AbemaTVの場合、Twitterとの連携機能や相性の良さということはありますが、地上波のテレビと全く同じように、出演者の発言や番組のスクショがSNSで拡散したり、ネットニュースやまとめサイトにピックアップされたり、時には出演者の失言が炎上することがありますよね。どちらもSNSで共有されるネタの補給源になっていることに目を向けると、AbemaTVは「テレビ」をうたっているから当然なのですが、シェアという観点から見ても、従来のテレビにかなり近いなという印象を持っています。
ただし、老舗のテレビ放送の方は、「今朝の◯◯新聞によれば…」「…と、明日発売の週刊◯◯が報じている」といった引用表現が満ちあふれています。新聞各紙の紙面をなぞりながら記事を読み上げているのは、すっかり見慣れた光景ですよね。番組それ自体が生放送であったとしても、19世紀に大衆化した出版の時間性とも不可分に結びついていて、これもまた一番近い過去の事物にしがみついているわけです。そういう結びつきが少ない分だけ、AbemaTVやYouTubeの方がある意味、純粋な「テレビ」に近いという見方さえできるかもしれませんね。
AbemaTVが映像業界や広告業界にとって新しいプラットフォームでも、多くの生活者にはあくまで「マス型」のメディアの一つとして受け止められています。一方で、むしろYouTubeは、生活者自身のメディア化に寄与しているプラットフォームという意味でも、テレビに比べると、情報拡散の構造が複雑化しているように思います。
いずれにしても、あるプラットフォーム上で、あるいはSNSを媒介して人々が同期している、あるいは疑似同期しているということがいえるとして、それがいったい何を達成しているのかを考えることが、重要だと思います。「異なる同期性」というのはそういう意味です。
「はかなさ」をメディアにどう実装するか
飯田:このことを考えるに当たって、本書のキーワードの一つである「エフェメラル」というのは、メディア論的にとても奥が深い言葉です。
長期的に使われることなく、保存されずにはかなく消えていく一枚刷りの印刷物のことを「エフェメラ」と呼びます。具体的にはビラ、パンフレット、壁新聞、同人誌などを指します。戦時宣伝の研究などにおいては、こうしたエフェメラが、大衆動員の手段として大きな影響力が持っていたことが指摘されています。いわゆる強力効果論(本来はマスメディアに対して、その直接的、即行的な影響力を強調する考え方)ですが、受け手には「不自由さ」が強調されます。
しかし、エフェメラの中でも、例えばジン(zine、個人で制作する小冊子)をめぐる思想や実践はまったく逆で、そのはかなさによってこそ、人々は「自由」なコミュニケーションに接近できるという見方がなされます。エフェメラルであるがゆえに発揮される創造性については、90年代末、文化人類学者の山口昌男氏も、「文化の仮設性」という問いを立てて議論を展開していました。エフェメラルSNSをめぐる天野さんの考察は、こうした議論と接続できる気がします。
つまり、エフェメラルであることが同期性と不可分に結びついているとして、それによってそのメディア特性が一義的に決まるわけではない。マスメディアの同期性も一枚岩ではないことに留意しつつ、それとは一線を画して、アーカイブ化されないエフェメラル・メディアの系譜もある。シェアの同期性は後者の系譜から読み解いていくのがいいのかなと思います。
天野:「エフェメラ」の議論は非常に興味深いですね。特に、ご指摘いただいたように「はかなさと自由」の関係性は私自身も著書の中で展開してみたテーマです。現にInstagramはストーリーズ機能の導入によって、シェアしたものがいつまでも残ってしまうことのデメリットをうまく乗り越え、ユーザーの滞在時間やアクティブ率を向上させました。これはユーザーに新しい「自由」が提供されたことの結果というふうに私は捉えています。
冒頭で話題に上がったライブストリーミング、そしていま考察したストーリーズのようなエフェメラルなコンテンツ。このような視点からも、これらは共に今後よりいっそう注目していかなければならないフォーマットであると感じています。
最後に、ここまでの議論を通じた所感、ないしは今後に向けた飯田先生の関心、フォーカスの在りかなどをお聞かせ願えますと幸いです!
飯田:ビジュアルコミュニケーションを介したシェア文化の可能性には、僕も強い魅力を感じていますが、SNSに限らず、今のインターネット全体を見渡すと、なんともいえない閉塞感が漂っているのも事実です。
フェイクニュースやヘイト表現といった問題の深刻さは言うまでもないですし、天野さんも本の中で触れているように、有益とは言い難い一部のまとめサイトやキュレーションサイトなどの隆盛が、サーチエンジンに対する信頼性の低下を招きました。
このような現実に対して、天野さんが「ググる」から「タグる」へと呼ぶ、SNS検索やビジュアルサーチといった方法が、応急処置的なメディアリテラシー的実践であることは間違いないでしょう。しかし、かつてインターネットに期待されたポテンシャルを鑑みると、撤退戦という感じが否めません…。
また、若年層の「SNS疲れ」についても、本書の中で天野さんが論じているよりは悲観的というか、深刻に捉えています。趣味縁にもとづく合理的な情報行動によって、SNS上でのマウンティングや炎上を巧みに回避するリテラシーは高まっているかもしれませんが、SNS疲れはむしろ、職場や学校などの「選択できない」人間関係がネットに持ち込まれる、いわば拡張現実としての息苦しさのほうが大きいですからね。
90年代の仮想現実的なネット文化を肯定的に歴史化していく機運が高まっているのも、逆にポスト・インターネットという概念が浮上しているのも、こうした閉塞感の裏返しでしょう。このような現実に対して、どのような突破口があり得るのか、少しずつでも考えていきたいと思っています。
天野:重要な視点の提起をありがとうございます! ご指摘の通り、SNSが普及するフェーズでどんどん膨れ上がっていった、人々がつながっていくことへのポジティブな期待感が、ここ最近はもう少し冷静に、さらに言ってしまえば反転しつつあるような、そんな空気感も広がり始めている気がしています。
著書の中では、「シェアするゆえに、我あり」と現代人のマインドを言い表しつつ、そのありように警鐘を鳴らしたMIT教授のシェリー・タークルの議論も引用しましたが、誰もが発信者であり、シェアなくしては成り立たない社会にシフトしたからこそ、コミュニケーションに関わることをなりわいとする私たちは、その問題点にもより強くフォーカスしなければならないのかもしれません。
貴重な対話の機会を頂き、誠にありがとうございました!