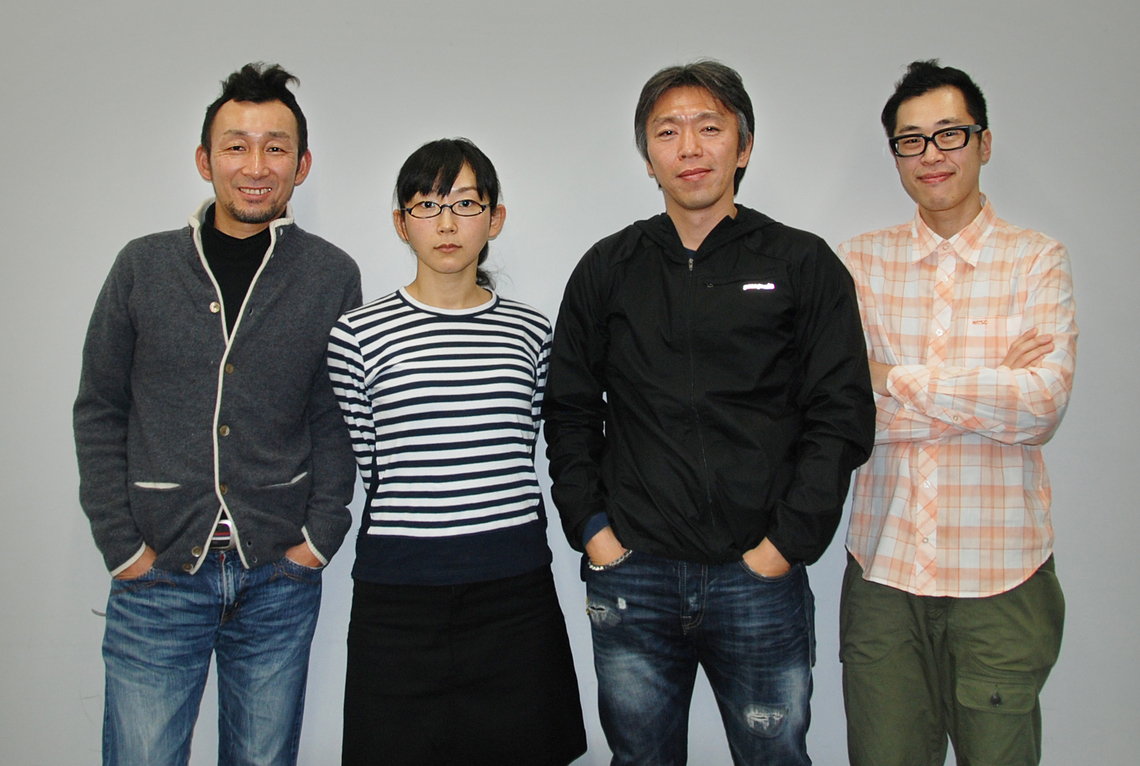「生体信号が拓くコミュニケーションの未来」第9回は、本連載初登場の加賀谷さんと、おなじみの神谷さん、なかのさん、土屋さんというneurowearチームでトークセッションを行いました。今回は再び、necomimiとmicoについて語ります。
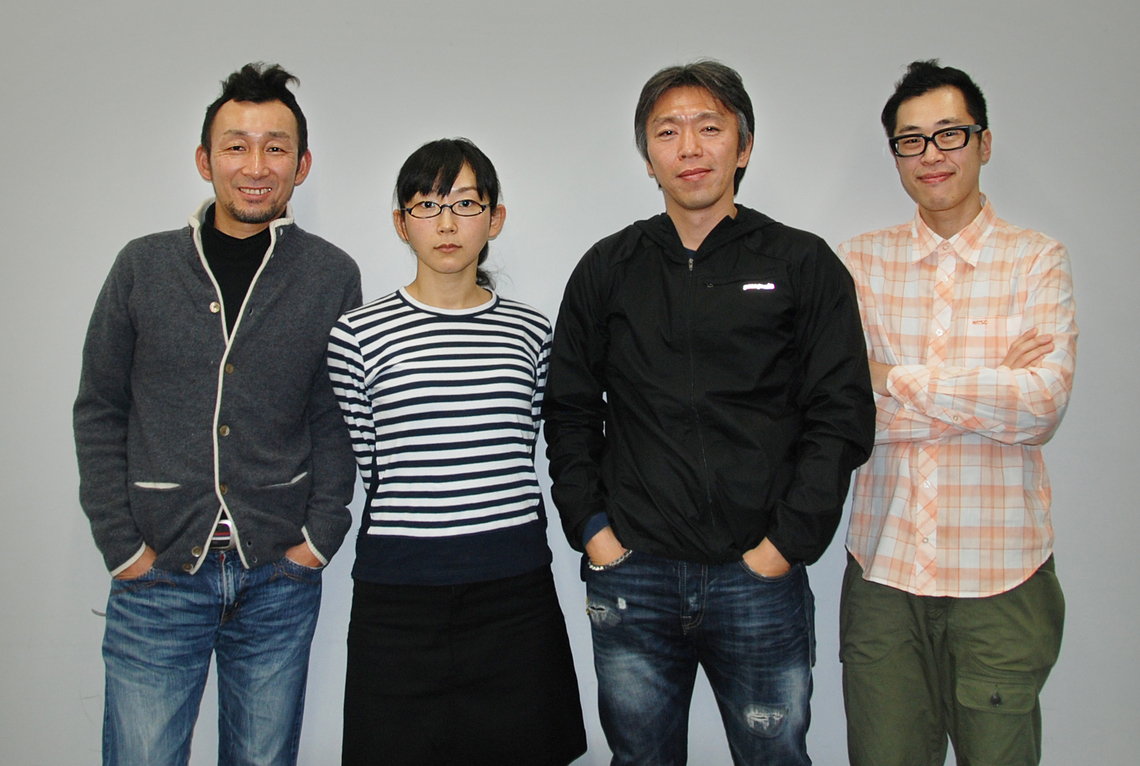
新しいコミュニケーション体験を作ることがミッション
加賀谷: 4人集まるのが久々なんで、今までのことを振り返ってみようか。necomimiのときは、土屋君はまだメンバーじゃなかったんだよね。
土屋: そうですね。プロトタイプがバズって商品化するというnecomimiのストーリーって、今は定番になりつつあるけど、当時はあまりなかった。それと脳波や生体信号も、世の中的にはあまり騒がれていなかったですよね。
加賀谷: 騒がれてないですね。僕がシリコンバレーに遊びに行ったとき、たまたまニューロスカイに行ったことが始まりで。
なかの: ニューロスカイさんの脳波ビジュアライザーを見せてもらって、アルファ波とかベータ波を初めて見て、脳波をビジュアル化することが面白いと思いました。
加賀谷: 文脈としてインビジブルなものがビジブルになるという体験が新しくて、情報化社会の潮流として価値は「見えない物」へシフトしているんだよね。
土屋: 確かに。人間が検知できる情報には限界があって、例えば目よりもイメージセンサーの方が優秀だし、微弱な表情の変化から感情を読み取るという研究もある。人よりセンサーの方が優秀になったとき、その技術で身体をどう拡張するのか、コミュニケーションがどう変わるのか。
加賀谷: そもそも新しいコミュニケーション体験を作ることがわれわれのチームのミッションで、「脳波を使った新しい表現およびメディアを作れないかな」っていうディスカッションの文脈で出てきたのが、necomimiというアイデアなんですよ。
神谷: お金も何もないところからスタートして、平日の夜に業務が終わってから集まって、部活みたいな感じでやってたんですよ。
加賀谷: necomimiで印象的なのが、コンセプトムービー制作以外にはプロモーション費用0円。これがすごかった。時流に乗ったというか。
神谷: そういうオーダーが来ても困るけどね(笑)。
なかの: キャンペーンでバズムービーを作るケースは存在していたので、そこの知見はあったんですよね。
加賀谷: ただ、われわれは海外をターゲットに仕掛けたんだよね。necomimiは非言語のコミュニケーションツールとして作っているから、世界に通じやすいんじゃないかなと。だから、なかのさんの妄想から作り上げたコンセプトムービーは、日本より海外での再生数が多かった。そこに手ごたえを感じましたね。
土屋: あと、コンセプトムービーとセットで被験者をそのまま撮影した体験映像を公開するスタイルも、ただのコンセプトモデルではなく、ワーキングプロトタイプだということが伝わってよかったのでしょうね。
加賀谷: 僕らのチームは全員ネット系の出身だから、ユーザーに刺さる出し方が直感で分かるんだよね。
土屋: necomimiのあと生体信号が認知されて、マーケットができてきた感じはありますよね。生体信号をトリガーにしていろいろ動かしてみるというものが出てきた。最近はnecomimiをハッキングして何かやってみるという動きもありますね。
神谷: ツイッターを見ていると、necomimiをハッキング用に買っている人がよくいて。一番手に入りやすい脳波センサーになってる。
なかの: AT&Tのハッカソン(プログラマーたちが集中的に共同作業を行う開発イベント)で、necomimiをハッキングして、集中してるときにかかってきた電話に「ゴメン。後からかけなおす」って自動応答するシステムを作ったエンジニアさんがいて。necomimiを片耳だけ付けて賞金もらってる映像がありましたね(笑)。ひとつのジャンルを広げることに貢献できた気がしてうれしかった。

micoといえば、データを作る苦行があった
神谷: micoは、土屋君がチームに入ったからできたんだよね。
加賀谷: 土屋君がメディアアートとコンピューターミュージックに強いから、そっちにいこうという話になった。
土屋: 当初micoは想起という研究をベースにしていました。例えば頭のなかで「クラシック、クラシック」と考えるとクラシックが流れるようなコントロールの仕組みです。
神谷: 無限にある音楽から、どうやって自分に合う曲を探すのかというテーマがあったんだよね。でも結構想起するのが難しくて、クラシックを意識したのに演歌がくるとガッカリだな、みたいな(笑)。
なかの: 私もロックとかジャズとか、音楽のジャンルをイメージできなかったんです。「フュージョンって何?」って。音楽を探すのに、まず音楽を勉強しなくちゃいけないのがナンセンスだと思って…。
土屋: というようなことを深く議論した結果、necomimiみたいにある程度結果に振れ幅があっても体験として面白いっていうことを意識して、いまのmicoのような、「こんなんでましたけど」っていう体験に落ち着きました。
加賀谷: micoといえば、データを作る苦行だよね。
土屋: 「こんな音楽を聴いたら、こんな脳波パターンが出ます」というデータを学習させるのに、脳波パターンを集めるんですよ。いろんな音楽を集めてきてメンバーも全員かり出されて脳波センサーを付けて聴いたんですが、これがメチャクチャ大変で(笑)。好きじゃない音楽も聴かなくちゃいけないし、しかもセンサーを付けたまま聴かなくちゃいけなくて。
加賀谷: あれはつらかったね。音楽って普段聞き流しているわけですよ。でも脳波測定しているから、音楽にのった状態をキープする必要があって、それってすごい集中力が必要で。あんなにつらい思いをしてタグ付けした人は、世界的にもいないと思う(笑)。ミュージックゲノムプロジェクトってあるでしょ、音楽を400個くらいの要素で分析する。あれに近いよね。
土屋: ミュージックゲノムプロジェクトの場合は、プロが音楽を分析するっていう立ち位置じゃないですか。だけどmicoは、普通の人が音楽を聴いたときの脳波データが欲しかったから、自分たちも含めてデータを採ったんですよね。大変でした。

分かりやすさは、neurowearのプランニングに一貫している
加賀谷: 外国のユーザーも含めて、micoにトライしてくれた人のフィードバックはどうだった?
土屋: 「その時の気分に合った音楽を選んでくれる」っていう体験自体が新鮮なので、すごく喜ばれるんです。それと、海外の反応で日本と違うのは「何のために作ったの?」って聞かれること。日本の場合は「これ儲かるの?」とかビジネス的な質問になることが多いけど、海外ではコンセプトについて聞かれる。そこをきちんと説明すると、みんな「なるほど」と納得してくれる。
加賀谷: 僕が海外で講演すると、プロダクトのなかでもmicoを熱烈に支持する人がいるんですよ。理由を聞くと「necomimiの面白さは分かるけど、あれはファンクショナルな感じがしない。でもmicoは使い方が完ぺきに分かる! ファンクショナルだと感じるから、僕はすごく気に入っている」って。
なかの: micoの問い合わせは、まだ結構きていますね。
土屋: micoの企画を考えるときに大事にしたのが、「一言で説明できる」こと。脳波を使って音楽がこうなってああなってみたいな複雑なことは、説明も複雑になってしまう。ドラえもんのひみつ道具って「ドアを開けると別の世界に行ける」とか「これを頭に付けたら飛べる」とか、明確なファンクションがあるじゃないですか。だから「自分のムードに合った音楽を選んでくれるヘッドフォン」だと分かりやすい。それってneurowearのプランニングに一貫していると思うんです。「集中すると再生するターンテーブル」とか「勝手に気になる所を撮ってくれるカメラ」とか。
なかの: そうですね。分かりやすいことが一番大事。結局、海外にも伝わるように頑張ろうと思ったら、一言で伝えられないと、英語で自分も苦しむわけだし(笑)。
土屋: 日本の市場だけを考えて、ハイコンテクストなものを作るっていうアプローチもあるとは思うんです。でもわれわれはそこを狙っているわけではない。
なかの: necomimiもかなり分かりやすくしたつもりだったけど、海外ではバニーって言われたり、カルチャーの違いを体験したので、誰にでも分かりやすいものを目指すって大変だなと思いました。
〔 次回へ続く 〕