ビジネスの基本は「フィット感」にあり
「オリジナリティ」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく本連載。第16回は、福島の中心街で5代続く眼鏡店が入る自社ビルをリニューアル。食堂や生花店、ギャラリーなど、さまざまなテナントを誘致することでマルチなビジネスを展開する藪内時計眼鏡店。その経営哲学の真髄に迫ります。
藪内くんとは、旧知の間柄だ。あえて藪内くん、と言わせてもらったが、藪内時計眼鏡店の藪内社長とは、プライベートも含めて仲良くさせていただいている。老舗の眼鏡店の5代目。それだけでもう、友人とはいえ畏敬の念しかない。でも、本人はいたって朗らかで、フレンドリーな男だ。だからこそ、多くの人を引きつける。
商店街にある個人経営の眼鏡屋さんのイメージは、家族経営の小さなビジネスというものだ。でも、藪内社長は、その眼鏡屋さんが入っているビルを「ひとつの街」のようなものにしたい、と言う。一体、どういうことなのか。
僕自身は、電通でアートディレクターとして活動している。中心となるのは「デザインとディレクション」だ。デザインやディレクションをする時、チームワークとか、時代の空気感、その先で触れる人々のこと、つまり、自分が作りたい世界観みたいなものよりも大事なものがある、ということを折に触れ、痛感する。藪内くん、いや、藪内社長には、今回そのあたりの極意を、あらためて教わりたいと思う。
文責:吉森太助(電通1CRP局)

明治8(1875)年創業、初代藪内弓五郎が時計台を土蔵の蔵の上に載せた藪内時計店を福島市大町に起業。当時は時計も貴重品で技術者も取扱店も少ないことから時計の販売、修理などの商売は順調だった。2代目、3代目も時計店として続くものの、クオーツ時計の登場などにより、時計の低価格化が進み経営が悪化。
危機を感じた4代目は、店舗の全面改装および商品の差別化を図り、時計店から眼鏡専門店へ業種転換を行うという思い切った舵(かじ)を切る。しかし新しい商品は受けいれてもらえず、ビジネスとしては大変な時期を経験。そのチャレンジ精神は、現代の5代目社長へと引き継がれていく。ビルのリノベーション、テナントの誘致、イベントの企画など、時代の変化を見据えたマルチな挑戦は、まさに藪内時計眼鏡店のDNAと言えよう。
「仲間」と、寄り添うということ
福島県のど真ん中、福島県庁通りの雑居ビルの中に、藪内時計眼鏡店はある。創業は、明治8(1875)年。老舗中の、老舗だ。その店主に今回、話を伺った。5代目となる藪内社長の取り組みは、とてもユニークだ。
どこにでもありそうな街の雑居ビルにある眼鏡店。その多くは、2階、3階を住居にし、1階で老夫婦が眼鏡を販売しているといったイメージだろう。ところが、藪内時計眼鏡店はちがう。1階は眼鏡店「OPTICAL YABUUCHI」、2階は生花店とレコード店、3階は食堂とアートギャラリー。ほとんどカオスという状態になっている。そのすべてを取り仕切っているのが眼鏡店の若き経営者、藪内義久氏なのだ。
藪内社長は元々、プロダクトデザイナーを志望していた。故郷の福島を離れて、東京の専門学校へ。そこから、ロンドンへの留学も経験した。帰国後、東京のおしゃれな雑貨店で働いたこともある。そのすべてには、なにかを自分の手でデザインしたい、という衝動があった。そんな彼の転機は、福島の実家へ戻ってこい、というお父様からの言葉だったのだという。地方の眼鏡店の店主になるのか、と正直、ふさぎこんだという。

1979年福島市生まれ、地元の商業高校卒業後、上京。眼鏡専門学校に入学し眼鏡について学んだ後、自由が丘の雑貨店に勤める。2003年に渡英し、デザインの大学を目指すも、帰国。
2004年にOPTICAL YABUUCHIに入社し、当ビル2階にDIYで店舗を作りOPEN。空いているテナントをDIYでリノベーションし、2012年、2階にレコード店「LITTLE BRID」がOPEN。この期間にたくさんのイベントを行う。
2014年、1階に「OPTICAL YABUUCHI」をリニューアルOPEN。同年2階に生花店「TOLAL PLANTS BLOOM」がOPEN。2016年3階に「食堂ヒトト」を誘致。2017年3階にギャラリー「OOMACHI GALLERY」をOPEN。現在も、屋上の改装、ビル横の広場に小屋を作るなど、自社ビルの持つ可能性、拡張性への挑戦を続けている。
「改めて見た実家の自社ビルは、古ぼけた雑居ビルでした。1階は、昔ながらのなんの変哲もない眼鏡店。2階には、場末感が漂うスナック。3階には雀荘、といった感じでした。父から眼鏡店をやってみろと言われた時に、これはなんとかしなければ、と思いました。幸い自分には、デザインの心得がある。この雑居ビルを自身の手でリデザインしてみよう、と思ったんです」
リデザインとは、単におしゃれな外観にする、ということではない。このビルに集まってくれる、志を同じくする「仲間」を探す、ということだ。「福島の街中にあるちっぽけなビルなのですが、そのビルを舞台になにかを仕掛けてやろうぜ、なにかを提供していこうぜ、みたいな仲間が集ったんです。それまでは正直、自分のデザイン力をなんとか生かしてやろう、ということばかりを考えていたんですが」
「街」に、寄り添うということ
藪内社長には、人生の転機となったある人からの言葉があるという。趣味の釣り仲間からのこんな言葉だ。「藪内くん。遊びは真面目に、仕事は楽しくするものだぞ」。目からうろこが落ちた、と藪内社長は当時のことを振り返る。
「正直、福島の眼鏡店の店主として、一生を終えるのかぁ、とふさぎこんでいた時だったんです。でも、自社ビルをリデザインして、仲間を集めていく中で、ああ、これはビルだけの話ではない。街ともっと、つながれるんじゃないか。楽しく仕事をするというのは、そういうことなんじゃないかという発想が湧いてきたんです」
ためしに、仲間といっしょにイベントを仕掛けてみた。なかなかの反響があった。「そこで気づいたんです。デザイン力って、なにも眼鏡のフレームをデザインする、自社ビルをリフォームするみたいなことだけではないんだな、と。ちょっと大げさな言い方になりますが、街をデザインするとか、福島をデザインするとか、そんなことに、ちっぽけな眼鏡店の店主でも、ちょっとは貢献できるのではないか、と」

「福島」に、寄り添うということ
「自社ビルをリフォームする時に第一に考えたのは『空気感』だったんです。ビルの匂いというか、たたずまいというか、その空気感に共鳴してくれる価値観が近い仲間が自然と集まってくる。お客さまも、そうです」
それって「福島」というエリアに関しても同じことじゃないか。と、ある時藪内社長は思い立った。福島という地域は、社長いわく中途半端なものだという。東京、大阪、福岡といった大都市ではない。かといって、人里はなれたど田舎でもない。そこに震災被害のイメージが重なる。その「空気感」を変えていくことはできないだろうか、と。
藪内くん(あえて藪内くんと呼ぶが)の指摘には、ハッとさせられた。僕自身もアートディレクターとして仕事をしているが、大事にしているのは「空気感」だ。もしかしたら、空気感を生み出す、価値観と言ってもいいかもしれない。仲間や世の中に共感してもらえるなにか。みんなにワクワクしてもらえるなにかをつくれないものか、と常日頃、思っている。
藪内社長は言う。「福島なんて、というレッテルを自ら貼っていたんだな、ということにある時気づいたんです。どうせ福島になんか、なにもないし、みたいな。でも、それがくやしい!という感情が湧いた時、では自分にはなにができるのだろう?ということを考え始めました。もちろん、一介の街の眼鏡店にできることなんか、しれたものですが(笑)」

「時代」に、寄り添うということ
眼鏡店というビジネスが、いつまで続けられるのかは、わからない。と、藪内社長は言う。「コンタクトレンズに替わるとんでもないものができるかもしれない。一滴点眼するだけで視力が回復する目薬ができるかもしれない。時代とは、そういうものだと思うんです。でも、その時代の変化と寄り添って、お客さまや地域の声に寄り添っていく気概があれば、なんとかなる」
東京という街は、とにかく「全力疾走」の街だ、と藪内社長は指摘する。確かに時代をけん引している街なのかもしれないが、全力で疾走しているがゆえに、息切れする場面も多い。福島は全力疾走で息切れするような街ではない。この街に流れている、いい意味での「ゆるさ」みたいなものの良さを引き出していきたい、と。

「お客さま」に、寄り添うということ
「これは、どんなビジネスにでも当てはまることだと思うのですが、結局最終的に『お客さま』に寄り添うことが大事だと思います」と藪内社長はインタビューを締めくくった。「福島にながれている『ゆるさ』は、あったかみとも言えると思うんです。お店同士が自分のお客さんに他のお店を紹介し合うとか、そういうことです」
「お店の扉を開けたら、街の入り口」という言葉を、藪内社長は心に刻んでいるという。売らんかな、の商売ではない。この街を、この福島を、好きになってほしい。そのきっかけが、眼鏡でもいい、食堂でもいい、ギャラリーでもいい。そんな思いで今日も藪内社長は、一点モノの眼鏡を自らの手で製作している。
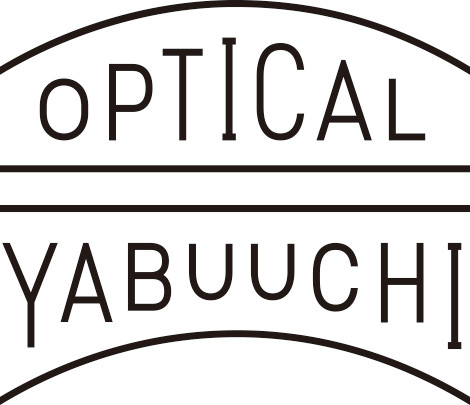
先代が立ち上げた店舗ブランドを受け継ぎたいと思いから、名称はそのまま、山形の友人の会社アカオニにデザインを依頼したとのこと。光学、視覚を意味する「OPTICAL」の文字と、凹レンズと凸レンズを表す曲線を組み合わせた。
藪内時計眼鏡店のHPは、こちら。
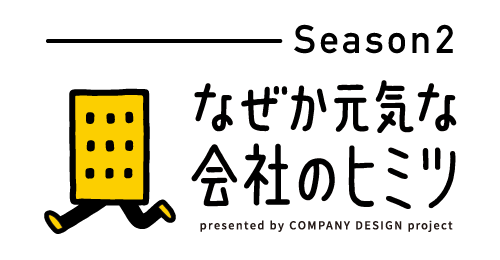 「オリジナリティ」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく連載のシーズン2。第16回は、福島の中心街でマルチなビジネスを展開する藪内時計眼鏡店をご紹介しました。
「オリジナリティ」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく連載のシーズン2。第16回は、福島の中心街でマルチなビジネスを展開する藪内時計眼鏡店をご紹介しました。
season1の連載は、こちら。
「カンパニーデザイン」プロジェクトサイトは、こちら。
【編集後記】
今回の取材で、藪内社長にどうしても聞いてみたいことがあった。いわゆる昔懐かしい商店街にあるたとえば豆腐屋さん、魚屋さんなどは、どんどん店を畳んでいく傾向にある。でも、眼鏡屋さんだけは、不思議なことに(と言っては失礼だが)健在だ。それって、どうしてなんでしょう?廉価を売りにする大型チェーン店とかが、あれだけもてはやされているというのに。
藪内社長の答えは、明白だった。「大切なことは、アフターフォローだと思います」。売ってしまえば、そこでおしまい、ではない。フレームがなんだかグラグラするのよ、とか、以前はよく見えていたのに、なんだか最近、視界がぼやっとするんだよ、とか。そういったことに細かく対応する。それが、眼鏡店の基本なのだと藪内社長は言う。「人が得る情報の8割は、目からだと言われています。眼鏡は、それをサポートするためのツール。そんな大切なことを担わせてもらっているということが、なによりの喜びなんです」
人に、地域に、時代に「フィット」していたい。そんな藪内社長の心根が垣間見えたコメントだった。
この記事は参考になりましたか?
著者

吉森 太助
株式会社 電通
第1CRプランニング局
アートディレクター・デザイナー
東京藝術大学美術学部デザイン科卒業 ・ 美術研究科修士課程修了 広告電通賞金賞/ADCノミネート/朝日広告賞部門賞/JAA部門賞など



