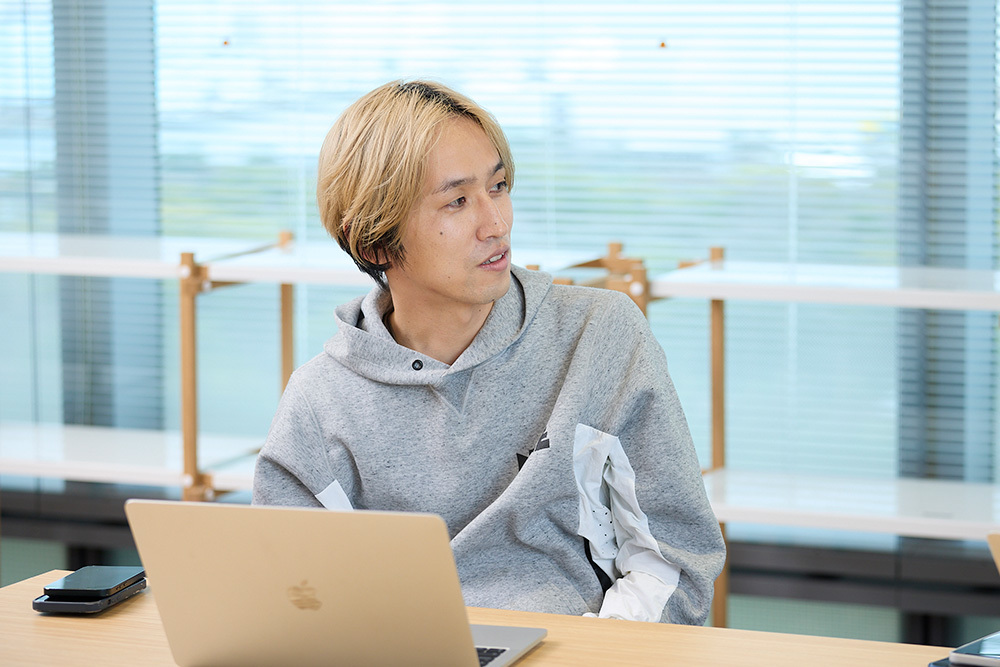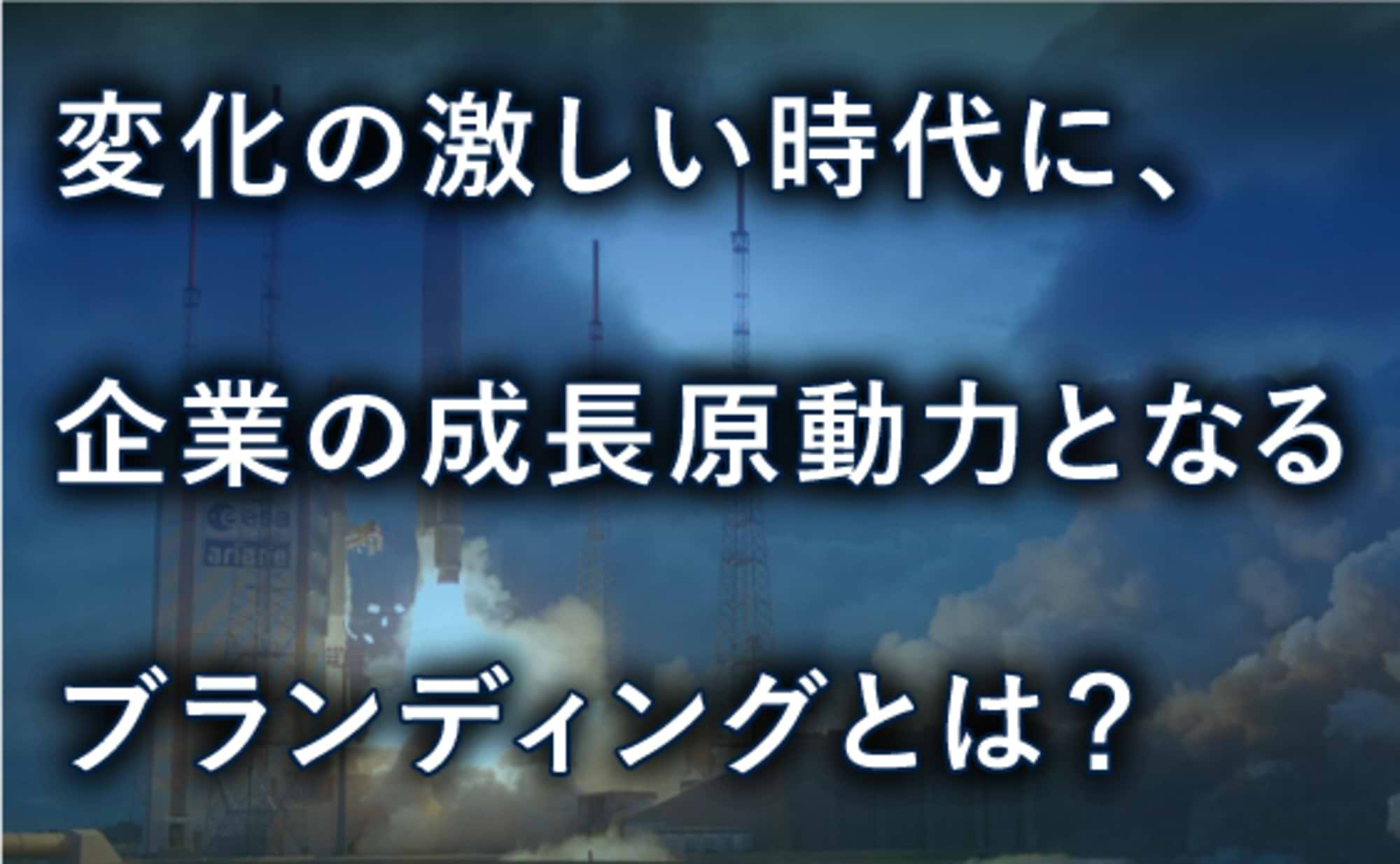電通のクリエイティブ横串組織「Future Creative Center(FCC)」は、広告の枠を超えて、未来づくりの領域をクリエイティビティでサポートする80人強による集団。この連載では、「Future×クリエイティビティ」をテーマに、センター員がこれからの取り組みについて語ります。
アートディレクターの活躍領域が広がっています。デザインだけでなく、体験を生み出すプロモーションやブランディングなどに携わるケースが増えています。こうした領域において、アートディレクターはどんな価値を発揮できるのでしょうか。FCCで活躍するアートディレクターの3人、玉置太一氏、田中せり氏、樋口裕二氏が集まり、それぞれが携わった事例を紹介しながら、その問いについて考えました。

(左から)樋口裕二氏、玉置太一氏、田中せり氏
ビジュアルが可能にする「チーム全員で未来の風景を共有すること」
樋口:「アートディレクターの価値」と聞いて僕が思い浮かべるのは、玉置さんが以前話していた沢田さん(沢田耕一氏)の「アートディレクターは未来の風景を旅行できる」という言葉です。
玉置:僕もその言葉は印象的でした。企画会議でいろいろなアイデアが挙がったとき、アートディレクターはそれを実装した未来、例えば街の中に掲出される広告や、あるいはウェブ上でアイデアを展開したときにどう見えるか。そしてそれに対する人の反応、表情が高解像度で想像できる。そのことを「会議中に未来に旅行できる」とおっしゃっていて「確かにそうだ!」と、自分の感覚が言語化された気がして、すごく納得しました。
田中:アートディレクターが一人で未来に旅行するのではなく、その未来を自ら可視化することで、チーム全員と未来に旅行するってことですね。それは一つの価値かもしれません。
樋口:もう一つ、アートディレクターは概念をビジュアライズすることで、「視覚から人の心を動かす」という点で貢献できると思います。FCCでは、広告だけではなく企業のビジョンやブランドアクションの企画にアートディレクターが関わることも多いですよね。こういうプロジェクトにおいて、感覚的に人の心を動かすデザインの力はとても重要ではないでしょうか。
東京都の防災ブック「東京防災」は、まさにそういう事例だと思います。プロジェクトの真ん中にデザインがあり、災害への備えをわかりやすくまとめています。デザインが人や社会の役に立っていますよね。
東京防災の関連記事はこちら
・東京防災
玉置:美大にいた頃、まさか自分が体験づくりやブランドアクションの仕事をやるとは思いませんでした。FCCでそういった仕事を経験する中で、だんだんと楽しめるようになってきたし、今は“新しい領域”と仲良くしています。
田中:“新しい領域”と仲良くしている、という感覚は私も近いです。FCCで携わるプロジェクトは、自分の私生活のコミュニティでは出会わないさまざまな領域の業種や専門家と出会うことが多いんです。その中で、アートディレクターという少し特殊な視点で時に無邪気に議論に参加することになるのですが、いわゆる広告グラフィックデザインの仕事では使わない領域の思考を働かせるので、FCCのプロジェクトは思考の筋トレをしているイメージです。
アートディレクターがクルマの広告を超えて「体験」を作った事例
樋口:玉置さんの仕事で僕が好きなのは、ホンダ「VEZEL(ヴェゼル)」のブランドムービーやプロモーションです。まさにVEZELが連れて行ってくれる景色が見えるというか、この車に乗ったときの気分が表現されていてワクワクしました。
玉置:2021年に公開したVEZELのブランドムービーは、僕らが映像を撮らないことをテーマにしました。ムービーに使われている写真や動画は、国籍も年齢もさまざまな方々が撮影したものなんです。撮影に使う機材と簡単なルールだけ決めて、皆さんが自由に撮った素材をこちらで編集しました。
田中:いろいろな方が撮った素材を使う形を選んだのはなぜですか?
玉置:人の感覚が多様化する中で、メーカーの考える「良いシーン」や「良い機能」だけを見せるのではなく、たくさんの人の「好き」を集めたほうが共感されるのでは、と思ったからです。クルマ離れが進んでいる背景には、こういった好きの多様化に対応できていない面ももしかしたらあるのかなと。例えば車がブレている写真は、普通ならボツにします。でもそれが良いと思う人もいるかもしれませんよね。そういう感じで、いろいろな人の感覚を信じ、リスペクトする。コ・クリエーション(共創)の精神でブランドムービーを制作しました。
あと、アートディレクターといえば普通は、写真を撮る。広告を作る。という仕事だと思われてると思うのですが、これは真逆です。みんなの好きを「編集する」というアートディレクションです。ブランドムービーでたくさんの人の「好き」を編集したのも、クルマの広告の未来がどうあったらいいか、これからはどういう表現が効果的かを、きちんと見据えることができたからだと思っています。
樋口:まさに体験を作った例ですよね。あと、僕が聞きたかったのは、玉置さんが携わっている富士フイルムの「写真幸福論」です。
玉置:これは、プリント写真は人を幸せにすると信じ、その価値を改めて世の中に伝えようと始まったプロジェクトです。FCCの小布施さん(小布施典孝氏)と一緒に進めてきました。
アートディレクターとして、まずはロゴを作りました。今後のプロジェクトデザインの旗印になるものなので、かなり考え抜いたつもりです。わかりやすさとか、展開のしやすさとか、強度とか、みんなで考えた信念が入ってるかとか、今っぽさとか。この旗印を掲げてこれからみんなで走るので、とっても大事な仕事です。
この仕事では他にもたくさんのプロジェクトを進行させてもらってますが、クライアントに常に伴走しながら、みんなで課題を見つけ、それを解決するアクションを考えていく。デザイン視点での意見もしますし、プロジェクトやアクションを可視化して整理したりもします。単なる広告のアウトプットだけじゃないアートディレクターの力で、プロジェクトに貢献できるように日々奮闘しています。
アートディレクターは「計画」と「意匠」を同時に考えられる
樋口:田中さんは、ロゴを作る仕事も多いですよね。どんなことを考えながら作っていますか。
田中:ロゴ制作は、その基となるブランドや商品の心臓部分を作っているようで、とても好きな仕事です。例えばブランドロゴを作るのは、ブランドの人格を決めるとさえ言えます。線一つをとっても、太さを変えるだけで印象は異なり、ブランドの性格や人物像も変化しますよね。
ロゴは一過性のものではなく、商品ラベルやグッズに展開され続けるのも魅力です。栃木の日本酒「仙禽(せんきん)」や、展覧会「AMBIENT KYOTO」のロゴなども作らせていただきましたが、ロゴからある人格が生まれて、その人格が好きになってもらえたら、ロゴが刻印された商品やグッズも、長く大切にしてもらえるかもしれません。ロゴを作ると、出会ったクライアントさんと長く一緒に関係を築けるので、それが何よりうれしいことです。
玉置:AMBIENT KYOTOもそうですが、田中さんは宣伝美術(※展覧会や舞台、演劇などの販促物やビジュアルの制作)にも多数携わっています。こちらもどういう思考で作っているのか、聞いてみたいです。
田中:宣伝美術で気をつけているのは、主役はあくまで展示作品ということです。例えば展覧会のポスターを作るにも、そのポスターに掲載される作品を引き立たせるのが重要で、私がデザインで作家性を出す必要はありません。ただし、その中でも展覧会のステートメントやアーティストの思考を私なりに視覚言語として翻訳して、タイポグラフィや写真の配置、色のぶつかり合いなどでグラフィックを再構築しています。
例として、2022年にDIC川村記念美術館で開催された企画展「カラーフィールド 色の海を泳ぐ」の宣伝美術を担当しました。カラーフィールドは、アメリカを中心とした抽象絵画の傾向なのですが、一辺が4〜5メートルほどある大きなキャンバス一面に色彩を使って場を作るようなペインティングの作品などが展示されていました。作品のサイズが身体よりもはるかに大きいので、一目では視界に収まらず、視点も定まらないので、まさに色の海を浮遊して泳いでいるような感覚になります。
この展覧会の宣伝美術では、「色の海を泳ぐ」という副題がとても印象的で、鑑賞体験を言い当てていたので、この言葉からインスピレーションを得ました。展覧会のタイトルロゴは、文字の下半分が消えてしまっていて、背景色の海に浸って泳いでいるかのようなデザインにしました。グッズにも展覧会ロゴを生かし、青いバッグには青の海に浸る文字、赤いパッケージには赤い海に浸る文字、というようにビジュアルアイデンティティとしての柔軟性も考慮しました。
玉置:樋口さんは、体験や戦略を考えるプロジェクトをたくさんやっていますよね。何か印象的な事例はありますか。
樋口:最初の方で「デザインを社会にどう生かすか」という話をしましたが、それだけでなく、ビジュアライズするということは、普段の業務にももっと生かせると改めて感じた事例があります。以前、モビリティ企業のグローバルプロジェクトに携わったのですが、プレゼン資料の一つ一つの素材にこだわりました。例えば、テンションが伝わる写真の選び方やグラフィックがGIFで動くなどです。
こうすることで、頭の中にあるイメージをしっかり伝えられますし、クライアントの方も資料を見てワクワクしたとおっしゃっていました。後回しになりがちな部分なのですが明確なビジュアルで早い段階からイメージを共有できると、狙うべきゴールのズレも起きませんでした。ビジュアルは、知覚を作る大切な要素だと感じています。最初の「旅行」の話ではないですが、未来との行き来ができた事例かなと思います。
玉置:すごくありきたりな表現ですが、デザインは言語や国境をこえて誰とでもコミュニケーションできます。さらに、アートディレクターはプロジェクトの計画から参画もできるので、「計画」と「意匠」を両方同時に考えられる唯一の職業なのかなと思います。それは、いろんな職種がある電通の中でもできる人が少なく、ましてやクライアントでもできる人がほとんどいないのではと思っています。そこに希少性がありますし、未来の価値づくりに貢献できるのではないか、と思っています。