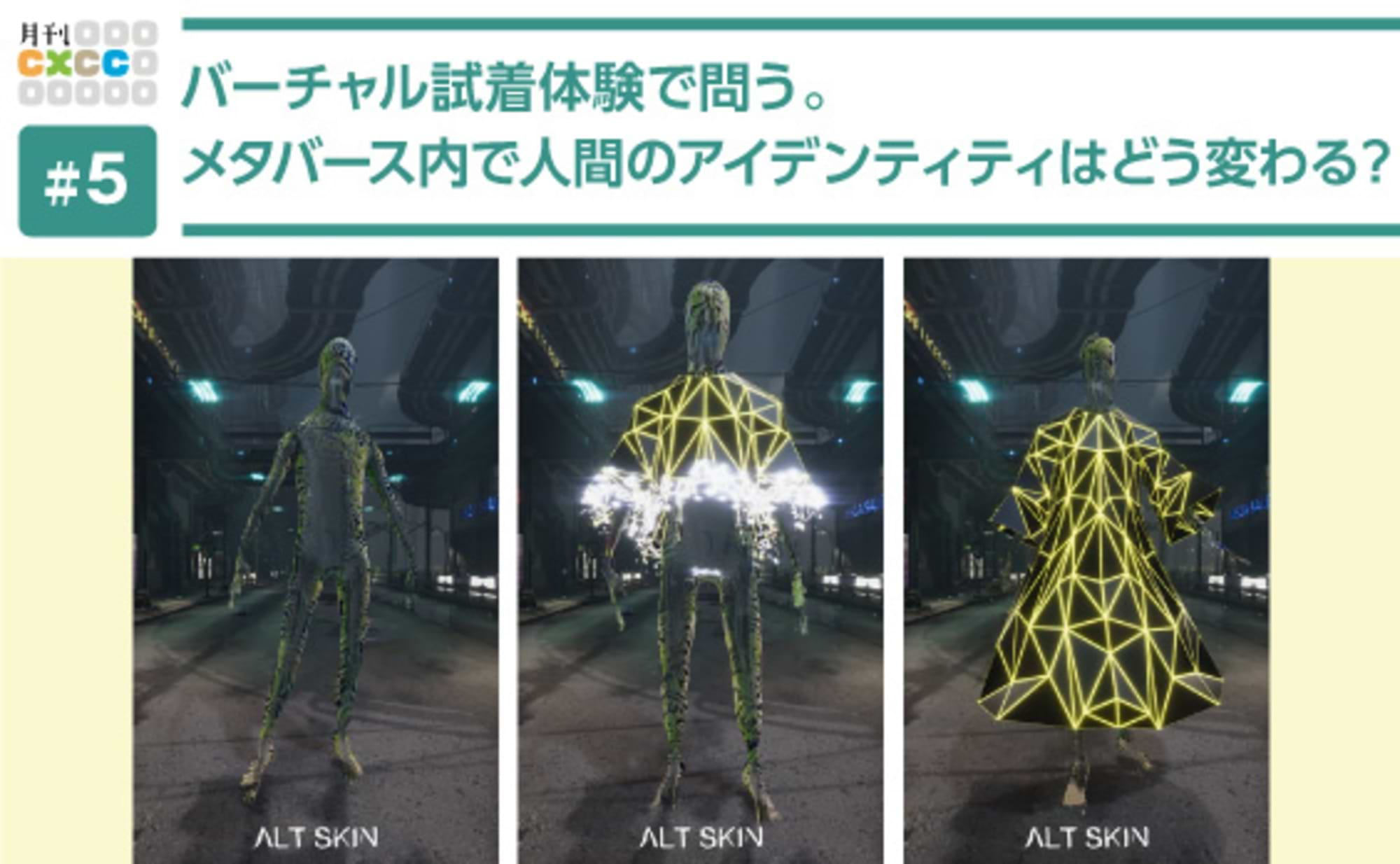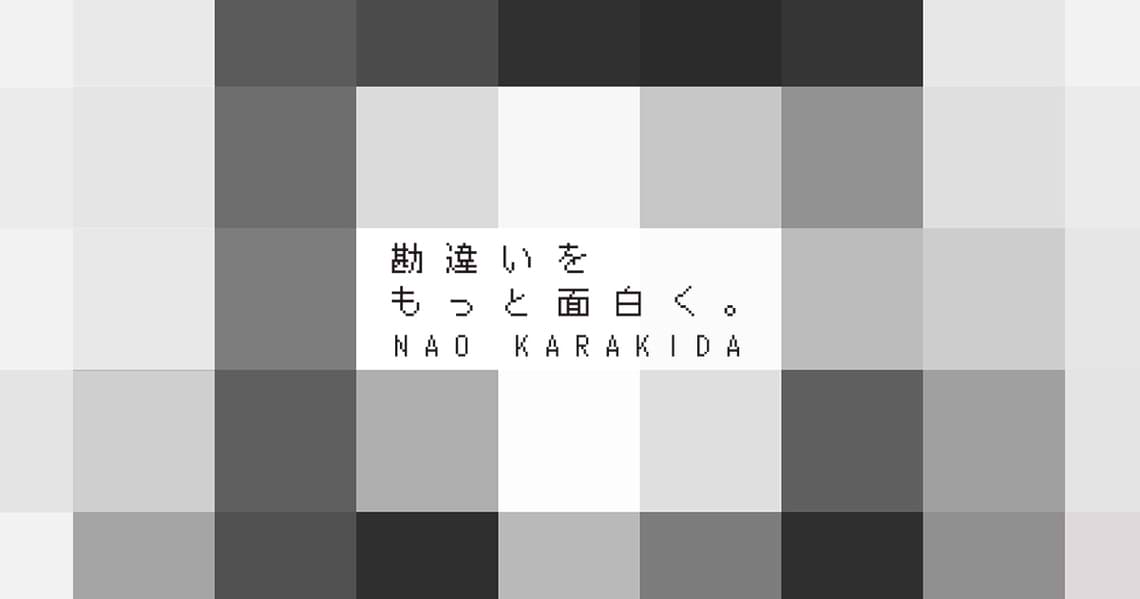日々進化し続けるCX(カスタマーエクスペリエンス=顧客体験)。
今やあらゆるシーンで求められるCX領域に対し、電通のクリエイティブはどのように貢献できるのか?
その可能性を解き明かすべく、電通のCX専門部署「CXCC」(カスタマーエクスペリエンス・クリエーティブ・センター)メンバーがCXとクリエイティブについて情報発信する連載。それが「月刊CX」です(月刊CXに関してはコチラ)。
今回は、アートディレクター(AD)としてイオンファンタジーの未来創造プロジェクトに参画している唐木田 奈緒氏に話を聞きました。
パーパス策定から事業のリブランディングまで、クライアントと直接話し、そのやり取りの中でクリエイティブの課題を発見、解決策を提案する。アートディレクターの新しい仕事への関わり方とは?
【唐木田 奈緒氏プロフィール】
電通
カスタマーエクスペリエンス・クリエーティブ・センター
アートディレクター
入社後、OOHや店頭などのグラフィックデザインを中心に、CMプランニング、ウェブデザイン、パッケージデザイン、ロゴデザイン、店舗デザインなどさまざまな分野でのアートディレクションを担当。
プロジェクトを推進するために、アートディレクターも前線に立つ
月刊CX:イオンファンタジーの取り組みについて教えてください。
唐木田:イオンファンタジーは、イオンの中にあるエンターテインメント事業や子ども向けプレイグラウンドなどを展開する企業です。「こどもと家族の笑顔のために、世界中に楽しい『あそび × まなび』を届けるオンリーワンのエデュテイメント(Education+Entertainment)企業」をビジョンに掲げており、ファミリー向けアミューズメント施設「モーリーファンタジー」、子どもがひとりで遊べるプレイグラウンド「スキッズガーデン」などさまざまな施設を世界中に展開しています。
電通は2014年から事業コンサルティングという形で支援をしており、課題の発見からアウトプットまで一貫して携わっています。私は、2021年にCXクリエーティブセンターに異動したタイミングで、プロジェクトに参画しています。
月刊CX:プロジェクトは、どのような形で進めていますか?
唐木田:イオンファンタジーの社長、役員と定期的な打ち合わせをしたり、さまざまな部署と合同で定例会を2週に1回実施し、その中で課題を見つけています。発注を受けてから動くのではなく、並走しながら課題解決に取り組んでいます。課題に対するアプローチは、関連する事業部と「分科会」という形で具体化していきます。アウトプットを発表するタイミングでは、広報部とも連携して市場調査を行うなど、世の中に発信するお手伝いをすることもあります。
月刊CX:アートディレクターとして、従来の広告などへの関わり方と、今回のプロジェクトでの関わり方はどう違うのでしょうか?
唐木田:電通の仕事は、基本的にビジネスプロデュース(BP)部門がクライアントの窓口になり、要件をまとめてクリエイティブ部門に仕事を渡しています。しかし今回の案件では、ADの私も含めていろいろな役割の人たちがクライアントと直接打ち合わせをしたり、日々連絡を取り合ったりしながらプロジェクトを進めていることがイレギュラーで、業務の領域が広がったと感じます。
普段クリエイティブは、クライアントから直接電話やメールを受けることはほとんどありませんが、イオンファンタジーの案件ではよくあるので、パッと聞かれて、その場で判断する瞬発力はかなり鍛えられました。
直接クライアントと話をすることで、BPが発見できない課題をクリエイティブ視点から発見して、その改善策を提案できていると思います。
月刊CX:プレイグラウンドのリブランディングにも携わったと聞いていますが、これはどういうものでしょうか。
唐木田:ファミリー向けアミューズメント施設「モーリーファンタジー」内に小さい子どもが遊べる時間制の有料プレイグラウンドの「わいわいぱーく」という施設があるのですが、よりあそびとまなびのコンセプトを強めるかたちで、リブランディングした「そびなび」がオープンしたというニュースが定例会で発表されました。
しかし、私たちの目から見ると、伝え方やデザインなどを変えればもっと伸びしろがあると感じました。たとえば「そびなび」はあそびとまなびを組み合わせた造語ですが、聞いた時にすぐにその意図が伝わらないですよね。ロゴのデザインや施設内に設置された遊具も、より統一感を出したり、カラー設計やデザインのトーン&マナーを統一することで一気に良くなるなと思いました。そこで、すぐに次の打ち合わせで、ブランドコンセプト、コピー、ロゴ、空間イメージなどを提案しました。
最初の提案でかなり最終形に近いものを提示できたことで、クライアントともイメージの共有がすぐでき、その場で即決していただけました。
そこからすぐに社内決裁を進めて、かなりのスピード感で新プレイグラウンド「NOBICCO(のびっこ)」が実現しました。オープン以来、以前の「わいわいぱーく」に比べて来客者数、滞在時間が増えて、売上増加にもつながっています。のびっこ内に子どもだけでなく、親が休める場所を用意したのもポイントです。

「イオンファンタジーで働いていることに誇りを持てる」パーパスを策定
月刊CX:クライアントの内側に入り込み、イオンファンタジーの新たなパーパス策定にも携わったそうですね。パーパスの策定について、詳しく教えてください。
唐木田:元々イオンファンタジーでは「遊びを通じて、夢と楽しさとふれあいを提案し、地域社会に奉仕しよう」という社是を掲げていました。そこに「社会や生活者」といった社外的視点をプラスして、新たなパーパスへと発展させていきました。
策定に当たってはまず、イオンファンタジーの従業員のみなさんの想いを込めていくことが重要だと考えました。ディスカッションの内容は、その場でホワイトボードに文字と絵で記録するグラフィックレコーディングで形に残して、打ち合わせに出ていない人にも議論の内容を共有し、みんなで納得感を深めていきました。また従業員の方々にアンケートをとって、日々の業務の中からもヒントを得るようにしました。
月刊CX:ディスカッションではどんな意見が出ましたか?
唐木田:特に印象的だったのが、「従業員がイオンファンタジーで働いていることに、より誇りを持ってもらいたい」という言葉です。一般的に言われるゲームセンターのイメージは、必ずしもポジティブなものだけではないと思います。ですが、イオンファンタジーの目指す“エデュテイメント”(Education+Entertainment)とは、子どもが夢中になって遊び学ぶことで、世界を笑顔にしていくという素晴らしい想いが込められているんです。
具体的には店舗が明るく開放的な造りになっていたり、環境音も子どもの耳に支障がない音量に調整されていたりと、細部までとても配慮されています。そのような想いをもっと世の中に知ってもらいたい、という気持ちを念頭に置きながらパーパスをつくっていきました。
月刊CX:パーパスは、どのように展開していく予定でしょうか。
唐木田:出来上がったパーパスは、日本だけでなく世界各国の言葉に翻訳して、従業員のみなさんへと伝えていきます。
また、パーパスをつくって終わりではなく、社外に向けて発信していくことも大事なので、生活者と接点がある場所でいかに伝えていくかが今後の課題です。

イオンファンタジーのパーパス
月刊CX:イオンファンタジーは、遊びと学びを大切にしている事業だと思いますが、学びはどういう事業があるのですか?
唐木田:子どもにとっては遊びと学びは常に表裏一体ということがベースとしてあり、遊びの中でいろいろなことを学んでいます。ただ、ビジョンに掲げる「あそびとまなび」を施設が体現していることが利用者には伝わりづらかったので、わかりやすい切り口で伝わるように支援しています。
一緒に制作したコンテンツで特に遊びと学びが感じられる事例としては、さかなクンが監修した「お魚のあそび!?まなび!?さかなクンと夏のギョギョッと大作戦!」があります。超リアルな魚のぬいぐるみが景品となった「リアルすぎる!ギョギョッと水族館!」では、イラストレーターもされているさかなクンならではのマニアックな視点を生かし、細かい模様や形まで再現されたぬいぐるみで、魚について学べるようになっています。
他にも、魚ではなく、ゴミを釣ると得点が入る魚釣りゲーム「海をまもろう!ギョギョッとレスキュー!」では、遊びながら自然と海のゴミ問題に関心を持ってもらい、絶滅危惧種についても学べるようにしました。

自ら課題を発見し、解決していくことがCXクリエイティブ
月刊CX:唐木田さんの考えるCXクリエイティブはどんなものですか?
唐木田:クライアントや生活者にどれだけ寄り添えるか、ということだと思います。ニーズ、課題は細分化されていて、答えを一つ出せばいいわけではありません。
定例会だけでなく、日々の業務のやり取りの中にも課題が隠れていて、それを見逃さないことがCXには重要です。クライアントから上がってくるのを待っているのではなく、何が課題なのかを発見して答えを出す能力が問われていると感じています。
例えば「年末に利用者にプレゼントするカレンダーを作る」という話を聞いたときには、普通のカレンダーではなく、イオンファンタジーのパーパスを反映したカレンダーにしたいと提案しました。
そして、好きなイベントまでの日数をカウントダウンできるカレンダーを作成したんです。
月刊CX:なぜカウントダウンできる形にしたのでしょうか?
唐木田:まず、子どもが日々をどう捉えているかということを考えました。子どもは、1週間、1カ月という単位ではなく、あと何回寝たら楽しいイベントになるかな、と考えます。特にコロナ禍においては、楽しみなイベントが減っているので、待っている時間そのものを楽しめるようにデザインしました。
これもカレンダーというワードを課題として拾い、よりよい形に広げていけた成果かなと思います。

ADから見ると、世の中にはアウトプットのクオリティが低いせいで、成功していないものがたくさんあります。そこを解決するだけで結果が変わるので、課題に気づいて手を動かせる立場にいることがとても大事だと感じます。
これまではクライアントからのオリエンを待っていました。ですが今回一歩前に出てクライアントと直接会話をしたら、入ってくる情報量がまるで違いました。やり取りを通して、相手の気持ちや想いも理解できましたし、その人のために頑張りたいというモチベーションにもつながりました。
(編集後記)
月刊CX 第6回では、イオンファンタジーの取り組みや成果について、アートディレクターの立場から教えてもらいました。
クライアントと直接対話する中からクリエイティブ視点で課題を発見し、即座にアウトプットを提案するという形が今回のプロジェクトにはマッチしていたようです。次々に新しい領域の支援もしており、クライアントからの信頼と期待の高さも感じました。
また今回のインタビューは、「CX Creative Studio note」(CX Creative Studio noteに関してはコチラ)とも協力しながら行っています。電通CXCCチームだけでなく電通デジタルのCXクリエイティブチームとも連携した、より幅広い事例の収集や紹介等も行っていますので、興味がおありでしたらそちらも併せてご覧ください。
また今後こういう事例やテーマを取り上げてほしいなどのご要望がありましたら、下記お問い合わせページから月刊CX編集部にメッセージをお送りください。いつもご愛読ありがとうございます。

月刊CX編集部
電通CXCC 小池 小田 高草木 金坂 奥村