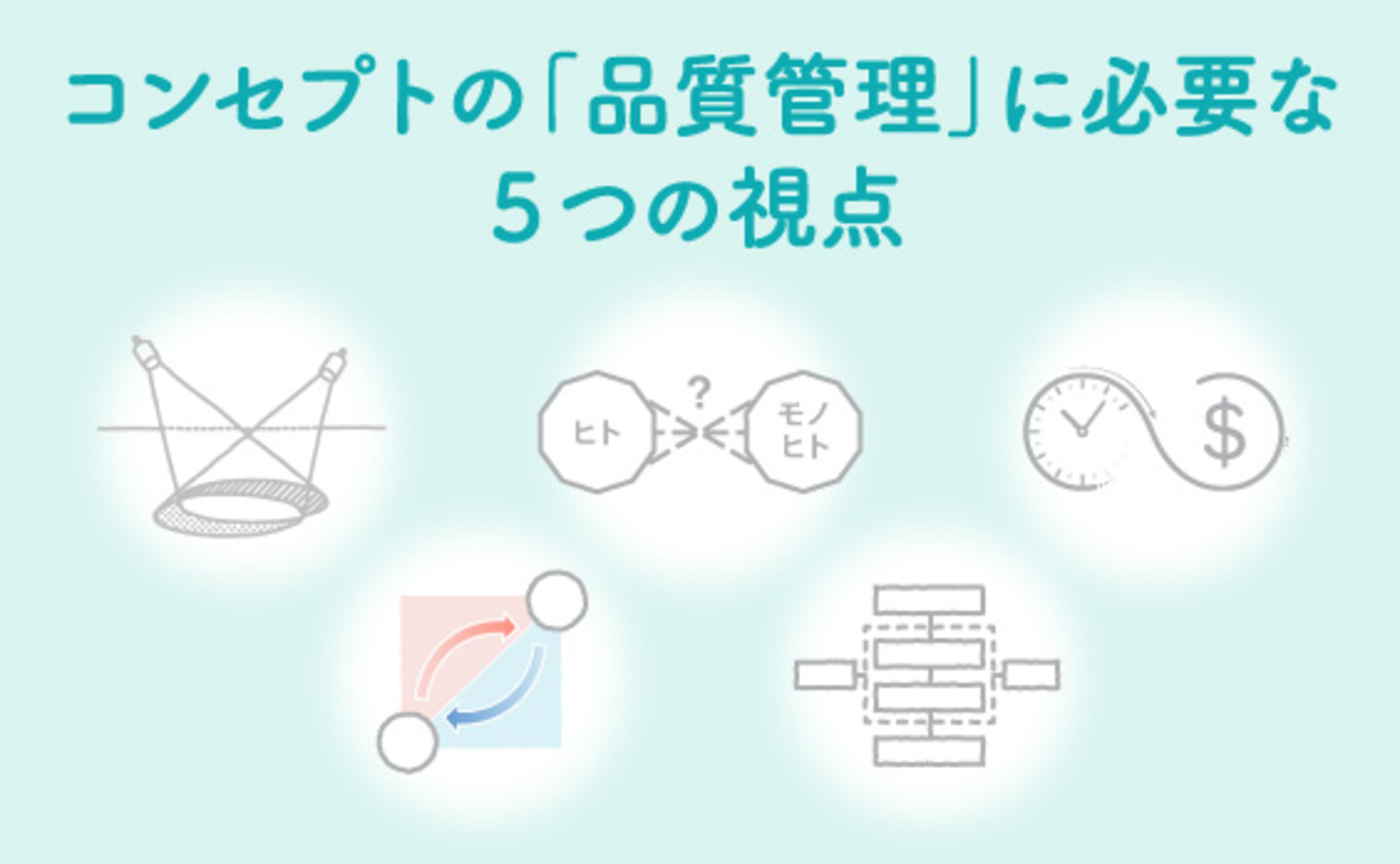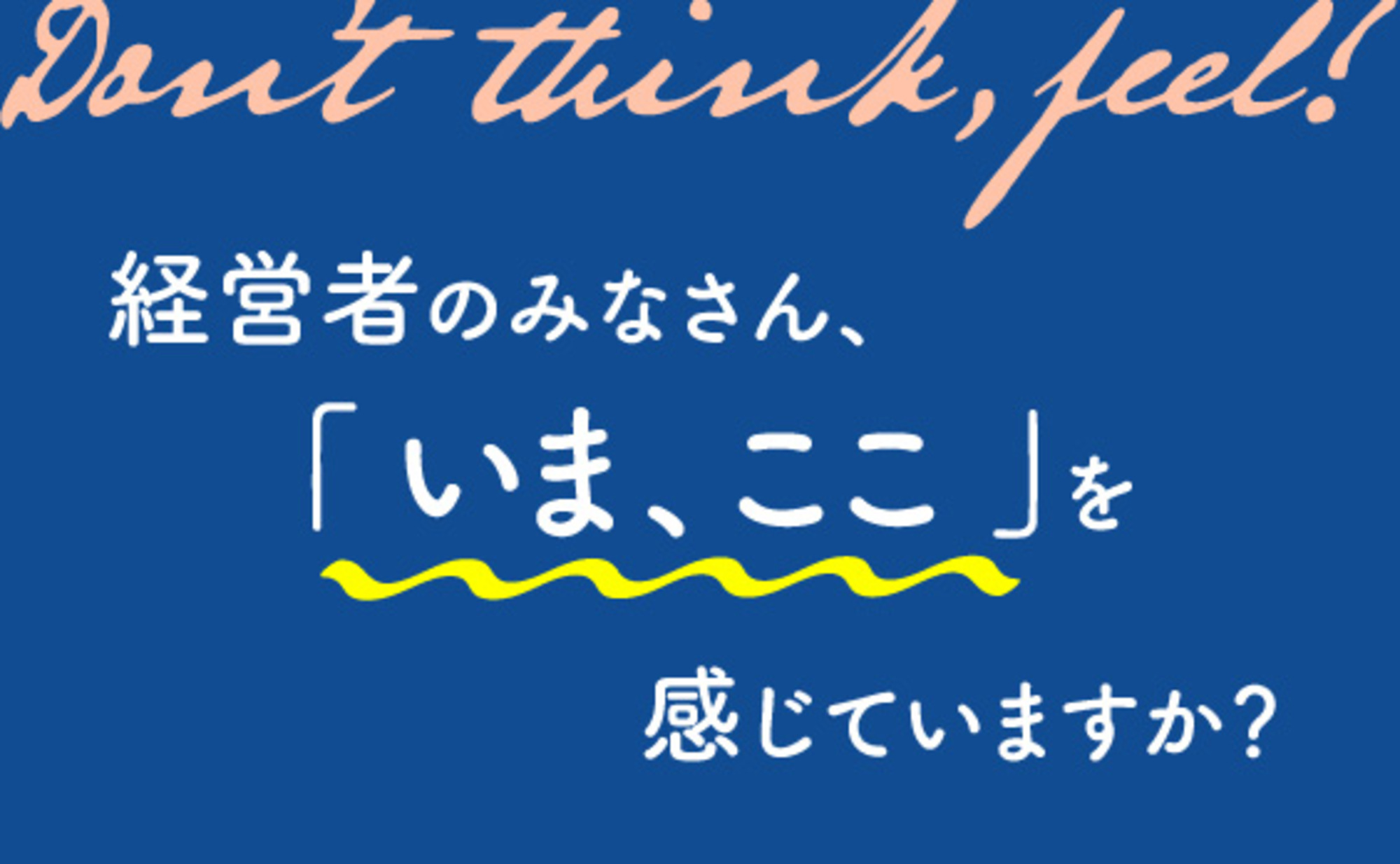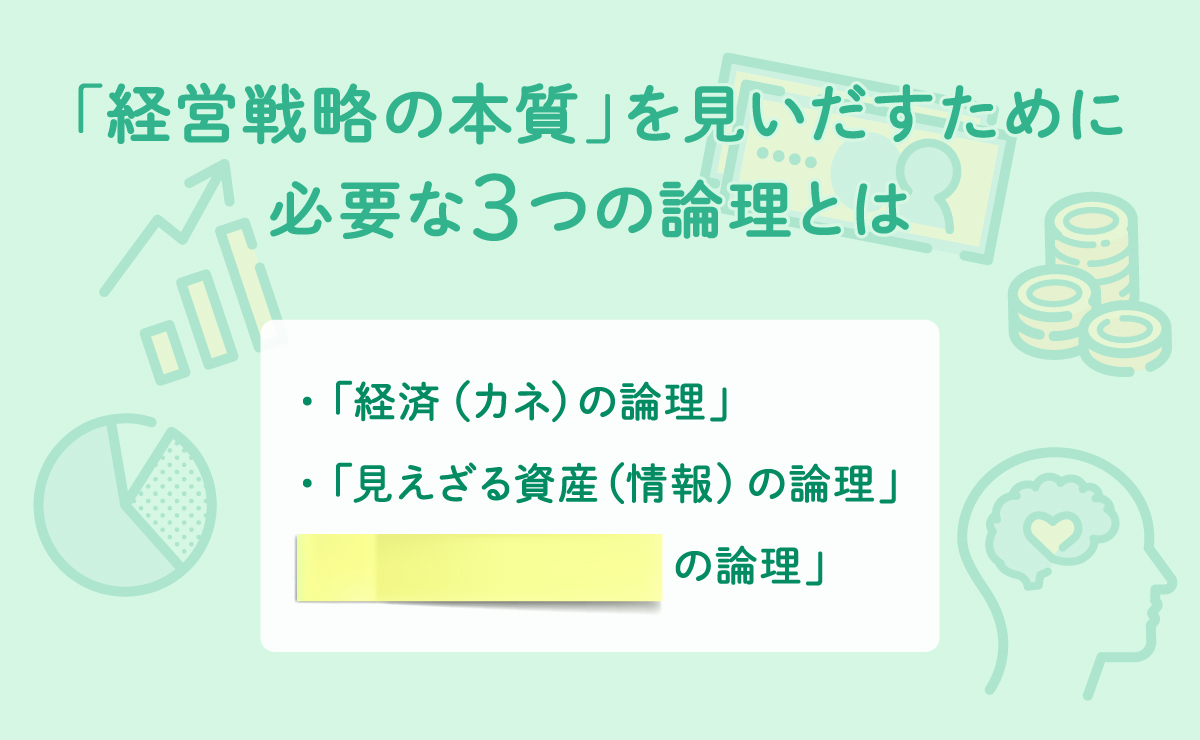前回のコラムでは「コンセプトの品質評価」を実践するための「5つの視点」をご紹介しました。
これさえ身に付ければ、企画書や計画書に「コンセプト」として掲げられた文言の良し悪しを見分けられるのはもちろん、さまざまな他者(他社)のインタビューや組織紹介の中に、競争優位性をもたらす「独自の視点(つまり実質的なコンセプト)」を見つけることができます。
ぼくは「お散歩」と称して、そんなコンセプト探しをすることがあります。今回はその“コンセプトのお散歩”をどのように行い、また、そこでどのようなものを発見しているかについてお伝えできればと思います。
福祉業界を「お散歩」する
たとえば、1963年に医療機関へのリネンサプライを中心事業として創業したヤマシタは、まだまだ高齢者の問題に関心が集まっていなかった1970年代、初代社長によって介護用品・福祉用具レンタル事業をスタートさせました。そのバトンを受け取った2代目社長は(社長に就任される以前の)1980年代から、
高齢化社会に対して、自立支援や人間の尊厳を高めるために福祉用具レンタル・サービスは必要なものだ。人は視力が落ちると簡単にメガネをかけるように、これからは福祉用具レンタルも高齢者にとってメガネのような存在になる
と、おっしゃっていたそうです。(『25歳で福祉用具レンタル・販売業を継承。「自ら考える組織」へ向けた3代目の挑戦 - relay Magazine』より)
「福祉用具を、メガネに」
さて、これを「コンセプト」としてみた場合、どのように評価できそうでしょうか?
まずこれは介護用ベッドや車いすといった高価な商品は富裕層のためのものだという「常識」を覆しています(=①)。と同時に、年を重ねても施設に頼ることなく「自立した生活を送りたい高齢者」という新しい顧客の姿を浮き彫りにしました(=②)。さらに、この取り組みによって「人間の尊厳が守られる社会」という理想が実現しそうです(=⑤)。
そして、それ以上に興味深いのは、「福祉用具を、メガネに」というメタファーによってどんな「方向性」が直感されるか?(=③)という点です。以下はまったくの推測ですが、そもそもは「メガネくらい、手軽に」という意味合いが強かったのかもしれません。しかし(同じく手軽で医療的な器具である)「福祉用具を、体温計に」といった表現にしなかったのには、何か理由があるはずです。どう思いますか?
ぼくは「福祉用具を、メガネに」という言葉の中に、メガネの「手軽さ」という側面だけでなく、「ファッション性」のニュアンスを感じます。
実際、母のために(別の会社からですが)介護用品をレンタルして感じたのが、全体的に「暗い」ということ。たとえば車いすも、母がもっと出掛けたくなる気分の上がるものを探したにもかかわらず、そこにあったのはどうにも心が躍らない、地味な選択肢でした。
メガネは、フレームやレンズの色や形を楽しく選べるからこそ、いつの間にか(器具を顔面の一番目立つところに装着する)憂鬱さを忘れさせてくれます。介護・福祉業界は、ここから大いに学ぶ余地がありそうです。そして「ファッショナブルな、介護用品」という視点から広がる新しい市場については、その規模を推計することもできます(=④)。
つまり「福祉用具を、メガネに」というたとえ話は、実は、組織に成長を促す「戦略」そのものだと思われるのです。
メガネ業界を「お散歩」する
福祉用具をメガネに喩える人がいる一方で、メガネを別のものに喩える人もいます。
全国に青いロゴの店舗を展開しているメガネ製造販売のZoff。彼らは「Tシャツを着替えるように、メガネ・サングラスを掛け替える世の中」を実現したいと言っています。これをまた、ぼくが勝手に「コンセプト」化すると……、
「メガネを、Tシャツに」
この文言を、ぜひ“味わって”ください。もう少し具体的に言えば、この言葉を聞いてどんな「方向性」が直感できるか、考えてみていただきたいのです。(=③)
まず浮かぶのは、Tシャツの「手軽さ」という側面でしょう。若い方はご存じないかもしれませんが、かつてメガネはフレームだけで数万円する高級品でした。それに対して、自社ブランドの商品を自社専門ストアで直販する(メーカーと小売が一体化した)、いわゆるSPA業態によって価格破壊をした企業のひとつが、Zoffでした。実際に店頭を見てもトレンドを押さえた定番商品が低価格で売られており、「メガネを、誰でも、いつでも気軽に買えるものにしていこう」という方向性は見事に実現できています。
一方で「メガネを、Tシャツに」には「気分に応じて着替える」というファッション性のニュアンスもありそうです。
ぼくはメガネが大好きなので、先日とある専門店でウインドーショッピングしていたところ、牛革と山羊革をつかった発色も美しいフランス製のフレーム、数十万円也が目に留まりました。店員さんに「これ…でも汗をかくシーズンは着けられないですよね?」と尋ねたところ「その通りでございます。こちらをお買い求めくださるお客さまは、日ごろから5本、6本を使い分けられるような方たちでいらっしゃいますので」とのこと……。
世の中には、確かに気分やシチュエーションによってメガネを掛け替える楽しみがあるようです。しかしそれはまだまだ一部の人々のもの。もっと多くの人がフレームの形で、色で、あるいはレンズカラーで楽しめるような状況をつくれれば、確実にメガネ市場は成長するでしょう。「メガネを、Tシャツに」は、そんな方向性をはっきりと示してくれます。
あるいはTシャツの「機能性」や、(おそろいを着る)「一体感」みたいな側面がヒントになるかもしれません。
ここで大切なのは、「福祉用具を、メガネに」にせよ「メガネを、Tシャツに」にせよ、それぞれの経営者がその言葉を喩え話に選んだ時点では、その含意を細部まで細かく設計していなかったかもしれない、ということです。
「体温計より、メガネだよな」「スニーカーやバッグより、Tシャツだよな」という感覚的な選択だからこそ、ニュアンスの広がりが生まれるのです。そして、そのニュアンスの広がりにこそ、「常識を覆すような新しい現実」を生み出すチカラがあります。
こんなふうに、さまざまなインタビューや組織紹介を「5つの評価基準」から眺めると、しばしばそこに組織の成長を促す「戦略」そのものを見つけることができます。その際、大きなコツは何かしらの「たとえ話」を探すこと。(いま存在しない未来は「たとえ話」でしか表現できないからです。詳しくはこちら の③を改めてご確認ください)
ぜひお気軽にトライしてみてください。
千葉県の勝浦といえば、朝市。前の晩、名物「なめろう」と地酒「腰古井」を堪能しすぎた重い頭を癒すには、ここをのんびり「お散歩」するのが一番です。
この日、見つけたのは地物のワカメとタケノコ。ワカメはいま海から出てきたみたいに新鮮だし、タケノコも今年、この界隈は裏年(はずれ年)で昨夏の雨不足も手伝って希少だと聞けば、ついつい手が伸びてしまいます。何よりこれをお土産にすれば、今宵の肴は春の大定番「若竹煮」で決まり。またまたおいしいお酒が飲めそうです。

写真左:庭で摘んだ山椒(サンショウ)の芽とともに/右:道の駅で見つけた「子持ち高菜」も肴に。
どうぞ、召し上がれ!