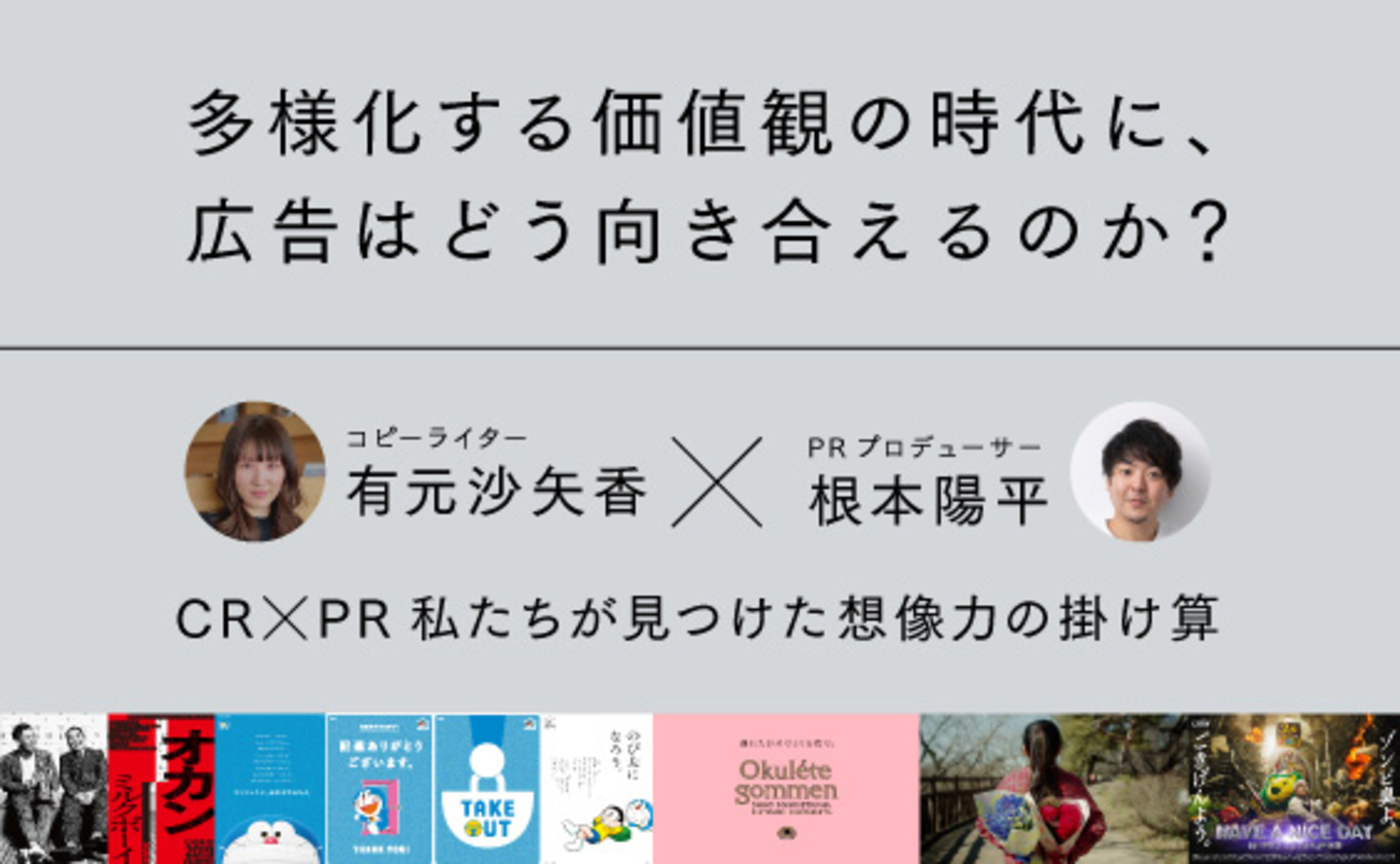電通のクリエイティブ横串組織「Future Creative Center」(FCC)は、広告の枠を超えて、未来づくりの領域をクリエイティビティーでサポートする70名強による集団。この連載では、「Future×クリエイティビティー」をテーマに、センター員がこれからの取り組みについて語ります。
新しい事業を作るとき、マーケット調査やターゲット分析によって「多くの人が求めるもの」を作ることを想像しがちです。しかし、世の中にはたった1人の「こんなもの欲しい」「これって価値かも」という発想から生まれた事業やサービスが普及するケースもあります。そんな逆転のマーケティング発想術「N=1」を実践しているのがスマイルズです。
食べるスープの専門店「スープストックトーキョー」を筆頭に、ファミレス「100本のスプーン」、シェアスペースにソフトクリーム専門店を置いた浜松町ビルディングの「ハマラボ!!!」など、N=1を起点とした事業を次々に実現しています。
とはいえ、1人が起点のアイデアは、尖っている半面、独善的になる可能性も。その中で、どのように世の中に広まるN=1を見つけるのでしょうか。今回は、上記の事業を手掛けてきたスマイルズ取締役兼CCOの野崎亙氏と、同社広報であり、新たにスタートしたスマイルズ生活価値拡充研究所所長兼研究員を務める花摘百江氏を招き、電通FCCメンバーの鈴木雄飛氏(クリエーティブ・プランナー)がN=1の極意に迫ります。

※この取材は、オンラインで行われました。
「ソフトクリームを食べる上司はかわいい」の発想が、新しいオフィスに
鈴木:スマイルズはユニークな事業を数多く手掛けていますが、それらを生んだ「N=1」の発想とはどんなものなのでしょうか。
野崎:たった1人の「こんなもの欲しいな」とか「これがあったら面白い」というミニマライズされたシーンを起点に、それを拡張して業態を作るのが「N=1」発想です。
例えばスマイルズが展開するファミリーレストラン「100本のスプーン」は、子どもが大人に憧れる気持ちを叶える場所というコンセプトからスタートしました。小さい頃、パパやママと同じものを食べたいと思った経験がありますよね。ここでは、お子様ランチなどの子ども用メニューではなく、大人のメニューの味やしつらえをそのままに、子どもが食べられるハーフサイズの料理を用意。また、子どもも大人と同じくグラスで乾杯できるなど、子どもが大人と同じ体験ができるようになっています。グラスの中身はワインではなく、ブドウジュースですが。
このコンセプトは、実は1人の原体験から生まれているんです。ある写真に、お父さんが髭剃りをする横で子どもが髭剃りの真似をしている様子が映っていた。それを見て「小さい頃って大人に憧れていたよね」と。そこで、子どもの「大人に対する憧れ」を叶える場所を作ろうと思ったのが始まりです。この発想をファミレスに落として、子どもが普段よりおしゃれをして、緊張しながらフォークとナイフを使うという、いわば“大人ぶれる場所”を作ったのです。

ファミリーレストラン「100本のスプーン」
鈴木:2020年12月には、浜松町ビルディングのシェアスペース「ハマラボ!!!」のリニューアルも手掛けましたよね。驚いたのは、このスペースにソフトクリーム専門店を出店したことです。これもN=1のアイデアなのでしょうか?
野崎:はい。外部企業の依頼で始まったリニューアルですが、打ち合わせの中で、気軽に上司に相談したり、オフィスではできない柔らかなコミュニケーションが生まれる場が欲しいという話がありました。
昔なら、タバコ部屋や給湯室がその役目を担っていたかもしれません。それを現代風にできないか模索し始めたのです。このとき、ふと「上司がソフトクリームをおいしそうに食べていたらかわいいな」と思ったんです。どんなおっちゃんでも愛らしく見えそうだし、普段厳しい上司でも少し許せるかもしれない(笑)。つまり、ソフトクリームを食べる機会を作れば、ゆるいコミュニケーションが生まれるきっかけになる。ソフトクリームがコミュニケーションの媒介になると。これも、1人の「こんなもの欲しいな」というアイデアがきっかけなのです。

浜松町ビルディングのシェアスペース「ハマラボ!!!」
鈴木:たった1人の気づきにスポットを当てて、今まで市場になかったもの、非連続なものを生み出されていますよね。しかも、そこから多くの人の共感が生まれているのがすごく面白いです。
企画者脳にとらわれず、生活者としての“なんとなく好き”を大切にする
野崎:出発点は1人の感覚ですが、それに対して「分かる、分かる!」という声が聞こえる、Nが2、3と増えていくことが重要です。上司のソフトクリームの話もそうですが、ソフトクリームを販売するオフィスは今までなくても、上司のソフトクリームを食べる姿がかわいいという気づきに共感する人はいる。であれば、それを一つのサービスとして提供したらどうなるかというプロセスです。
僕らのサービスは非連続なものが多いですが、それはサービスとして今まで市場になかっただけで、心の奥底で気づいていたものです。それを拡張してサービス化できるのがN=1の良さではないでしょうか。
花摘:N=1起点の発想は独善的とも考えられがちですが、私たちは、自分が欲しいと思えないものを世に生み出してもリアリティーがないと考えています。野崎さんは、会議でよく「それ本当に欲しい?」「この商品にその金額払える?」と聞くのですが、それは、誰もが本来は生活者であるはずなのに、その人格を切り離して事業設計をしているケースがあるからです。N=1は、作る側だけでなく、生活者としての視点を織り交ぜた発想術とも言えます。
鈴木:とても共感します。確かにプランニングをする際、企画者視点で考えすぎて、生活者の心情が置いてけぼりになることがあります。自戒を込めて“企画者脳”と呼んでいますが、それ以前に、生活者としての感覚を大事にできるかが企画の出発点です。
野崎:その事象が起きる理由は、社内で企画を通そうとすると、合理的な理論や価値の説明がなければ社内の理解や承認を得にくいからです。しかし、人の消費活動の多くは非合理で、理論や合理性では捉えきれない行動がたくさんあります。
自分が生活者に立ち返ったとき、なんとなく好きで買う商品はたくさんあるけれど、その感覚がビジネス上では軽視される。この“なんとなく好き”という、きわめて個人的な感覚をまず大事にして、そこにビジネス上で通用するロジックや翻訳を付加するのがN=1のプロセスと言えます。
花摘:N=1はBtoCだけでなくBtoBのビジネスでも活用できます。なぜなら、BtoBも決裁の責任者は一人のC(コンシューマー)と捉えられるからです。そしてまた自分も、同じく働いている個人です。であれば、自分の個人としての感覚や価値、「これがあればいいな」というN=1を大切にすれば、BtoBにも生かせると考えています。
鈴木:記事だと伝わりませんが、先ほどから頷きすぎて首がもげそうです(笑)。
電通のFCCでもN=1を軸に企画を立てることが多く、メンバーのN=1を集めてみたら面白いんじゃないかと思って新しい取り組みを始めています。具体的にはFCCのメンバーが個人的にラジオを始めました。そこにメンバーを毎週1人呼んで、それぞれが価値を感じるものや「なんでこうなっちゃうの?」という疑問をラジオで話してもらい、共有ノートに書き溜めています。
ゆくゆくは新しいサービスや研修制度につなげたいと思っているのですが、難しいのは、多様なN=1が多くの人に受け入れられる事業に成長するのか、あるいは一人の独善的な感覚で終わるのか、その線引きです。どうすれば独善的で終わらないN=1を育てられるのでしょうか。
野崎:N=1を単体で取り上げると、特殊な状況や個人的な思いで終わるので、いったんそれを抽象的にロジック化します。すると、そのロジックが他分野に応用しても共感が生まれるケースが出てきます。この場合は、多くの人に受け入れられる可能性が高いですね。
先ほど話した「100本のスプーン」のコンセプトも、髭剃りを真似している写真(N=1)から「大人への憧れ」という要素を見つけて、ファミレスという別分野に応用しました。つまり、他分野に応用しても共感が発生するかどうかがサービス化の分岐点ですね。
そのため、N=1から生まれた業態は、必ずしもニッチなマーケット向けとは限らないのです。出発点は1人の個人的な感覚でも、それが広く共感されていく可能性があるということです。
N=1を研究し、未来で普及する事業やサービスを生んでいく
鈴木:N=1の今後の可能性や展望についても聞きたいと思います。スマイルズでは「スマイルズ生活価値拡充研究所」という研究機関を新たに立ち上げました。こちらもN=1の発想術に関連すると伺いましたが、どんなものでしょうか。
花摘:この研究所は、生活の端々に潜む「生活価値」について、その拡充の方法論も含めて探求する場所です。まさに個人が感じていたN=1、それまで価値と捉えられなかったことにこそ新たな価値のタネがあると考え、さまざまなテーマを研究していきます。
現在行っているのが「不便益を含む未知なる益」の研究です。不便益とは、一見、不便と思われることが逆に価値になるのではないかという考えで、まさにN=1のような素朴な感覚を研究していきます。
野崎:今は物質的な豊かさに満たされ、また、テクノロジーによって情報や体験へのアクセスの自由度が高くなりました。獲得のハードルが低い中で、商品やサービスが選ばれる理由は、自分の文脈との合致になるでしょう。単純なメリット・デメリットで判断するのではなく、各々が自分の文脈で価値を判断するので、不便なものも人によっては価値になるかもしれない。
逆に企業は、自分たちの事業やサービスを、どう消費者の文脈と結びつけるかが求められます。合理的な良さよりも、背景やストーリーを作らないといけません。競争の主軸が意味性や文脈性に移行すると思うのです。
鈴木:合理性一辺倒ではない、ストーリーや背景に価値が出てくると。しかも、一人一人が求める文脈は違う。その中で、不便益をはじめ、さまざまなN=1の感覚を掘り起こして研究するわけですね。
野崎:そうですね。特に最近は市場が大きく変わっていて、多様化が進む中で、必ずしもマスマーケティングが正しい時代ではないと感じています。例として「TENT」という2人のクリエイティブユニットがいるのですが、彼らは自分たちが欲しいプロダクト、まさにN=1を徹底して作っています。
尖ったプロダクトならば、たとえニッチなマーケットでも一部のファンのニーズに深く刺さり、価格も自分たちで決められます。しかし、マスに合わせようとすれば、広く受け入れられるためにプロダクトは中庸にならざるを得ず、強いニーズが生まれにくい。その分、値段も下げる必要がある。プロモーションなどの経費もかかってきます。
面白いのは、マスを見ずに深く刺さるものの方が、特徴が強く、結果的に広がる可能性があることです。先ほど、N=1は決してニッチマーケットを意識した手法ではないと言ったように、個人の感覚を起点にした方が、結果的に世の中に広がっていく新しいものが生まれると考えています。
鈴木:いいですね。何より、私たちが未来に普及する事業やサービスを考えるとき、自分が欲しいもの、自分の内面に答えがあるかもしれないと考えるN=1の発想法はすごく楽しいですし、それが新しい未来をつくるかもしれないというのは勇気が出ますよね。さまざまな企業が“いっせいのせ”でN=1発想の事業を構想し始めたら……と思うとすごくワクワクします。